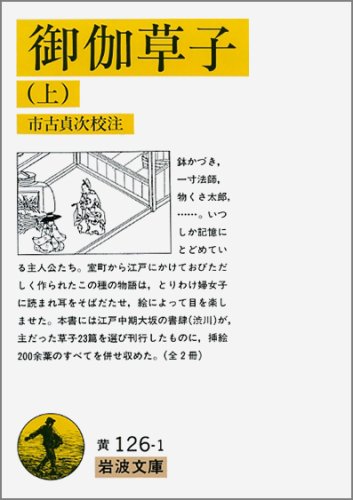ぽんきちさん
レビュアー:
▼
つれづれを慰めた物語たち
御伽草子は室町のころに成立した短い物語群である。平安期の物語文学の流れを汲むが、対象読者は幅広く庶民であり、ぐっと短いのが特徴である。
場面を詳しく描写するというよりは、ストーリーを簡単に紹介する形。貴族の恋愛ばかりではなく、民間説話のようなものも多い。庶民が主人公で、それが実は貴人の末裔であるという話や、動物が擬人化されたもの、神社仏閣の成立譚、外国から入ってきたお話もある。
広義には400編もの物語が含まれる。挿絵なども豊富で、子女に楽しまれたものも多い。
江戸時代に入り、大阪の書肆、渋川清右衛門が23編を刊行し、狭義にはこの渋川版『御伽草子』を指すこともある。
岩波文庫版は渋川版を上下に分けて収録。
上は
古文なのだが、庶民向けであるので、さほど読みにくくはない。一度でわからなくても二度三度読むと何となく呑み込める。
「鉢かづき」(鉢かつぎ)は現代でも比較的知られている話だろうか。
とある貴族の家。一粒種の姫君が豊かに幸せに暮らしていたが、母君が病となり死の床に就く。母君は姫君の生い先を案じ、頭に鉢をかぶせる。母君は亡くなり、姫の頭の鉢は取れないままで、片輪のような扱いになる。父君が再婚し、継母が姫をいじめて、ついに姫は家を出ることになる。川に身を投げようとしたが、鉢のために助かり、さるお屋敷で奉公することになる。
不幸続きの姫君だが、最後には鉢も取れ、富を得て幸せに暮らしました、というお話。
「御曹子島渡」はちょっと変わったお話で、和製ガリバー旅行記といった風。澁澤龍彦の『高丘親王航海記』もちょっと思い出す。
御曹子とは源義経のこと。まだ世に出る前の少年のころ、藤原秀衡に勧められて兵法が書かれた巻物を手に入れるために旅に出る。上半身が馬、下半身が人間の馬人の島があれば、全員が裸で暮らす島があり、アマゾネスのような女性ばかりの島があれば、小人ばかりの島もある。いろいろあってたどり着いたのが鬼ばかりの島。どうやらここの大王が巻物を持っているらしい。はてさて義経、無事巻物を手に入れられるのか。
「猿源氏草紙」は、三島由紀夫が歌舞伎の演目「鰯売恋曳網」に仕立てた話だが、原話は頓智話+歌の才覚の功名といった印象。鰯売りが貴族のふりをするというお話なのだが、この鰯売りの名前が「猿源氏」。どういう命名なのかちょっと不思議。せっかく「源氏」と言っているのに、「猿」とつけたら台無しというか、上げてるのか下げてるのかよくわからないと思うのだが。なんちゃって源氏ですよ、というような感じなのだろうか?
ともあれ、意中の遊女を射止め、めでたしめでたしではある。
貴種流離譚は庶民の夢をくすぐり、和歌の才があるものが得をする話は学びを推奨し、神仏の功徳を説くものは信心を後押しし、といったところだろうか。
そこそこ楽しい話もありつつ、ところどころ顔を出す説教臭さがやや鼻につく気がするのは、現代のすれっからし読者であるゆえか。
場面を詳しく描写するというよりは、ストーリーを簡単に紹介する形。貴族の恋愛ばかりではなく、民間説話のようなものも多い。庶民が主人公で、それが実は貴人の末裔であるという話や、動物が擬人化されたもの、神社仏閣の成立譚、外国から入ってきたお話もある。
広義には400編もの物語が含まれる。挿絵なども豊富で、子女に楽しまれたものも多い。
江戸時代に入り、大阪の書肆、渋川清右衛門が23編を刊行し、狭義にはこの渋川版『御伽草子』を指すこともある。
岩波文庫版は渋川版を上下に分けて収録。
上は
文正さうしの10編を収める。
鉢かづき
小町草紙
御曹子島渡
唐糸さうし
木幡狐
七草草紙
猿源氏草紙
物くさ太郎
さざれ石
古文なのだが、庶民向けであるので、さほど読みにくくはない。一度でわからなくても二度三度読むと何となく呑み込める。
「鉢かづき」(鉢かつぎ)は現代でも比較的知られている話だろうか。
とある貴族の家。一粒種の姫君が豊かに幸せに暮らしていたが、母君が病となり死の床に就く。母君は姫君の生い先を案じ、頭に鉢をかぶせる。母君は亡くなり、姫の頭の鉢は取れないままで、片輪のような扱いになる。父君が再婚し、継母が姫をいじめて、ついに姫は家を出ることになる。川に身を投げようとしたが、鉢のために助かり、さるお屋敷で奉公することになる。
不幸続きの姫君だが、最後には鉢も取れ、富を得て幸せに暮らしました、というお話。
「御曹子島渡」はちょっと変わったお話で、和製ガリバー旅行記といった風。澁澤龍彦の『高丘親王航海記』もちょっと思い出す。
御曹子とは源義経のこと。まだ世に出る前の少年のころ、藤原秀衡に勧められて兵法が書かれた巻物を手に入れるために旅に出る。上半身が馬、下半身が人間の馬人の島があれば、全員が裸で暮らす島があり、アマゾネスのような女性ばかりの島があれば、小人ばかりの島もある。いろいろあってたどり着いたのが鬼ばかりの島。どうやらここの大王が巻物を持っているらしい。はてさて義経、無事巻物を手に入れられるのか。
「猿源氏草紙」は、三島由紀夫が歌舞伎の演目「鰯売恋曳網」に仕立てた話だが、原話は頓智話+歌の才覚の功名といった印象。鰯売りが貴族のふりをするというお話なのだが、この鰯売りの名前が「猿源氏」。どういう命名なのかちょっと不思議。せっかく「源氏」と言っているのに、「猿」とつけたら台無しというか、上げてるのか下げてるのかよくわからないと思うのだが。なんちゃって源氏ですよ、というような感じなのだろうか?
ともあれ、意中の遊女を射止め、めでたしめでたしではある。
貴種流離譚は庶民の夢をくすぐり、和歌の才があるものが得をする話は学びを推奨し、神仏の功徳を説くものは信心を後押しし、といったところだろうか。
そこそこ楽しい話もありつつ、ところどころ顔を出す説教臭さがやや鼻につく気がするのは、現代のすれっからし読者であるゆえか。
掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
分子生物学・生化学周辺の実務翻訳をしています。
本の大海を漂流中。
日々是好日。どんな本との出会いも素敵だ。
あちらこちらとつまみ食いの読書ですが、点が線に、線が面になっていくといいなと思っています。
「実感」を求めて読書しているように思います。
赤柴♀(もも)は3代目。
この夏、有精卵からヒヨコ4羽を孵化させました。そろそろ大雛かな。♂x2、♀x2。ニワトリは割と人に懐くものらしいですが、今のところ、懐く気配はありませんw
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:岩波書店
- ページ数:270
- ISBN:9784003012611
- 発売日:1985年10月16日
- 価格:756円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。