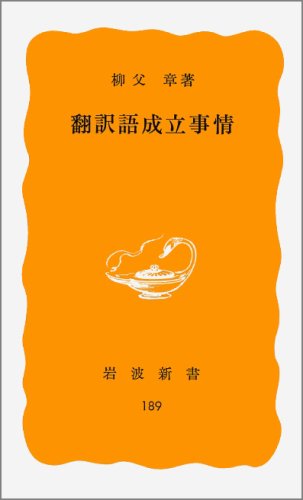こうしたものを日本人に紹介するには、もちろん英語のままではなく、日本語に取り入れる必要があったわけだが、そこには障害もあった。
思想や学問に関わる言葉の中には、日本にはその概念がないようなものもあり、ただ言葉を置き換えればよいというわけにはいかない。
そのため、翻訳用に新たに造語されたものもあり、一方で、それまで日本語として使用されてきたが、新たに意味を付け加えられたものもある。
漢字を受容し、中国から入ってくる学問を受け入れてきた歴史からすると、とりあえず日常語と切り離された翻訳語を作る例は伝統的にあった。そうしておくと、ひとまずその学問を取り入れることは形式としてできるのだが、造語であれ、新しく意味を加えられたのであれ、翻訳語の意味がわかりにくかったり矛盾が含まれたりということがありうる。そうなると、結局何を言っているのかわからない、ということも生じうるわけである。
本書では、「社会」「個人」「近代」「美」「恋愛」「存在」「自然」「権利」「自由」「彼、彼女」といった言葉を取り上げて論じる。
このうち、「社会」「個人」「近代」「美」「恋愛」「存在」の6つは、翻訳のための新造語またはほぼ新造語であり、残りは日本語としての歴史があるものである(「彼女」は新造語)。
「社会」は現在、日常的に目に触れる言葉だが、実はsocietyにあたる言葉は日本語にはなかった。
江戸期の辞書には、「侶伴(りょはん)」「寄合又集会」「仲間、交リ、一致」「仲間、懇、交リ」「仲間、組、連中、社中」といった言葉が並び、明治初期の辞書には「会(ナカマ)、会社(クミアイ)、連衆(レンジュ)、交際(カウサイ)、合同(イッチ)、社友(シャチュウ)」などとある。
英語としてのsocietyには、「仲間の人々との結びつき」という側面と、「同じ種類のもの同士の結びつき、個人の集合体が用いている生活の組織、やり方」という側面がある。けれども当時の日本では、前者のような狭い範囲の人間関係は見られても、後者の広い意味での人間関係は見られなかった。そのため、訳語も自然、前者の意味に寄ったものとなっている。
後者の視点は「個individual」を基本にするものであり、封建時代の「国」や「藩」では、人々は身分で分けられ、「個人」としての存在に注目されることはなかったのだ。
後者の意味を拾おうと考えると、新しい訳語を考えるのが適当であったというところだろう。
「社会」と似た言葉に「世間」があり、こちらは長く使用されてきた言葉であり、具体的・日常的な言葉である。けれども同時に、どこか通俗的なイメージがある。
上等舶来の言葉を置き換えるには、より「高級」な「抽象的」な言葉が選ばれがちであった。
このころ作られた翻訳語には、漢字二字の新造語が多いという。特に、学問・思想の基本用語にはこうした言葉が多く、日本語に本来なかった概念を、意味のずれが生じないように取り入れようという思惑があったのだろう。しかし、意味の裏付けのない言葉が使われるようになり、よくわからないまま、何となくかっこいいから乱用されるというような例も多々あったという。「社会」もそのような言葉のひとつであったようだ。
一方、「自由」という語は、日本語では、元来は勝手気ままとか、あまりよくない意味で使われてきた言葉である。英語のfreedomやlibertyに「勝手」というニュアンスがあるというよりも、「自由」の方にその意味合いがあり、本来は、訳語として充てるには適切ではない言葉であったと著者は論じる。福沢諭吉などもこの語は適当ではないと考えていたものの、他にちょうどよい言葉がなく、仕方なくこれを使用していたようである。『自由之理』という当時広く読まれ、翻訳語「自由」の定着に一役買った本の訳者である中村正直も、「リベルテイ」という言葉の訳し難さに触れている。別の文章では、「寛弘」という訳語も用いているが、定着しなかった。その他、「自主」「自在」「不羈」など、少なくとも悪い語感のない言葉が訳語候補に挙がっても来たが、いずれも定着はしなかった。
もっとも適切な言葉が残るわけではなく、残ったものが正しいわけでもない、というのは、皮肉だが正しいことであるようだ。
いくつかの「翻訳語」の成立事情を追ってみると、翻訳というものがいかに一筋縄でいかないかが見えてくる。時にそれは概念そのものの紹介であり、日本には存在しなかったものの解説であるからだ。
たかが翻訳、されど翻訳、と言おうか、いや、そもそも「たかが」といえないのが翻訳という気もする。
分子生物学・生化学周辺の実務翻訳をしています。
本の大海を漂流中。
日々是好日。どんな本との出会いも素敵だ。
あちらこちらとつまみ食いの読書ですが、点が線に、線が面になっていくといいなと思っています。
「実感」を求めて読書しているように思います。
赤柴♀(もも)は3代目。
この夏、有精卵からヒヨコ4羽を孵化させました。そろそろ大雛かな。♂x2、♀x2。ニワトリは割と人に懐くものらしいですが、今のところ、懐く気配はありませんw
この書評へのコメント
- くにたちきち2024-10-15 16:15
ぽんきちさん:翻訳ということの奥深さを感じました。同時に、日本語には文字がないことがその要因の一つではないか、というのは、中国人に「日本には固有の文字がない」と言われて、よく考えてみると、確かにその通りで、漢字は中国の文字であり、初めはそれを借用して日本語は文字化されたのではないか、ということに気付かされました。翻訳をする時の用語は、その意味を漢字で考え、それが困難な時には、その発音をカタカナで示しますが、中国人はその意味はもとより発音も漢字化しているのではないでしょうか。そこが、文字を持っている民族と、文字を持っていなかった民族の違いなのかなと思いました。
クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - ぽんきち2024-10-15 17:26
くにたちきちさん
コメントありがとうございます。
日本語は漢字(表意文字)も使いますが、かな文字(表音文字)も使うところがなかなか特殊な言語なのではないかと思います。
漢字を取り入れつつも、そこからアレンジして音のみを表す字を作っていったあたり、外国からのものを取り入れつつ、使い勝手のよいように工夫する、という姿勢だったのかなと思います。
中国語の外来語表記については私は詳しくないのですが、音を取り入れる場合と意味を取り入れる場合とあるようですね。
人名は漢字で音をあらわす場合が多く、マルクスは「馬克思」、アインシュタインは「愛因思坦」、ニュートンは「牛頓」といった例があるようです。
商品名や社名など、ビジネスが絡むと、わかりやすく見映えがする?言葉に置き換えられることが多く、ホットドッグ「熱狗」、コカコーラ「可口可楽」(これは音も含む感じですかね)
、ファーストフード「快餐」、ボーイング「波音」など。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - ぽんきち2024-10-15 17:28
参考:https://www3.cuc.ac.jp/~zhao/wailaiyu.htm#:~:text=%E3%82%B3%E3%82%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%92%E3%80%8C%E5%8F%AF%E5%8F%A3%E5%8F%AF%E6%A5%BD,%E6%9C%89%E5%90%8D%E3%81%AA%E4%BE%8B%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%80%82
いずれにしても、各国それぞれ言語構造も違い、翻訳事情も違うのがおもしろいところでしょうかね。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 
コメントするには、ログインしてください。
- 出版社:岩波書店
- ページ数:212
- ISBN:9784004201892
- 発売日:1982年04月20日
- 価格:735円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。