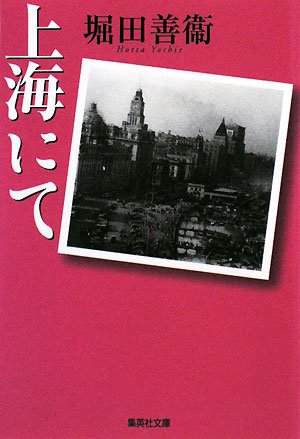三太郎さん
レビュアー:
▼
日本の敗戦前後に上海に滞在経験のあった作家の堀田が1957年に中国を再訪して書いた本。
元は1959年(戦後14年目)に出された本だとか。文庫版の解説を大江健三郎が書いている。その大江によると、この本は戦後に日本人が中国に関して書いた本としては、酸鼻を極める事実と苦渋に満ちた省察が込められた「美しい」本なのだという。堀田の作家としての出発点を知りたいと思ってこの本を手に取った。
著者の堀田善衛は1945年3月の東京大空襲を体験した直後に上海に渡った。そして終戦後にも国民党宣伝部の対日文化工作委員会に雇われた身分(留用と呼ばれた)で上海に留まり、終戦前後の中国を内側から観察することになった。
<堀田と対日文化工作委員会の役割についてはウェブで研究論文が読める⇒堀田善衞の被徴用体験>
この物語は1957年に6人の文学者とともに中国からの招待旅行に出かけるところから始まる。1957年は毛沢東が共産党を批判した右派の粛清に乗り出した頃で、1966年からの文化大革命が始まる前だった。毛沢東による独裁体制が次第に固まっていく時期だったろう。
当時の中国政府は、日中戦争の責任は日本の一部の軍国主義者にあって大部分の日本国民には責任がないという対日二分論を唱えていた。(今では中国人も日本人もそんな綺麗ごとは信じていないと思うけれど。)まだ日中国交回復前のことである。
堀田は上海の街を歩きながら、戦前に共同租界やフランス租界があった頃から、日本軍の占領、国民党軍の占領、共産党軍による「解放」とその度に街の通りの名前が何度も変わったことを思い出す。
堀田は終戦直後、国民党に留用されていた頃に上海の大学で学生を前に講演をした経験があった。大学とは言え戦時中は日本軍が接収して弾薬の保管場所になり、その後国民党が接収すると米国から贈られた軍用車の集積所になっていたとか。学生たちはみなぼろを着て眼だけギラギラしていたらしい。
戦前の上海の様子は当時中国にいた欧米人による著作からの引用であるが、上海は欧米資本に牛耳られ、中国人労働者は奴隷のような扱いで子供の労働も当たり前だったらしい。終戦直後の上海を堀田は当時の上司に当たる重慶から来た国民党の役人のF氏と歩いた。米国からの支援物資は地方への配送ができずに上海の街に溢れて、その結果上海の製造業はみな潰れたとのこと。物資が地方に送れないのは共産党のせいだとF氏は言った。当時は米国が国民党と共産党の仲を取り持とうとしたが、結局は共産党が国民党を追い出すことになった。
国民党のF氏は地方の地主階級の出であったが、堀田が上海で見かけた共産党員は見るからに農民であった。堀田は共産党の農民による上海の奪取が起こりつつあると考えた。それまでは農村は都会に搾取されてきたが、農村が都市を支配するようになったのだと。
(この小説が書かれてから60年以上たって、今日の中国では再び都市が農村部を搾取しているように見えるけれど。)
堀田は1945年当時ある婦人を見舞いに病院を毎晩のように訪問していた。その時に知り合いになった中国人看護婦に堀田は1957年の上海で偶然再会し、そのことで45年当時のことをいろいろ思いだした。当時のことを書こうとしたのはそれがキッカケだったらしい。
1946年の秋、堀田が日本へ帰国する少し前に上海では労働者によるゼネストと暴動が起こったという。これを契機に上海でも国民党への支持は低下し共産党が優位に立った。
(結局1949年には毛沢東の率いる共産党が国民党を台湾へ追放し、米国は中国での足がかりを無くした。)
堀田は1957年時点で中国人自身がこれらの社会変革を「革命」ではなく「解放」と呼んでいることに注目している。これは国民の大多数を占める小作農が地主から解放されたことを主に指すらしい。当時の中国では中国人自身により目覚ましい勢いで学校や工場が建設されていて、堀田はあと「30年」で中国の国力は米国に並ぶのではと予想している。慧眼だったと思う。現実にはその2倍の60年がかかったが、中国はいまや米国と並ぶ国力を蓄えている。
そしてこの60年間に日本は経済的に中国に深く依存するようになった。中米の対立の間でどっちにもつけない日本はこのままでは衰退するしかないのかも。堀田が今の状況を見たら何を思うのかな。
著者の堀田善衛は1945年3月の東京大空襲を体験した直後に上海に渡った。そして終戦後にも国民党宣伝部の対日文化工作委員会に雇われた身分(留用と呼ばれた)で上海に留まり、終戦前後の中国を内側から観察することになった。
<堀田と対日文化工作委員会の役割についてはウェブで研究論文が読める⇒堀田善衞の被徴用体験>
この物語は1957年に6人の文学者とともに中国からの招待旅行に出かけるところから始まる。1957年は毛沢東が共産党を批判した右派の粛清に乗り出した頃で、1966年からの文化大革命が始まる前だった。毛沢東による独裁体制が次第に固まっていく時期だったろう。
当時の中国政府は、日中戦争の責任は日本の一部の軍国主義者にあって大部分の日本国民には責任がないという対日二分論を唱えていた。(今では中国人も日本人もそんな綺麗ごとは信じていないと思うけれど。)まだ日中国交回復前のことである。
堀田は上海の街を歩きながら、戦前に共同租界やフランス租界があった頃から、日本軍の占領、国民党軍の占領、共産党軍による「解放」とその度に街の通りの名前が何度も変わったことを思い出す。
堀田は終戦直後、国民党に留用されていた頃に上海の大学で学生を前に講演をした経験があった。大学とは言え戦時中は日本軍が接収して弾薬の保管場所になり、その後国民党が接収すると米国から贈られた軍用車の集積所になっていたとか。学生たちはみなぼろを着て眼だけギラギラしていたらしい。
戦前の上海の様子は当時中国にいた欧米人による著作からの引用であるが、上海は欧米資本に牛耳られ、中国人労働者は奴隷のような扱いで子供の労働も当たり前だったらしい。終戦直後の上海を堀田は当時の上司に当たる重慶から来た国民党の役人のF氏と歩いた。米国からの支援物資は地方への配送ができずに上海の街に溢れて、その結果上海の製造業はみな潰れたとのこと。物資が地方に送れないのは共産党のせいだとF氏は言った。当時は米国が国民党と共産党の仲を取り持とうとしたが、結局は共産党が国民党を追い出すことになった。
国民党のF氏は地方の地主階級の出であったが、堀田が上海で見かけた共産党員は見るからに農民であった。堀田は共産党の農民による上海の奪取が起こりつつあると考えた。それまでは農村は都会に搾取されてきたが、農村が都市を支配するようになったのだと。
(この小説が書かれてから60年以上たって、今日の中国では再び都市が農村部を搾取しているように見えるけれど。)
堀田は1945年当時ある婦人を見舞いに病院を毎晩のように訪問していた。その時に知り合いになった中国人看護婦に堀田は1957年の上海で偶然再会し、そのことで45年当時のことをいろいろ思いだした。当時のことを書こうとしたのはそれがキッカケだったらしい。
1946年の秋、堀田が日本へ帰国する少し前に上海では労働者によるゼネストと暴動が起こったという。これを契機に上海でも国民党への支持は低下し共産党が優位に立った。
(結局1949年には毛沢東の率いる共産党が国民党を台湾へ追放し、米国は中国での足がかりを無くした。)
堀田は1957年時点で中国人自身がこれらの社会変革を「革命」ではなく「解放」と呼んでいることに注目している。これは国民の大多数を占める小作農が地主から解放されたことを主に指すらしい。当時の中国では中国人自身により目覚ましい勢いで学校や工場が建設されていて、堀田はあと「30年」で中国の国力は米国に並ぶのではと予想している。慧眼だったと思う。現実にはその2倍の60年がかかったが、中国はいまや米国と並ぶ国力を蓄えている。
そしてこの60年間に日本は経済的に中国に深く依存するようになった。中米の対立の間でどっちにもつけない日本はこのままでは衰退するしかないのかも。堀田が今の状況を見たら何を思うのかな。
お気に入り度:





掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
1957年、仙台に生まれ、結婚後10年間世田谷に住み、その後20余年横浜に住み、現在は仙台在住。本を読んで、思ったことあれこれを書いていきます。
長年、化学メーカーの研究者でした。2019年から滋賀県で大学の教員になりましたが、2023年3月に退職し、10月からは故郷の仙台に戻りました。プロフィールの写真は還暦前に米国ピッツバーグの岡の上で撮ったものです。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:集英社
- ページ数:256
- ISBN:9784087463644
- 発売日:2008年10月17日
- 価格:600円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。