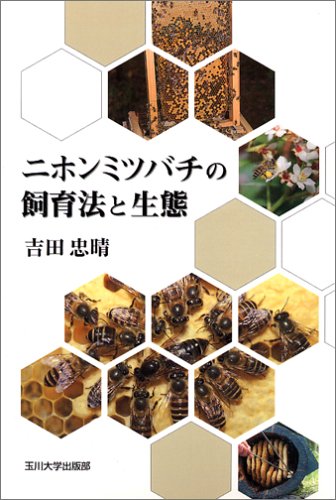ぽんきちさん
レビュアー:
▼
セイヨウミツバチは商業養蜂、ニホンミツバチは趣味養蜂
山の家で週末養蜂は可能なのか?ということで、ミツバチの本を読んで3冊目(『我が家にミツバチがやって来た』、『蜂からみた花の世界』)。
2000年発行と若干古いですが、このあたりの話はあまり古くなるということもないかなぁというところ。著者はミツバチ研究者で、ミツバチ研究では長い歴史を持つ玉川大学の教授を務めています。
本書はニホンミツバチ総論といったところ。学術寄りではありますが、一般向けに書かれていて、ミツバチに興味のある人ならば、読み物としても楽しく読めるのではないかと思います。
ニホンミツバチはトウヨウミツバチの一亜種で、日本固有の野生種です。古くは『日本書紀』に記載があるそうで、627年、推古天皇35年の箇所に、ミツバチの分蜂群についての記事があるとのこと。
明治期に、ハチミツ生産がより効率的にできるセイヨウミツバチが導入され、セイヨウミツバチに蜜源を奪われたり、蓄えた蜜を盗まれたり(盗蜂)したことから、セイヨウミツバチが生息しない山間僻地に追いやられたといわれています。
但し、ニホンミツバチは、セイヨウミツバチには壊滅的な打撃を与えるスズメバチやミツバチヘギイタダニに高い抵抗性を持ち、多様な場所で営巣することができる点が利点です。性質が温和で、燻煙器などを使う必要がない点も飼う側にとっては長所になります。
個人単位で趣味的に養蜂をしてみようと思うならば、ニホンミツバチは悪くない選択肢のようです。ミツバチと暮らしてみて、運がよければハチミツも食べられるかもよ?くらいのスタンスで始めてみるのがよいのかもしれません。
基本は、春の分蜂の際のニホンミツバチを巣箱に誘導して飼う、ということになります。ただ、ニホンミツバチは結構クセがあるというか、好き嫌いがあるようで、一度巣に誘導しても、環境が気に入らないと出て行ってしまったりするのだとか。
蜜が足りない場合には砂糖水等を給餌する必要もあります。
昔からいたというニホンミツバチ、飼育法も各地でいろいろであったようで、巣箱の形や採蜜法も地域性があります。中には採蜜の際に、蜂群は全部殺してしまうという地域もあったようで、いろいろですね。かつてよりは数が減っていることを考えると、蜂群は維持しながら、採蜜ができるとよいように思います。この辺りは、取捨選択していくのがよいのかな。
各地の例がいくつか取り上げられている中で、うちの拠点のすぐ近くの話もあったので、自生のニホンミツバチ群はいる模様です。但し、ミツバチを飼うとクマがやってくる(!)のだそうで、巣箱を2階に設置したりするとか。クマかぁ・・・。クマは困るなぁ・・・。
相変わらず、本を読んだだけだとあまりピンとこないのですが、いずれ実際やってみるとか、経験者に話を聞くとか、まぁ気長にやっていこうかなというところです。
2000年発行と若干古いですが、このあたりの話はあまり古くなるということもないかなぁというところ。著者はミツバチ研究者で、ミツバチ研究では長い歴史を持つ玉川大学の教授を務めています。
本書はニホンミツバチ総論といったところ。学術寄りではありますが、一般向けに書かれていて、ミツバチに興味のある人ならば、読み物としても楽しく読めるのではないかと思います。
ニホンミツバチはトウヨウミツバチの一亜種で、日本固有の野生種です。古くは『日本書紀』に記載があるそうで、627年、推古天皇35年の箇所に、ミツバチの分蜂群についての記事があるとのこと。
明治期に、ハチミツ生産がより効率的にできるセイヨウミツバチが導入され、セイヨウミツバチに蜜源を奪われたり、蓄えた蜜を盗まれたり(盗蜂)したことから、セイヨウミツバチが生息しない山間僻地に追いやられたといわれています。
但し、ニホンミツバチは、セイヨウミツバチには壊滅的な打撃を与えるスズメバチやミツバチヘギイタダニに高い抵抗性を持ち、多様な場所で営巣することができる点が利点です。性質が温和で、燻煙器などを使う必要がない点も飼う側にとっては長所になります。
個人単位で趣味的に養蜂をしてみようと思うならば、ニホンミツバチは悪くない選択肢のようです。ミツバチと暮らしてみて、運がよければハチミツも食べられるかもよ?くらいのスタンスで始めてみるのがよいのかもしれません。
基本は、春の分蜂の際のニホンミツバチを巣箱に誘導して飼う、ということになります。ただ、ニホンミツバチは結構クセがあるというか、好き嫌いがあるようで、一度巣に誘導しても、環境が気に入らないと出て行ってしまったりするのだとか。
蜜が足りない場合には砂糖水等を給餌する必要もあります。
昔からいたというニホンミツバチ、飼育法も各地でいろいろであったようで、巣箱の形や採蜜法も地域性があります。中には採蜜の際に、蜂群は全部殺してしまうという地域もあったようで、いろいろですね。かつてよりは数が減っていることを考えると、蜂群は維持しながら、採蜜ができるとよいように思います。この辺りは、取捨選択していくのがよいのかな。
各地の例がいくつか取り上げられている中で、うちの拠点のすぐ近くの話もあったので、自生のニホンミツバチ群はいる模様です。但し、ミツバチを飼うとクマがやってくる(!)のだそうで、巣箱を2階に設置したりするとか。クマかぁ・・・。クマは困るなぁ・・・。
相変わらず、本を読んだだけだとあまりピンとこないのですが、いずれ実際やってみるとか、経験者に話を聞くとか、まぁ気長にやっていこうかなというところです。
掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
分子生物学・生化学周辺の実務翻訳をしています。
本の大海を漂流中。
日々是好日。どんな本との出会いも素敵だ。
あちらこちらとつまみ食いの読書ですが、点が線に、線が面になっていくといいなと思っています。
「実感」を求めて読書しているように思います。
赤柴♀(もも)は3代目。
この夏、有精卵からヒヨコ4羽を孵化させました。そろそろ大雛かな。♂x2、♀x2。ニワトリは割と人に懐くものらしいですが、今のところ、懐く気配はありませんw
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:玉川大学出版部
- ページ数:136
- ISBN:9784472400810
- 発売日:2000年01月25日
- 価格:2100円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。