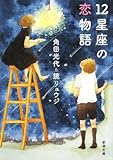darklyさん
レビュアー:
▼
揺るぎない自分を持っている人はいない。
この本はかなり昔に読んだのですが、数年前に電子書籍のクーポンがあってダウンロードできる中に本書があり、ダウンロードしたまま積読(積電)となっていたものを出張の移動時間や手持無沙汰の時間で再読しました。
ご存知のとおり、カズオ・イシグロの小説は記憶が重要な役割を果たします。話が現在進行しながら回想が挿入され話の全容が明らかになる手法です。本作品もその構成を取りながら戦前・戦後を生きた主人公で画家の小野の揺れ動く心を描いた作品です。
画家として一定の地位を築いた小野は未だに戦前・戦中の亡霊に悩まされている。小野はその当時の時代の空気である政府や戦争を肯定する姿勢を取っていたが、戦後の空気は一変し、若者を中心に政府及び体制側についたものを非難する空気が支配的となる。
大衆はいつの時代も以前の自分たちの考えや行動は棚に上げ、小野のような著名人に直接・間接に非難の矛先を向ける。戦争賛美者としてのレッテルが娘の縁談や娘婿との関係にも暗い影を落とす。以前は自分だけでなく日本全体がそのような雰囲気だったのだと主張したところで詮無いことである。
小野は絵画の世界においても師匠や弟子を裏切った過去もある。それは小野としてはもちろん裏切りではなく、自分の信念を貫いた結果だと自分に言い聞かせているが、その心も揺れ動く。
人は社会あるいは世間という大きな波を構成していると同時にその波に漂う存在です。人はその波に乗っていると感じれば高揚感を得ることもあるでしょう。そして波に乗れていないと感じれば疎外感を感じるかもしれません。
それは時代が大きく動く時には特に感じられるでしょうし、また著名人であれば尚更でしょう。しかし、実は個人が思っているほど世間はその個人のことについて何も思っていないのが真理のような気がします。そもそも世間というものには実体がなく幻影のようなものだと言えます。
小野は娘の何気ない言葉の裏に隠されていると勘繰る世間の自分に対する評価に怯え、その懸念を払拭しようと空回りします。これは丸谷才一の「笹まくら」の主人公の心情に似ているような気がします。信念を持ってリスクを冒し成功したという自負心を持ち、そうでない平凡な者を蔑みます。自己を肯定するために同じような信念を持った死にゆく友も自分と同じように人生に満足しているのだろうと考えます。絵画での考え方の違いにより袂を分かった師匠が没落し、自分が成功したことに満足感を覚える卑小性も持ちます。すべては世間という幻影に戦いを挑んでいるといえ、さながらドン・キホーテのようです。
世間の波つまり浮世に漂いながら自己肯定と自己否定を繰り返す小野の心の揺れはそのまますべての人にもあるように思います。自己肯定も他人の評価ではなく自分自身の中から出てきた自信や誇りを元にしなければ浮世と共にはかなく移ろいゆくものなのでしょう。当初この小説は東洋的な情緒を表現したものとして評価された後に、文化を問わず普遍的に共通するものであるとの評価を得ています。もっと言えば人類が社会を築いたときから個人と社会の間で繰り返されてきたものなのかもしれません。主人公を画家としたのは、まさに絵画とは本質的に移ろいゆく浮世での一瞬の美を切り取るものであり、その象徴として相応しいとカズオ・イシグロが考えたのではないでしょうか。
日本にいた頃の記憶がほとんどないカズオ・イシグロは、自分のイメージを頼りに日本を描きますが、やはり少しだけ違和感を感じることがあります。この物語では小野の孫である一郎の言動と行動が、うまく言えないのですが、「こういったことを聞かれたときはこう反応する、あるいは行動する」という日本文化をプログラミングされたアンドロイドの反応のような不自然な感じがします。
カズオ・イシグロは新作が出れば必ず読む作家の一人です。できればもう少し執筆のペースが速ければ良いのですが。
ご存知のとおり、カズオ・イシグロの小説は記憶が重要な役割を果たします。話が現在進行しながら回想が挿入され話の全容が明らかになる手法です。本作品もその構成を取りながら戦前・戦後を生きた主人公で画家の小野の揺れ動く心を描いた作品です。
画家として一定の地位を築いた小野は未だに戦前・戦中の亡霊に悩まされている。小野はその当時の時代の空気である政府や戦争を肯定する姿勢を取っていたが、戦後の空気は一変し、若者を中心に政府及び体制側についたものを非難する空気が支配的となる。
大衆はいつの時代も以前の自分たちの考えや行動は棚に上げ、小野のような著名人に直接・間接に非難の矛先を向ける。戦争賛美者としてのレッテルが娘の縁談や娘婿との関係にも暗い影を落とす。以前は自分だけでなく日本全体がそのような雰囲気だったのだと主張したところで詮無いことである。
小野は絵画の世界においても師匠や弟子を裏切った過去もある。それは小野としてはもちろん裏切りではなく、自分の信念を貫いた結果だと自分に言い聞かせているが、その心も揺れ動く。
人は社会あるいは世間という大きな波を構成していると同時にその波に漂う存在です。人はその波に乗っていると感じれば高揚感を得ることもあるでしょう。そして波に乗れていないと感じれば疎外感を感じるかもしれません。
それは時代が大きく動く時には特に感じられるでしょうし、また著名人であれば尚更でしょう。しかし、実は個人が思っているほど世間はその個人のことについて何も思っていないのが真理のような気がします。そもそも世間というものには実体がなく幻影のようなものだと言えます。
小野は娘の何気ない言葉の裏に隠されていると勘繰る世間の自分に対する評価に怯え、その懸念を払拭しようと空回りします。これは丸谷才一の「笹まくら」の主人公の心情に似ているような気がします。信念を持ってリスクを冒し成功したという自負心を持ち、そうでない平凡な者を蔑みます。自己を肯定するために同じような信念を持った死にゆく友も自分と同じように人生に満足しているのだろうと考えます。絵画での考え方の違いにより袂を分かった師匠が没落し、自分が成功したことに満足感を覚える卑小性も持ちます。すべては世間という幻影に戦いを挑んでいるといえ、さながらドン・キホーテのようです。
世間の波つまり浮世に漂いながら自己肯定と自己否定を繰り返す小野の心の揺れはそのまますべての人にもあるように思います。自己肯定も他人の評価ではなく自分自身の中から出てきた自信や誇りを元にしなければ浮世と共にはかなく移ろいゆくものなのでしょう。当初この小説は東洋的な情緒を表現したものとして評価された後に、文化を問わず普遍的に共通するものであるとの評価を得ています。もっと言えば人類が社会を築いたときから個人と社会の間で繰り返されてきたものなのかもしれません。主人公を画家としたのは、まさに絵画とは本質的に移ろいゆく浮世での一瞬の美を切り取るものであり、その象徴として相応しいとカズオ・イシグロが考えたのではないでしょうか。
日本にいた頃の記憶がほとんどないカズオ・イシグロは、自分のイメージを頼りに日本を描きますが、やはり少しだけ違和感を感じることがあります。この物語では小野の孫である一郎の言動と行動が、うまく言えないのですが、「こういったことを聞かれたときはこう反応する、あるいは行動する」という日本文化をプログラミングされたアンドロイドの反応のような不自然な感じがします。
カズオ・イシグロは新作が出れば必ず読む作家の一人です。できればもう少し執筆のペースが速ければ良いのですが。
お気に入り度:







掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
昔からずっと本は読み続けてます。フィクション・ノンフィクション問わず、あまりこだわりなく読んでます。フィクションはSF・ホラー・ファンタジーが比較的多いです。あと科学・数学・思想的な本を好みます。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:早川書房
- ページ数:319
- ISBN:9784151200397
- 発売日:2006年11月01日
- 価格:756円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。