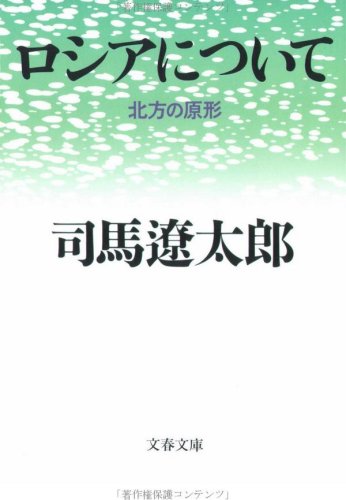三太郎さん
レビュアー:
▼
司馬遼太郎が語るロシアとシベリアの歴史。
これは1986年(僕が就職した年)に出た本で、司馬さんがロシアの歴史について考察している。まだペレストロイカが始まったばかりで、ロシアは当時はソ連と呼ばれる共産党独裁の国だった。その後共産主義体制が崩れて民主化されたと思ったら、ロシアはまた独裁国家になってしまっている。
そしてロシアが隣国ウクライナに軍事侵攻して一年以上が経過した。この軍事侵攻に関して僕は今でも理解しかねる個人的体験をした。僕の近親者が僕に対して、ロシアの歴史を学べば今回の軍事侵攻は正しいと解るのだ、と主張したのだ。この近親者のいうロシアの歴史とは何を指すのか、何の説明もなかったから僕は戸惑うばかりだった。歴史云々など無関係に戦車で隣国の国境を侵す行為は、正当化しがたいと僕は答えたのだが。
司馬さんはロシアという国の成立が西欧や日本よりずっと遅かったことを指摘している。ロシアという土地は東の遊牧民族の通り過ぎる通路のような場所にあって、ロシアの農民はいつも遊牧民から虐げられてきた。特にモンゴル帝国が支配してからは、ロシアの農民はモンゴル人の農奴として生きるしかなかった。のちにモスクワを中心としてロシア国が成立したが、社会のありようはモンゴル人がロシア人の貴族に置き換わっただけだった。つまり農民は小作人としての農奴のままで、自営農民は存在しなかった。西欧や日本では封建制度の中で自営農民が現われて、国民国家の基盤となっていったと思われるが、ロシアでは20世紀のロシア革命の時まで農民は農奴のままで、社会の成熟度が西欧や日本とは比べものにならなかった。
近代のロシア帝国が周辺地域を侵略し略奪する国家だったのは、古のモンゴル帝国のやり方を習ったものだったのかも知れない。
また、ロシアに国民国家へと成熟する時間がなかったことが、共産主義体制が崩壊した後にプーチンの独裁体制が成立した原因なのかも。ロシアの民主化は遠い将来のことなのかもしれないなあ。
一方のウクライナはモンゴルの支配を受ける前、9世紀にはすでに北方のバイキングによってキーウを中心とした国家が成立していたので、ロシアよりは成熟した近代国家なのかもしれない。もっとも司馬さんは当時はソ連に属していたウクライナについてはあまり触れていないが。
僕らの知っているロシア帝国が成立したのは16世紀後半のイワン雷帝の時代にロシアがウラル山脈の東側に進出し、遊牧民国家のシビル・ハン国を滅ぼして、シベリアをロシア帝国の版図に組み込んでからだろう。このシベリア征服にはあのコザックが関わっていた。コザックとは元はトルコ系遊牧民がハザクと呼んだ連中で、遊牧民の集団からのあぶれ者という意味らしい。誰にも従わず、川伝いに少人数で行動し、略奪行為を行う謂わばお尋ね者だった。そんな彼らが皇帝からシベリア略奪を受け負ったらしい。
ロシアはその頃から傭兵を使って周辺国を侵略するスタイルをとっていた。この度のウクライナへの侵略でも傭兵部隊(ワグネル)を活用している。そしてこの傭兵が反乱を起こす危険があるのも、コザックを使った頃から変わらない。
後半の主な話題は、シベリアの周辺地域へのロシアの進出だ。日本の幕末の頃までアラスカはロシア領で、そこでラッコの毛皮を集めて欧州へ売るために露米会社というものが作られた。大株主はロシア皇帝でトップはロシア貴族だった。これが鎖国の日本と通商しようとして何度も接触してきたが、幕府により拒絶された。米国のペリーは武力をちらつかせて幕府に対して高圧的だったが、それと比較してロシアは紳士的だった。
もう一つの周辺はモンゴル高原で、清朝の圧政に苦しんだモンゴル人はロシアに助けを求めたという。遊牧で暮らしてきたモンゴル人は中国よりロシアに親しみを感じたらしい。
最後の話題は今ロシアが占拠しているクリミア半島について。第二次大戦末期にここのヤルタで連合国側の三首脳が戦後処理について会談したが、このクリミア半島は紀元前にスキタイ人が遊牧を始めた土地であった。つまり遊牧文化の発祥の地だった。
学生時代はモンゴル語専攻で遊牧民族が好きだった司馬さんの語るロシアは独特の視点がある。ご存命だったら今度のロシアのウクライナ侵攻について何を語ったろうか。
この本を読み終わっての感想ですが、歴史からはロシアの軍事進攻を正当化する根拠は何も見出せなかったとだけ書いておこうと思います。
そしてロシアが隣国ウクライナに軍事侵攻して一年以上が経過した。この軍事侵攻に関して僕は今でも理解しかねる個人的体験をした。僕の近親者が僕に対して、ロシアの歴史を学べば今回の軍事侵攻は正しいと解るのだ、と主張したのだ。この近親者のいうロシアの歴史とは何を指すのか、何の説明もなかったから僕は戸惑うばかりだった。歴史云々など無関係に戦車で隣国の国境を侵す行為は、正当化しがたいと僕は答えたのだが。
司馬さんはロシアという国の成立が西欧や日本よりずっと遅かったことを指摘している。ロシアという土地は東の遊牧民族の通り過ぎる通路のような場所にあって、ロシアの農民はいつも遊牧民から虐げられてきた。特にモンゴル帝国が支配してからは、ロシアの農民はモンゴル人の農奴として生きるしかなかった。のちにモスクワを中心としてロシア国が成立したが、社会のありようはモンゴル人がロシア人の貴族に置き換わっただけだった。つまり農民は小作人としての農奴のままで、自営農民は存在しなかった。西欧や日本では封建制度の中で自営農民が現われて、国民国家の基盤となっていったと思われるが、ロシアでは20世紀のロシア革命の時まで農民は農奴のままで、社会の成熟度が西欧や日本とは比べものにならなかった。
近代のロシア帝国が周辺地域を侵略し略奪する国家だったのは、古のモンゴル帝国のやり方を習ったものだったのかも知れない。
また、ロシアに国民国家へと成熟する時間がなかったことが、共産主義体制が崩壊した後にプーチンの独裁体制が成立した原因なのかも。ロシアの民主化は遠い将来のことなのかもしれないなあ。
一方のウクライナはモンゴルの支配を受ける前、9世紀にはすでに北方のバイキングによってキーウを中心とした国家が成立していたので、ロシアよりは成熟した近代国家なのかもしれない。もっとも司馬さんは当時はソ連に属していたウクライナについてはあまり触れていないが。
僕らの知っているロシア帝国が成立したのは16世紀後半のイワン雷帝の時代にロシアがウラル山脈の東側に進出し、遊牧民国家のシビル・ハン国を滅ぼして、シベリアをロシア帝国の版図に組み込んでからだろう。このシベリア征服にはあのコザックが関わっていた。コザックとは元はトルコ系遊牧民がハザクと呼んだ連中で、遊牧民の集団からのあぶれ者という意味らしい。誰にも従わず、川伝いに少人数で行動し、略奪行為を行う謂わばお尋ね者だった。そんな彼らが皇帝からシベリア略奪を受け負ったらしい。
ロシアはその頃から傭兵を使って周辺国を侵略するスタイルをとっていた。この度のウクライナへの侵略でも傭兵部隊(ワグネル)を活用している。そしてこの傭兵が反乱を起こす危険があるのも、コザックを使った頃から変わらない。
後半の主な話題は、シベリアの周辺地域へのロシアの進出だ。日本の幕末の頃までアラスカはロシア領で、そこでラッコの毛皮を集めて欧州へ売るために露米会社というものが作られた。大株主はロシア皇帝でトップはロシア貴族だった。これが鎖国の日本と通商しようとして何度も接触してきたが、幕府により拒絶された。米国のペリーは武力をちらつかせて幕府に対して高圧的だったが、それと比較してロシアは紳士的だった。
もう一つの周辺はモンゴル高原で、清朝の圧政に苦しんだモンゴル人はロシアに助けを求めたという。遊牧で暮らしてきたモンゴル人は中国よりロシアに親しみを感じたらしい。
最後の話題は今ロシアが占拠しているクリミア半島について。第二次大戦末期にここのヤルタで連合国側の三首脳が戦後処理について会談したが、このクリミア半島は紀元前にスキタイ人が遊牧を始めた土地であった。つまり遊牧文化の発祥の地だった。
学生時代はモンゴル語専攻で遊牧民族が好きだった司馬さんの語るロシアは独特の視点がある。ご存命だったら今度のロシアのウクライナ侵攻について何を語ったろうか。
この本を読み終わっての感想ですが、歴史からはロシアの軍事進攻を正当化する根拠は何も見出せなかったとだけ書いておこうと思います。
お気に入り度:







掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
1957年、仙台に生まれ、結婚後10年間世田谷に住み、その後20余年横浜に住み、現在は仙台在住。本を読んで、思ったことあれこれを書いていきます。
長年、化学メーカーの研究者でした。2019年から滋賀県で大学の教員になりましたが、2023年3月に退職し、10月からは故郷の仙台に戻りました。プロフィールの写真は還暦前に米国ピッツバーグの岡の上で撮ったものです。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:文藝春秋
- ページ数:259
- ISBN:9784167105587
- 発売日:1989年06月01日
- 価格:530円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。