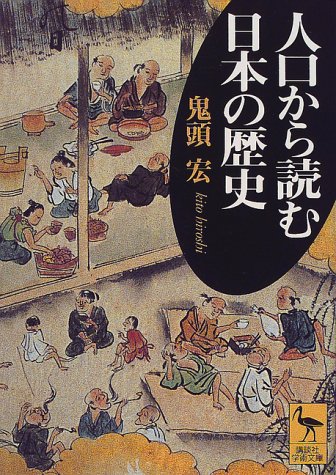三太郎さん
レビュアー:
▼
江戸時代の堕胎や間引きは農家が余裕のある生活を守るために行った出産制限だったという驚くべき事実が示されています。
著者は歴史人口学の研究者で、本書は1987年刊行の「日本二千年の人口史」を底本として、2000年に文庫化された。
縄文時代の人骨から推測した寿命に関するデータが載っていて、15歳まで生きていた場合の平均寿命が男女とも31歳だった。新生児の23歳までの生存率が26%とすると、人口を維持するには一人の女性が平均8名の子供を産む必要があったことになる。しかし15歳から31歳まで16年間で8人の子供を産むのは生物として限界に近く、疑問があったようだ。
(最近の研究ではこの遺骨の解析結果に異論があり、それによると寿命は1.5倍は長かったことになるそうです。平均で46歳くらいまで生きられたのかもしれません。)
縄文時代の人口は縄文中期にピークを迎え、気候変動の影響でその後減少する。最盛期の人口は25万人で、大部分は東日本に偏っていたようだ。ただし人口は遺骨による推定なので誤差は大きそうだ。
弥生時代になると稲作により人口は急速に増加したが、農業が人口増加の理由だとは言い切れないらしい。炭水化物中心の食事ではタンパク質が不足し却って寿命が短くなった可能性がある。そのため大陸からの移住者による人口増の可能性も否定できないようだ。
弥生時代の人口は集落跡の解析から約60万人、3世紀の人口は魏志倭人伝の記述から180万人、8世紀には出挙稲数からの推定で560万人と増えていった。10世紀には人口の増加は停滞した。その後14世紀までの人口ははっきりしないが、弥生時代以降は西日本に人口中心があったのが、10世紀以降は東日本の人口が追い付いてきて、人口中心は京都から琵琶湖のあたりに移動したとか。
江戸時代の人口は宗門改帳などにより細かく調べることができる。17世紀初頭の人口は1200万人程度でその後の150年間は人口が3倍に増加し、その後は幕末まで人口はほぼ横ばいになる。しかし詳しく見ると、西日本ではその間も人口は増え続けており、一方東北の太平洋側から北関東では小氷期の冷夏による凶作で人口減少が認められた。従って全国一律に人口増が止まっていた訳ではなかった。東北でも冷夏でない時期には人口は増えている。
江戸期の前半の人口増の期間では農村の一家族の人数が減少していき、大家族から核家族へと変化していた。農家の大規模経営から家族経営への移行がはっきり表れた。この間に人口が3倍に増加した訳だ。つまり大家族ではそれまで一生涯独身だった次男三男や下人が独立して結婚できるようになったので人口が増加したと考えられる。
一方、江戸期の後半では堕胎や新生児の間引きにより産児制限していた様子が伺われる。しかしこれは、一般に言われているように、生活に困窮したからではなく、ゆとりのある生活を守るためだったと思われる。(子供が多ければ田畑を分けて分家しなければならなくなるから。)実際にこの間の田畑の生産性は向上していて、出産制限によって蓄財できるようになったのが江戸期の農民だった。
江戸時代の小児科医の本には、新生児には乳母をあてがわずに自分の母乳で育てると次の子供が出来にくいと推奨されている。できれば数え年で5歳までは母乳を与えるとよいとか。
農村の女性は20歳〜40歳過ぎまで約4年に一人を生んでいたが、死産の割合は10%以上と高かった。またほぼ等間隔に出産していることからも間引きによる出産制限が推測される。また石高が5石以上の農家と比べて、5石未満の農家は子供の数が1人分少なかった。乳幼児の死亡率が高く、集落全体としては女性が平均四人の子供を育てないと集落が維持できないが、5石未満の農家では家が絶え、その分を5石以上の農家の分家がカバーしていた。(農村でも貧富の差は大きかったのだろうな。)
なお、冷害や疫病による人口減少が度々あった東北や関東では、生活困窮による間引きもあったようで、幾つかの藩では妊婦を監視し間引きを抑制するとともに育児手当を支給したという。日本は地方により事情が異なり一様ではなかったらしい。
江戸や大坂などの大都市ではかなりの人口が農村からの出稼ぎ者で未婚だったため、都市部の出生率は低く、地方からの流入により人口を保っていたとか。出稼ぎに出た女性は農村に帰ってから結婚したが晩婚のため、生める子供の人数は少なくなった。つまり都市が人口調整の役割を演じていた。(この辺は現代の少子化の事情にも通じるものがありそうだ。)
江戸時代後期の人口増加が停滞していた時期は農村が裕福になっていった時期だったという指摘が印象的でした。この頃の日本人の多くは家族経営の自営農であり、自分たちの資産を守る意識が高かったのでしょう。それが明治以降の日本の発展の原動力だったのかも。
縄文時代の人骨から推測した寿命に関するデータが載っていて、15歳まで生きていた場合の平均寿命が男女とも31歳だった。新生児の23歳までの生存率が26%とすると、人口を維持するには一人の女性が平均8名の子供を産む必要があったことになる。しかし15歳から31歳まで16年間で8人の子供を産むのは生物として限界に近く、疑問があったようだ。
(最近の研究ではこの遺骨の解析結果に異論があり、それによると寿命は1.5倍は長かったことになるそうです。平均で46歳くらいまで生きられたのかもしれません。)
縄文時代の人口は縄文中期にピークを迎え、気候変動の影響でその後減少する。最盛期の人口は25万人で、大部分は東日本に偏っていたようだ。ただし人口は遺骨による推定なので誤差は大きそうだ。
弥生時代になると稲作により人口は急速に増加したが、農業が人口増加の理由だとは言い切れないらしい。炭水化物中心の食事ではタンパク質が不足し却って寿命が短くなった可能性がある。そのため大陸からの移住者による人口増の可能性も否定できないようだ。
弥生時代の人口は集落跡の解析から約60万人、3世紀の人口は魏志倭人伝の記述から180万人、8世紀には出挙稲数からの推定で560万人と増えていった。10世紀には人口の増加は停滞した。その後14世紀までの人口ははっきりしないが、弥生時代以降は西日本に人口中心があったのが、10世紀以降は東日本の人口が追い付いてきて、人口中心は京都から琵琶湖のあたりに移動したとか。
江戸時代の人口は宗門改帳などにより細かく調べることができる。17世紀初頭の人口は1200万人程度でその後の150年間は人口が3倍に増加し、その後は幕末まで人口はほぼ横ばいになる。しかし詳しく見ると、西日本ではその間も人口は増え続けており、一方東北の太平洋側から北関東では小氷期の冷夏による凶作で人口減少が認められた。従って全国一律に人口増が止まっていた訳ではなかった。東北でも冷夏でない時期には人口は増えている。
江戸期の前半の人口増の期間では農村の一家族の人数が減少していき、大家族から核家族へと変化していた。農家の大規模経営から家族経営への移行がはっきり表れた。この間に人口が3倍に増加した訳だ。つまり大家族ではそれまで一生涯独身だった次男三男や下人が独立して結婚できるようになったので人口が増加したと考えられる。
一方、江戸期の後半では堕胎や新生児の間引きにより産児制限していた様子が伺われる。しかしこれは、一般に言われているように、生活に困窮したからではなく、ゆとりのある生活を守るためだったと思われる。(子供が多ければ田畑を分けて分家しなければならなくなるから。)実際にこの間の田畑の生産性は向上していて、出産制限によって蓄財できるようになったのが江戸期の農民だった。
江戸時代の小児科医の本には、新生児には乳母をあてがわずに自分の母乳で育てると次の子供が出来にくいと推奨されている。できれば数え年で5歳までは母乳を与えるとよいとか。
農村の女性は20歳〜40歳過ぎまで約4年に一人を生んでいたが、死産の割合は10%以上と高かった。またほぼ等間隔に出産していることからも間引きによる出産制限が推測される。また石高が5石以上の農家と比べて、5石未満の農家は子供の数が1人分少なかった。乳幼児の死亡率が高く、集落全体としては女性が平均四人の子供を育てないと集落が維持できないが、5石未満の農家では家が絶え、その分を5石以上の農家の分家がカバーしていた。(農村でも貧富の差は大きかったのだろうな。)
なお、冷害や疫病による人口減少が度々あった東北や関東では、生活困窮による間引きもあったようで、幾つかの藩では妊婦を監視し間引きを抑制するとともに育児手当を支給したという。日本は地方により事情が異なり一様ではなかったらしい。
江戸や大坂などの大都市ではかなりの人口が農村からの出稼ぎ者で未婚だったため、都市部の出生率は低く、地方からの流入により人口を保っていたとか。出稼ぎに出た女性は農村に帰ってから結婚したが晩婚のため、生める子供の人数は少なくなった。つまり都市が人口調整の役割を演じていた。(この辺は現代の少子化の事情にも通じるものがありそうだ。)
江戸時代後期の人口増加が停滞していた時期は農村が裕福になっていった時期だったという指摘が印象的でした。この頃の日本人の多くは家族経営の自営農であり、自分たちの資産を守る意識が高かったのでしょう。それが明治以降の日本の発展の原動力だったのかも。
お気に入り度:





掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
1957年、仙台に生まれ、結婚後10年間世田谷に住み、その後20余年横浜に住み、現在は仙台在住。本を読んで、思ったことあれこれを書いていきます。
長年、化学メーカーの研究者でした。2019年から滋賀県で大学の教員になりましたが、2023年3月に退職し、10月からは故郷の仙台に戻りました。プロフィールの写真は還暦前に米国ピッツバーグの岡の上で撮ったものです。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:
- ページ数:288
- ISBN:9784061594302
- 発売日:2000年05月10日
- 価格:1008円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。