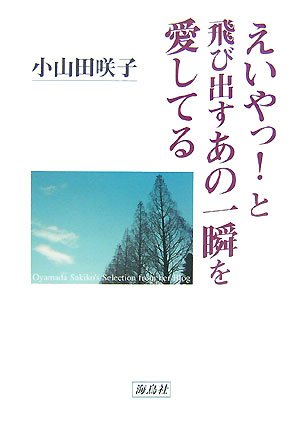ウロボロスさん
レビュアー:
▼
この本の帯や序文を著名な劇作家・演出家である鴻上尚史氏がどうして引受けたのか?その疑問が解けました。この序文を読んだだけですでにして名作の予感がします。
冒頭から身も蓋もない話をしますが、著者小山田咲子さんは2005年9月に旅行先のアルゼンチンで同乗していた車が横転し、24歳で亡くなられています。もうこの世にはいません。この車を運転していた人は著名な写真家であり登山家、冒険家で、戦後文学の中でも異彩を放ち人口に膾炙している芥川賞作家のお孫さんでもあります。
大学生(早稲田大学卒業)とは思えない思考の弾力性みたいなものを感じました。そしてそれの言語化への巧みさにおいて、将来は物書きとして大成するであろうと思われました。
その早すぎる死を悼む言葉が見つかりません。
その才能は小学生の頃からめばえていて詩や作文や歌で発揮され、高校や大学に進学してその才能はさらに開花したようです。
いろいろと心に沁みる文章がありますが咲子さんの確信というか核心のなかのひとつが、次の文章に、込められているような気がします。
《どんなに深くサンタクロースを信じた子どもでも、いずれはその正体を知り、枕もとにプレゼントの無いクリスマスの朝を迎えるようになる。
でも目には見えない大きな不思議な存在を一度真っ直ぐに信じた事実は消えないし、それは同じ誠実さで他の何かを信じることができる場所を心のなかに培うということだと思う。》
今に生きるわれわれはこの「大きな不思議な存在」を忘れ、蔑ろにしてきたのではないでしょうか?以下にこの本を読みながらメモした箇所をランダムに記載します。
黒四ダムからの中島みゆきの紅白中継のLive評は、秀逸である。本のタイトル買いの事例も面白い!
『燃え上がる緑の木』『夏の朝の成層圏』『風濤』『神様のボート』『落日燃ゆ』『光の帝国』『僕は勉強ができない』『天涯の花』『最終便に間に合えば』『ずいぶんなおねだり』『優しくって少しばか』『僕に踏まれた町と僕が踏まれた町』『あたしが海に還るまで』など等。
ぱつんぱつんな顔で80年代アイドル写真集みたいなメモリアルアルバムのできあがり。この「ぱつんぱつん」という表現がたまらなく好き。
『呪術の帝国 秘境チンチェーロ』三浦信行著
で超越的なるもの(信仰や宗教)への観想とインド旅行における祈り人への畏敬に著者のセンスの鋭敏なしなやかさを感じた。
あの金八先生にモデルがいたことや、あの9.11テロの被害者に現役の早稲田の大学生がいたこともこの本で初めて知った。
2003/2/3の『ばあちゃん』の日記の最後の文章が切なすぎる。
論理的な思考の帰結としての「本質的な正しさ」についての著者の意見に心うたれた。
「圧倒的に正しいその言葉の中の、温度の無い正しさが私には恐ろしい」と。
ブライアン・イーノのBy this Riverへの言及とその曲を使用した映画のワンシーンの描写が秀逸である。
とにかく言葉への距離のとり方とより添い方に煌めくような才能を感じた。「春めく」を皮切りにした「きらめく」「ざわめく」「さざめく」「どよめく」「ときめく」などの「〜めく」への考察に重層的な感性の迸りがそれこそきらめいていました。
『青のり』のエピソードにはくすっ くすっ最後は大爆笑させられました。そしてストーンズの東京ドームLiveでの著者の立ち居振る舞いには心から同意します。(笑)。そして涙………。ストーンズ、最高!
この本のタイトルであるワードがでてくる『北にむいた岬のように』には、この時の著者の心情が著者が生きてきた時代をを遡行し還流し貫通し、共有的で共時的な時間の断面としてみごとに凝縮されていると感じた。
バイト先で羊のモノマネをしたり「あのおじさんとおばさんはデキている」と著者に言い寄ってくる美術史学専攻のバイト仲間のYちゃん!今どうされているのだろうか?
F・コッポラ制作、ゴッドフリー・レジオ監督の映画『コヤニスカッティ』を観ての感想も秀逸。
「バランスを欠いて膨れ上がった知性はどこかで破壊されなければならない」「自分が痛みを知るまで他者の痛みを知れないというのは悲しいことだと思う」
この映画を観たあとのある種の爽快感と後ろめたさは、9.11の衝撃が自身が寄りかかっているものの脆さを目の当たりにしたことへの恐怖かもしれない。と告白している。
諏訪の御柱祭における地方と都市の関係を自然と伝統文化に根付いた生活を時間の積層の連続性として捉えて相対化し普遍化するその言葉の表現の巧みさに惹かれる。
「こんな故郷を誰でもが持てるわけではない。自分の存在に、時間と空間に裏打ちされた確固たる寄る辺があるのは、その不自由さを差し引いても、幸せなことだと思う」と。
駄文にして長文になってしまいましたがまだまだ書き足りないことがありますが……。
自分は知らなかったのですがこの本の中にも登場する弟の小山田 壮平さんは、ロックバンドandymoriの元ギター・ボーカルでインディーズ界ではカリスマ的なミュージシャンだったそうです。現在はソロ及び4人組バンドALで活動され福岡県福岡市在住で妻はPredawnとして活動する清水美和子さんだそうです。
大学生(早稲田大学卒業)とは思えない思考の弾力性みたいなものを感じました。そしてそれの言語化への巧みさにおいて、将来は物書きとして大成するであろうと思われました。
その早すぎる死を悼む言葉が見つかりません。
その才能は小学生の頃からめばえていて詩や作文や歌で発揮され、高校や大学に進学してその才能はさらに開花したようです。
いろいろと心に沁みる文章がありますが咲子さんの確信というか核心のなかのひとつが、次の文章に、込められているような気がします。
《どんなに深くサンタクロースを信じた子どもでも、いずれはその正体を知り、枕もとにプレゼントの無いクリスマスの朝を迎えるようになる。
でも目には見えない大きな不思議な存在を一度真っ直ぐに信じた事実は消えないし、それは同じ誠実さで他の何かを信じることができる場所を心のなかに培うということだと思う。》
今に生きるわれわれはこの「大きな不思議な存在」を忘れ、蔑ろにしてきたのではないでしょうか?以下にこの本を読みながらメモした箇所をランダムに記載します。
黒四ダムからの中島みゆきの紅白中継のLive評は、秀逸である。本のタイトル買いの事例も面白い!
『燃え上がる緑の木』『夏の朝の成層圏』『風濤』『神様のボート』『落日燃ゆ』『光の帝国』『僕は勉強ができない』『天涯の花』『最終便に間に合えば』『ずいぶんなおねだり』『優しくって少しばか』『僕に踏まれた町と僕が踏まれた町』『あたしが海に還るまで』など等。
ぱつんぱつんな顔で80年代アイドル写真集みたいなメモリアルアルバムのできあがり。この「ぱつんぱつん」という表現がたまらなく好き。
『呪術の帝国 秘境チンチェーロ』三浦信行著
で超越的なるもの(信仰や宗教)への観想とインド旅行における祈り人への畏敬に著者のセンスの鋭敏なしなやかさを感じた。
あの金八先生にモデルがいたことや、あの9.11テロの被害者に現役の早稲田の大学生がいたこともこの本で初めて知った。
2003/2/3の『ばあちゃん』の日記の最後の文章が切なすぎる。
論理的な思考の帰結としての「本質的な正しさ」についての著者の意見に心うたれた。
「圧倒的に正しいその言葉の中の、温度の無い正しさが私には恐ろしい」と。
ブライアン・イーノのBy this Riverへの言及とその曲を使用した映画のワンシーンの描写が秀逸である。
とにかく言葉への距離のとり方とより添い方に煌めくような才能を感じた。「春めく」を皮切りにした「きらめく」「ざわめく」「さざめく」「どよめく」「ときめく」などの「〜めく」への考察に重層的な感性の迸りがそれこそきらめいていました。
『青のり』のエピソードにはくすっ くすっ最後は大爆笑させられました。そしてストーンズの東京ドームLiveでの著者の立ち居振る舞いには心から同意します。(笑)。そして涙………。ストーンズ、最高!
この本のタイトルであるワードがでてくる『北にむいた岬のように』には、この時の著者の心情が著者が生きてきた時代をを遡行し還流し貫通し、共有的で共時的な時間の断面としてみごとに凝縮されていると感じた。
バイト先で羊のモノマネをしたり「あのおじさんとおばさんはデキている」と著者に言い寄ってくる美術史学専攻のバイト仲間のYちゃん!今どうされているのだろうか?
F・コッポラ制作、ゴッドフリー・レジオ監督の映画『コヤニスカッティ』を観ての感想も秀逸。
「バランスを欠いて膨れ上がった知性はどこかで破壊されなければならない」「自分が痛みを知るまで他者の痛みを知れないというのは悲しいことだと思う」
この映画を観たあとのある種の爽快感と後ろめたさは、9.11の衝撃が自身が寄りかかっているものの脆さを目の当たりにしたことへの恐怖かもしれない。と告白している。
諏訪の御柱祭における地方と都市の関係を自然と伝統文化に根付いた生活を時間の積層の連続性として捉えて相対化し普遍化するその言葉の表現の巧みさに惹かれる。
「こんな故郷を誰でもが持てるわけではない。自分の存在に、時間と空間に裏打ちされた確固たる寄る辺があるのは、その不自由さを差し引いても、幸せなことだと思う」と。
駄文にして長文になってしまいましたがまだまだ書き足りないことがありますが……。
自分は知らなかったのですがこの本の中にも登場する弟の小山田 壮平さんは、ロックバンドandymoriの元ギター・ボーカルでインディーズ界ではカリスマ的なミュージシャンだったそうです。現在はソロ及び4人組バンドALで活動され福岡県福岡市在住で妻はPredawnとして活動する清水美和子さんだそうです。
掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
これまで読んできた作家。村上春樹、丸山健二、中上健次、笠井潔、桐山襲、五木寛之、大江健三郎、松本清張、伊坂幸太郎
堀江敏幸、多和田葉子、中原清一郎、等々...です。
音楽は、洋楽、邦楽問わず70年代、80年代を中心に聴いてます。初めて行ったLive Concertが1979年のエリック・クラプトンです。好きなアーティストはボブ・ディランです。
格闘技(UFC)とソフトバンク・ホークス(野球)の大ファンです。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:海鳥社
- ページ数:320
- ISBN:9784874156490
- 発売日:2007年10月10日
- 価格:1680円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。