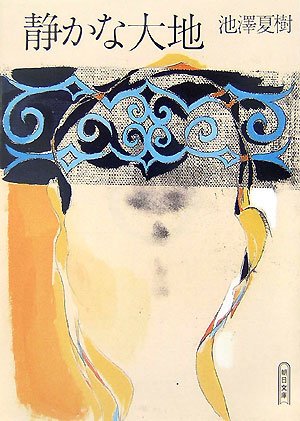折しもbarbarus陛下と「濁流に呑まれる」ことについて語り(?)合った週末であった.(いつも阿呆なお喋りばかりしているわけではない)
時代の濁流に呑まれる者,それに抗う者,濁流であることにも呑み込まれていることにも気づかない者……我々は兎にも角にも泥水の中の一滴でしかない.
濁流に抗える者は良かれ悪しかれ力を持つ者であろう.
それは言論の力かもしれないし武力かもしれない.知能かもしれないし容姿や声の良さかもしれない.いずれにしても,狂的な何かを秘めた者でないと,濁流に抗うことは困難だ.
そんな彼らは,後に英雄と呼ばれるかもしれないし,時代の徒花であったと冷笑交じりに評されるだけかもしれない.いずれにしても後世に名が残っていれば良い方で,多くの者はいずれは力屈し,濁流の中に埋もれ消えていく.
そんな,一滴の雫の物語である.
昔々は蝦夷地はすべてアイヌのものだった.
だからここをアイヌモシリという.アイヌの静かな地ということだ.平和な地ということだ.
いや,アイヌはそこが自分たちのものだとさえ思っていなかった.
天地は限りなく広がり,アイヌはその一部だった.
明治二年.「北海道」命名なる.
明治四年.淡路島の稲田一統の北海道移住本隊が北海道静内に到着し,この中に幼い宗形三郎・志郎の兄弟がいた.
物語は,志郎の娘である由良の回想の形で語られる.
その文体は父の話口調そのものであったり,父と叔父(三郎)間の書簡体であったり,または父の口伝を娘が自分の子らに話しなおす体であったりして纏まりがなく,故にこそ奇妙なリズムが生まれ,読者を飽きさせない.
暖かい瀬戸内からひねり出されるように送られた最果ての地――三郎や志郎の親たちにとって,其処は苦難の地であった.侍という身分を失い,禄もなく,家財道具も火災で失い,慣れぬ土地で開いたこともない土地を拓いていかねばならぬのだ.
しかし.子供らにとって,そこは恵みの地であった.
川には鮭が遡上し,山には鹿が群れ,アイヌがそれを獲っていた.
特に兄・三郎は強くアイヌの人々に惹かれ,率先してその中に混じっていく.
どこかしら,狂を秘めた情熱でーー.
開拓という名の下で倭(和)人がアイヌに為した行為は,この物語では「没義道」という言葉で評されている.
そこにはまさに「同化」という言葉に隠れ一つの民族を断絶させるという意図があったとしか思えない.
搾取,強姦,暴力,恐喝……もちろん倭人の皆が悪だったわけではないし,アイヌの中にも倭人に進んで協力する者もいた.
濁流だったのだ.
北海道を開墾し,その土地と土地から生まれる山の幸海の幸全てを「大日本帝国」のものにする,そのために邪魔なものは排除する,それが国家の使命でありそれが当時の「善」だったのだ.
勿論,それに疑問を呈する者はいた.アイヌに心寄せ,政府に否やを唱える者はいた.しかしそれらの声は流れを変える事まではできずに消えていった.
三郎もまた,アイヌに心寄せて育った青年だった.北の事など何も知らぬ瀬戸内の侍の子供に,鮭の捕り方,弓矢の扱い方,雪山の歩き方……北の大地で生きる術を教えたのは全てアイヌだった.
彼は札幌で酪農の実学を学ぶと,アイヌ達と牧場を始める.
ある意味,それも「同化」であり「文明化」であった.
アイヌは本来自然の中に生きる.必要なものだけを自然から頂き,恵はまた来年に残し,感謝を捧げる.
馬鈴薯を育て牧草を刈り馬を殖やす,つまり自然を支配するかの如き生業はアイヌの生き方ではない.
それでも.
三郎は残したかった.アイヌの生きる場所を.活計を.
全てのアイヌを救うことはできない.国の方針を変えることはできない.
しかし,彼の腕で囲える範囲は.彼の妻の家族,兄のように慕った仲間,その縁者たちくらいは護りたい.
それが,彼の濁流への抗い方だった.
ささやかで,危ういその抵抗は,呆気ない終焉を迎える.
彼もまた,濁流に呑まれる側の者だったのだ.
三郎は,池澤夏樹の曽祖父の兄をモデルとする.
誰もが英雄にはなれるわけではない.三郎もまた消えた.
残されたアイヌや弟の志郎にも,三郎の戦いを引き継ぐ気力や精力は残されていなかった.
結局,三郎は何も変えることは出来なかった.
だが,残った.
弟や友たちの記憶に.弟は娘に語った.娘は夫や子供達に語った.また,娘はその記憶が薄れないうちに記録を残した.
だが,発表は控えた.
時代は昭和十一年.二・二六事件が起こり,日本は更なる濁流に身を投じようとしていた.
かつて蝦夷地で行ったことを別の大陸・別の島で行うために.
それが,時代の「善」であった.
※ ※ ※
同じ開拓時代の北海道とアイヌの悲劇を描いた作品は多いが,花村萬月の「私の庭」(浅草篇,蝦夷地篇,北海無頼篇)をレビューしている.
あれは創作であるが,かつては親友であった男たちが,方やアイヌに同化し,方や倭人による開拓の先鋒となってしまい,立場を違えて行く悲劇を描いていた.萬月のほうはほぼ無頼の者たちの物語だが,飛蝗の被害や砂金についてなど本作にも語られたエピソードが多く興味深く思い返した.
あの頃は山に木が生えていた.
あの頃は川にたくさん鮭が上った.
あの頃は山にたくさん鹿がいた.
今はみないなくなった.誰もいない何もない山に風が吹くばかり.
風が吹くばかり.
追伸,みかん星人さま
地びーる復刻版,未ダ入手ナラズ...





色々世界がひっくり返って読書との距離を測り中.往きて還るかは神の味噌汁.「セミンゴの会」会員No1214.別名焼き粉とも.読書は背徳の蜜の味.毒を喰らわば根元まで.
この書評へのコメント
- あかつき2018-10-16 17:34
濁流に呑まれたくはない、けれど自分に抵抗するまでの力はなく、結局いつかはそこに呑まれるのだろう。
ただその時にこれが濁流であり、自分が嬉々としてそこに参加しているのではないことだけは明らかにしたい、と言っても小声でプチプチ言うだけなのだろうけど、ああ情けない。
でも、そんな情けなさすら捨てたら終わりだと思う、なんていうのも負け惜しみに過ぎない、、
この、情けない一雫こそが人の愛おしい営みだよね、と開き直っています。
パオロ↓ も、国なんて大層なものより自分の手に届くところの自分の大事な人だけ守んなさいと言っていますってふざけたレビューじゃねえかぁっ!
つう、つう、つう (©︎焼き粉;ちょっと違うんだもん!) ←ふざけないと〆られない。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - あかつき2018-10-16 20:14
@陛下
職場でも友人の前でもペトロニウスの如く「最後まで快活」であろうとしておりますが、家族の前では不機嫌な女になって傷つけてしまうことが多い、それが私の親への甘え。
だから「笑顔で溢れる家庭」っていうのはつまり「家でも気が抜けない家庭」ということで寛ぐどころのもんじゃない、家でくらい表情作らずボーとしていたいんだよ、となると愛する人(おらんけど)とは一番一緒に暮らせない。故に一人が一番寛げるし誰も傷つけない……「孤独について」、共感ボタンを押させて頂きました。
で、対談方式は©︎未取得だからいいんだもん!……え、なんだお前t、あう!
つう、つう、つう(鶴の恩返しかよ) ©︎焼き粉 ← くどさは諧謔の一要素クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 
コメントするには、ログインしてください。
- 出版社:朝日新聞社
- ページ数:672
- ISBN:9784022644008
- 発売日:2007年06月07日
- 価格:1050円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。