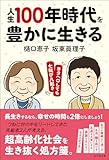ぽんきちさん
レビュアー:
▼
率直だがわかりやすくはない
大河ドラマで紫式部が主人公、清少納言も注目されているというところで、『枕草子』を読んでみた。
何となく知っているような気になっているが、そういえば、「春はあけぼの」とか「香炉峰の雪」とかごく限られた章段しか読んだことがないのである。はて、全体としてはどのような感じなのだろうか。
すべてを原文で読めればよいのだろうが、あいにくそこまで古典の教養はない。しかし、せっかくだから抄訳や“超訳”的なものでないものにトライしたい。
というわけで、角川学芸出版の角川ソフィア文庫にしてみた。
上下巻2冊構成、各巻とも、前半に脚注付きの原文、補注を挟んで、後半が現代語訳である。上巻末尾には資料と解説、後半末尾には年表と索引が付く。
基本は現代語訳で読み進める。引っかかったら原文に戻り、適宜、脚注や補注を確認する。
・・・ん、これなら読めるかな・・・?
その前に、ちょっと予備知識を入れる。
全体としては約300の短い章段からなる。
池田亀鑑によれば、大まかに、「虫は」「うつくしきもの」といった「ものづくし」の“類聚(るいじゅう)章段”、日常生活や四季の自然を観察した“随想章段”、作者が出仕した中宮定子周辺の宮廷社会を振り返った日記風の“回想章段”の3つに分けられる。が、「春はあけぼの」のように類聚と随想が混ざったようなものもあり、いずれにも分類しにくいものもある。
執筆動機も諸説あり、また、「枕草子」と題された理由についてもいくつか説がある。
執筆時期も正確には不明だが、長保3(1001)年ころには大半が書かれていたとみられている。このころにはもう清少納言は宮仕えを退いている。清少納言が仕えた中宮定子が3人目の御子を産んだのちに早逝したのはその前年、長保2年のことだったのだ。加筆修正は後々まで続けられたようである。
原本は残っておらず、4系統の伝本があり、内容や章段の順序に相違がある。
角川ソフィア文庫版は、三巻本と呼ばれる伝本を底本としている。
・・・いやはや、なかなか大変ですね・・・。
実際に読んでみる。
冒頭は「春はあけぼの」である。
うん、この辺は原文でもいける?と思うくらい読める。というか、中学か高校の古文で習ったよな、これ。「山ぎは」と「山の端」の違いとか。あー、それじゃ自力で読めているんじゃなくて、習ったから読めるのか・・・。古文の先生、ありがとう(今更)。
このあたりを読んでいると、清少納言は「感性」の人なんだな、という感じがする。誰もが見たことがあるであろう風景を、誰もが語れるわけではない視点で、鮮やかにすっきりと切り取って見せる。
聡明で小気味よい。
いわゆる類聚系のものは、章段自体短く、ぽんぽんぽんと列挙されるので、まぁそんなものかとわかりやすい。文化や習慣の違いで、よくわからないものもあるが、千年も前のものだから、そんなものだろう。鳥や虫の話などは、実際にどうだったというよりも、伝承や和歌の中の話が多い。蓑虫は鬼が生んだものだとか、山鳥は仲間を恋しがり鏡を見せると仲間がいると安心するとか、そういうお話があったのか、という意味ではおもしろい。
難しいのは特に日記系のものである。
宮廷のあれやらこれやらがとにかくわからない。
第78段。頭中将(藤原斉信)は清少納言との交流があったことで知られ、枕草子にも何度か登場する人物だが、何かしら清少納言の悪い噂を聞いて、清少納言の悪口を言ったり、無視したりするようになる。清少納言は誤解ならそのうち晴れるだろうと特に何もせず、放っておいている。ところがある夜、急に斉信から文が来て、それに白氏文集にある漢詩の一節が書いてある。使いの者は、清少納言に早く返事を書けと急かしてくる。清少納言はこの漢詩の続きを知ってはいるのだが、したり顔で、またうまくもない(謙遜?)漢字を書くのもためらわれ、藤原公任による「公任集」から連歌の一句を借用し、斉信が寄越した手紙に書き足して返す。この返事が気が利いていたため、斉信はすっかり機嫌を直し、宮中でも評判になり、中宮定子も喜んだ、というもの。
・・・そもそもの白氏文集の漢詩もわからなければ、公任の句もどう解釈するのかよくわからない。それで皆がほめそやすというのもよくわからない。
現代文の方に「評」が付いていて、これは単なる清少納言の自慢話ではなく、仕える女房のこうした素質が、定子後宮の評価に直結しているのであるから、清少納言は中宮の面目を保ったのであり、中宮が喜ぶのも当然なのだという。
・・・気の利いたやりとりをするってことがつまり、政治的に意味があった、ってことですかね・・・?
訳注の石田譲二による解説が含蓄深い。
枕草子は「親しみやす」く、それは「作者のほとんど無垢といっていいほどの人の好さ、単純さによる」という。一方で、「事柄の一つ一つが、裸のまま、つまり世界解釈の隈取りや陰影を帯びることなく、我々の前に投げ出されている」というのである。著者は書いている対象について、「自明」のものとして扱っている。さまざまな事柄について、特段の説明がない。そのため、著者に接近していくためには、1つ1つの事柄を「綿密に仔細に点検する」「注釈」が必要だというのである。
やさしく見えて容易くはない。
どうやら『枕草子』を真に味わうということは、宮廷生活を生きた1人の女性の内面にまで分け入っていくということであるようだ。
→下巻
何となく知っているような気になっているが、そういえば、「春はあけぼの」とか「香炉峰の雪」とかごく限られた章段しか読んだことがないのである。はて、全体としてはどのような感じなのだろうか。
すべてを原文で読めればよいのだろうが、あいにくそこまで古典の教養はない。しかし、せっかくだから抄訳や“超訳”的なものでないものにトライしたい。
というわけで、角川学芸出版の角川ソフィア文庫にしてみた。
上下巻2冊構成、各巻とも、前半に脚注付きの原文、補注を挟んで、後半が現代語訳である。上巻末尾には資料と解説、後半末尾には年表と索引が付く。
基本は現代語訳で読み進める。引っかかったら原文に戻り、適宜、脚注や補注を確認する。
・・・ん、これなら読めるかな・・・?
その前に、ちょっと予備知識を入れる。
全体としては約300の短い章段からなる。
池田亀鑑によれば、大まかに、「虫は」「うつくしきもの」といった「ものづくし」の“類聚(るいじゅう)章段”、日常生活や四季の自然を観察した“随想章段”、作者が出仕した中宮定子周辺の宮廷社会を振り返った日記風の“回想章段”の3つに分けられる。が、「春はあけぼの」のように類聚と随想が混ざったようなものもあり、いずれにも分類しにくいものもある。
執筆動機も諸説あり、また、「枕草子」と題された理由についてもいくつか説がある。
執筆時期も正確には不明だが、長保3(1001)年ころには大半が書かれていたとみられている。このころにはもう清少納言は宮仕えを退いている。清少納言が仕えた中宮定子が3人目の御子を産んだのちに早逝したのはその前年、長保2年のことだったのだ。加筆修正は後々まで続けられたようである。
原本は残っておらず、4系統の伝本があり、内容や章段の順序に相違がある。
角川ソフィア文庫版は、三巻本と呼ばれる伝本を底本としている。
・・・いやはや、なかなか大変ですね・・・。
実際に読んでみる。
冒頭は「春はあけぼの」である。
うん、この辺は原文でもいける?と思うくらい読める。というか、中学か高校の古文で習ったよな、これ。「山ぎは」と「山の端」の違いとか。あー、それじゃ自力で読めているんじゃなくて、習ったから読めるのか・・・。古文の先生、ありがとう(今更)。
このあたりを読んでいると、清少納言は「感性」の人なんだな、という感じがする。誰もが見たことがあるであろう風景を、誰もが語れるわけではない視点で、鮮やかにすっきりと切り取って見せる。
聡明で小気味よい。
いわゆる類聚系のものは、章段自体短く、ぽんぽんぽんと列挙されるので、まぁそんなものかとわかりやすい。文化や習慣の違いで、よくわからないものもあるが、千年も前のものだから、そんなものだろう。鳥や虫の話などは、実際にどうだったというよりも、伝承や和歌の中の話が多い。蓑虫は鬼が生んだものだとか、山鳥は仲間を恋しがり鏡を見せると仲間がいると安心するとか、そういうお話があったのか、という意味ではおもしろい。
難しいのは特に日記系のものである。
宮廷のあれやらこれやらがとにかくわからない。
第78段。頭中将(藤原斉信)は清少納言との交流があったことで知られ、枕草子にも何度か登場する人物だが、何かしら清少納言の悪い噂を聞いて、清少納言の悪口を言ったり、無視したりするようになる。清少納言は誤解ならそのうち晴れるだろうと特に何もせず、放っておいている。ところがある夜、急に斉信から文が来て、それに白氏文集にある漢詩の一節が書いてある。使いの者は、清少納言に早く返事を書けと急かしてくる。清少納言はこの漢詩の続きを知ってはいるのだが、したり顔で、またうまくもない(謙遜?)漢字を書くのもためらわれ、藤原公任による「公任集」から連歌の一句を借用し、斉信が寄越した手紙に書き足して返す。この返事が気が利いていたため、斉信はすっかり機嫌を直し、宮中でも評判になり、中宮定子も喜んだ、というもの。
・・・そもそもの白氏文集の漢詩もわからなければ、公任の句もどう解釈するのかよくわからない。それで皆がほめそやすというのもよくわからない。
現代文の方に「評」が付いていて、これは単なる清少納言の自慢話ではなく、仕える女房のこうした素質が、定子後宮の評価に直結しているのであるから、清少納言は中宮の面目を保ったのであり、中宮が喜ぶのも当然なのだという。
・・・気の利いたやりとりをするってことがつまり、政治的に意味があった、ってことですかね・・・?
訳注の石田譲二による解説が含蓄深い。
枕草子は「親しみやす」く、それは「作者のほとんど無垢といっていいほどの人の好さ、単純さによる」という。一方で、「事柄の一つ一つが、裸のまま、つまり世界解釈の隈取りや陰影を帯びることなく、我々の前に投げ出されている」というのである。著者は書いている対象について、「自明」のものとして扱っている。さまざまな事柄について、特段の説明がない。そのため、著者に接近していくためには、1つ1つの事柄を「綿密に仔細に点検する」「注釈」が必要だというのである。
やさしく見えて容易くはない。
どうやら『枕草子』を真に味わうということは、宮廷生活を生きた1人の女性の内面にまで分け入っていくということであるようだ。
→下巻
掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
分子生物学・生化学周辺の実務翻訳をしています。
本の大海を漂流中。
日々是好日。どんな本との出会いも素敵だ。
あちらこちらとつまみ食いの読書ですが、点が線に、線が面になっていくといいなと思っています。
「実感」を求めて読書しているように思います。
赤柴♀(もも)は3代目。
この夏、有精卵からヒヨコ4羽を孵化させました。そろそろ大雛かな。♂x2、♀x2。ニワトリは割と人に懐くものらしいですが、今のところ、懐く気配はありませんw
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:角川学芸出版
- ページ数:445
- ISBN:9784044026011
- 発売日:1979年08月01日
- 価格:900円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。