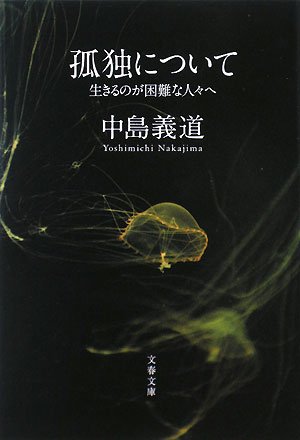有坂汀さん
レビュアー:
▼
本書は「戦う哲学者」の異名を持つ中島義道先生が自らの「来し方」を振り返りつつ、艱難辛苦の果てに「孤独を楽しみ、孤独を磨きあげ、孤独に死のう」という積極的孤独を選びとるまでの思索を描ききった軌跡です。
「お前は人を遠ざけて生きている!」
僕は幼少期に肉親からこの言葉を擲着けられて以来、そのまま現在に至るわけですが、そう思えば僕が中島義道先生の著作および「中島哲学」に惹かれたのは「必然」だったのでしょう。
何度も書いたので詳細は省きますが僕が中島義道先生のことを知ったのはカリスマ予備校講師である林修先生がナビゲート役を務める『- 林先生の「痛快!生きざま大辞典」』(|2014年8月30日(土)放送分)を視聴して衝撃を受けたからであります。
本書には中島義道先生が自らの「来し方」を振り返りつつ、艱難辛苦の果てに
「孤独を楽しみ、孤独を磨きあげ、孤独に死のう」
という積極的孤独を選びとるまでの思索の軌跡を綴ったノンフィクションであり、エッセイです。
中島先生は本書の中で
『私は第一に上下関係と習俗習慣にがんじがらめになった(冠婚葬祭を典型とする)「正しいつき合い」が嫌なのだ。そして第二に、「明るく希望をもって生きよう」とする鈍感で欺瞞的な多数派とのつき合いが嫌なのだ。この二つが世間を支配している。』
とおっしゃっており、僕自身もまた、執筆と思索を生活の中心に据えるようになってからは身内の冠婚葬祭の類には一切呼ばれることはなくなり(長男なのに!!)、彼らの冷たい視線を受け続けることと引き換えに自由を得たわけですが、その確信をより強固なものにしたのが前述の引用でした。
本書の中で中島先生は過去を回想する形で誰一人からも理解されない偏った少年時代、七転八倒を繰り広げた混迷極まる青年時代(詳しくは『ウィーン愛憎―ヨーロッパ精神との格闘 (中公新書)』(中央公論社)を参照のこと)を振り返り、助手時代の教授による壮絶なイジメ地獄(この時も延々と描かれていたがそれをさらに特化させたのが『東大助手物語 (新潮文庫)』(新潮社)であろう)を経て
『あなたの孤独は、あなた自身が選びとったものだということを認めなさい。そして、その(表面的な)不幸を利用し尽くしなさい。それは、とても「よい」状況になりうることを信じなさい。心からこう言いたい。』
と書くまでに至る境地に達したことを宣言したわけです。
自分も中島先生の「境地」をみていると
「あぁ、まだまだ修行が足りんなぁ…。」
と反省の至りですが、今後も精進を続けて、自らの『孤独』を磨き上げていく所存です。
僕は幼少期に肉親からこの言葉を擲着けられて以来、そのまま現在に至るわけですが、そう思えば僕が中島義道先生の著作および「中島哲学」に惹かれたのは「必然」だったのでしょう。
何度も書いたので詳細は省きますが僕が中島義道先生のことを知ったのはカリスマ予備校講師である林修先生がナビゲート役を務める『- 林先生の「痛快!生きざま大辞典」』(|2014年8月30日(土)放送分)を視聴して衝撃を受けたからであります。
本書には中島義道先生が自らの「来し方」を振り返りつつ、艱難辛苦の果てに
「孤独を楽しみ、孤独を磨きあげ、孤独に死のう」
という積極的孤独を選びとるまでの思索の軌跡を綴ったノンフィクションであり、エッセイです。
中島先生は本書の中で
『私は第一に上下関係と習俗習慣にがんじがらめになった(冠婚葬祭を典型とする)「正しいつき合い」が嫌なのだ。そして第二に、「明るく希望をもって生きよう」とする鈍感で欺瞞的な多数派とのつき合いが嫌なのだ。この二つが世間を支配している。』
とおっしゃっており、僕自身もまた、執筆と思索を生活の中心に据えるようになってからは身内の冠婚葬祭の類には一切呼ばれることはなくなり(長男なのに!!)、彼らの冷たい視線を受け続けることと引き換えに自由を得たわけですが、その確信をより強固なものにしたのが前述の引用でした。
本書の中で中島先生は過去を回想する形で誰一人からも理解されない偏った少年時代、七転八倒を繰り広げた混迷極まる青年時代(詳しくは『ウィーン愛憎―ヨーロッパ精神との格闘 (中公新書)』(中央公論社)を参照のこと)を振り返り、助手時代の教授による壮絶なイジメ地獄(この時も延々と描かれていたがそれをさらに特化させたのが『東大助手物語 (新潮文庫)』(新潮社)であろう)を経て
『あなたの孤独は、あなた自身が選びとったものだということを認めなさい。そして、その(表面的な)不幸を利用し尽くしなさい。それは、とても「よい」状況になりうることを信じなさい。心からこう言いたい。』
と書くまでに至る境地に達したことを宣言したわけです。
自分も中島先生の「境地」をみていると
「あぁ、まだまだ修行が足りんなぁ…。」
と反省の至りですが、今後も精進を続けて、自らの『孤独』を磨き上げていく所存です。
投票する
投票するには、ログインしてください。
有坂汀です。偶然立ち寄ったので始めてみることにしました。ここでは私が現在メインで運営しているブログ『誇りを失った豚は、喰われるしかない。』であげた書評をさらにアレンジしてアップしております。
- この書評の得票合計:
- 48票
| 読んで楽しい: | 6票 | |
|---|---|---|
| 参考になる: | 37票 | |
| 共感した: | 5票 |
あなたの感想は?
投票するには、ログインしてください。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:文藝春秋
- ページ数:210
- ISBN:9784167753184
- 発売日:2008年11月07日
- 価格:550円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。