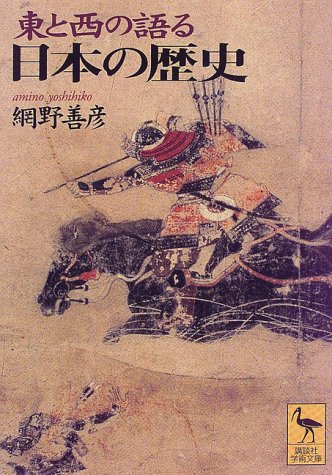三太郎さん
レビュアー:
▼
東日本と西日本では、今でも言葉のイントネーションや食文化の違いがあるのはよく知られているが、中世にはすでに東西の違いが生まれていたらしい。
日本の中世史の研究家である網野善彦さんが1982年に上梓した本の文庫版を読んだ。旧石器時代から江戸時代まで、西日本と東日本には別々に発展してきた歴史があったことを論証する。著者は中世期が専門だから、この本は様々な専門家の研究成果をまとめた総説のような体裁である。このテーマは民俗学者の宮本常一さんから託されたものだという。
ところで僕自身は幼い頃から歴史が苦手というか興味が薄くて、大学入試の科目に日本史を選んだ関係で最低限の勉強はしたけれど今では大分忘れてしまっている。だからこの本で荘園とか公領とか出て来てもその違いが分からないし、関東管領と鎌倉公方の関係も知らなかった(たぶん忘れてしまっていた)。
だから本書の内容もあまり深くは理解できていないと思うが、ざっくりと理解できた範囲でも東と西の違いは少なくとも中世にまで遡れそうだ。
以下は本を読んで得た僕の勝手な見解です。
ところで、最近のニュースで、沖縄で発掘された旧石器人のDNAと縄文人のDNAの比較が可能になり、縄文人の先祖は南方からやってきた旧石器人とは別に北方から日本列島にやってきた旧石器人とが混血したものらしいことが明らかになった。一方、本書では旧石器時代の石器のタイプが東日本と西日本では異なり、中部日本では両者が混じっていることが示されている。
しかしこの旧石器時代の東西の違いが今日の日本人社会に影響したとは考えられないだろう。弥生時代から古墳時代が終わるまでに日本には大量の移民が朝鮮半島から入って来て、今の日本人が出来上がったと考えられるからだ。むしろ中部山岳地帯を形成した大地溝帯が人や物の移動を制限した結果、自然に表れるのが東西の半独立性ともいえる日本の特徴なのかも。
むろん東西の違いは自然にできたものではないだろう。中世末期に平家と源氏が東西に分かれて対峙した。平家は水軍によって、源氏は坂東武士(騎馬)によって、どちらも全国を制覇しようとしたのだろうが、結果は東の鎌倉幕府と西の朝廷が実質的には別個に日本を治めるようになった。
実は鎌倉幕府の内部には、西日本には干渉せずに東日本の独立を目指す方向と、朝廷に従う形を見せながら実質的に西国への実効支配を進める方向とがせめぎ合っていたらしい。しかし鎌倉幕府が西から独立を果たす前に元寇がやってきて独立の野望は実現しなかったのかも。
この時代には既に東西日本で農村が別々のかたちで進化していたらしい。東の農村では長子相続と本家分家の厳密な序列化が進み、西日本での横の連携を重視した共同体としての農村との違いが出てきた。
この農村の違いは東西の武士団の性格の違いにも反映されていたという。東の武士団は厳密な主従関係により統率がとれた戦いができた。
西国に赴任した東国出身の地頭らは現地の武士とではなく専ら東国出身の地頭同士で婚姻関係を結んだことからも、武士階級でも東西の文化の違いは大きかったのだろう。
東日本の西からの独立を目指す方向が解るのは鎌倉幕府が日光山を東の比叡山として重要視したことが挙げられる。これは後に江戸幕府が日光に東照宮を建てることにつながっているとか。
室町時代には西日本の職人集団(木地師、鋳物師など)は天皇家に起源があるという書状を持っていたが、東日本では鎌倉幕府に承認されたという書状が見られたとか。東日本では天皇家ではなく鎌倉に権威を求めたということらしい。
ところで僕自身は幼い頃から歴史が苦手というか興味が薄くて、大学入試の科目に日本史を選んだ関係で最低限の勉強はしたけれど今では大分忘れてしまっている。だからこの本で荘園とか公領とか出て来てもその違いが分からないし、関東管領と鎌倉公方の関係も知らなかった(たぶん忘れてしまっていた)。
だから本書の内容もあまり深くは理解できていないと思うが、ざっくりと理解できた範囲でも東と西の違いは少なくとも中世にまで遡れそうだ。
以下は本を読んで得た僕の勝手な見解です。
ところで、最近のニュースで、沖縄で発掘された旧石器人のDNAと縄文人のDNAの比較が可能になり、縄文人の先祖は南方からやってきた旧石器人とは別に北方から日本列島にやってきた旧石器人とが混血したものらしいことが明らかになった。一方、本書では旧石器時代の石器のタイプが東日本と西日本では異なり、中部日本では両者が混じっていることが示されている。
しかしこの旧石器時代の東西の違いが今日の日本人社会に影響したとは考えられないだろう。弥生時代から古墳時代が終わるまでに日本には大量の移民が朝鮮半島から入って来て、今の日本人が出来上がったと考えられるからだ。むしろ中部山岳地帯を形成した大地溝帯が人や物の移動を制限した結果、自然に表れるのが東西の半独立性ともいえる日本の特徴なのかも。
むろん東西の違いは自然にできたものではないだろう。中世末期に平家と源氏が東西に分かれて対峙した。平家は水軍によって、源氏は坂東武士(騎馬)によって、どちらも全国を制覇しようとしたのだろうが、結果は東の鎌倉幕府と西の朝廷が実質的には別個に日本を治めるようになった。
実は鎌倉幕府の内部には、西日本には干渉せずに東日本の独立を目指す方向と、朝廷に従う形を見せながら実質的に西国への実効支配を進める方向とがせめぎ合っていたらしい。しかし鎌倉幕府が西から独立を果たす前に元寇がやってきて独立の野望は実現しなかったのかも。
この時代には既に東西日本で農村が別々のかたちで進化していたらしい。東の農村では長子相続と本家分家の厳密な序列化が進み、西日本での横の連携を重視した共同体としての農村との違いが出てきた。
この農村の違いは東西の武士団の性格の違いにも反映されていたという。東の武士団は厳密な主従関係により統率がとれた戦いができた。
西国に赴任した東国出身の地頭らは現地の武士とではなく専ら東国出身の地頭同士で婚姻関係を結んだことからも、武士階級でも東西の文化の違いは大きかったのだろう。
東日本の西からの独立を目指す方向が解るのは鎌倉幕府が日光山を東の比叡山として重要視したことが挙げられる。これは後に江戸幕府が日光に東照宮を建てることにつながっているとか。
室町時代には西日本の職人集団(木地師、鋳物師など)は天皇家に起源があるという書状を持っていたが、東日本では鎌倉幕府に承認されたという書状が見られたとか。東日本では天皇家ではなく鎌倉に権威を求めたということらしい。
お気に入り度:







掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
1957年、仙台に生まれ、結婚後10年間世田谷に住み、その後20余年横浜に住み、現在は仙台在住。本を読んで、思ったことあれこれを書いていきます。
長年、化学メーカーの研究者でした。2019年から滋賀県で大学の教員になりましたが、2023年3月に退職し、10月からは故郷の仙台に戻りました。プロフィールの写真は還暦前に米国ピッツバーグの岡の上で撮ったものです。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:講談社
- ページ数:340
- ISBN:9784061593435
- 発売日:1998年09月10日
- 価格:1155円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。