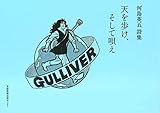すずはら なずなさん
レビュアー:
▼
胸に『緋文字』(刺繍された赤いAの文字)を一生付け続けるという罰。
ヘスタのしたことがどれほどの罪なのか。本当の「罪人」は誰なのか、「神の赦し」「人の許し」はいつになったら与えられるのだろうか。
子供の成長に合わせ、絵本や平成のジュブナイル小説を読んでいた時期が長く、昭和の翻訳物に立ち戻って四苦八苦しております。
多くの作品に感じるのは(文字が小さいのも一つですが)、説明的な文がが多く挿入されているので一つの文が長かったり、形容が美しいのはいいけれど主語と述語がすぐには読み取れなかったりとなかなか慣れるまで手間がかかります。最新の訳ならもっと別の印象だったかもしれませんが。(何しろ新しく買わずに実家の本棚の本を読んでいっているものなので)
でも、なんとか読み切って良かった。読了後はそう感じます。
さて内容です。
場所はニューイングランド、ボストン。時代は十七世紀。信仰と法が切り離されずに存在した厳格なピューリタン社会です。
「姦淫の罪」は重罪。その上へスタは「罪の子」を出産。
小説の冒頭からヘスタは赤ん坊を抱いて晒し台の上に立たされます。胸に「Adultery(不貞)」の罪の意味を表わす緋色の刺繍の「A」。(ワッペンのようなものでしょうか、必ず見えるようにつけなくてはならないようです)そんな法的な罰がある世界です。
ヘスタは周囲の「相手の名を言え」という圧力に頑として沈黙を守ります。それは一体誰のためなのか。
相手を推理させる意図の小説ではないようなので、だんだんうっすらと解り、やがて二人と成長した娘のパールが密かに会うシーンではっきりします。早く感づいた人なら沈黙した「父親」がどういう風に表面的に立ち回りながら 陰で苦しんでいる様子も追っていけます。
けれど二人がそういう関係になった経緯も特に描かれておらず、そこに「罪」を犯してまでの「愛」があったのかもわからないまま物語は進んでくるのです。
ましてや妻の不倫を自分の「恥」として、名乗り出ず相手の男を探り出し復讐しようとするロジャー・チリングワース(偽名で登場します)との結婚に、もともと深い愛情が存在したかも疑問です。
ロジャー・チリングワースは財産家で歳もかなり離れているようですので何か事情はありそうですが。
不倫に絡む主要な三人と不義の子パール。
潔く罪のしるしをつけ続け、差別にも白い目にも負けずに刺繍の腕を生かした仕事を続け、また他人への奉仕や病人の介護などで黙々と徳を積むヘスタ。周囲の見る目も遠巻きながら少しずつ緩やかになってはきています。けれど法と神、人々からの積極的な「赦し」は与えられません。
相手の男に目星をつけ、原住民の部落で学んだ怪しげな(?)薬草を煎じたりしつつ医者として近づき冷酷に観察し続けるロジャー・チリングワース。
説教が上手く、町の人の尊敬と称賛を集める若い牧師ディムズデール。彼は断食や苦行を自らに課し、日々弱っているようです。
気まぐれな妖精のようなパールは無邪気なその目で 母の胸の文字を見つめ、その意味について、また父親についても問いを繰り返し、ヘスタにそのたび現実を突きつけます。
ヘスタと牧師の人目を避けた森での会話辺りでは、二人の罪よりもロジャー・チリングワースの執念や人を憎む心の方が悪のように描かれています。
寂しさとか愛やいたわりの気持ちから出ただろう不倫という結びつきと、妻を奪われた男の嫉妬や名誉棄損の感情から来る憎しみでは、どちらが醜いでしょうか。現代のドラマなら前者の方が美しく描かれそうですね。
ただし ここでは厳しい宗教観が付いて来ます。神が許すのはどちらか、一生許されないのはどんな罪なのか、ということです。
また 名前を隠してもらって今の地位や名声をそのままにしている牧師。この人ってどうなんだろう。
幾度も信者の前で自分の「罪深さ」を告白するものの、具体的には言えないでいるのです。結果は信者たちから「何と謙虚で素晴らしい方」「こんなに立派な方なのに自分をさえ『罪びと』と言われるんだ」なんて逆に称賛される始末。
ヘスタが罪のしるしをつけて一人で生きているのに、誰も見ていないところだけで悩んで、自分の身体を責めさいなんでいるだけ。
二人とパールの森での邂逅では罪や罰の手の届かない土地へ一緒に逃げ出そうとヘスタから提案されます。そしてヘスタは一度はその胸のしるしを引きはがすのです。今までこの場所での「罪」と「罰」と向き合っていたヘスタがここで別の考え方を持つのは何故でしょう。
この土地から出たら法や人の目は変えられても、「神の赦し」は得られるのものなのでしょうか。
結末ではやはり「罪悪感からの解放」や「神の赦し」はこの世界では簡単に得ることはできず、牧師は晒し台で罪を告白して息絶え、夫はこのような形の牧師の死では自分の成し遂げたかった復讐心は充たされず、ヘスタも結局亡くなるまで、いや墓の上まで緋色のAの文字を付け続けることになります。
読んだ後で知ったことですが この物語には序章「税関」があるとのこと。
ホーソーンが税関に勤めていて、税関の古い書類の中に緋文字に関する書類を発見したことなどが、述べられているそうです。またホーソーンの先祖に「魔女狩り」にかかわった者がいたらしいことが解ります。
そういうことがあって、自らは正しいと信じている(狂信的な)人々の暴走や、静かではあるけれど酷薄な偏見や差別について考えさせられる小説が綴られたのだと判ります。
牧師の死の間際の告白について見聞きした人々のいくつかの違った記憶が付け足されているのは何だか皮肉です。
結局、人々は見たいように物事を見るのでしょうか。牧師の最期の告白を聞いてもヘスタとの「不倫」の張本人と汲み取ることもなく、胸に直接現れたというAの文字も本当にあったのかどうかもうやむや。
何故そんな罪のしるしの文字が彼の胸に(あったとしたら)現れていたのかは謎のままです。ロジャー・チリングワースが医者として彼に付きまとっていたので何らかの呪術的な手段で刻まれたのかともとれます。魔女といわれている女性も意味ありげで不気味な発言を作中で挟みますし、ファンタジー的な要素として読めるところもあるのかもしれません。
彼が罪の意識に苛まれ、いつもその文字が刻み付けられている(実際のところはわかりませんが)胸に手をあてていたことは確かです。
主人公を取り巻く民衆を含め 読者が誰を一番の罪びとと感じ、どの生き方を良しとし、赦しを与えるのか、自分なら誰を許せるか、それぞれに問うと、自分の宗教観や法への考え方、愛情や憎しみへの感じ方が見えて来ると思います。
色々と深い物語でした。
多くの作品に感じるのは(文字が小さいのも一つですが)、説明的な文がが多く挿入されているので一つの文が長かったり、形容が美しいのはいいけれど主語と述語がすぐには読み取れなかったりとなかなか慣れるまで手間がかかります。最新の訳ならもっと別の印象だったかもしれませんが。(何しろ新しく買わずに実家の本棚の本を読んでいっているものなので)
でも、なんとか読み切って良かった。読了後はそう感じます。
さて内容です。
場所はニューイングランド、ボストン。時代は十七世紀。信仰と法が切り離されずに存在した厳格なピューリタン社会です。
「姦淫の罪」は重罪。その上へスタは「罪の子」を出産。
小説の冒頭からヘスタは赤ん坊を抱いて晒し台の上に立たされます。胸に「Adultery(不貞)」の罪の意味を表わす緋色の刺繍の「A」。(ワッペンのようなものでしょうか、必ず見えるようにつけなくてはならないようです)そんな法的な罰がある世界です。
ヘスタは周囲の「相手の名を言え」という圧力に頑として沈黙を守ります。それは一体誰のためなのか。
相手を推理させる意図の小説ではないようなので、だんだんうっすらと解り、やがて二人と成長した娘のパールが密かに会うシーンではっきりします。早く感づいた人なら沈黙した「父親」がどういう風に表面的に立ち回りながら 陰で苦しんでいる様子も追っていけます。
けれど二人がそういう関係になった経緯も特に描かれておらず、そこに「罪」を犯してまでの「愛」があったのかもわからないまま物語は進んでくるのです。
ましてや妻の不倫を自分の「恥」として、名乗り出ず相手の男を探り出し復讐しようとするロジャー・チリングワース(偽名で登場します)との結婚に、もともと深い愛情が存在したかも疑問です。
ロジャー・チリングワースは財産家で歳もかなり離れているようですので何か事情はありそうですが。
不倫に絡む主要な三人と不義の子パール。
潔く罪のしるしをつけ続け、差別にも白い目にも負けずに刺繍の腕を生かした仕事を続け、また他人への奉仕や病人の介護などで黙々と徳を積むヘスタ。周囲の見る目も遠巻きながら少しずつ緩やかになってはきています。けれど法と神、人々からの積極的な「赦し」は与えられません。
相手の男に目星をつけ、原住民の部落で学んだ怪しげな(?)薬草を煎じたりしつつ医者として近づき冷酷に観察し続けるロジャー・チリングワース。
説教が上手く、町の人の尊敬と称賛を集める若い牧師ディムズデール。彼は断食や苦行を自らに課し、日々弱っているようです。
気まぐれな妖精のようなパールは無邪気なその目で 母の胸の文字を見つめ、その意味について、また父親についても問いを繰り返し、ヘスタにそのたび現実を突きつけます。
ヘスタと牧師の人目を避けた森での会話辺りでは、二人の罪よりもロジャー・チリングワースの執念や人を憎む心の方が悪のように描かれています。
寂しさとか愛やいたわりの気持ちから出ただろう不倫という結びつきと、妻を奪われた男の嫉妬や名誉棄損の感情から来る憎しみでは、どちらが醜いでしょうか。現代のドラマなら前者の方が美しく描かれそうですね。
ただし ここでは厳しい宗教観が付いて来ます。神が許すのはどちらか、一生許されないのはどんな罪なのか、ということです。
また 名前を隠してもらって今の地位や名声をそのままにしている牧師。この人ってどうなんだろう。
幾度も信者の前で自分の「罪深さ」を告白するものの、具体的には言えないでいるのです。結果は信者たちから「何と謙虚で素晴らしい方」「こんなに立派な方なのに自分をさえ『罪びと』と言われるんだ」なんて逆に称賛される始末。
ヘスタが罪のしるしをつけて一人で生きているのに、誰も見ていないところだけで悩んで、自分の身体を責めさいなんでいるだけ。
二人とパールの森での邂逅では罪や罰の手の届かない土地へ一緒に逃げ出そうとヘスタから提案されます。そしてヘスタは一度はその胸のしるしを引きはがすのです。今までこの場所での「罪」と「罰」と向き合っていたヘスタがここで別の考え方を持つのは何故でしょう。
この土地から出たら法や人の目は変えられても、「神の赦し」は得られるのものなのでしょうか。
結末ではやはり「罪悪感からの解放」や「神の赦し」はこの世界では簡単に得ることはできず、牧師は晒し台で罪を告白して息絶え、夫はこのような形の牧師の死では自分の成し遂げたかった復讐心は充たされず、ヘスタも結局亡くなるまで、いや墓の上まで緋色のAの文字を付け続けることになります。
読んだ後で知ったことですが この物語には序章「税関」があるとのこと。
ホーソーンが税関に勤めていて、税関の古い書類の中に緋文字に関する書類を発見したことなどが、述べられているそうです。またホーソーンの先祖に「魔女狩り」にかかわった者がいたらしいことが解ります。
そういうことがあって、自らは正しいと信じている(狂信的な)人々の暴走や、静かではあるけれど酷薄な偏見や差別について考えさせられる小説が綴られたのだと判ります。
牧師の死の間際の告白について見聞きした人々のいくつかの違った記憶が付け足されているのは何だか皮肉です。
結局、人々は見たいように物事を見るのでしょうか。牧師の最期の告白を聞いてもヘスタとの「不倫」の張本人と汲み取ることもなく、胸に直接現れたというAの文字も本当にあったのかどうかもうやむや。
何故そんな罪のしるしの文字が彼の胸に(あったとしたら)現れていたのかは謎のままです。ロジャー・チリングワースが医者として彼に付きまとっていたので何らかの呪術的な手段で刻まれたのかともとれます。魔女といわれている女性も意味ありげで不気味な発言を作中で挟みますし、ファンタジー的な要素として読めるところもあるのかもしれません。
彼が罪の意識に苛まれ、いつもその文字が刻み付けられている(実際のところはわかりませんが)胸に手をあてていたことは確かです。
主人公を取り巻く民衆を含め 読者が誰を一番の罪びとと感じ、どの生き方を良しとし、赦しを与えるのか、自分なら誰を許せるか、それぞれに問うと、自分の宗教観や法への考え方、愛情や憎しみへの感じ方が見えて来ると思います。
色々と深い物語でした。
掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
実家の本棚の整理を兼ねて家族の残した本や自分の買ったはずだけど覚えていない本などを読んでいきます。今のところ昭和の本が中心です。平成にたどり着くのはいつのことやら…。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:新潮社
- ページ数:284
- ISBN:9784102040010
- 発売日:1982年04月03日
- 価格:460円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。