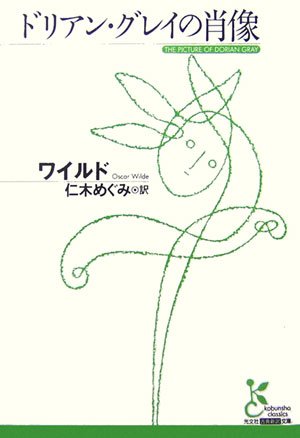hackerさん
レビュアー:
▼
『ジーキル博士とハイド氏』のヴァリエーションに、『ウィリアム・ウィルソン』を味付けした絵画怪談ですが、19世紀末という時代に書かれたということを感じさせる作品でした。
本書も、かもめ通信さん主催の「#やりなおし世界文学 読書会」で挙げられている作品で、ダブリン生まれのオスカー・ワイルド(1854-1900)の唯一の長編小説として知られています。相当前に読んだきりで、細部は忘れていましたが、さすがに、若くて身も心も美しい時に肖像画に描かれたドリアン・グレイが、年齢と共に内面が醜悪になっても、本人の外見は少しも変わらないのに、肖像画の方は醜悪になっていくというあらすじだけは覚えていました。
物語は、スティーヴンスンの『ジーキル博士とハイド氏』(1886年)のヴァリエーションに、ポーの『ウィリアム・ウィルソン』(1839年)を味付けした絵画怪談と言って良いでしょう。ポーからの影響という点では、外見と内面の差をコメディータッチで描いた『使い切った男』(1939年)や、モデルが肖像画に生気を吸い取られる『楕円形の肖像』(1842年)も挙げて良いかもしれません。今回再読していて感じたのは、1891年、いかにも19世紀の終りに刊行された作品だと言うことです。それは、全体として、ワイルドが生きていた時代のイギリスの雰囲気を強く感じさせるからです。その時代とは、ヴィクトリア朝(1837-1901)のことで、イギリス帝国の絶頂期であり、資本主義と資本家とアメリカの台頭、そして産業革命が始まった時期、言い換えると気候変動が始まった時期でもありました。
本書は、基本的には上流階級の人々の話ではあるのですが、当時の世相を反映したような様々な人物―政治家、芸術家、軍人、貴族等―が、大半は端役ではあるものの、意外なほど数多く登場することに気づかされます。同時に、下層階級の人間たち―場末の劇場主、そこの女優、船乗り、召使等―も数多く登場します。そして、その両者に対して、作者の眼がシニカルなことには驚かされます。要するに、一般的な意味で善と言える登場人物は、初めのうちのドリアン・グレイだけなのです。私には、19世紀という時代が、本来は無垢であるはずの人間をよってたかって醜悪にしてしまう話、あるいは醜悪な19世紀が表面だけはとりつくろっている話のように思えてしまいました。それと同時に、来るべき20世紀に対しては、ワイルドはきっと悲観的、あるいは絶望的だったのでないでしょうか。そういう意味では、19世紀最後の年に作者が亡くなったのも、どこか象徴的です。
また、本書には、イギリスの文化でもある皮肉なユーモア溢れる会話や表現がふんだんに使われていますが、面白いと思う反面、一部ミソジスト的な印象を受けるものがあるのは、ちょっと気になります。一例を挙げます。
「幸せな結婚について語る人たちのなんとばかげていることか!どんな女といても男は幸せになれる。その女を愛していない限り」
そんな中で、気に入っているのは、次の言葉です。
「人生は魂を育てるが、一方で肉体を損なう」
残念ですが、その通りですね。私も「精神はともかく、肉体は確実に老いる」とよく言っていました。現在では、肉体は既に立派に老いてしまったので、そういうことも言わないようになりましたが。
ただ、本書全体の印象とすると、いささか詰め込み過ぎの感があり、もう少し短くしても良かったようにも感じます。この題材そのものは、短中篇の怪奇小説向きのものですし、絵画怪談の側面を強調した方が、物語としては圧縮された傑作になったような気がします。しかし、作者の意図として、もちろんドリアン・グレイの人間としての美醜の変化が中心のテーマではあるものの、それだけでなく、ヴィクトリア朝という時代の醜悪さも書き残しておきたいということがあったのでしょう。結局、ここで描かれた19世紀末の世相を引きずりながら、世界は20世紀に突入していったわけですから。そういう点も含めて、やはり一度は読んでおきたい本だと思います。
物語は、スティーヴンスンの『ジーキル博士とハイド氏』(1886年)のヴァリエーションに、ポーの『ウィリアム・ウィルソン』(1839年)を味付けした絵画怪談と言って良いでしょう。ポーからの影響という点では、外見と内面の差をコメディータッチで描いた『使い切った男』(1939年)や、モデルが肖像画に生気を吸い取られる『楕円形の肖像』(1842年)も挙げて良いかもしれません。今回再読していて感じたのは、1891年、いかにも19世紀の終りに刊行された作品だと言うことです。それは、全体として、ワイルドが生きていた時代のイギリスの雰囲気を強く感じさせるからです。その時代とは、ヴィクトリア朝(1837-1901)のことで、イギリス帝国の絶頂期であり、資本主義と資本家とアメリカの台頭、そして産業革命が始まった時期、言い換えると気候変動が始まった時期でもありました。
本書は、基本的には上流階級の人々の話ではあるのですが、当時の世相を反映したような様々な人物―政治家、芸術家、軍人、貴族等―が、大半は端役ではあるものの、意外なほど数多く登場することに気づかされます。同時に、下層階級の人間たち―場末の劇場主、そこの女優、船乗り、召使等―も数多く登場します。そして、その両者に対して、作者の眼がシニカルなことには驚かされます。要するに、一般的な意味で善と言える登場人物は、初めのうちのドリアン・グレイだけなのです。私には、19世紀という時代が、本来は無垢であるはずの人間をよってたかって醜悪にしてしまう話、あるいは醜悪な19世紀が表面だけはとりつくろっている話のように思えてしまいました。それと同時に、来るべき20世紀に対しては、ワイルドはきっと悲観的、あるいは絶望的だったのでないでしょうか。そういう意味では、19世紀最後の年に作者が亡くなったのも、どこか象徴的です。
また、本書には、イギリスの文化でもある皮肉なユーモア溢れる会話や表現がふんだんに使われていますが、面白いと思う反面、一部ミソジスト的な印象を受けるものがあるのは、ちょっと気になります。一例を挙げます。
「幸せな結婚について語る人たちのなんとばかげていることか!どんな女といても男は幸せになれる。その女を愛していない限り」
そんな中で、気に入っているのは、次の言葉です。
「人生は魂を育てるが、一方で肉体を損なう」
残念ですが、その通りですね。私も「精神はともかく、肉体は確実に老いる」とよく言っていました。現在では、肉体は既に立派に老いてしまったので、そういうことも言わないようになりましたが。
ただ、本書全体の印象とすると、いささか詰め込み過ぎの感があり、もう少し短くしても良かったようにも感じます。この題材そのものは、短中篇の怪奇小説向きのものですし、絵画怪談の側面を強調した方が、物語としては圧縮された傑作になったような気がします。しかし、作者の意図として、もちろんドリアン・グレイの人間としての美醜の変化が中心のテーマではあるものの、それだけでなく、ヴィクトリア朝という時代の醜悪さも書き残しておきたいということがあったのでしょう。結局、ここで描かれた19世紀末の世相を引きずりながら、世界は20世紀に突入していったわけですから。そういう点も含めて、やはり一度は読んでおきたい本だと思います。
お気に入り度:







掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
「本職」は、本というより映画です。
本を読んでいても、映画好きの視点から、内容を見ていることが多いようです。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:光文社
- ページ数:447
- ISBN:9784334751180
- 発売日:2006年12月07日
- 価格:780円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。