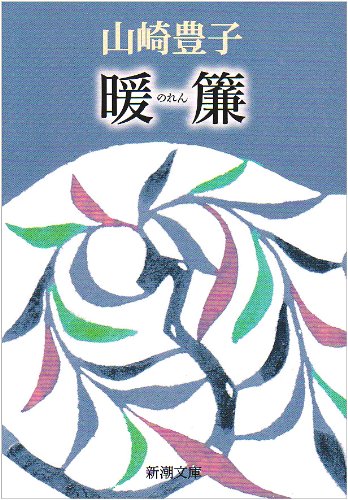すずはら なずなさん
レビュアー:
▼
丁稚奉公 「暖簾」が担保、平成、令和の子供たちにはピンとこないかもしれないけれど…
山崎豊子のデビュー作。
残念ながら本作が初読なのだが、医学界の権力闘争を題材にした有名な「白い巨塔」や中国残留孤児を扱った「大地の子」など、多くの社会問題を扱う骨太な長編作家というイメージがあった。
取材が大変そうな作品群だが、この作品の舞台は船場、主人公が携わるのが昆布商ということで、実は作者の実家がモデルなのだそうだ。昆布の仕入れの様子から種類、店頭に並ぶまでの加工の描写の細かさはリアルに見てきたことも大きいかもしれない。
淡路島から単身で大阪まで出てきた少年 吾平。たまたま通りかかった浪花屋の旦那に拾われて 丁稚として住み込んで仕事を学ぶことに。とはいえ最初は掃除だけの日々なのだが、先輩の働く姿を目で追い、声を聞き、女中たちも含め 昆布にまつわる仕事だけでなく、人間関係の作り方や世渡りのノウハウまで身に着けていく。
旦那さんに気に入ってもらえ、才能と努力を認めてもらい、着実に店の中の地位を上げていく。立場によって名前が吾平でなく吾吉、吾七などに変えられることは初めて知った。
「何事堪忍」。
旦那さんから教えられたこの言葉どおり、周囲のいじめや嫉妬にも耐え抜き、暖簾を分けてもらって自分の店を持つ。こつこつと努力を重ね、真面目で商品の質にこだわる姿勢でお客や取引先の信用を得る。
融資を頼んで工場を建てて順調にいきだしたかと思えば 水害、地震 火事。
結婚して子供ができ、家族の中に働き手、後継ぎを期待したころには 戦争。
戦争が終わり息子の代になるのが第二章だが、そこでもまた 統制経済、スト。お金の価値までごろりと変わる打撃。
「大阪は日本の経済のへそ」と言った吾平だったが、息子たちの世代では着実に経済の中心は東京へ移っていく。
デパートへの出店努力、ビル内の老舗暖簾街の計画の失敗などもあり、昔風の「堪忍」や「暖簾の力」だけでは乗り越えられない昭和のビジネス。
それでも焼け跡になったままだった本店の地に店を損得抜きで再興するところに、父への尊敬と、父から受け継いだ「暖簾」への気持ちを感じる。招待客が集まり、口伝えに再興した本店まで足を向けてくるお客様が増えていく様に心が温かくなった。
物語全編「男性の生きざま」で、親子とも結婚相手の女性に対する恋愛感情はなく、勧められた「働き者」「健康」「家計をしっかり守れる」などが決め手となり連れ合いを決めている。妻たちは文句を言うこともなく朝から晩まで夫とともに働き子供を育てていて、特に彼女らにまつわるエピソードはない。
後継ぎとして男子を産むことを望まれ、生まれたのが女の子だと詫びろと言われ、まあ、出来のいい婿を取ればいいのだと気を取り直す。すべて「暖簾」を守るためだ。
突っ込みたいところだが、ほかに女の人が主人公の立身出世、商売の話も書かれているみたいなのでこれはこれで こういう世の中だったのだ、と思っておこうと思う。理不尽だなぁとは思うけど。
二代目はぼんぼんで商才がない、というキャラクターが二人出てくる。吾平の息子たちに関してはそうでなくてよかったと心から思う。
大阪万博の掲示物があちこちにみられる昨今だが 浪速のあきんどの根性論ではもう経済は回らない世の中になったのだろうか。どこかに少しでも昔ながらの商売の道に続いてきた「よいもの」は残されているのだろうか。
残念ながら本作が初読なのだが、医学界の権力闘争を題材にした有名な「白い巨塔」や中国残留孤児を扱った「大地の子」など、多くの社会問題を扱う骨太な長編作家というイメージがあった。
取材が大変そうな作品群だが、この作品の舞台は船場、主人公が携わるのが昆布商ということで、実は作者の実家がモデルなのだそうだ。昆布の仕入れの様子から種類、店頭に並ぶまでの加工の描写の細かさはリアルに見てきたことも大きいかもしれない。
淡路島から単身で大阪まで出てきた少年 吾平。たまたま通りかかった浪花屋の旦那に拾われて 丁稚として住み込んで仕事を学ぶことに。とはいえ最初は掃除だけの日々なのだが、先輩の働く姿を目で追い、声を聞き、女中たちも含め 昆布にまつわる仕事だけでなく、人間関係の作り方や世渡りのノウハウまで身に着けていく。
旦那さんに気に入ってもらえ、才能と努力を認めてもらい、着実に店の中の地位を上げていく。立場によって名前が吾平でなく吾吉、吾七などに変えられることは初めて知った。
「何事堪忍」。
旦那さんから教えられたこの言葉どおり、周囲のいじめや嫉妬にも耐え抜き、暖簾を分けてもらって自分の店を持つ。こつこつと努力を重ね、真面目で商品の質にこだわる姿勢でお客や取引先の信用を得る。
融資を頼んで工場を建てて順調にいきだしたかと思えば 水害、地震 火事。
結婚して子供ができ、家族の中に働き手、後継ぎを期待したころには 戦争。
戦争が終わり息子の代になるのが第二章だが、そこでもまた 統制経済、スト。お金の価値までごろりと変わる打撃。
「大阪は日本の経済のへそ」と言った吾平だったが、息子たちの世代では着実に経済の中心は東京へ移っていく。
デパートへの出店努力、ビル内の老舗暖簾街の計画の失敗などもあり、昔風の「堪忍」や「暖簾の力」だけでは乗り越えられない昭和のビジネス。
それでも焼け跡になったままだった本店の地に店を損得抜きで再興するところに、父への尊敬と、父から受け継いだ「暖簾」への気持ちを感じる。招待客が集まり、口伝えに再興した本店まで足を向けてくるお客様が増えていく様に心が温かくなった。
物語全編「男性の生きざま」で、親子とも結婚相手の女性に対する恋愛感情はなく、勧められた「働き者」「健康」「家計をしっかり守れる」などが決め手となり連れ合いを決めている。妻たちは文句を言うこともなく朝から晩まで夫とともに働き子供を育てていて、特に彼女らにまつわるエピソードはない。
後継ぎとして男子を産むことを望まれ、生まれたのが女の子だと詫びろと言われ、まあ、出来のいい婿を取ればいいのだと気を取り直す。すべて「暖簾」を守るためだ。
突っ込みたいところだが、ほかに女の人が主人公の立身出世、商売の話も書かれているみたいなのでこれはこれで こういう世の中だったのだ、と思っておこうと思う。理不尽だなぁとは思うけど。
二代目はぼんぼんで商才がない、というキャラクターが二人出てくる。吾平の息子たちに関してはそうでなくてよかったと心から思う。
大阪万博の掲示物があちこちにみられる昨今だが 浪速のあきんどの根性論ではもう経済は回らない世の中になったのだろうか。どこかに少しでも昔ながらの商売の道に続いてきた「よいもの」は残されているのだろうか。
掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
電車通勤になって 少しずつでも一日のうちに本を読む時間ができました。これからも マイペースで感想を書いていこうと思います。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:新潮社
- ページ数:218
- ISBN:9784101104010
- 発売日:1979年07月04日
- 価格:420円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。