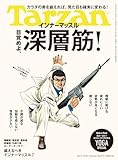hackerさん
レビュアー:
▼
「僕は世界を小さな目から見ているんだ。その目はあまりにも小さいので、世界の方は見られていることに気づかないのさ」(本書収録作『ウーリー』の登場人物の台詞)
「僕の詩を読んでくれるのは、だいたい僕の友だちぐらいだろうと思っている。でも僕の本は僕の友だちの数よりいくぶん多く売れるんだ。だからきっとどこかに僕の読者というものが存在しているんだろうね」
これは、訳者あとがきで紹介されている、カナダのプリンス・エドワード島生まれの詩人マーク・ストランド(1934-2014)の言葉です。なんか好感が持てます。本書は、彼が1985年に出版した唯一の短篇集で、全14作が収録されています。例によって、とくに印象的な作品を紹介します。
●『更なる人生を』
原題は"More Life"です。lifeをどう訳すのか、難しいところで、ネット上のロングマン現代英英辞典では、次のようになっています。
1.the period of time when someone is alive
2.the state of being alive
3.the way you live your life, and what you do and experience during it
他にも、いくつか意味が掲載されていましたが、主なものはこれぐらいでしょうか。
この話の内容は、二冊の小説を発表したものの、それ以上は書けなくなってしまい、「まったく世に認められないまま死んでしまった」父親が、時として「僕」の身近な物若しくは者に憑りついて、時々やって来る話です。しかし、自分の恋人に父親が憑りついた時から、「僕」は父親の呪縛から次第に解放されるのです。この内容と、この題名、ちょっと分かったような、分からないような話です。
●『真実の愛』
「これは告白である。私は40代半ばの男性で、これまで五度結婚した。恋愛のほうは六度―どれも結婚の枠の外側でなされたものだった。でもだからといって、妻たちをひどい目にあわせてきたというわけではない。(中略)私がこれだけ恐れも知らず結婚の回数を重ねているのをみれば、私がその制度に対して揺らぎない信念を持ち続けてきたことを理解していただけるはずだ。しかし、ならばどうして、妻以外との恋愛の数が結婚の数よりひとつ多いのだろう?それはただ単に、私の愛がどれも真実であったからだ!」
「私」の六度の「真実の愛」の顛末を語った作品です。
●『犬の人生』
夫が、ある日、妻におずおずとこんなことを言います。
「ねえ、前から君に言わなくちゃと思っていたことがあるんだよ」
だいたい、こんな風に切り出すと、いい話じゃありませんよね。
「君と会う以前は、僕は今とは違っていたというだけのことだよ」
「違っていたって、それどういうことなの?」
「いや、実を言うとな、僕は以前は犬だったんだよ」
そして夫は、それは「幸せな生活だった」と言い、どんな人生(犬生?)だったかを妻に話すのでした。
本作の原題は"Dog Life"です。実は、チャールズ・チャップリン(1889-1977)の短篇に『犬の生活』(1918年)という映画があり、チャップリンが山高帽とチョビ髭の放浪者というイメージを確立させた作品として知られています。映画の方の原題は"A Dog's Life"で、そもそも英語で"dog's life"というと「ひどい生活」「惨めな生活」という意味になります。ですから、「幸せな生活」を送っていた「犬の人生」の原題が、チャップリンの映画と違っているのは、当然なのですが、同じことを言っているようでも、片方は「ひどい生活」であり、片方は「幸せな生活」であるという二面性を語る意図があったとも解釈できます。
考えすぎと思われるかもしれませんが、複数の収録作には、しばしば映画や俳優の言及があり、作者は相当の映画ファンだったことがうかがえます。ですから、作者がチャップリンの映画の存在を知らないで、この作品を書いたとは思えないのです。
●『ウーリー』
「世間は彼の名を知らなかったし、彼にチャンスを与えなかったし、彼は認められぬまま墓に葬られてしまった」
こんな「僕の友だち」ジョージ・ウーリーの人生を語った話です。
「ウーリーの人生に比べれば、僕のほかの友人たちの人生なんて、みんな核心を欠いているように見える。彼らは退屈さを愚痴る。ウーリーならきっと『昼下がりがいささか長すぎるね』とでも言ったところだろう」
他人とは、違う物差しで生きてきた「僕の友だち」へのオマージュです。
●『ザダール』
題名は、クロアチアのダルマチア海岸にある都市の名前です。一人で旅をしていた「わたし」は、そこで出会った「どことなく陰気に美しい女」に魅せられてしまいます。女には連れの男がいましたが、「わたし」は二人の後をつけ、泊っているホテルと彼らの部屋をつきとめます。翌朝には、「わたし」は彼らの部屋を見上げるカフェで朝食を取っていました。そして、ある夜、女は「わたし」が見ていることを知りながら、バルコニーに出て、バスローブの前をはだけたのでした。そして、「わたし」と女の間には、何も起こらなかったわけではないのですが、何も起こらなかったのです。
この小説は、私に、ルイス・ブニュエル監督の映画『哀しみのトリスターナ』(1970年)を思い起こさせました。ヒロインを演じたのは『昼顔』に引き続きカトリーヌ・ドヌーヴですが、病気により片足を失ったヒロインが、窓の外にいる聾唖の少年に向かって、バスローブの前を開き、艶然と狂気の笑みを浮かべる強烈な印象を残す場面があるのです。前述しましたが、映画好きだった作者も、この映画を観ているはずで、それが頭にあったのだろうと思います。
さて、本書全体を通してみると、lifeとloveがキーワードの作品ばかりなことに気づきます。ただし、単純な結果を提示しているものはありません。村上春樹は、訳者あとがきで次のように述べています。
「ひとことで言えば、この短篇集に収められた作品はどれをとっても『ちょっと変な』ものである。『ちょっと変な』を超えて、『なんのこっちゃ』というのもいくつかある。(中略)ここでは『物語性』よりは『語り口』の方がより大きな意味を持っているように感じられるからだ。一見して寓意のようにとられる要素が多く含まれているようだが、それらの多くは計算された寓意というよりはむしろ、前にも述べたようにきわめて自発的な『イメージの羅列』に近いのではあるまいかと僕は考えている」
これは、参考になる指摘だと思います。「イメージの羅列」というと、小説ではピンと来ないかもしれませんが、映画ではブニュエルとダリが脚本を書いた『アンダルシアの犬』(1928年)という好例があります。空の月が横長の雲で遮られるカットと、女の目がカミソリで横に切られるカットが交互に映し出される冒頭の場面が有名ですが、これに「物語性」を求めても、無意味なのはお分かりでしょう。
ただし、詩ならば、この「イメージの羅列」が、より自然であり、生きてくるような気がします。もちろん、「物語性」のある詩もあるわけですが、それは詩人としての作者が求めるものではなかったのでしょう。本書は、そういう詩人の感覚で、読むべき本のようです。
これは、訳者あとがきで紹介されている、カナダのプリンス・エドワード島生まれの詩人マーク・ストランド(1934-2014)の言葉です。なんか好感が持てます。本書は、彼が1985年に出版した唯一の短篇集で、全14作が収録されています。例によって、とくに印象的な作品を紹介します。
●『更なる人生を』
原題は"More Life"です。lifeをどう訳すのか、難しいところで、ネット上のロングマン現代英英辞典では、次のようになっています。
1.the period of time when someone is alive
2.the state of being alive
3.the way you live your life, and what you do and experience during it
他にも、いくつか意味が掲載されていましたが、主なものはこれぐらいでしょうか。
この話の内容は、二冊の小説を発表したものの、それ以上は書けなくなってしまい、「まったく世に認められないまま死んでしまった」父親が、時として「僕」の身近な物若しくは者に憑りついて、時々やって来る話です。しかし、自分の恋人に父親が憑りついた時から、「僕」は父親の呪縛から次第に解放されるのです。この内容と、この題名、ちょっと分かったような、分からないような話です。
●『真実の愛』
「これは告白である。私は40代半ばの男性で、これまで五度結婚した。恋愛のほうは六度―どれも結婚の枠の外側でなされたものだった。でもだからといって、妻たちをひどい目にあわせてきたというわけではない。(中略)私がこれだけ恐れも知らず結婚の回数を重ねているのをみれば、私がその制度に対して揺らぎない信念を持ち続けてきたことを理解していただけるはずだ。しかし、ならばどうして、妻以外との恋愛の数が結婚の数よりひとつ多いのだろう?それはただ単に、私の愛がどれも真実であったからだ!」
「私」の六度の「真実の愛」の顛末を語った作品です。
●『犬の人生』
夫が、ある日、妻におずおずとこんなことを言います。
「ねえ、前から君に言わなくちゃと思っていたことがあるんだよ」
だいたい、こんな風に切り出すと、いい話じゃありませんよね。
「君と会う以前は、僕は今とは違っていたというだけのことだよ」
「違っていたって、それどういうことなの?」
「いや、実を言うとな、僕は以前は犬だったんだよ」
そして夫は、それは「幸せな生活だった」と言い、どんな人生(犬生?)だったかを妻に話すのでした。
本作の原題は"Dog Life"です。実は、チャールズ・チャップリン(1889-1977)の短篇に『犬の生活』(1918年)という映画があり、チャップリンが山高帽とチョビ髭の放浪者というイメージを確立させた作品として知られています。映画の方の原題は"A Dog's Life"で、そもそも英語で"dog's life"というと「ひどい生活」「惨めな生活」という意味になります。ですから、「幸せな生活」を送っていた「犬の人生」の原題が、チャップリンの映画と違っているのは、当然なのですが、同じことを言っているようでも、片方は「ひどい生活」であり、片方は「幸せな生活」であるという二面性を語る意図があったとも解釈できます。
考えすぎと思われるかもしれませんが、複数の収録作には、しばしば映画や俳優の言及があり、作者は相当の映画ファンだったことがうかがえます。ですから、作者がチャップリンの映画の存在を知らないで、この作品を書いたとは思えないのです。
●『ウーリー』
「世間は彼の名を知らなかったし、彼にチャンスを与えなかったし、彼は認められぬまま墓に葬られてしまった」
こんな「僕の友だち」ジョージ・ウーリーの人生を語った話です。
「ウーリーの人生に比べれば、僕のほかの友人たちの人生なんて、みんな核心を欠いているように見える。彼らは退屈さを愚痴る。ウーリーならきっと『昼下がりがいささか長すぎるね』とでも言ったところだろう」
他人とは、違う物差しで生きてきた「僕の友だち」へのオマージュです。
●『ザダール』
題名は、クロアチアのダルマチア海岸にある都市の名前です。一人で旅をしていた「わたし」は、そこで出会った「どことなく陰気に美しい女」に魅せられてしまいます。女には連れの男がいましたが、「わたし」は二人の後をつけ、泊っているホテルと彼らの部屋をつきとめます。翌朝には、「わたし」は彼らの部屋を見上げるカフェで朝食を取っていました。そして、ある夜、女は「わたし」が見ていることを知りながら、バルコニーに出て、バスローブの前をはだけたのでした。そして、「わたし」と女の間には、何も起こらなかったわけではないのですが、何も起こらなかったのです。
この小説は、私に、ルイス・ブニュエル監督の映画『哀しみのトリスターナ』(1970年)を思い起こさせました。ヒロインを演じたのは『昼顔』に引き続きカトリーヌ・ドヌーヴですが、病気により片足を失ったヒロインが、窓の外にいる聾唖の少年に向かって、バスローブの前を開き、艶然と狂気の笑みを浮かべる強烈な印象を残す場面があるのです。前述しましたが、映画好きだった作者も、この映画を観ているはずで、それが頭にあったのだろうと思います。
さて、本書全体を通してみると、lifeとloveがキーワードの作品ばかりなことに気づきます。ただし、単純な結果を提示しているものはありません。村上春樹は、訳者あとがきで次のように述べています。
「ひとことで言えば、この短篇集に収められた作品はどれをとっても『ちょっと変な』ものである。『ちょっと変な』を超えて、『なんのこっちゃ』というのもいくつかある。(中略)ここでは『物語性』よりは『語り口』の方がより大きな意味を持っているように感じられるからだ。一見して寓意のようにとられる要素が多く含まれているようだが、それらの多くは計算された寓意というよりはむしろ、前にも述べたようにきわめて自発的な『イメージの羅列』に近いのではあるまいかと僕は考えている」
これは、参考になる指摘だと思います。「イメージの羅列」というと、小説ではピンと来ないかもしれませんが、映画ではブニュエルとダリが脚本を書いた『アンダルシアの犬』(1928年)という好例があります。空の月が横長の雲で遮られるカットと、女の目がカミソリで横に切られるカットが交互に映し出される冒頭の場面が有名ですが、これに「物語性」を求めても、無意味なのはお分かりでしょう。
ただし、詩ならば、この「イメージの羅列」が、より自然であり、生きてくるような気がします。もちろん、「物語性」のある詩もあるわけですが、それは詩人としての作者が求めるものではなかったのでしょう。本書は、そういう詩人の感覚で、読むべき本のようです。
お気に入り度:





掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
「本職」は、本というより映画です。
本を読んでいても、映画好きの視点から、内容を見ていることが多いようです。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:中央公論新社
- ページ数:0
- ISBN:9784122039285
- 発売日:2001年11月01日
- 価格:649円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。