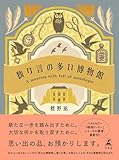三太郎さん
レビュアー:
▼
芥川賞受賞作家が50代になってから登山を始めた話。
著者の南木佳士さんは1951年というから戦後まもなくの生まれで僕より6歳年上。群馬県の浅間山の麓の嬬恋村で生まれ、奥さんとはお隣同士の幼馴染らしい。
この本は2011年に上梓されたが、もとは雑誌「山と渓谷」に連載されたもの。著者は現役の医師で小説家であったが、38歳で芥川賞を受賞して直ぐにパニック障害とうつに悩まされるようになった。50歳になった頃から奥さんと一緒に山歩きを始めたことでやっと心身の健康を取り戻せたという。
内容は雑誌に掲載された「ためらいの笠ヶ岳から槍ヶ岳」、「何度でも浅間山」、「つれられて白峰三山」の紀行文3篇と書下ろしの「山を下りてから」からなる。
掲載された雑誌は名前から分かるように、山歩きの好きなハイカー向けの山岳雑誌で、著者が訪れた山は読者もよく知っている(登ったことのある)山だ。僕も浅間山を除けばよく知っている山域である。
最初の北アルプス(笠ヶ岳〜槍ヶ岳)と三番目の南アルプス(白峰三山)の山行はどちらも著者の勤務先の看護師や技師達とのテント山行で、30〜40代の若いメンバーに50代の著者が引っ張ってもらっている感じだ。
メンバーは6名でテントを持ち食事もすべて自炊だから背負う荷物もかなりの重さだが、著者はだいぶ若い人に持ってもらったらしい。夏休みを利用してのテント山行は、僕も20〜30代の頃に東北の山の縦走登山で経験したが、北アルプスや南アルプスでは山小屋を利用して自炊していた。テントを背負っての3000m級の山歩きは体にかなりの負担を強いるはずだ。
北アルプスの時は生の米を炊飯したらしく3000m近い高度では芯の残ったご飯になったが、2年後の南アルプスの時にはレトルトご飯を使ったらしい。気圧の低い高山では沸点が下がるのでお米は炊きにくい。
著者は中高とサッカーをやっていたからか山道での下りの足運びは得意で、坂を走って下ったとか(僕は登りには強いが下りが大の苦手だった)。
最後の「山を下りてから」ではNHKの番組「ようこそ先輩」に出演した話が載っている。この時は母校の小学生を連れて浅間山に登り生徒に作文を書かせている。生徒を連れての登山は想像以上に大変だったようだ。
著者にとって、何も考えずに無心で(苦しくて何も考えられないので)山道を上り下りする過程が心の治療にもなったようだ。これは誰にとっても同じようなことがいえるのかも。
著者は僕も大好きな古代ギリシャの哲学者のエピクロスのファンらしい。岩波文庫の「エピクロス」からの引用が何個所かあった。山登りはエピクロスの哲学に通じるものがあるのかも。
この本は2011年に上梓されたが、もとは雑誌「山と渓谷」に連載されたもの。著者は現役の医師で小説家であったが、38歳で芥川賞を受賞して直ぐにパニック障害とうつに悩まされるようになった。50歳になった頃から奥さんと一緒に山歩きを始めたことでやっと心身の健康を取り戻せたという。
内容は雑誌に掲載された「ためらいの笠ヶ岳から槍ヶ岳」、「何度でも浅間山」、「つれられて白峰三山」の紀行文3篇と書下ろしの「山を下りてから」からなる。
掲載された雑誌は名前から分かるように、山歩きの好きなハイカー向けの山岳雑誌で、著者が訪れた山は読者もよく知っている(登ったことのある)山だ。僕も浅間山を除けばよく知っている山域である。
最初の北アルプス(笠ヶ岳〜槍ヶ岳)と三番目の南アルプス(白峰三山)の山行はどちらも著者の勤務先の看護師や技師達とのテント山行で、30〜40代の若いメンバーに50代の著者が引っ張ってもらっている感じだ。
メンバーは6名でテントを持ち食事もすべて自炊だから背負う荷物もかなりの重さだが、著者はだいぶ若い人に持ってもらったらしい。夏休みを利用してのテント山行は、僕も20〜30代の頃に東北の山の縦走登山で経験したが、北アルプスや南アルプスでは山小屋を利用して自炊していた。テントを背負っての3000m級の山歩きは体にかなりの負担を強いるはずだ。
北アルプスの時は生の米を炊飯したらしく3000m近い高度では芯の残ったご飯になったが、2年後の南アルプスの時にはレトルトご飯を使ったらしい。気圧の低い高山では沸点が下がるのでお米は炊きにくい。
著者は中高とサッカーをやっていたからか山道での下りの足運びは得意で、坂を走って下ったとか(僕は登りには強いが下りが大の苦手だった)。
最後の「山を下りてから」ではNHKの番組「ようこそ先輩」に出演した話が載っている。この時は母校の小学生を連れて浅間山に登り生徒に作文を書かせている。生徒を連れての登山は想像以上に大変だったようだ。
著者にとって、何も考えずに無心で(苦しくて何も考えられないので)山道を上り下りする過程が心の治療にもなったようだ。これは誰にとっても同じようなことがいえるのかも。
著者は僕も大好きな古代ギリシャの哲学者のエピクロスのファンらしい。岩波文庫の「エピクロス」からの引用が何個所かあった。山登りはエピクロスの哲学に通じるものがあるのかも。
お気に入り度:





掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
1957年、仙台に生まれ、結婚後10年間世田谷に住み、その後20余年横浜に住み、現在は仙台在住。本を読んで、思ったことあれこれを書いていきます。
長年、化学メーカーの研究者でした。2019年から滋賀県で大学の教員になりましたが、2023年3月に退職し、10月からは故郷の仙台に戻りました。プロフィールの写真は還暦前に米国ピッツバーグの岡の上で撮ったものです。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:山と渓谷社
- ページ数:0
- ISBN:9784635320030
- 発売日:2011年03月18日
- 価格:57円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。
『山行記』のカテゴリ
登録されているカテゴリはありません。