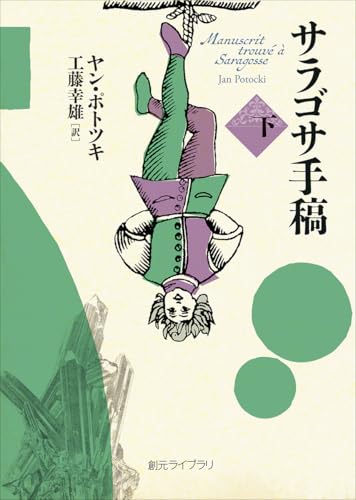そうきゅうどうさん
レビュアー:
▼
本作が奇書と呼ばれる由縁は、その来歴と物語の構造によるものと思われる。そこで語られるのは、史実の中に虚構を混ぜ込んだ、言わば「ヨーロッパ・中東裏面史(嘘)」である。
ポーランド人の大貴族にして旅行家、考古学者、歴史家であるヤン・ポトツキによって書かれた奇想小説──この『サラゴサ手稿』をごく短く紹介するなら、そんなところになるだろうか。そしてまた、『サラゴサ手稿』は奇書だと言われている。世にはさまざまな奇書と呼ばれる本があるが、本作が奇書と呼ばれる由縁は、その来歴と物語の構造によるものと思われる。
ナポレオン軍によるエスパーニャ(注:スペインのこと)の町、サラゴサの包囲戦に加わった、とあるフランス軍士官が町の小館で手書きの原稿の束を見つける。つたないエスパーニャ語の知識で頑張って読んでみるとかなり面白く、それを持ち帰ろうとしたのだが、勢いを盛り返したエスパーニャ軍に押されて撤退する中で敵の捕虜となり、手稿も奪われそうになる。ところが、その手稿を読んだ敵の隊長が「この中に自分の先祖の1人が出てくる。よく見つけてくれた」と大いに喜び、歓待してくれた。そこで隊長に頼んでフランス語に訳してもらったものを書き留めたのが本作『サラゴサ手稿』である──という設定で、この物語は始まる(もちろん、あくまでも「設定」である。なお、こういう設定が物語の何らかの伏線になっているのでは?と思う人もいるだろうが、それはない)。
このように、本作は「実在した手稿に書かれていた話」という虚構の枠の中で語られるのだが、そこにあるのは、物語の語り手が語る物語の中の登場人物が、また物語の語り手として別の物語を語り出し、更にその物語の中の登場人物が、また物語の語り手として別の物語を語り出し…という形の、いくつもの物語が入れ子構造になった物語だ。その複雑さに物語の登場人物の1人、数学者のベラスケスは、こんな風に嘆く。
ちなみに私が読んだ創元ライブラリの『サラゴサ手稿』は、その真正版が特定されるまで最も信頼性が高いとされた異本から訳出されたもので、真正版が61日間の物語なのに対して、こちらは66日間の物語となっている(つまり、ポトツキが書いたものに別の誰かが勝手に物語を付け加えていた、ということだ)。
さて、本作で語られるのは、史実の中に虚構を混ぜ込んだ、言わば「ヨーロッパ・中東裏面史(嘘)」である。だがそれは、山田風太郎忍法帖のような奇々怪々な冒険活劇ではなく、どちらかというと史実に『源氏物語』を絡めたような、貴族たちの恋愛遊戯兼政治劇の色合いが強い。とはいえ「面白いか?」と問われると、少なくとも私には「メチャメチャ面白い」とは言い難い。ヨーロッパ・中東の政治史、宗教史などに精通している人が読めば、ここでの色恋沙汰があの事件に関わってくるのか!?といった驚きやワクワクがあるかもしれないが、私のように膨大な注釈に頼ってやっと話について行っているようだと、物語構造の複雑さと相まって読み通すのは結構大変だと言っておこう。
読んでいると、こんな複雑で取り止めのない話、どうやって終わらせるんだろう?と心配になるが、不思議なことに物語はちゃんと終わるので、その点はご心配なく。
現在、日本では2種類の『サラゴサ手稿』の全訳が出ている。いずれも上中下の全3巻からなり、1つはこの工藤幸雄訳による創元ライブラリ版、もう1つは畑浩一郎訳による岩波文庫版である。前者は異本、後者は真正版からの翻訳であり、特に中巻の内容が大きく異なる。実はどちらを読むか迷ったのだが、“なんちゃってフォトリーディング”を行ってみたところ、後者は何も感じるところがなかったのに対して、前者は多少なりとも引っかかりを感じて、前者を読むことにした次第。まあ奇書と言われている本なので、より変な版で読んだ方が面白いということはあると思う。
余談だが、この創元ライブラリ版のカバーは、底本となったポーランド語の異本の表紙で使われていたマルセイユ版タロットの「吊るし」あるいは「吊るされた男」を踏襲していて(上中下の各巻で色を変えているが)、なぜこの絵が使われているのかは本文を読むと分かる。なお、岩波文庫版の表紙はポトツキ本人の書いたイラストが使われているとか。
ナポレオン軍によるエスパーニャ(注:スペインのこと)の町、サラゴサの包囲戦に加わった、とあるフランス軍士官が町の小館で手書きの原稿の束を見つける。つたないエスパーニャ語の知識で頑張って読んでみるとかなり面白く、それを持ち帰ろうとしたのだが、勢いを盛り返したエスパーニャ軍に押されて撤退する中で敵の捕虜となり、手稿も奪われそうになる。ところが、その手稿を読んだ敵の隊長が「この中に自分の先祖の1人が出てくる。よく見つけてくれた」と大いに喜び、歓待してくれた。そこで隊長に頼んでフランス語に訳してもらったものを書き留めたのが本作『サラゴサ手稿』である──という設定で、この物語は始まる(もちろん、あくまでも「設定」である。なお、こういう設定が物語の何らかの伏線になっているのでは?と思う人もいるだろうが、それはない)。
このように、本作は「実在した手稿に書かれていた話」という虚構の枠の中で語られるのだが、そこにあるのは、物語の語り手が語る物語の中の登場人物が、また物語の語り手として別の物語を語り出し、更にその物語の中の登場人物が、また物語の語り手として別の物語を語り出し…という形の、いくつもの物語が入れ子構造になった物語だ。その複雑さに物語の登場人物の1人、数学者のベラスケスは、こんな風に嘆く。
話の辻褄がどうも合わない。だれが話して、だれが聞いてるのか、混乱しますよ。(中略)あっちに飛んだり、こっちに戻ったり、これじゃまるで迷路だ。そして、その構造ゆえか、本作には数多くの異本、剽窃本が存在し、一体何が真正本なのか分からない状態が長らく続いていた。それが21世紀になって、ポトツキが生前に完結させた版が特定され、現在ではそれが真正版とされている。
ちなみに私が読んだ創元ライブラリの『サラゴサ手稿』は、その真正版が特定されるまで最も信頼性が高いとされた異本から訳出されたもので、真正版が61日間の物語なのに対して、こちらは66日間の物語となっている(つまり、ポトツキが書いたものに別の誰かが勝手に物語を付け加えていた、ということだ)。
さて、本作で語られるのは、史実の中に虚構を混ぜ込んだ、言わば「ヨーロッパ・中東裏面史(嘘)」である。だがそれは、山田風太郎忍法帖のような奇々怪々な冒険活劇ではなく、どちらかというと史実に『源氏物語』を絡めたような、貴族たちの恋愛遊戯兼政治劇の色合いが強い。とはいえ「面白いか?」と問われると、少なくとも私には「メチャメチャ面白い」とは言い難い。ヨーロッパ・中東の政治史、宗教史などに精通している人が読めば、ここでの色恋沙汰があの事件に関わってくるのか!?といった驚きやワクワクがあるかもしれないが、私のように膨大な注釈に頼ってやっと話について行っているようだと、物語構造の複雑さと相まって読み通すのは結構大変だと言っておこう。
読んでいると、こんな複雑で取り止めのない話、どうやって終わらせるんだろう?と心配になるが、不思議なことに物語はちゃんと終わるので、その点はご心配なく。
現在、日本では2種類の『サラゴサ手稿』の全訳が出ている。いずれも上中下の全3巻からなり、1つはこの工藤幸雄訳による創元ライブラリ版、もう1つは畑浩一郎訳による岩波文庫版である。前者は異本、後者は真正版からの翻訳であり、特に中巻の内容が大きく異なる。実はどちらを読むか迷ったのだが、“なんちゃってフォトリーディング”を行ってみたところ、後者は何も感じるところがなかったのに対して、前者は多少なりとも引っかかりを感じて、前者を読むことにした次第。まあ奇書と言われている本なので、より変な版で読んだ方が面白いということはあると思う。
余談だが、この創元ライブラリ版のカバーは、底本となったポーランド語の異本の表紙で使われていたマルセイユ版タロットの「吊るし」あるいは「吊るされた男」を踏襲していて(上中下の各巻で色を変えているが)、なぜこの絵が使われているのかは本文を読むと分かる。なお、岩波文庫版の表紙はポトツキ本人の書いたイラストが使われているとか。
お気に入り度:







掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
「ブクレコ」からの漂流者。「ブクレコ」ではMasahiroTakazawaという名でレビューを書いていた。今後は新しい本を次々に読む、というより、過去に読んだ本の再読、精読にシフトしていきたいと思っている。
職業はキネシオロジー、クラニオ、鍼灸などを行う治療家で、そちらのHPは→https://sokyudo.sakura.ne.jp
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:東京創元社
- ページ数:0
- ISBN:9784488070618
- 発売日:2024年08月30日
- 価格:1320円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。