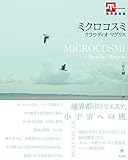かもめ通信さん
レビュアー:
▼
「おそらく人間はみな、生きるという行為でもって、どこにもない一つの詩を綴る。」店にも町にも山間の村にもそうした詩がしみついていて、いまもいつも誰かに読み解かれることを待っているのかもしれない。
自分の足で訪れたことはないにもかかわらず、私にとってトリエステはどこか懐かしい街だ。
大好きな須賀敦子が最愛の夫ペッピーノとともに読み明かしたウンベルト・サバの詩集。
夫の死後、
旧市街の黒いスレート屋根の上に、淡い色の空がひろがり、その向こうにアドリア海。
それらすべてを背に大きな白い花束のようなカモメの群れが、円く輪をえがきながら宙に舞っている。
『トリエステの坂道』で須賀が綴る町並みは、そのまま私の記憶となる。
だからだろうか、この本を開いて黒い寄せ木細工でできたバーカウンターのあるカフェ・サンマルコを訪れた時、なぜだかとても懐かしい気持ちになったのは。
カフェは、そのままトリエステの縮図でもあるかのように、人種も国籍も、職業も思想も…なにもかもが多様性に満ちている。
イタリア北東部、アドリア海最奥に位置する港湾都市トリエステは、中世にはヴェネツィア領に、オーストリアーハンガリー帝国の時代を経て、第一次世界大戦後にイタリア領となるも、第二次世界大戦でドイツ軍に占領され、その後チトーによって解放され、戦後はイタリアとユーゴ間の紛争地になるという複雑な歴史をもつ街で、歴史的にも地理的にも人種的にも文化的にもイタリアはもとより、ドイツ、スロヴェニア、クロアチアと切っても切れない縁を持っているのだという。
様々な人が訪れるそのカフェで、作家は物思いに沈み、詩人は詩を書く。
ページをめくり、ストーリーがあるようでないような展開に戸惑いながらも、ああこれは、主人公が何かを成し遂げた、あるいは成し遂げなかったとかいう物語ではなく、おそらくはそのカフェの、あるいはその土地の、記憶を読み解く、そんな物語なのだろうとあたりをつける。
カフェを出て谷あいの小さな村を訪れ、潟が点在するグラードに向かい、スロヴェニアとの国境に広がる森林を探索する。
少し離れたトリノにも、湾を超えてクロアチアにも。
その土地で暮らす人々の歴史やその土地が生んだ作家や詩人が行間からあふれだす。
山間の村で育ち頑として信仰に従っていた少女は、やがてその生涯の半分以上を将軍への愛にささげることになった。そのほとんどは結婚したことのないはずの相手の未亡人として。
ファシズムにも共産主義にも加担したくなかった男が恐れていたのは、戦争でも地雷でも魚雷でもなく「飢え」だった。
ネオファシストになった女には、彼女なりの理由があった。
店にも町にも山間の村にもそうした詩がしみついていて、誰かに読み解かれることを待っているそうした詩を訪ね歩いて、作家は物語を紡いでいるに違いないという気がしてくる。
同時に作家は、遭遇することを期待して歩きまわっても会うことができない動物を思いながら、排泄物を見て喜び合う森歩きのあるあるや、夏の夜の青みがかった黒い夜など、その土地に限らず、広い世界の普遍的なあれこれを美しく語りあげもする。
タイトルのついた章ごとであっても、ひと段落ごとであっても、なんなら一行ずつであっても、どこから読んでも、どこへ飛んでも、不思議と読みごたえがあって、読むたびになにか気づきがあるような、そんな不思議な物語。
実をいうと読み始めてもう2年ほどになるのだが、最後までページをめくっても不思議と読み終えたという感じがしない。
わかるとかわからないとかいうことではなく、読み終えることを目的としない、そんな読書があってもいいと思える一冊。
物語は、細部にだわって読み込むときと、全体を遠巻きに眺めるときとはみえるものが違ってくる、そんなところも面白い。
大好きな須賀敦子が最愛の夫ペッピーノとともに読み明かしたウンベルト・サバの詩集。
夫の死後、
実像のトリエステにあって、たぶんそこにはない詩の中の虚構をたしかめようとするのは、無意味ではないかと自問自答しながらも、無理を押してでも須賀が訪れずにはいられなかった、詩人を生んだ街それがトリエステだ。
旧市街の黒いスレート屋根の上に、淡い色の空がひろがり、その向こうにアドリア海。
それらすべてを背に大きな白い花束のようなカモメの群れが、円く輪をえがきながら宙に舞っている。
『トリエステの坂道』で須賀が綴る町並みは、そのまま私の記憶となる。
だからだろうか、この本を開いて黒い寄せ木細工でできたバーカウンターのあるカフェ・サンマルコを訪れた時、なぜだかとても懐かしい気持ちになったのは。
カフェは、そのままトリエステの縮図でもあるかのように、人種も国籍も、職業も思想も…なにもかもが多様性に満ちている。
イタリア北東部、アドリア海最奥に位置する港湾都市トリエステは、中世にはヴェネツィア領に、オーストリアーハンガリー帝国の時代を経て、第一次世界大戦後にイタリア領となるも、第二次世界大戦でドイツ軍に占領され、その後チトーによって解放され、戦後はイタリアとユーゴ間の紛争地になるという複雑な歴史をもつ街で、歴史的にも地理的にも人種的にも文化的にもイタリアはもとより、ドイツ、スロヴェニア、クロアチアと切っても切れない縁を持っているのだという。
様々な人が訪れるそのカフェで、作家は物思いに沈み、詩人は詩を書く。
ページをめくり、ストーリーがあるようでないような展開に戸惑いながらも、ああこれは、主人公が何かを成し遂げた、あるいは成し遂げなかったとかいう物語ではなく、おそらくはそのカフェの、あるいはその土地の、記憶を読み解く、そんな物語なのだろうとあたりをつける。
カフェを出て谷あいの小さな村を訪れ、潟が点在するグラードに向かい、スロヴェニアとの国境に広がる森林を探索する。
少し離れたトリノにも、湾を超えてクロアチアにも。
その土地で暮らす人々の歴史やその土地が生んだ作家や詩人が行間からあふれだす。
山間の村で育ち頑として信仰に従っていた少女は、やがてその生涯の半分以上を将軍への愛にささげることになった。そのほとんどは結婚したことのないはずの相手の未亡人として。
ファシズムにも共産主義にも加担したくなかった男が恐れていたのは、戦争でも地雷でも魚雷でもなく「飢え」だった。
ネオファシストになった女には、彼女なりの理由があった。
おそらく人間はみな、生きるという行為でもって、どこにもない一つの詩を綴る。(p147)
店にも町にも山間の村にもそうした詩がしみついていて、誰かに読み解かれることを待っているそうした詩を訪ね歩いて、作家は物語を紡いでいるに違いないという気がしてくる。
同時に作家は、遭遇することを期待して歩きまわっても会うことができない動物を思いながら、排泄物を見て喜び合う森歩きのあるあるや、夏の夜の青みがかった黒い夜など、その土地に限らず、広い世界の普遍的なあれこれを美しく語りあげもする。
タイトルのついた章ごとであっても、ひと段落ごとであっても、なんなら一行ずつであっても、どこから読んでも、どこへ飛んでも、不思議と読みごたえがあって、読むたびになにか気づきがあるような、そんな不思議な物語。
実をいうと読み始めてもう2年ほどになるのだが、最後までページをめくっても不思議と読み終えたという感じがしない。
わかるとかわからないとかいうことではなく、読み終えることを目的としない、そんな読書があってもいいと思える一冊。
世界はよく知られているが、近いはずの地域社会は知られていない(p169)
物語は、細部にだわって読み込むときと、全体を遠巻きに眺めるときとはみえるものが違ってくる、そんなところも面白い。
掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
本も食べ物も後味の悪くないものが好きです。気に入ると何度でも同じ本を読みますが、読まず嫌いも多いかも。2020.10.1からサイト献本書評以外は原則★なし(超絶お気に入り本のみ5つ★を表示)で投稿しています。
この書評へのコメント
- かもめ通信2024-11-25 05:32
祝! #共和国 10周年読書会 参加レビューです。
https://www.honzuki.jp/bookclub/theme/no442/index.html?latest=20
12/1までやっていますので、よかったらぜひ覗いてみてください。
クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - たけぞう2024-11-25 22:06
>かもめ通信さん
「わかるとかわからないとかいうことではなく、読み終えることを目的としない、そんな読書があってもいいと思える一冊。」
すごい一文に出合った気持ちです。そうか、そうなんですね。まだまだ修行が足りないです。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 
コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:共和国
- ページ数:0
- ISBN:9784907986551
- 発売日:2022年01月25日
- 価格:3740円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。