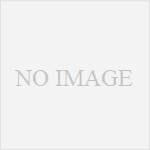hackerさん
レビュアー:
▼
「命は安い、だが楽しめもする」 (本書収録、作者の長男マーク・ベルリン著『物語こそがすべて』で引用されているメキシコの人生訓)
皆さま、あけましておめでとうございます。昨年中はお世話になりました。本年も、いろいろな本のことを教えて下さい。よろしくお願いいたします。
さて、本年度最初に読む本は、昨年より本書と決めていました。ルシア・ベルリン(1936-2004)の『掃除婦のための手引書』『すべての月、すべての年』に続く、三冊目の邦訳短篇集ですから、面白くないはずがありません。早速、内容の紹介に入りますが、本書には作者の長男マーク・ベルリンが母のことを書いた『物語こそがすべて』と題するエッセーも収録されていますから、まずそれに触れます。このエッセーは次のように始まります。
「いまは亡き母ルシアは、反逆の徒にして腕ききの職人、そして若かりし頃はつねに踊っていた。思い出をここでぜんぶ話せたらどんなにいいだろう」
そして、次のように終わります。
「母は本当にあったことを書いた。完全に事実ではないにせよ、ほぼそれに近いことを。わが家の逸話や思い出話は徐々に改変され、脚色され、編集され、しまいにはどれが本当のできごとかわからなくなった。それでいい、とルシアは言った。物語こそがすべてなのだから」
彼女の波乱万丈、ある意味で壮絶な人生については、『掃除婦のための手引書』のレビューでも述べていますし、その本の解説にも詳しいので、省略しますが、この文の中でも、軽く触れています。
「彼女は三人の夫より長生きしたし、何人いたかもわからない恋人となるともはや神のみぞ知るだ。14歳のときに医者から一生子供は産めないだろう、30より長くは生きられまいと言われた彼女が、結局4人の息子を産んだ。(中略)4人が4人とも育てるにはひどく難物だった。でも彼女はやり遂げた。もののみごとに」
本書には20の短篇と、単行本2ページに収まる2掌編が収められています。後者の方では、内容は紹介しませんが、男性の語りによる『雨の日』が印象的でした。例によって、特に印象的なものを紹介します。
●『日干しレンガのブリキ屋根の家』
「建って百年はたつ」井戸はあるものの「水道もないし電気もない」メキシコの荒野の一軒家に住むことになった、二人の連れ子と一緒にジャズミューシャンの夫と二度目の結婚をした、19歳のマヤの苦労を語る話です。おかしいという意味では、本書でいちばんおかしい話です。三人称で書かれていますが、ヒロインが作者の反映であることは間違いないでしょう。
●『楽園の夕べ』
メキシコの海に面したプエルト・パジャルタの近くでロケをした映画『イグアナの夜』(1964年)撮影中のエピソードを語った作品です。テネシー・ウィリアムズ原作で、監督ジョン・ヒューストンを始めとし、出演者リチャード・バートン、彼に連れ添って来た前夫と離婚手続き中だったエリザベス・テイラー、同じく出演者でキューブリック監督の『ロリータ』で主演したスー・リオン、そしてエヴァ・ガードナーらが実名で登場していて、小説としてよりも、そういう下世話な観点で面白かったので紹介しておきます。エヴァ・ガードナーが撮影時、メキシコ人の若いビーチ・ボーイをいわば飼っていたのは、ジョン・ヒューストンの自伝『王になろうとした男』にも同じ記述がありますから、本当でしょう。
●『わたしの人生は開いた本』
小高い丘にあり、他の家からもよく見える、町でも評判のボロ屋にクレアという女性が引っ越してきました。
「クレアは30そこそこ、旦那とは離婚していて、4人の子持ちだった。いちばん上が10ぐらい、いちばんちっこいのはまだ歩けもしなかった。大学でスペイン語を教えていて、家庭教師もしていた。毎朝上の子たちを学校に送っていき、チビたちはルペ・バルガスのとこへ預ける。家の内壁にペンキを塗るのも、家畜の囲いを立てるのも野菜を植えるのも、ウサギ小屋を作るのもぜんぶ独りでやった。もちろん自分たちではウサギもアヒルも食べやしない。ただそこらじゅう走りまわらせていた。ヤギとポニーも一頭ずつ、それに犬が二頭と猫も十匹かそこらいた。(中略)
子供がわんさかいた、自分の子も、近所の子たちも。木に登り、バンに乗り、三輪車やポニーにまたがってスプリンクラーの中をくぐり抜けた。窓という窓に猫がいた」
作者自身の、四人の子育て中のシングル・マザー時代に材をとった作品です。別の町民の語りと、作者自身の一人称が、交互に使われているスタイルで、他人からどう見られていたか、そして自分がどう思っていたかのギャップが面白いです。また、町民からは、なかなか働き者のお母さんじゃないという評価を得られそうだったのが、まだ十代の不良と定評のある少年とできてしまったため、愛想を尽かされるという展開も、作者の恋愛に対する奔放ぶりが、よく表れています。そして、ある事件が起こるのですが、この顛末が、また、おかしいのです。
●『妻たち』
同じ男と結婚・離婚し、共にアル中になった二人の女友達が、二度目に結婚した女の家で、酒を呑みながら、クダをまく話です。同じ男性と結婚した女同士の会話ということで、これもおかしいのですが、悲しくもあります。
●『ルーブルで迷子』
「子供のころ、自分に眠りが訪れる瞬間をなんとかしてとらえようとした。横になってじっとその時を待つが、次に気づくともう朝だった。(中略)
死の瞬間をとらえようなどと考えたことはなかったけれど、パリでそれを経験した。人に死が訪れる瞬間を感じたのだ」
本書でいちばん好きな作品です。パリの優れた紀行文と呼んでもいいでしょう。ただし、パリの街を徘徊したり、カフェに何時間も座って道行く人を眺めたり、ルーブルで「サモトラケのニケ」に感銘を受けたり、でも人が多すぎるので「モナリザ」は見なかったり、そして、ある程度年老いて自分の死を意識するようになった人向きかもしれません。プルーストが好きな方なら、プルーストがコンブレーのモデルとした村イリエ(現在の名前はイリエ・コンブレー)を訪れた時の虚無感に感銘を受けるでしょう。
死ぬ前にもう一度パリに行き、50年前と行き交う人間が変わっただけのパリの街を徘徊し、どこかのカフェで自分の過去と自分の死を見つめておこうと思わせてくれました。
●『陰』
作者が20年ぶりにメキシコを訪れ、闘牛見物をした時の話です。牛にあざやかに死を与えたり、それに手こずったりする闘牛士の技と観客の熱狂と並行して、客席に訪れるありふれた突然死が語られる話です。闘牛場に引き出され、一撃で死ぬ牛も、死ぬのに時間がかかる牛もいる姿が、人間の最期を連想させます。
さて最後にですが、本書に関しては、正直なところ、全体の印象としては前二冊ほどではありません。もちろん、つまらないということではなく、前二冊が素晴らしすぎたということなのでしょう。前二冊は2015年に出版された、『物語こそがすべて』を序文としたルシア・ベルリン選集の全訳だったので、当然なのかもしれません。本書は、その選集からもれた作品が収録されているわけですが、初期の作品よりは、生きる苦しみとやけっぱちな喜びが同居している後期の作品の方に、作者の本領が発揮されていることを感じます。いずれにしても、ルシア・ベルリンは繰り返し読む価値があります。そして、おそらく何度も読んだ方が、味わいが深まることでしょう。
さて、本年度最初に読む本は、昨年より本書と決めていました。ルシア・ベルリン(1936-2004)の『掃除婦のための手引書』『すべての月、すべての年』に続く、三冊目の邦訳短篇集ですから、面白くないはずがありません。早速、内容の紹介に入りますが、本書には作者の長男マーク・ベルリンが母のことを書いた『物語こそがすべて』と題するエッセーも収録されていますから、まずそれに触れます。このエッセーは次のように始まります。
「いまは亡き母ルシアは、反逆の徒にして腕ききの職人、そして若かりし頃はつねに踊っていた。思い出をここでぜんぶ話せたらどんなにいいだろう」
そして、次のように終わります。
「母は本当にあったことを書いた。完全に事実ではないにせよ、ほぼそれに近いことを。わが家の逸話や思い出話は徐々に改変され、脚色され、編集され、しまいにはどれが本当のできごとかわからなくなった。それでいい、とルシアは言った。物語こそがすべてなのだから」
彼女の波乱万丈、ある意味で壮絶な人生については、『掃除婦のための手引書』のレビューでも述べていますし、その本の解説にも詳しいので、省略しますが、この文の中でも、軽く触れています。
「彼女は三人の夫より長生きしたし、何人いたかもわからない恋人となるともはや神のみぞ知るだ。14歳のときに医者から一生子供は産めないだろう、30より長くは生きられまいと言われた彼女が、結局4人の息子を産んだ。(中略)4人が4人とも育てるにはひどく難物だった。でも彼女はやり遂げた。もののみごとに」
本書には20の短篇と、単行本2ページに収まる2掌編が収められています。後者の方では、内容は紹介しませんが、男性の語りによる『雨の日』が印象的でした。例によって、特に印象的なものを紹介します。
●『日干しレンガのブリキ屋根の家』
「建って百年はたつ」井戸はあるものの「水道もないし電気もない」メキシコの荒野の一軒家に住むことになった、二人の連れ子と一緒にジャズミューシャンの夫と二度目の結婚をした、19歳のマヤの苦労を語る話です。おかしいという意味では、本書でいちばんおかしい話です。三人称で書かれていますが、ヒロインが作者の反映であることは間違いないでしょう。
●『楽園の夕べ』
メキシコの海に面したプエルト・パジャルタの近くでロケをした映画『イグアナの夜』(1964年)撮影中のエピソードを語った作品です。テネシー・ウィリアムズ原作で、監督ジョン・ヒューストンを始めとし、出演者リチャード・バートン、彼に連れ添って来た前夫と離婚手続き中だったエリザベス・テイラー、同じく出演者でキューブリック監督の『ロリータ』で主演したスー・リオン、そしてエヴァ・ガードナーらが実名で登場していて、小説としてよりも、そういう下世話な観点で面白かったので紹介しておきます。エヴァ・ガードナーが撮影時、メキシコ人の若いビーチ・ボーイをいわば飼っていたのは、ジョン・ヒューストンの自伝『王になろうとした男』にも同じ記述がありますから、本当でしょう。
●『わたしの人生は開いた本』
小高い丘にあり、他の家からもよく見える、町でも評判のボロ屋にクレアという女性が引っ越してきました。
「クレアは30そこそこ、旦那とは離婚していて、4人の子持ちだった。いちばん上が10ぐらい、いちばんちっこいのはまだ歩けもしなかった。大学でスペイン語を教えていて、家庭教師もしていた。毎朝上の子たちを学校に送っていき、チビたちはルペ・バルガスのとこへ預ける。家の内壁にペンキを塗るのも、家畜の囲いを立てるのも野菜を植えるのも、ウサギ小屋を作るのもぜんぶ独りでやった。もちろん自分たちではウサギもアヒルも食べやしない。ただそこらじゅう走りまわらせていた。ヤギとポニーも一頭ずつ、それに犬が二頭と猫も十匹かそこらいた。(中略)
子供がわんさかいた、自分の子も、近所の子たちも。木に登り、バンに乗り、三輪車やポニーにまたがってスプリンクラーの中をくぐり抜けた。窓という窓に猫がいた」
作者自身の、四人の子育て中のシングル・マザー時代に材をとった作品です。別の町民の語りと、作者自身の一人称が、交互に使われているスタイルで、他人からどう見られていたか、そして自分がどう思っていたかのギャップが面白いです。また、町民からは、なかなか働き者のお母さんじゃないという評価を得られそうだったのが、まだ十代の不良と定評のある少年とできてしまったため、愛想を尽かされるという展開も、作者の恋愛に対する奔放ぶりが、よく表れています。そして、ある事件が起こるのですが、この顛末が、また、おかしいのです。
●『妻たち』
同じ男と結婚・離婚し、共にアル中になった二人の女友達が、二度目に結婚した女の家で、酒を呑みながら、クダをまく話です。同じ男性と結婚した女同士の会話ということで、これもおかしいのですが、悲しくもあります。
●『ルーブルで迷子』
「子供のころ、自分に眠りが訪れる瞬間をなんとかしてとらえようとした。横になってじっとその時を待つが、次に気づくともう朝だった。(中略)
死の瞬間をとらえようなどと考えたことはなかったけれど、パリでそれを経験した。人に死が訪れる瞬間を感じたのだ」
本書でいちばん好きな作品です。パリの優れた紀行文と呼んでもいいでしょう。ただし、パリの街を徘徊したり、カフェに何時間も座って道行く人を眺めたり、ルーブルで「サモトラケのニケ」に感銘を受けたり、でも人が多すぎるので「モナリザ」は見なかったり、そして、ある程度年老いて自分の死を意識するようになった人向きかもしれません。プルーストが好きな方なら、プルーストがコンブレーのモデルとした村イリエ(現在の名前はイリエ・コンブレー)を訪れた時の虚無感に感銘を受けるでしょう。
死ぬ前にもう一度パリに行き、50年前と行き交う人間が変わっただけのパリの街を徘徊し、どこかのカフェで自分の過去と自分の死を見つめておこうと思わせてくれました。
●『陰』
作者が20年ぶりにメキシコを訪れ、闘牛見物をした時の話です。牛にあざやかに死を与えたり、それに手こずったりする闘牛士の技と観客の熱狂と並行して、客席に訪れるありふれた突然死が語られる話です。闘牛場に引き出され、一撃で死ぬ牛も、死ぬのに時間がかかる牛もいる姿が、人間の最期を連想させます。
さて最後にですが、本書に関しては、正直なところ、全体の印象としては前二冊ほどではありません。もちろん、つまらないということではなく、前二冊が素晴らしすぎたということなのでしょう。前二冊は2015年に出版された、『物語こそがすべて』を序文としたルシア・ベルリン選集の全訳だったので、当然なのかもしれません。本書は、その選集からもれた作品が収録されているわけですが、初期の作品よりは、生きる苦しみとやけっぱちな喜びが同居している後期の作品の方に、作者の本領が発揮されていることを感じます。いずれにしても、ルシア・ベルリンは繰り返し読む価値があります。そして、おそらく何度も読んだ方が、味わいが深まることでしょう。
- 『イグアナの夜』の俳優陣、後列左よりスー・リオン、デボラ・カー、エヴァ・ガードナー、前列R・バートン
- 『ロリータ』(1962年)のロリータ役スー・リオン、初登場の場面、撮影当時15歳
- 代表作『裸足の伯爵夫人』(1954年)のエヴァ・ガードナー
お気に入り度:







掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
「本職」は、本というより映画です。
本を読んでいても、映画好きの視点から、内容を見ていることが多いようです。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:講談社
- ページ数:0
- ISBN:9784065332290
- 発売日:2024年09月26日
- 価格:2860円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。