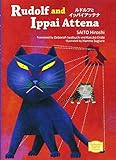休蔵さん
レビュアー:
▼
秋田県の上岩川遺跡群は、縄文時代の石器素材である珪質頁岩の採掘跡。生活遺跡ではないため土器はほとんど出土しておらず、石器生産の痕跡ばかりという特徴的な遺跡。本書はそんな遺跡群を紹介した概説書。
縄文時代の人たちは、その辺の石ころを拾って、巧みに石器を作ったわけではなく、適切な石材を選択し、苦労して入手するという活動を行ってきた。
黒曜石は石器の石材として有名だろう。
しかし、本書の主人公は、東北地歩の縄文人が石器石材として利用してきた珪質頁岩で、縄文時代の石器素材としてはそんなに知られていないかもしれない。
その採掘遺跡が、本書が紹介する秋田県の上岩川遺跡群である。
本書のタイトルは「北の縄文鉱山」である。
上岩川遺跡群は複数の縄文遺跡から構成されるが、大きく2種類に分かれるようだ。
1つは原石を採掘した遺跡で、もう1つは石器を製作した遺跡である。
原石を採掘して、そのまま石器を作るというわけではないようだ。
興味深いことに、遺跡群から出土した石器は相当少ないとのこと。
石器を作るための原石や作った際に生じた残滓を含めて、上岩川遺跡群では13万3999点の石器関係遺物が出土しているが、確実な製品は0.01%に過ぎないという。
石器製作遺跡も石器製作が目的で、生活は行わないようだ。
そのことを反映して、土器はほとんど出土しないという。
当然のことながら、生活のための集落は別地点にあり、人々は原石の採掘・石器の生産をするために来訪することになる。
そこには複数の集落が関わったと予測される。
上岩川遺跡群は、多くの人たちが訪れて活動する共有材を提供する作業場ということのようだ。
それは人々の交流を促進し、広域のネットワーク構築に繋がったことだろう。
縄文時代の人々は、イノシシやシカを追ってその日暮らしをしていたわけではないはずだ。
必要なものは蓄え、物々交換という商いもし、様々なネットワークを構築して、広げていた。
周辺域で見つかる珪質頁岩は、質から3分類できるそうだ。
最上質のものは上岩川でしか見つからないという。
それは「上岩川ブランド」として認識され、ネットワークの拡大にも一役買ったと思われる。
人々の価値観は時代とともに推移するが、石器石材の質は縄文時代ならではの価値判断が下されていたに違いない。
それを入手した際には“ハイタッチ”することもあった、かも?
上岩川遺跡群で縄文人は生活を送っていない。
生活道具である石器の素材を採掘するための鉱山跡だ。
土器は出土せず、石屑ばかりが見つかる場所を遺跡として認定するのは、相当に難しいこととなんとなく思った。
それを見抜き、実際に発掘調査を実施して遺跡の性格を明確にしてきた活動は、相当に大変なものだったのではないだろうか。
本書からはその間の大変さも窺い知ることができた。
黒曜石は石器の石材として有名だろう。
しかし、本書の主人公は、東北地歩の縄文人が石器石材として利用してきた珪質頁岩で、縄文時代の石器素材としてはそんなに知られていないかもしれない。
その採掘遺跡が、本書が紹介する秋田県の上岩川遺跡群である。
本書のタイトルは「北の縄文鉱山」である。
上岩川遺跡群は複数の縄文遺跡から構成されるが、大きく2種類に分かれるようだ。
1つは原石を採掘した遺跡で、もう1つは石器を製作した遺跡である。
原石を採掘して、そのまま石器を作るというわけではないようだ。
興味深いことに、遺跡群から出土した石器は相当少ないとのこと。
石器を作るための原石や作った際に生じた残滓を含めて、上岩川遺跡群では13万3999点の石器関係遺物が出土しているが、確実な製品は0.01%に過ぎないという。
石器製作遺跡も石器製作が目的で、生活は行わないようだ。
そのことを反映して、土器はほとんど出土しないという。
当然のことながら、生活のための集落は別地点にあり、人々は原石の採掘・石器の生産をするために来訪することになる。
そこには複数の集落が関わったと予測される。
上岩川遺跡群は、多くの人たちが訪れて活動する共有材を提供する作業場ということのようだ。
それは人々の交流を促進し、広域のネットワーク構築に繋がったことだろう。
縄文時代の人々は、イノシシやシカを追ってその日暮らしをしていたわけではないはずだ。
必要なものは蓄え、物々交換という商いもし、様々なネットワークを構築して、広げていた。
周辺域で見つかる珪質頁岩は、質から3分類できるそうだ。
最上質のものは上岩川でしか見つからないという。
それは「上岩川ブランド」として認識され、ネットワークの拡大にも一役買ったと思われる。
人々の価値観は時代とともに推移するが、石器石材の質は縄文時代ならではの価値判断が下されていたに違いない。
それを入手した際には“ハイタッチ”することもあった、かも?
上岩川遺跡群で縄文人は生活を送っていない。
生活道具である石器の素材を採掘するための鉱山跡だ。
土器は出土せず、石屑ばかりが見つかる場所を遺跡として認定するのは、相当に難しいこととなんとなく思った。
それを見抜き、実際に発掘調査を実施して遺跡の性格を明確にしてきた活動は、相当に大変なものだったのではないだろうか。
本書からはその間の大変さも窺い知ることができた。
お気に入り度:







掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
ここに参加するようになって、読書の幅が広がったように思います。
それでも、まだ偏り気味。
いろんな人の書評を参考に、もっと幅広い読書を楽しみたい!
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:新泉社
- ページ数:0
- ISBN:9784787712332
- 発売日:2012年02月15日
- 価格:1650円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。