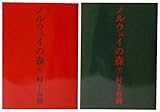ゆうちゃんさん
レビュアー:
▼
宇宙と生命を同時に論じつつ、首尾一貫した内容を語っている。地球外生命を探索するには生命とは何かという定義と、太陽系の惑星、系外惑星の探査技術が重要だが、この2点について詳しく説明している。
朝日新聞の書評で知った本。「14歳の世渡り術」シリーズの一冊で、年齢からすると自分向きとは言えない本ではあるが、題名に惹かれた。
内容は、三分の二が科学史、残りが宇宙における生物探査の現状である。科学史は人間の宇宙観の変化を惑星の観点から捉えている。宇宙に関する科学史と言うと天動説からビッグバンへと言うのが定番だが、本書の宇宙科学史の概要は以下の通りである。
・天動説から地動説へ
・太陽系中心の宇宙観から太陽もありふれた恒星のひとつであることへ
・太陽系が宇宙で唯一の惑星系なのかどうか
最後は系外惑星(太陽系以外の惑星)探査の開発秘話で終わっている。
二番目の科学史は生物学史である。アリストテレスの動物の分類に始まり、リンネの分類学、ダーウィンの進化論、遺伝のメカニズムやDNAの発見に至るまでごく普通の生物学の発展を説明している。ただ本書の特徴は生命の共通性(細胞構造やタンパク質の生成過程)と多様性(突然変異と環境変化による種の分岐)の観点を強調している点である。宇宙での生命探査は本書の重要なテーマであるが、地球以外の生命がどんなものかを探るには生命とは何かをしっかり定義しなければならない。宇宙における生命の定義は現時点ではできないが、共通性と多様性の観点から地球の生命の定義はしっかりできている。
で、この宇宙と生命の説明を経て、題名の宇宙から考えてみる「生命とは何か?」であるが、ここは地球外生命の探索の話となっている。月、火星の生命の可能性、土星の惑星エウロパに存在するかもしれない生命の可能性に始まり、最後は系外惑星の探索の過程と今後について述べている。系外惑星の探索は光のスペクトル分析と言う技術が重要になっている。こちらは評者の技術者としての社会人経験からなじみのある分野ではあるが、一般的には話が専門的でちょっと難しいかもしれない。結局ここでは、ある星から来る光を分析すれば、大気の組成や地表の状況などがある程度わかると言う話と、恒星のすぐ側を公転する惑星の観測の難しさ(著者はこれを灯台の周囲を飛ぶ蛍の光を遠くから観測することに例えている)の話を述べている。
子供向けのシリーズではあるが、内容は高度と言う印象。宇宙と生命は子供に限らず興味を引くテーマで、本も多数書かれているが、ふたつをドッキングさせて著者のしっかりした観点から記述しているので、異分野を同時に論じながらも首尾一貫した読後感を得られる。系外惑星の探索についてはよく一般紙でも記事として取り上げられるので、興味を持って読んでいるから、ある程度は知っているつもりだったが、この本の第三部で、系統的な説明を読み、知識を深めることが出来た。著者はまだ若い方らしいが、行間に研究への情熱も感じ取られ、その点も好印象である。
内容は、三分の二が科学史、残りが宇宙における生物探査の現状である。科学史は人間の宇宙観の変化を惑星の観点から捉えている。宇宙に関する科学史と言うと天動説からビッグバンへと言うのが定番だが、本書の宇宙科学史の概要は以下の通りである。
・天動説から地動説へ
・太陽系中心の宇宙観から太陽もありふれた恒星のひとつであることへ
・太陽系が宇宙で唯一の惑星系なのかどうか
最後は系外惑星(太陽系以外の惑星)探査の開発秘話で終わっている。
二番目の科学史は生物学史である。アリストテレスの動物の分類に始まり、リンネの分類学、ダーウィンの進化論、遺伝のメカニズムやDNAの発見に至るまでごく普通の生物学の発展を説明している。ただ本書の特徴は生命の共通性(細胞構造やタンパク質の生成過程)と多様性(突然変異と環境変化による種の分岐)の観点を強調している点である。宇宙での生命探査は本書の重要なテーマであるが、地球以外の生命がどんなものかを探るには生命とは何かをしっかり定義しなければならない。宇宙における生命の定義は現時点ではできないが、共通性と多様性の観点から地球の生命の定義はしっかりできている。
で、この宇宙と生命の説明を経て、題名の宇宙から考えてみる「生命とは何か?」であるが、ここは地球外生命の探索の話となっている。月、火星の生命の可能性、土星の惑星エウロパに存在するかもしれない生命の可能性に始まり、最後は系外惑星の探索の過程と今後について述べている。系外惑星の探索は光のスペクトル分析と言う技術が重要になっている。こちらは評者の技術者としての社会人経験からなじみのある分野ではあるが、一般的には話が専門的でちょっと難しいかもしれない。結局ここでは、ある星から来る光を分析すれば、大気の組成や地表の状況などがある程度わかると言う話と、恒星のすぐ側を公転する惑星の観測の難しさ(著者はこれを灯台の周囲を飛ぶ蛍の光を遠くから観測することに例えている)の話を述べている。
子供向けのシリーズではあるが、内容は高度と言う印象。宇宙と生命は子供に限らず興味を引くテーマで、本も多数書かれているが、ふたつをドッキングさせて著者のしっかりした観点から記述しているので、異分野を同時に論じながらも首尾一貫した読後感を得られる。系外惑星の探索についてはよく一般紙でも記事として取り上げられるので、興味を持って読んでいるから、ある程度は知っているつもりだったが、この本の第三部で、系統的な説明を読み、知識を深めることが出来た。著者はまだ若い方らしいが、行間に研究への情熱も感じ取られ、その点も好印象である。
お気に入り度:







掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
神奈川県に住むサラリーマン(技術者)でしたが24年2月に会社を退職して今は無職です。
読書歴は大学の頃に遡ります。粗筋や感想をメモするようになりましたのはここ10年程ですので、若い頃に読んだ作品を再読した投稿が多いです。元々海外純文学と推理小説、そして海外の歴史小説が自分の好きな分野でした。しかし、最近は、文明論、科学ノンフィクション、音楽などにも興味が広がってきました。投稿するからには評価出来ない作品もきっちりと読もうと心掛けています。どうかよろしくお願い致します。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:河出書房新社
- ページ数:0
- ISBN:9784309617572
- 発売日:2023年10月23日
- 価格:1562円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。