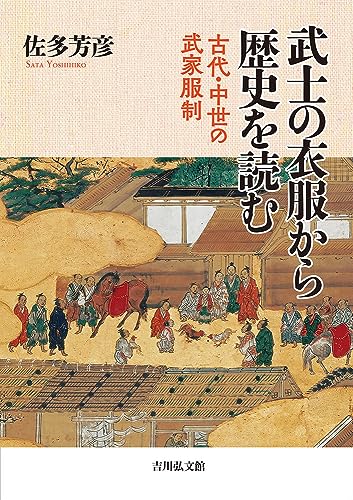祐太郎さん
レビュアー:
▼
源頼朝を演じた大泉洋は、なぜ白い「水干」を着ていたのか。貴族と武士との衣服の違いから読み解いていく。
鎌倉殿の13人で、源頼朝は直垂ではなく、白い「水干」という衣服を着続けていた。一方、北条義時はじめ一般の武士たちは「直垂」を着ていた。この違いは何だったのか。近世以前は「衣服」と社会階層が密接に関係していたのはいうまでもない。
古代、貴族たちは衣冠束帯、直衣、狩衣を着ていた一方、庶民は袖細直垂という袖が細く衽(おくみ)のない経済的な服を着ていた。そこで一つ問題が生じた。それは貴族たちに使える下人たちは何を着させたのかということである。それが袖がある水干なのである。武士たちも貴族に使える際は、この水干を着ていたのだそうだ。頼朝は平治の乱まで京都で朝廷に仕えていたのであり、その意識があったのではないのか。
その水干と直垂の関係を変えたのが平氏政権である。彼らは袖細直垂に水干の大きな袖をつけた直垂を作り上げ、洗練していった。本来なら麻とかで作られた直垂も最上位の平家の人々は絹製のものを着ていた。
主要な平家のなかで唯一源氏に下った平頼盛と源頼朝が鎌倉で対面した際、頼盛は唐綾の直垂、頼朝は白葛糸の水干を着ていたのが象徴的であった。
鎌倉時代にはいると、初期は水干が武家では最上位の衣服となったが、徐々に直垂が最上位になり、室町時代になるとその地位は確固たるものとなる。
ところが、大きな袖では動きにくい。そこで戦国時代に登場したのが「肩衣」である。小袖の上に肩衣を着るころで、動きやすくなったのだが、その大きく虚勢をはるような姿は、まるでバブル時代の肩パットのような感じだなと思う。
その時代ごとにTPOにあわせて人々は服を選んでいった。現在、東京国立博物館で「やまと絵」展をやっているが、細かな階級ごとにどのような服を着ていたかを知ることで、より深い理解を得られると思う。
古代、貴族たちは衣冠束帯、直衣、狩衣を着ていた一方、庶民は袖細直垂という袖が細く衽(おくみ)のない経済的な服を着ていた。そこで一つ問題が生じた。それは貴族たちに使える下人たちは何を着させたのかということである。それが袖がある水干なのである。武士たちも貴族に使える際は、この水干を着ていたのだそうだ。頼朝は平治の乱まで京都で朝廷に仕えていたのであり、その意識があったのではないのか。
その水干と直垂の関係を変えたのが平氏政権である。彼らは袖細直垂に水干の大きな袖をつけた直垂を作り上げ、洗練していった。本来なら麻とかで作られた直垂も最上位の平家の人々は絹製のものを着ていた。
主要な平家のなかで唯一源氏に下った平頼盛と源頼朝が鎌倉で対面した際、頼盛は唐綾の直垂、頼朝は白葛糸の水干を着ていたのが象徴的であった。
鎌倉時代にはいると、初期は水干が武家では最上位の衣服となったが、徐々に直垂が最上位になり、室町時代になるとその地位は確固たるものとなる。
ところが、大きな袖では動きにくい。そこで戦国時代に登場したのが「肩衣」である。小袖の上に肩衣を着るころで、動きやすくなったのだが、その大きく虚勢をはるような姿は、まるでバブル時代の肩パットのような感じだなと思う。
その時代ごとにTPOにあわせて人々は服を選んでいった。現在、東京国立博物館で「やまと絵」展をやっているが、細かな階級ごとにどのような服を着ていたかを知ることで、より深い理解を得られると思う。
お気に入り度:









掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
片道45分の通勤電車を利用して読書している
アラフィフ世代の3児の父。
★基準
★★★★★:新刊(定価)で買ってでも満足できる本
★★★★:新古書価格・kindleで買ったり、図書館で予約待ちしてでも満足できる本
★★★:100均価格で買ったり図書館で何気なくあって借りるなら満足できる本
★★:どうしても本がないときの時間つぶし程度ならいいのでは?
★:う~ん
★なし:雑誌などの一言書評
※仕事関係の本はすべて★★★で統一します。
プロフィールの画像はうちの末っ子の似顔絵を田中かえが描いたものです。
2024年3月20日更新
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:吉川弘文館
- ページ数:0
- ISBN:9784642084376
- 発売日:2023年09月22日
- 価格:2420円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。