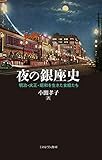ぽんきちさん
レビュアー:
▼
銀座発展の陰にいた女性たち
銀座と言えば何を思い浮かべるだろうか。
三越のライオン。ブランドの旗艦店。老舗バー。
いずれにしても、どこか高級、どこかおしゃれ、普段着よりもドレスアップして出かけるところというイメージがあるように思う。
本書はそんな銀座の変遷を、主にそこで働いた「女性たち」に重点を置いて追う。おおむね、明治期から第二次大戦後までの夜の銀座女性史である。
繁華街としての銀座の歴史の始まりは、明治期にさかのぼる。
当時の銀座は西洋文化の玄関口であった。明治5年の銀座大火を受け、不燃の街を作ることを目的に、煉瓦街が作られた。この街並みそのものが見物客を呼んだ。横浜と新橋をつなぐ鉄道が開通したのもこのころのこと。明治7年にはガス灯も登場し、夜のそぞろ歩きも楽しめるようになった。
明治期は新聞社や雑誌社が数多く存在し、現在でも出版社が所有するビルがある。
隣接する築地は東京唯一の外国人居留地。舶来品を取り扱う店が集まっていた。
そして新橋芸者を抱える置屋も数多くあった。
そんな中から、舶来品物販店が「舶来飲料」をその場で飲ませる商売が登場する。最初は簡易な店だったが、ビアホールや喫茶店が登場し、外食産業が発達していく。
そうなってくると、料理や飲み物を運ぶ「給仕」が必要になってくるわけである。
西洋であれば、外食は夫婦や家族連れでするのが一般的であったのに対して、当時の日本では客は男性だった。格式が高い西洋料理店では男性が給仕することもあったが、女性が給仕する店が大半になっていく。そうなるとそこに容姿や色恋といった要素が絡んでくる。このあたり、芸者や置屋の多い土地柄であったことも無縁ではなかっただろう。
少し時代が下ると、カフェーという業態が出てくる。
カフェー・ライオンはエプロンで給仕する女性給仕で人気を博した。著名人や知識人が集まるサロンのような場所。店内で客と女性給仕が親しくなることは許容されていたわけではないが、しかし、そうはいっても恋愛沙汰が生じることはあったようである。
著者は社会史、ジェンダー史の研究者であるので、重点は女性たちの立場に置かれる。
女性給仕が「職業婦人」かどうかというのはやや微妙な問題で、当時の女性雑誌の職業案内には、女工はあれど女性給仕は見当たらない。カフェー等が全国的に広がっていたわけではないこともあるだろう。それに加えて、例えば「蕎麦屋の女中」と比べると、「カフェーの女性給仕」には水商売に近いイメージもあり、やや色眼鏡で見られがちなところもあったようだ。
大正12年、関東大震災が起こる。
銀座も甚大な被害を負う。焼け野原の街の人々は、しかし、たくましく復興へと向かった。二大百貨店が進出することになり、それに伴い、それまで物販店だった店がカフェーなどの飲食店に転業する例も多かった。女性給仕が「女給」と呼ばれるようになってくるのはこのころである。女給の容姿を売りにするような店も出てくる。
このころの雑誌には「女給」特集が組まれることも出てくる。知名度も上がってきたということだろう。
行政が女給を対象とした大規模調査が残っている。収入はさほど多いわけではなく、震災のため、やむを得ず女給になった人も多い。若年層が多いが、既婚者や子持ちの女性もいる。ただ、中には、職業婦人として生活ができる生活を是とし、いずれは自ら店を持ちたいという自立心の高い人もあったようだ。
カフェーの数が増えるにつれて、各店が独自色を出そうとすることもあって、高級路線を取る店、キャバレー化していく店と多様化していく。風紀を乱すと取り締まられる店も出てくる。
この辺りは、水商売と飲食業の境目にあるようなカフェーの立ち位置の曖昧さを思わせる。
第二次世界大戦後、銀座は廃墟となった。が、進駐軍向けの特殊慰安施設協会(Recreation and Amusement Association:RAA)の本部が銀座に置かれたことから、徐々に賑わいを取り戻していく。RAA本部には仕事を求めて若い女性たちが集まった。キャバレーやダンスホールがいくつもでき、ダンサーや接待婦が必要であった。
銀座がそうした場所に選ばれたのは、やはり歴史的経緯から、この地が外国人になじみやすいことがあっただろう。
バーや喫茶店も増えていき、現在の銀座繁栄の基盤となっていく。
あとがきによれば、女給の史料を集める苦労があったそうで、なるほど、歴史の陰にいた女給のような存在は、表立って語られ、記録に残されることが少なかったのかもしれない。
いわゆる「正史」とは趣を異にするが、これはこれで1つの興味深い視点から見た銀座史である。
三越のライオン。ブランドの旗艦店。老舗バー。
いずれにしても、どこか高級、どこかおしゃれ、普段着よりもドレスアップして出かけるところというイメージがあるように思う。
本書はそんな銀座の変遷を、主にそこで働いた「女性たち」に重点を置いて追う。おおむね、明治期から第二次大戦後までの夜の銀座女性史である。
繁華街としての銀座の歴史の始まりは、明治期にさかのぼる。
当時の銀座は西洋文化の玄関口であった。明治5年の銀座大火を受け、不燃の街を作ることを目的に、煉瓦街が作られた。この街並みそのものが見物客を呼んだ。横浜と新橋をつなぐ鉄道が開通したのもこのころのこと。明治7年にはガス灯も登場し、夜のそぞろ歩きも楽しめるようになった。
明治期は新聞社や雑誌社が数多く存在し、現在でも出版社が所有するビルがある。
隣接する築地は東京唯一の外国人居留地。舶来品を取り扱う店が集まっていた。
そして新橋芸者を抱える置屋も数多くあった。
そんな中から、舶来品物販店が「舶来飲料」をその場で飲ませる商売が登場する。最初は簡易な店だったが、ビアホールや喫茶店が登場し、外食産業が発達していく。
そうなってくると、料理や飲み物を運ぶ「給仕」が必要になってくるわけである。
西洋であれば、外食は夫婦や家族連れでするのが一般的であったのに対して、当時の日本では客は男性だった。格式が高い西洋料理店では男性が給仕することもあったが、女性が給仕する店が大半になっていく。そうなるとそこに容姿や色恋といった要素が絡んでくる。このあたり、芸者や置屋の多い土地柄であったことも無縁ではなかっただろう。
少し時代が下ると、カフェーという業態が出てくる。
カフェー・ライオンはエプロンで給仕する女性給仕で人気を博した。著名人や知識人が集まるサロンのような場所。店内で客と女性給仕が親しくなることは許容されていたわけではないが、しかし、そうはいっても恋愛沙汰が生じることはあったようである。
著者は社会史、ジェンダー史の研究者であるので、重点は女性たちの立場に置かれる。
女性給仕が「職業婦人」かどうかというのはやや微妙な問題で、当時の女性雑誌の職業案内には、女工はあれど女性給仕は見当たらない。カフェー等が全国的に広がっていたわけではないこともあるだろう。それに加えて、例えば「蕎麦屋の女中」と比べると、「カフェーの女性給仕」には水商売に近いイメージもあり、やや色眼鏡で見られがちなところもあったようだ。
大正12年、関東大震災が起こる。
銀座も甚大な被害を負う。焼け野原の街の人々は、しかし、たくましく復興へと向かった。二大百貨店が進出することになり、それに伴い、それまで物販店だった店がカフェーなどの飲食店に転業する例も多かった。女性給仕が「女給」と呼ばれるようになってくるのはこのころである。女給の容姿を売りにするような店も出てくる。
このころの雑誌には「女給」特集が組まれることも出てくる。知名度も上がってきたということだろう。
行政が女給を対象とした大規模調査が残っている。収入はさほど多いわけではなく、震災のため、やむを得ず女給になった人も多い。若年層が多いが、既婚者や子持ちの女性もいる。ただ、中には、職業婦人として生活ができる生活を是とし、いずれは自ら店を持ちたいという自立心の高い人もあったようだ。
カフェーの数が増えるにつれて、各店が独自色を出そうとすることもあって、高級路線を取る店、キャバレー化していく店と多様化していく。風紀を乱すと取り締まられる店も出てくる。
この辺りは、水商売と飲食業の境目にあるようなカフェーの立ち位置の曖昧さを思わせる。
第二次世界大戦後、銀座は廃墟となった。が、進駐軍向けの特殊慰安施設協会(Recreation and Amusement Association:RAA)の本部が銀座に置かれたことから、徐々に賑わいを取り戻していく。RAA本部には仕事を求めて若い女性たちが集まった。キャバレーやダンスホールがいくつもでき、ダンサーや接待婦が必要であった。
銀座がそうした場所に選ばれたのは、やはり歴史的経緯から、この地が外国人になじみやすいことがあっただろう。
バーや喫茶店も増えていき、現在の銀座繁栄の基盤となっていく。
あとがきによれば、女給の史料を集める苦労があったそうで、なるほど、歴史の陰にいた女給のような存在は、表立って語られ、記録に残されることが少なかったのかもしれない。
いわゆる「正史」とは趣を異にするが、これはこれで1つの興味深い視点から見た銀座史である。
お気に入り度:





掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
分子生物学・生化学周辺の実務翻訳をしています。
本の大海を漂流中。
日々是好日。どんな本との出会いも素敵だ。
あちらこちらとつまみ食いの読書ですが、点が線に、線が面になっていくといいなと思っています。
「実感」を求めて読書しているように思います。
赤柴♀(もも)は3代目。
この夏、有精卵からヒヨコ4羽を孵化させました。そろそろ大雛かな。♂x2、♀x2。ニワトリは割と人に懐くものらしいですが、今のところ、懐く気配はありませんw
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:ミネルヴァ書房
- ページ数:0
- ISBN:9784623095605
- 発売日:2023年04月11日
- 価格:2640円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。
『夜の銀座史:明治・大正・昭和を生きた女給たち』のカテゴリ
- ・文学・小説 > 評論
- ・文学・小説 > ノンフィクション
- ・歴史 > 日本史
- ・政治・経済・社会・ビジネス > 社会
- ・政治・経済・社会・ビジネス > 地域・都市
- ・政治・経済・社会・ビジネス > メディア
- ・政治・経済・社会・ビジネス > 社会問題
- ・政治・経済・社会・ビジネス > 経営
- ・政治・経済・社会・ビジネス > ビジネス
- ・趣味・実用 > 旅・レジャー
- ・趣味・実用 > 生活の知恵
- ・趣味・実用 > 自己啓発