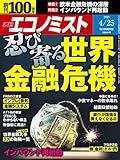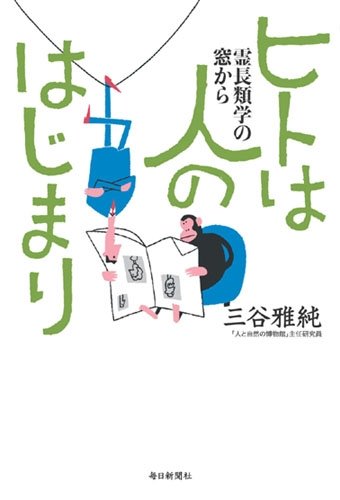休蔵さん
レビュアー:
▼
霊長類の進化史の概説書と思って読み始めけれど、もっと深いテーマがある。種の進化、そして存続において、いかに多様性が大切であるか。現代社会についても考えさせられた1冊。
本書の筆者は霊長類学者としてアフリカやインドネシアなどでフィールドワークを重ねてきた。
現地入りし、詳細に霊長類の観察をして研究を深めていく。
様々な環境で霊長類の調査を推進するためには現地で暮らす人びとの協力や彼らとの交流が欠かせず、その過程で様々な環境で生活する「ヒト」の観察も同時に行うことになったようだ。
そこでこのタイトルだ。
『ヒトは人のはじまり』とはいうタイトルにある「ヒト」は、人間を生物学的にみる場合に用い、「人」はまわりにいる現実に生きた人を見る場合に用いるとのこと。
これは本書の軸となる重要な視点である。
さらに著者は脳梗塞脳になり、右半身と発声に少しまひが残ったという。
そのため、筆者の「ヒト」に対する観察眼は鋭さを増したのではないか。
いわゆる「健常者」が当たり前のように使う表現、例えば自閉症に関する遺伝子について触れた論文で「発症」や「患者」という言葉に違和感を覚えたそうだ。
社会多数派の健康な人間が当たり前の存在という「常識」が垣間見られるというのだ。
このことに対する筆者の思いは嫌悪というより哀しさと捉えた方がよさそうだ。
本書には「「障がい」を進化史からとらえ直す」という一文がある。
現在の日本では発達障がいとされるADHDの特徴も、危険が満ちた狩猟採集の世の中だったら大きな力を発揮する可能性が高いのではと述べている。
発達障がいは、あくまで現在の社会で生きるにはやや難というところにマイナス評価を下したものとなろうか。
しかし、生物の多様性という観点から考えると、様々な性質・気質・体質は種の存続のためには大きな力となる。
本来なら・・・。
生物は多様な特徴を持つからこそ、様々な環境で生き抜くことができる。
恐竜が絶滅しても哺乳類が生き延びたのは、恐竜と哺乳類の性質の差、つまり多様なあり方のおかげだろう。
それは同じ種の生物にも当てはまるはず。
現在の基準での障がいというレッテルも、異なる環境では優位な存在になることが十分にあり得るはず。
ただ、筆者が説く本質はそこではない。
筆者はどんな環境下でもあらゆる境遇の人が普通に生きていけることを当たり前と説いているのだ。
多様性を何の気負いもなく受容することこそ筆者が求め、主張していること。
発達障がいを〈病気〉とみなせばそれは医学がカバーし、〈ヒトの自然な性質〉とみなせば霊長類学の領域になると本書は記す。
そもそも読み書きという現代の「人」に求められる能力で全てを推し量ろうとすること自体、種の存続から考えるとずれているのではなかろうか。
ただ、多数派に属するうちには、なかなかその「常識」の享受して思考が停止しがちだ。
それは「先進国」と自分たちを位置付ける国の論理にも通じると考える。
本書はそんなことを平易な表現を用いて教えてくれるような気がした。
個性を伸ばすと言えば我儘を助長するだけと感じていたが、本書には個性の本当の意味が記されていると思う。
現地入りし、詳細に霊長類の観察をして研究を深めていく。
様々な環境で霊長類の調査を推進するためには現地で暮らす人びとの協力や彼らとの交流が欠かせず、その過程で様々な環境で生活する「ヒト」の観察も同時に行うことになったようだ。
そこでこのタイトルだ。
『ヒトは人のはじまり』とはいうタイトルにある「ヒト」は、人間を生物学的にみる場合に用い、「人」はまわりにいる現実に生きた人を見る場合に用いるとのこと。
これは本書の軸となる重要な視点である。
さらに著者は脳梗塞脳になり、右半身と発声に少しまひが残ったという。
そのため、筆者の「ヒト」に対する観察眼は鋭さを増したのではないか。
いわゆる「健常者」が当たり前のように使う表現、例えば自閉症に関する遺伝子について触れた論文で「発症」や「患者」という言葉に違和感を覚えたそうだ。
社会多数派の健康な人間が当たり前の存在という「常識」が垣間見られるというのだ。
このことに対する筆者の思いは嫌悪というより哀しさと捉えた方がよさそうだ。
本書には「「障がい」を進化史からとらえ直す」という一文がある。
現在の日本では発達障がいとされるADHDの特徴も、危険が満ちた狩猟採集の世の中だったら大きな力を発揮する可能性が高いのではと述べている。
発達障がいは、あくまで現在の社会で生きるにはやや難というところにマイナス評価を下したものとなろうか。
しかし、生物の多様性という観点から考えると、様々な性質・気質・体質は種の存続のためには大きな力となる。
本来なら・・・。
生物は多様な特徴を持つからこそ、様々な環境で生き抜くことができる。
恐竜が絶滅しても哺乳類が生き延びたのは、恐竜と哺乳類の性質の差、つまり多様なあり方のおかげだろう。
それは同じ種の生物にも当てはまるはず。
現在の基準での障がいというレッテルも、異なる環境では優位な存在になることが十分にあり得るはず。
ただ、筆者が説く本質はそこではない。
筆者はどんな環境下でもあらゆる境遇の人が普通に生きていけることを当たり前と説いているのだ。
多様性を何の気負いもなく受容することこそ筆者が求め、主張していること。
発達障がいを〈病気〉とみなせばそれは医学がカバーし、〈ヒトの自然な性質〉とみなせば霊長類学の領域になると本書は記す。
そもそも読み書きという現代の「人」に求められる能力で全てを推し量ろうとすること自体、種の存続から考えるとずれているのではなかろうか。
ただ、多数派に属するうちには、なかなかその「常識」の享受して思考が停止しがちだ。
それは「先進国」と自分たちを位置付ける国の論理にも通じると考える。
本書はそんなことを平易な表現を用いて教えてくれるような気がした。
個性を伸ばすと言えば我儘を助長するだけと感じていたが、本書には個性の本当の意味が記されていると思う。
お気に入り度:







掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
ここに参加するようになって、読書の幅が広がったように思います。
それでも、まだ偏り気味。
いろんな人の書評を参考に、もっと幅広い読書を楽しみたい!
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:毎日新聞社
- ページ数:0
- ISBN:9784620320663
- 発売日:2011年06月25日
- 価格:1540円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。