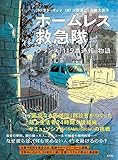三太郎さん
レビュアー:
▼
遺伝子から見た人間の寿命とは。何が我々の健康寿命を決めているのか、研究はまだ始まったばかりのようです。
著者の森先生は1953年の生まれで、東大薬学部卒。若い頃は米国の大学で脳細胞の老化について主導的な研究をされた方とか。本書ではこれまで明らかになった12種類の「寿命遺伝子」の発見の経緯とその実態について書かれています。
ブルーバックスですから、僕のような生化学や生理学についての門外漢でも内容のあらましは理解できました。ただし、遺伝子(DNA)の仕組みや細胞内外での情報伝達の仕組みについての初歩的な知識がないと読むのは難しいかも。
それでも、DNAからmRNAができて、それを使って特定の構造のタンパク質が作られること、タンパク質は筋肉や臓器を形成する以外にも、酵素となって体内の様々な情報伝達に関与すること、DNAに結合して遺伝子発現の活性化や抑止を行うタンパク質もあることが分れば、概略は理解できそうです。化学の初歩的な知識もあった方がよいかも。
神経細胞以外の細胞は幹細胞の分裂によって新しい細胞に生まれ変わる訳ですが、分裂の際に染色体の末端のテロメアという部位が短くなり、細胞分裂が60回くらいになるともう細胞分裂しなくなります。そのために人間には自ずから寿命があります。もしテロメアが短くならないと細胞分裂は続きますが、細胞が癌化するようになるのでやはり人間は死ぬことになります。(テロメアは癌化を防ぐ安全装置みたいですね。)
ところが脳の神経細胞は一度できあがったら一生分裂せずにそのまま残ります。人間は70歳を超えると脳の神経細胞が老化して変形してきます。脳の老化に伴う現象としてアルツハイマー型認知症がありますが、アルツハイマーになり易い人となり難い人との個人差は大きく、これにはある遺伝子が関わっていることが解ってきました。
マウスにifg-1という遺伝子からできるIFG-1というタンパク質がありますが、これはインスリン様成長因子の受容体で、このIFG-1が出来にくいマウスを遺伝子操作でつくると、雌のマウスでは著しく寿命が延びました。このマウスは酸化ストレスに強くそのため老化し難いようなのです。
(ここでは遺伝子を小文字のアルファベットで、その遺伝子から作られるタンパク質を大文字で表しています。)
さらにこのifg-1が欠損したマウスとアルツハイマーになり易いマウスを掛け合わせると、アルツハイマーになり易い遺伝子を持っていてもアルツハイマーの症状が出ないことが解りました。アルツハイマーは脳内にアミロイドβが蓄積して起こるのですが、このハイブリッドのマウスではアミロイドβが蓄積しても記憶力の低下が起きなったといいます。インスリンが関係することから、アルツハイマーの発症は糖の代謝と関係がありそうです。
また、restという遺伝子があります。この遺伝子が活性化するとRESTというタンパク質ができますが、人間では70歳を超えると脳の前頭葉にRESTが多くできます。しかしアルツハイマーの人ではこのRESTが少ないことが分かっています。RESTができないマウスを作ったところ、脳の老化が早まりました。RESTは高齢者の脳の老化を抑制する働きがあるようです。(アルツハイマーの人は遺伝子のrestの発現を制御する部分に問題があるのかも。)
それ以外にも多くの寿命遺伝子が見つかっています。史上初めて見つかった寿命遺伝子は無脊椎動物の線虫の遺伝子でage-1と名付けられらした。この遺伝子はタンパク質AGE-1を作りますが、このタンパク質は細胞内のリン脂質をリン酸化する酵素でした。線虫ではage-1を正常に働かなくすると線虫の寿命が伸びました。この酵素はマウスが持っているPI3Kという酵素と同じものでした。
続いて線虫でdaf-2という寿命遺伝子が見つかりました。age-1もdaf-2もその遺伝子が正常に働かなくすると寿命が伸びるのでした。線虫が実験に使われるのは寿命が短いので短時間で寿命の増減がわかるためです。
線虫のdaf-2が作るタンパク質はインスリン様成長因子の受容体でした。またもインスリンと寿命に関係が見られました。インスリンは人の糖代謝に関係するホルモンですが、無脊椎動物の線虫もインスリン様の物質を利用していたのでした。線虫でも人間でも糖代謝が寿命に関係しているらしく思われました。
次は酵母の寿命遺伝子sir-2について。この遺伝子が欠損すると酵母の寿命が短くなり、sir-2からできるタンパク質SIR-2を酵母に加えると寿命が長くなりました!SIR-2は染色体のヒストンのアセチル化を制御することで遺伝子の発現を制御しているらしいです。さらにSIR-2により線虫やショウジョウバエの寿命も延びました。
マウスの場合にはsirに対応する遺伝子はsirtですが、sirt-1を過剰に発現させても寿命は変わりませんでした。ただし痩せ型になってカロリー制限したようなより健康な状態になりました。(できたら僕もsirt-1を過剰に発現させたいものです!)
マウスの遺伝子sirtには7種類の遺伝子がありますが、なかでもsirt-6での長寿効果について解説しています。SIRT-6が過剰に発現した雄のマウスでは寿命が延びましたが雌では変化がありませんでした。雄のマウスでは脂肪細胞からのインスリン様成長因子IGF-1のシグナルの発信が抑制されていました。動物では(たぶん人間も)カロリー制限をするとsirt遺伝子が活性化してより健康になるということらしいです。
sirt遺伝子を活性化させる物質の探索が盛んになり、ポリフェノールの一種のレスベラトロールが有効だと分かりました。この化合物はブドウの皮などに含まれるので、ワインが健康によいと言われました。このレスベラトロールの効果はマウスで確認されています。つまり、高脂肪食のマウスは肝硬変になりますが、食事と一緒にレスベラトロールを摂取すると肝硬変になりません。ただし、人間に換算すると一日30gのレスベラトロールを摂らねばならず、現実的ではないようです。
最期の話題は長寿な酵母から見つかったtor遺伝子について。その後の研究によりカロリー制限してもtor遺伝子がないと寿命は延びないことがわかりました。sir-2よりtorの方が重要なのでした。
torの話はまだまだ続きますが、本書の紹介はこのくらいにしておきます。何が我々の健康寿命を決めているのか、研究はまだ始まったばかりのようです。
ブルーバックスですから、僕のような生化学や生理学についての門外漢でも内容のあらましは理解できました。ただし、遺伝子(DNA)の仕組みや細胞内外での情報伝達の仕組みについての初歩的な知識がないと読むのは難しいかも。
それでも、DNAからmRNAができて、それを使って特定の構造のタンパク質が作られること、タンパク質は筋肉や臓器を形成する以外にも、酵素となって体内の様々な情報伝達に関与すること、DNAに結合して遺伝子発現の活性化や抑止を行うタンパク質もあることが分れば、概略は理解できそうです。化学の初歩的な知識もあった方がよいかも。
神経細胞以外の細胞は幹細胞の分裂によって新しい細胞に生まれ変わる訳ですが、分裂の際に染色体の末端のテロメアという部位が短くなり、細胞分裂が60回くらいになるともう細胞分裂しなくなります。そのために人間には自ずから寿命があります。もしテロメアが短くならないと細胞分裂は続きますが、細胞が癌化するようになるのでやはり人間は死ぬことになります。(テロメアは癌化を防ぐ安全装置みたいですね。)
ところが脳の神経細胞は一度できあがったら一生分裂せずにそのまま残ります。人間は70歳を超えると脳の神経細胞が老化して変形してきます。脳の老化に伴う現象としてアルツハイマー型認知症がありますが、アルツハイマーになり易い人となり難い人との個人差は大きく、これにはある遺伝子が関わっていることが解ってきました。
マウスにifg-1という遺伝子からできるIFG-1というタンパク質がありますが、これはインスリン様成長因子の受容体で、このIFG-1が出来にくいマウスを遺伝子操作でつくると、雌のマウスでは著しく寿命が延びました。このマウスは酸化ストレスに強くそのため老化し難いようなのです。
(ここでは遺伝子を小文字のアルファベットで、その遺伝子から作られるタンパク質を大文字で表しています。)
さらにこのifg-1が欠損したマウスとアルツハイマーになり易いマウスを掛け合わせると、アルツハイマーになり易い遺伝子を持っていてもアルツハイマーの症状が出ないことが解りました。アルツハイマーは脳内にアミロイドβが蓄積して起こるのですが、このハイブリッドのマウスではアミロイドβが蓄積しても記憶力の低下が起きなったといいます。インスリンが関係することから、アルツハイマーの発症は糖の代謝と関係がありそうです。
また、restという遺伝子があります。この遺伝子が活性化するとRESTというタンパク質ができますが、人間では70歳を超えると脳の前頭葉にRESTが多くできます。しかしアルツハイマーの人ではこのRESTが少ないことが分かっています。RESTができないマウスを作ったところ、脳の老化が早まりました。RESTは高齢者の脳の老化を抑制する働きがあるようです。(アルツハイマーの人は遺伝子のrestの発現を制御する部分に問題があるのかも。)
それ以外にも多くの寿命遺伝子が見つかっています。史上初めて見つかった寿命遺伝子は無脊椎動物の線虫の遺伝子でage-1と名付けられらした。この遺伝子はタンパク質AGE-1を作りますが、このタンパク質は細胞内のリン脂質をリン酸化する酵素でした。線虫ではage-1を正常に働かなくすると線虫の寿命が伸びました。この酵素はマウスが持っているPI3Kという酵素と同じものでした。
続いて線虫でdaf-2という寿命遺伝子が見つかりました。age-1もdaf-2もその遺伝子が正常に働かなくすると寿命が伸びるのでした。線虫が実験に使われるのは寿命が短いので短時間で寿命の増減がわかるためです。
線虫のdaf-2が作るタンパク質はインスリン様成長因子の受容体でした。またもインスリンと寿命に関係が見られました。インスリンは人の糖代謝に関係するホルモンですが、無脊椎動物の線虫もインスリン様の物質を利用していたのでした。線虫でも人間でも糖代謝が寿命に関係しているらしく思われました。
次は酵母の寿命遺伝子sir-2について。この遺伝子が欠損すると酵母の寿命が短くなり、sir-2からできるタンパク質SIR-2を酵母に加えると寿命が長くなりました!SIR-2は染色体のヒストンのアセチル化を制御することで遺伝子の発現を制御しているらしいです。さらにSIR-2により線虫やショウジョウバエの寿命も延びました。
マウスの場合にはsirに対応する遺伝子はsirtですが、sirt-1を過剰に発現させても寿命は変わりませんでした。ただし痩せ型になってカロリー制限したようなより健康な状態になりました。(できたら僕もsirt-1を過剰に発現させたいものです!)
マウスの遺伝子sirtには7種類の遺伝子がありますが、なかでもsirt-6での長寿効果について解説しています。SIRT-6が過剰に発現した雄のマウスでは寿命が延びましたが雌では変化がありませんでした。雄のマウスでは脂肪細胞からのインスリン様成長因子IGF-1のシグナルの発信が抑制されていました。動物では(たぶん人間も)カロリー制限をするとsirt遺伝子が活性化してより健康になるということらしいです。
sirt遺伝子を活性化させる物質の探索が盛んになり、ポリフェノールの一種のレスベラトロールが有効だと分かりました。この化合物はブドウの皮などに含まれるので、ワインが健康によいと言われました。このレスベラトロールの効果はマウスで確認されています。つまり、高脂肪食のマウスは肝硬変になりますが、食事と一緒にレスベラトロールを摂取すると肝硬変になりません。ただし、人間に換算すると一日30gのレスベラトロールを摂らねばならず、現実的ではないようです。
最期の話題は長寿な酵母から見つかったtor遺伝子について。その後の研究によりカロリー制限してもtor遺伝子がないと寿命は延びないことがわかりました。sir-2よりtorの方が重要なのでした。
torの話はまだまだ続きますが、本書の紹介はこのくらいにしておきます。何が我々の健康寿命を決めているのか、研究はまだ始まったばかりのようです。
お気に入り度:





掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
1957年、仙台に生まれ、結婚後10年間世田谷に住み、その後20余年横浜に住み、現在は仙台在住。本を読んで、思ったことあれこれを書いていきます。
長年、化学メーカーの研究者でした。2019年から滋賀県で大学の教員になりましたが、2023年3月に退職し、10月からは故郷の仙台に戻りました。プロフィールの写真は還暦前に米国ピッツバーグの岡の上で撮ったものです。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:講談社
- ページ数:0
- ISBN:9784065229125
- 発売日:2021年03月18日
- 価格:1100円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。
『寿命遺伝子 なぜ老いるのか 何が長寿を導くのか』のカテゴリ
登録されているカテゴリはありません。