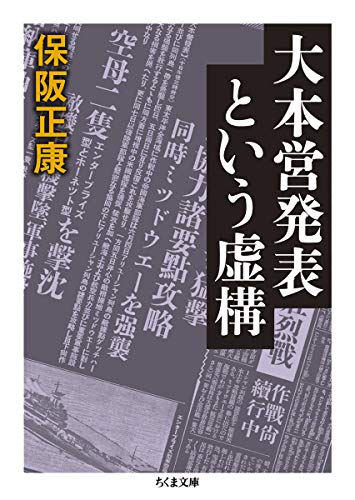hackerさん
レビュアー:
▼
フェイク・ニュースや虚構空間がいかに生み出されるのか、現在にもつながるテーマを、太平洋戦争時の大本営発表を題材にまとめたノンフィクションです。
フェイク・ニュースやファクト・チェックという言葉が、すっかり日本語として定着しましたが、昔は「それ大本営発表じゃないの」という冗談交じりの会話は珍しくありませんでした。もしかしたら、この大本営発表という言葉自体、若い世代にはなじみが薄くなっているかもしれませんが、簡単に言えば、太平洋戦争開始時は比較的客観的つまり事実に近いものだったのが、戦局が悪化するにつれフェイク・ニュースが当たり前になっていた、陸海軍が行っていた戦争報道のことです。
有名な例としては、昭和19年10月19日午後6時に発表され、パール・ハーバー以来の大勝利を謳った台湾沖航空戦についてのものがあります。
「我部隊は10月12日以降連日連夜台湾及『ルソン』東方海面の敵機動部隊を猛攻し其の過半の兵力を壊滅して之を潰走せしめたり。
(一)我方の収めたる綜合戦果次の如し
轟撃沈 航空母艦十一隻、戦艦二隻、巡洋艦三隻、巡洋艦若は駆逐艦一隻
撃破 航空母艦八隻、戦艦二隻、巡洋艦四隻、巡洋艦若は駆逐艦一隻、艦種不詳十三隻、其の他火炎火柱を認めたもの十二を下らず
撃墜 百十二機(基地に於ける撃墜を含まず)
(二)我方の損害 飛行機未帰還三百十二機」
ところが、実際には、米巡洋艦二隻に軽微な損傷を与えただけだったのです。その理由としては、帰還したパイロットからの報告を鵜呑みにして、検証せずに積み上げた数字であったことを、本書では挙げています。アメリカ海軍の大将だったニミッツが書いた『太平洋海戦史』では、日本軍は未熟なパイロット、実戦経験のないパイロットばかりだったので、自軍機が墜落して海上にあがった火柱を、敵艦の撃沈と勘違いしたのではないかと述べられています。まさかと思うかもしれませんが、当時海軍飛行部隊は、サイパン島をめぐる戦いだったマリアナ沖海戦で壊滅状態でしたし、参戦したのは海戦に不慣れな陸軍機中心だったでしょうから、十分あり得ることだったのです。こうして見ると、312機という被害の甚大さゆえに、実態は完全な負け戦だったことが分かります。
もう一つ別の例を挙げます。こちらは、意図的に、情報を隠蔽したものです。
「第835回・大本営発表(昭和20年8月7日15時30分)
一、昨8月6日広島市は敵B29少数機の攻撃により相当の被害を生じたり
二、敵は右攻撃に新型爆弾を使用せるものの如きも詳細目下調査中なり」
これは広島原爆投下時の、有名な「新型爆弾」という言葉を使った大本営発表です。本書で初めて知ったのですが、実はこの発表は原爆投下より30時間以上経ってからなされたもので、その時点ではトルーマン大統領が原爆である旨の発表を既に行っており、原子爆弾という言葉を使うかどうか、関係各省が集まって協議したとのことです。関係者の証言によれば、内務省と陸軍が「原子爆弾に対する防衛策も指示することなしに、原子爆弾の出現を報道するのは、国民に対し非常な衝撃を与え戦意を失わせるから不利である。殊に原子爆弾かどうかは目下調査中であるからであるから、少なくとも原子爆弾が出現したと云うことの発表は差し控えたい」と主張し、この表現になったとのことです。既に沖縄と硫黄島が陥落し、日本全土の制空権がアメリカに奪われている状況下で「原子爆弾の防衛策」などおかしい限りですが、主張する側は真剣だったのではないかと推測します。一方で、「陸軍内部の技術将校の間では、アメリカの保有する原子爆弾の数量がどの程度になるか、ウランの生産量を推測し試算さえ行われていた」とあります。そして重要なのは、こういう事実を知らなければ、この大本営発表を聞く側は、「ああ、そうか」と思うだけだろうということです。陸軍がこのような隠蔽を主張したのは「客観的事実より主観的願望が前面に出る国家に変質」した結果だと本書では述べています。
この客観的事実より主観的願望を優先する考え方は、2020年の米大統領選挙や昨年のブラジル大統領選挙の結果に不正があったと主張する人間が少なくない現状を見ると、どんな国家、いつの時代でも起こりうることが分かります。太平洋戦争中の日本の大本営発表は、その一例に過ぎませんが、結果がどんなに悲惨なことになったかは触れるまでもありません。
そもそも大本営という組織は、陸軍報道部と海軍報道部から成り、実は「大本営陸海軍部」の名前で発表されたのは、昭和16年12月8日開戦時の第一回のみで、その後は陸軍と海軍は別々に発表をしていました。では、大本営とは何かというと、元々は日清戦争前の明治26年に法令で定められたそうですが、昭和12年に大本営令(勅令第658号)により「天皇ノ大纛(たいとう)下ニ最高ノ統史部ヲ置キ之ヲ大本営ト称ス」(第一条)と定義されました。ですが、実際には陸軍も海軍も大本営下で作戦協議をしていたわけではなく、バラバラで様々な決定をしていて、それが戦争中の大きな弊害になっていたことはよく知られています。情報交換はしていたでしょうが、本書では、東絛首相がミッドウェー海戦における海軍の大損害を知ったのは天皇との会話からだったという例が述べられていますから、よく知られている陸軍と海軍の面子の張り合いが、曖昧な大本営という組織内でも展開されていたことになります。
ところで、戦争に突入していった背景について、作者は次のように述べています。
「私の見るところ、近代日本で昭和8年ごろから15年ごろまでの”日本社会の空間”は正常な感覚を失った空間になっていたと思う。それが太平洋戦争を皇帝する国民心理に転化していったと断言していいだろう。国民をこのような酩酊状態に似た、つまり正常な感覚を失った状態にするには、四つの条件で縛りあげれば苦もない。
その四つの条件とは、『教育の国家統制』『情報の一元化』『弾圧立法の適用』『暴力装置の発動』である」
大本営発表と、その検閲・指導によって記事を書いていた新聞が「情報の一元化」に貢献したのは、言うまでもありません。そして、この四つの条件は、現在のロシアのウクライナ戦争の報道ぶりを見れば(見るも不愉快ですがNHKBSやBBCやCNNで時々報道されています)、現在でも活きていることが分かります。
また、その思想的背景については、本書では東條首相の戦時中の国会答弁を紹介しています。
「私は元来、この英米を相手とするこの戦争において(中略)戦勝の確信については、十分持っております。負けるものとは毛頭考えておりません」
これに対し、鶴見祐輔議員から「首相のいう”必勝の信念”とは何を根拠にしているのか」という質問が飛びます。
「由来皇軍の御戦さは、御稜威(みいつ)の下、戦えば、必ず勝つのであります。これは光輝ある皇国三千年来の伝統であり、信念であります。吾々の祖先は御稜威の下、この信念の下にあらゆる努力を傾倒し、戦えば必ず勝って今日の帝国を築き上げてまいったのであります」
なんと無茶苦茶なと思うかもしれませんが、現在の国会でも質問にまともに答えていない答弁が目立つことを思えば、不思議ではありません。「見たいものしか見えない」「聞きたいことしか聞こえない」というのは、いつの時代でも珍しいことではないのです。
もちろん、こういう状況における、新聞のヨイショ記事の働きは無視できません。サイパン島陥落と玉砕を伝える讀賣報知新聞の一面には東條首相の「決戦の機、来れり! 戦ひはこれから 一億決死覚悟せよ」という、まるで国民総自殺をそそのかすような談話が載っています。更に、次のような見出しが、新聞全体を覆っていました。
「燃ゆ・復仇への闘魂 叩きつけん一億の力」
「米鬼を粉砕すべし 武器なきは竹槍にて」
「サイパンの痛憤 なほ足らず我らが努力」
「死が即命」
サイパン島は絶対防衛圏と位置付けられていたのですが、その理由は、捕虜にした米軍パイロットからテスト飛行中だったB29の性能を日本軍が正確につかんでおり、サイパン島が陥落すれば、日本全土がその爆撃圏内に入ることは分かっていたからですが、それに対する国民への警告のようなものは一切なかったようです。また、本書では触れていませんが、先に述べたマリアナ沖海戦によって、海軍の飛行部隊は全滅状態になったことも、きちんと報道はされなかったと思われます。あちこちで書いていますが、この戦いによって、はっきりと目に見える形で太平洋戦争の勝敗は決着していたのです。
さて、本書の中で、作者は次のような感慨を述べています。
「嘘で固めた情報空間のなかに身を置くように強制され、その情報のみを信じるように押さえ込まれ、そしてその空間に疑問をもつことも、そこから脱けだすことも許されないという社会では、どれほどの人間的退廃がうまれるのだろう」
しかし同時に作者は「大本営発表の嘘や、その嘘を補完する装飾について想像も及ばないほど鈍感であった」日本人たちを批判してもいます。少し前ですが、ある若い女性と話した際、ネットに飛び交うニュースや情報について「どれが本当なのか分からない」と言っていました。これは正直な感想なのでしょうし、偽情報を安易に信じこむよりは、まだ「分からない」と言っているだけ良いのかもしれませんが、こういう話をすると、いつも思い出すのは、映画監督伊丹万作(伊丹十三の父)が1946年に発表した『戦争責任者の問題』と題する次の文章です。
「さて、多くの人が、今度の戦争で騙されていたと言う。皆が皆口を揃えて騙されていたという。私の知っている範囲では俺が騙したのだと言った人間は未だ一人もいない。(中略)多くの人は騙した者と騙される者との区別は、はっきりしていると思っているようであるが、それが実は錯覚らしいのである。(中略)
騙されたということは、不正者による被害を意味するが、しかし、騙されたものは正しいとは、古来いかなる辞書にも決して書いてはいないのである。騙されたと言えば、一切の責任から解放され、無条件で正義派に成れるように勘違いしている人は、もう一度よく顔を洗い直さなければならぬ。
(中略)私は更に進んで、『騙されるということ自体が既に一つの悪である』ことを主張したいのである。(中略)
そして騙されたものの罪は、只単に騙されていたという事実そのものの中にあるのではなく、あんなにも雑作なく騙される程批判力を失い、思考力を失い、信念を失い、家畜的な盲従に自己の一切を委ねるように成ってしまっていた国民全体の文化的無気力、無自覚、無反省、無責任等が悪の本体なのである。(中略)
『騙されていた』と言って平気でいられる国民なら、恐らく今後も何度でも騙されるだろう。いや、現在でも既に別の嘘によって騙され始めているに違いないのである。
一度騙されたら、二度と騙されまいとする真剣な自己反省と努力がなければ人間が進歩するわけがない。」(「映画春秋」創刊号より)
「雑作なく騙される程批判力を失い、思考力を失い、信念を失い、家畜的な盲従に自己の一切を委ねるように成って」しまわないようにするには、結局のところ、我々自身がアンテナを広く張り知識と事実の収集に努め、自分の意見というものをしっかり持つしかなさそうです。少なくとも、「教育の国家統制」や「情報の一元化」に対抗するためには、それが大切です。現代は、偽情報も多いとはいえ、有益な情報にもアクセスしやすくなっているのは間違いないのですから。
有名な例としては、昭和19年10月19日午後6時に発表され、パール・ハーバー以来の大勝利を謳った台湾沖航空戦についてのものがあります。
「我部隊は10月12日以降連日連夜台湾及『ルソン』東方海面の敵機動部隊を猛攻し其の過半の兵力を壊滅して之を潰走せしめたり。
(一)我方の収めたる綜合戦果次の如し
轟撃沈 航空母艦十一隻、戦艦二隻、巡洋艦三隻、巡洋艦若は駆逐艦一隻
撃破 航空母艦八隻、戦艦二隻、巡洋艦四隻、巡洋艦若は駆逐艦一隻、艦種不詳十三隻、其の他火炎火柱を認めたもの十二を下らず
撃墜 百十二機(基地に於ける撃墜を含まず)
(二)我方の損害 飛行機未帰還三百十二機」
ところが、実際には、米巡洋艦二隻に軽微な損傷を与えただけだったのです。その理由としては、帰還したパイロットからの報告を鵜呑みにして、検証せずに積み上げた数字であったことを、本書では挙げています。アメリカ海軍の大将だったニミッツが書いた『太平洋海戦史』では、日本軍は未熟なパイロット、実戦経験のないパイロットばかりだったので、自軍機が墜落して海上にあがった火柱を、敵艦の撃沈と勘違いしたのではないかと述べられています。まさかと思うかもしれませんが、当時海軍飛行部隊は、サイパン島をめぐる戦いだったマリアナ沖海戦で壊滅状態でしたし、参戦したのは海戦に不慣れな陸軍機中心だったでしょうから、十分あり得ることだったのです。こうして見ると、312機という被害の甚大さゆえに、実態は完全な負け戦だったことが分かります。
もう一つ別の例を挙げます。こちらは、意図的に、情報を隠蔽したものです。
「第835回・大本営発表(昭和20年8月7日15時30分)
一、昨8月6日広島市は敵B29少数機の攻撃により相当の被害を生じたり
二、敵は右攻撃に新型爆弾を使用せるものの如きも詳細目下調査中なり」
これは広島原爆投下時の、有名な「新型爆弾」という言葉を使った大本営発表です。本書で初めて知ったのですが、実はこの発表は原爆投下より30時間以上経ってからなされたもので、その時点ではトルーマン大統領が原爆である旨の発表を既に行っており、原子爆弾という言葉を使うかどうか、関係各省が集まって協議したとのことです。関係者の証言によれば、内務省と陸軍が「原子爆弾に対する防衛策も指示することなしに、原子爆弾の出現を報道するのは、国民に対し非常な衝撃を与え戦意を失わせるから不利である。殊に原子爆弾かどうかは目下調査中であるからであるから、少なくとも原子爆弾が出現したと云うことの発表は差し控えたい」と主張し、この表現になったとのことです。既に沖縄と硫黄島が陥落し、日本全土の制空権がアメリカに奪われている状況下で「原子爆弾の防衛策」などおかしい限りですが、主張する側は真剣だったのではないかと推測します。一方で、「陸軍内部の技術将校の間では、アメリカの保有する原子爆弾の数量がどの程度になるか、ウランの生産量を推測し試算さえ行われていた」とあります。そして重要なのは、こういう事実を知らなければ、この大本営発表を聞く側は、「ああ、そうか」と思うだけだろうということです。陸軍がこのような隠蔽を主張したのは「客観的事実より主観的願望が前面に出る国家に変質」した結果だと本書では述べています。
この客観的事実より主観的願望を優先する考え方は、2020年の米大統領選挙や昨年のブラジル大統領選挙の結果に不正があったと主張する人間が少なくない現状を見ると、どんな国家、いつの時代でも起こりうることが分かります。太平洋戦争中の日本の大本営発表は、その一例に過ぎませんが、結果がどんなに悲惨なことになったかは触れるまでもありません。
そもそも大本営という組織は、陸軍報道部と海軍報道部から成り、実は「大本営陸海軍部」の名前で発表されたのは、昭和16年12月8日開戦時の第一回のみで、その後は陸軍と海軍は別々に発表をしていました。では、大本営とは何かというと、元々は日清戦争前の明治26年に法令で定められたそうですが、昭和12年に大本営令(勅令第658号)により「天皇ノ大纛(たいとう)下ニ最高ノ統史部ヲ置キ之ヲ大本営ト称ス」(第一条)と定義されました。ですが、実際には陸軍も海軍も大本営下で作戦協議をしていたわけではなく、バラバラで様々な決定をしていて、それが戦争中の大きな弊害になっていたことはよく知られています。情報交換はしていたでしょうが、本書では、東絛首相がミッドウェー海戦における海軍の大損害を知ったのは天皇との会話からだったという例が述べられていますから、よく知られている陸軍と海軍の面子の張り合いが、曖昧な大本営という組織内でも展開されていたことになります。
ところで、戦争に突入していった背景について、作者は次のように述べています。
「私の見るところ、近代日本で昭和8年ごろから15年ごろまでの”日本社会の空間”は正常な感覚を失った空間になっていたと思う。それが太平洋戦争を皇帝する国民心理に転化していったと断言していいだろう。国民をこのような酩酊状態に似た、つまり正常な感覚を失った状態にするには、四つの条件で縛りあげれば苦もない。
その四つの条件とは、『教育の国家統制』『情報の一元化』『弾圧立法の適用』『暴力装置の発動』である」
大本営発表と、その検閲・指導によって記事を書いていた新聞が「情報の一元化」に貢献したのは、言うまでもありません。そして、この四つの条件は、現在のロシアのウクライナ戦争の報道ぶりを見れば(見るも不愉快ですがNHKBSやBBCやCNNで時々報道されています)、現在でも活きていることが分かります。
また、その思想的背景については、本書では東條首相の戦時中の国会答弁を紹介しています。
「私は元来、この英米を相手とするこの戦争において(中略)戦勝の確信については、十分持っております。負けるものとは毛頭考えておりません」
これに対し、鶴見祐輔議員から「首相のいう”必勝の信念”とは何を根拠にしているのか」という質問が飛びます。
「由来皇軍の御戦さは、御稜威(みいつ)の下、戦えば、必ず勝つのであります。これは光輝ある皇国三千年来の伝統であり、信念であります。吾々の祖先は御稜威の下、この信念の下にあらゆる努力を傾倒し、戦えば必ず勝って今日の帝国を築き上げてまいったのであります」
なんと無茶苦茶なと思うかもしれませんが、現在の国会でも質問にまともに答えていない答弁が目立つことを思えば、不思議ではありません。「見たいものしか見えない」「聞きたいことしか聞こえない」というのは、いつの時代でも珍しいことではないのです。
もちろん、こういう状況における、新聞のヨイショ記事の働きは無視できません。サイパン島陥落と玉砕を伝える讀賣報知新聞の一面には東條首相の「決戦の機、来れり! 戦ひはこれから 一億決死覚悟せよ」という、まるで国民総自殺をそそのかすような談話が載っています。更に、次のような見出しが、新聞全体を覆っていました。
「燃ゆ・復仇への闘魂 叩きつけん一億の力」
「米鬼を粉砕すべし 武器なきは竹槍にて」
「サイパンの痛憤 なほ足らず我らが努力」
「死が即命」
サイパン島は絶対防衛圏と位置付けられていたのですが、その理由は、捕虜にした米軍パイロットからテスト飛行中だったB29の性能を日本軍が正確につかんでおり、サイパン島が陥落すれば、日本全土がその爆撃圏内に入ることは分かっていたからですが、それに対する国民への警告のようなものは一切なかったようです。また、本書では触れていませんが、先に述べたマリアナ沖海戦によって、海軍の飛行部隊は全滅状態になったことも、きちんと報道はされなかったと思われます。あちこちで書いていますが、この戦いによって、はっきりと目に見える形で太平洋戦争の勝敗は決着していたのです。
さて、本書の中で、作者は次のような感慨を述べています。
「嘘で固めた情報空間のなかに身を置くように強制され、その情報のみを信じるように押さえ込まれ、そしてその空間に疑問をもつことも、そこから脱けだすことも許されないという社会では、どれほどの人間的退廃がうまれるのだろう」
しかし同時に作者は「大本営発表の嘘や、その嘘を補完する装飾について想像も及ばないほど鈍感であった」日本人たちを批判してもいます。少し前ですが、ある若い女性と話した際、ネットに飛び交うニュースや情報について「どれが本当なのか分からない」と言っていました。これは正直な感想なのでしょうし、偽情報を安易に信じこむよりは、まだ「分からない」と言っているだけ良いのかもしれませんが、こういう話をすると、いつも思い出すのは、映画監督伊丹万作(伊丹十三の父)が1946年に発表した『戦争責任者の問題』と題する次の文章です。
「さて、多くの人が、今度の戦争で騙されていたと言う。皆が皆口を揃えて騙されていたという。私の知っている範囲では俺が騙したのだと言った人間は未だ一人もいない。(中略)多くの人は騙した者と騙される者との区別は、はっきりしていると思っているようであるが、それが実は錯覚らしいのである。(中略)
騙されたということは、不正者による被害を意味するが、しかし、騙されたものは正しいとは、古来いかなる辞書にも決して書いてはいないのである。騙されたと言えば、一切の責任から解放され、無条件で正義派に成れるように勘違いしている人は、もう一度よく顔を洗い直さなければならぬ。
(中略)私は更に進んで、『騙されるということ自体が既に一つの悪である』ことを主張したいのである。(中略)
そして騙されたものの罪は、只単に騙されていたという事実そのものの中にあるのではなく、あんなにも雑作なく騙される程批判力を失い、思考力を失い、信念を失い、家畜的な盲従に自己の一切を委ねるように成ってしまっていた国民全体の文化的無気力、無自覚、無反省、無責任等が悪の本体なのである。(中略)
『騙されていた』と言って平気でいられる国民なら、恐らく今後も何度でも騙されるだろう。いや、現在でも既に別の嘘によって騙され始めているに違いないのである。
一度騙されたら、二度と騙されまいとする真剣な自己反省と努力がなければ人間が進歩するわけがない。」(「映画春秋」創刊号より)
「雑作なく騙される程批判力を失い、思考力を失い、信念を失い、家畜的な盲従に自己の一切を委ねるように成って」しまわないようにするには、結局のところ、我々自身がアンテナを広く張り知識と事実の収集に努め、自分の意見というものをしっかり持つしかなさそうです。少なくとも、「教育の国家統制」や「情報の一元化」に対抗するためには、それが大切です。現代は、偽情報も多いとはいえ、有益な情報にもアクセスしやすくなっているのは間違いないのですから。
お気に入り度:







掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
「本職」は、本というより映画です。
本を読んでいても、映画好きの視点から、内容を見ていることが多いようです。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:筑摩書房
- ページ数:0
- ISBN:9784480436375
- 発売日:2019年12月10日
- 価格:858円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。
『大本営発表という虚構』のカテゴリ
- ・文学・小説 > ノンフィクション
- ・歴史 > 日本史
- ・政治・経済・社会・ビジネス > 社会
- ・政治・経済・社会・ビジネス > メディア
- ・人文科学 > 倫理・道徳