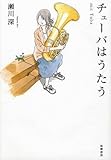ぽんきちさん
レビュアー:
▼
牛は球であり、猫は液体である・・・?
のっけから自分の話で恐縮だが、SFがあまり得意でない。
読んで読めないこともないのだが、読みながらどうしても結局嘘話じゃん、と思ってしまう。そんなことをいったらフィクションはすべて嘘話ともいえるのだが、特にSF(サイエンス・フィクション)となると、それなら実際、今どういうことになっているのか、サイエンスのノンフィクションを読んだ方がよくないか?と思ってしまうのだ。
SFファンの方にはわかってないなと言われそうだが(いや、実際わかってないし)、まぁそんなわけで普段は自分から進んでSFは手に取らないのだが。
定期購読している『日経サイエンス』2月号に本書の著者の短編が載っていた。SF短編が掲載されることはあまりなく(少なくとも私が購読している数年間では見た覚えがない)珍しいなと思いながら読んだ。そしたら予想以上におもしろかった。
近未来、月面でビジネスとして臓器培養をするお話である。
・・・へぇ。
予想外のおもしろさの理由は、現実と空想の織り交ぜ方の絶妙さにあるように感じた。
著者プロフィールを見ると、少し前に話題になっていた『横浜駅SF』の著者さんだった。『横浜駅SF』を読んでみてもよかったのだが、とりあえず短編集を読んでみることにした。
本書は、短編13編+あとがき+ボーナス・トラックという構成。
冒頭が表題作(「まず牛を球とします」)である。なにやらトポロジーの(ドーナツとマグカップは同じ、みたいな)話なのかと思わせるタイトルだが、そうではなくて、本当に球状の牛を作るというもの。それってどういうこと?
3話目の「数を食べる」は、純粋な概念としての「数」って何なの?というお話。尖っていてなかなかおもしろい。
5話目「東京都交通安全責任課」。機械ができることがどんどん増えている昨今。じゃあ結局人間しかできないこととして最後に残るのは何?
10話目「大正電気女学生」と12話目「改暦」は、お題ありきの企画もので、前者は大正レトロ、後者は中国・元を舞台としたもの。楽しく読める。
11話「令和二年の箱男」。いや、なんか実際こんな人いそうである。
13話「沈黙のリトルボーイ」。広島に投下された原爆が不発であったら、というIF話。エンディングが少し軽すぎるような気がするが、存外考えさせられる。
あとがきは各話の著者による自作解説。1話目の解説で笑ってしまった。
総じて、科学的知識の裏付けがあったうえで、ちょっと「はずす」、その匙加減がうまいように思う。加えて、どこかオタク的でシニカル、すっとぼけたユーモアセンスがアクセントになっている。
著者は、元々は大学で任期付きの生物学研究者で、任期が切れた後、専業作家に転じられたとのこと。なるほどと思う経歴である。
さて、これでSFに開眼したか、と言われると、残念ながらそこまでではないのだが。でも、この著者の作品はまた手に取ることがあるかもしれない。
冒頭のひとことに書いた「猫は液体」は、本書とは直接の関係はないのだが、本書を読みながら、ひところイグノーベル賞でも話題になったこの話を何となく思い出した(参考URL)。「猫液体」説にくすっとした人なら、本書も楽しめるのではないかと思う。
読んで読めないこともないのだが、読みながらどうしても結局嘘話じゃん、と思ってしまう。そんなことをいったらフィクションはすべて嘘話ともいえるのだが、特にSF(サイエンス・フィクション)となると、それなら実際、今どういうことになっているのか、サイエンスのノンフィクションを読んだ方がよくないか?と思ってしまうのだ。
SFファンの方にはわかってないなと言われそうだが(いや、実際わかってないし)、まぁそんなわけで普段は自分から進んでSFは手に取らないのだが。
定期購読している『日経サイエンス』2月号に本書の著者の短編が載っていた。SF短編が掲載されることはあまりなく(少なくとも私が購読している数年間では見た覚えがない)珍しいなと思いながら読んだ。そしたら予想以上におもしろかった。
近未来、月面でビジネスとして臓器培養をするお話である。
・・・へぇ。
予想外のおもしろさの理由は、現実と空想の織り交ぜ方の絶妙さにあるように感じた。
著者プロフィールを見ると、少し前に話題になっていた『横浜駅SF』の著者さんだった。『横浜駅SF』を読んでみてもよかったのだが、とりあえず短編集を読んでみることにした。
本書は、短編13編+あとがき+ボーナス・トラックという構成。
冒頭が表題作(「まず牛を球とします」)である。なにやらトポロジーの(ドーナツとマグカップは同じ、みたいな)話なのかと思わせるタイトルだが、そうではなくて、本当に球状の牛を作るというもの。それってどういうこと?
3話目の「数を食べる」は、純粋な概念としての「数」って何なの?というお話。尖っていてなかなかおもしろい。
5話目「東京都交通安全責任課」。機械ができることがどんどん増えている昨今。じゃあ結局人間しかできないこととして最後に残るのは何?
10話目「大正電気女学生」と12話目「改暦」は、お題ありきの企画もので、前者は大正レトロ、後者は中国・元を舞台としたもの。楽しく読める。
11話「令和二年の箱男」。いや、なんか実際こんな人いそうである。
13話「沈黙のリトルボーイ」。広島に投下された原爆が不発であったら、というIF話。エンディングが少し軽すぎるような気がするが、存外考えさせられる。
あとがきは各話の著者による自作解説。1話目の解説で笑ってしまった。
総じて、科学的知識の裏付けがあったうえで、ちょっと「はずす」、その匙加減がうまいように思う。加えて、どこかオタク的でシニカル、すっとぼけたユーモアセンスがアクセントになっている。
著者は、元々は大学で任期付きの生物学研究者で、任期が切れた後、専業作家に転じられたとのこと。なるほどと思う経歴である。
さて、これでSFに開眼したか、と言われると、残念ながらそこまでではないのだが。でも、この著者の作品はまた手に取ることがあるかもしれない。
冒頭のひとことに書いた「猫は液体」は、本書とは直接の関係はないのだが、本書を読みながら、ひところイグノーベル賞でも話題になったこの話を何となく思い出した(参考URL)。「猫液体」説にくすっとした人なら、本書も楽しめるのではないかと思う。
お気に入り度:





掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
分子生物学・生化学周辺の実務翻訳をしています。
本の大海を漂流中。
日々是好日。どんな本との出会いも素敵だ。
あちらこちらとつまみ食いの読書ですが、点が線に、線が面になっていくといいなと思っています。
「実感」を求めて読書しているように思います。
赤柴♀(もも)は3代目。
この夏、有精卵からヒヨコ4羽を孵化させました。そろそろ大雛かな。♂x2、♀x2。ニワトリは割と人に懐くものらしいですが、今のところ、懐く気配はありませんw
- この書評の得票合計:
- 36票
| 読んで楽しい: | 11票 | |
|---|---|---|
| 参考になる: | 25票 |
あなたの感想は?
投票するには、ログインしてください。
この書評へのコメント
- miol mor2023-04-18 14:27
おもしろそうですね。いつか読もうかな。
ところで、SFについてですが、中学生のときに創元推理文庫のSFをたぶん殆ど読んだ経験からいうと、Fは二種類あります。
一つはFiction. もう一つがFantasyです。
思いつく例は、古典ですが、OvidのMetamorphosesです。
あれはジャンルは何でしょうね。たぶん小説とはいえないですね。
では何でしょう。神話をfantasyの形で語り直したものかもしれません。
で、その神話にscienceがからむ場合(現代だと殆どそうなると思います)、
Metamorphoses的なものを書くとすると、SFになるしかないのではと思います。ですので、どこかでピンときたり、何か引っかかる場合は、ジャンルに関係なく、おもしろいことがありそうです。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:河出書房新社
- ページ数:0
- ISBN:9784309030562
- 発売日:2022年07月21日
- 価格:1980円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。