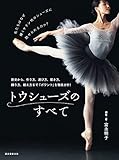ゆうちゃんさん
レビュアー:
▼
ある年の4月、リング状の物体O(オー)が日本に降って来た。中央政府はその下敷きになり、物体Oに囲まれた中部から九州に至る地は生き残りを賭けて工夫を重ねる。ミニ日本沈没と言えるアイデア小説他9編を収める
この中でSFと呼べるのは表題作「物体O」だけと言える。他は幻想的な小説、星新一的な味わいのあるショート・ショート、一般小説のように思える。
「物体O」は、本書最長の小説で50頁程度の中編。1960年代のある日(きっと執筆時からすると未来なのだろう)の4月、日本列島にリング状の物体が落ちて来た。それを物体Oと呼び、関東地方がその物体のリングの壁の底、物体Oの内部に中部以西から九州まで取り込まれた。外側には北海道と東北が取り残された。物体Oのリングの高さは200キロ、厚みは100キロ。中央政府を失った自治体は右往左往したが、京大理学部地球物理学科教授の大隈孝雄博士を中心に物体Oの解明と生き残り策の検討が進む。物体Oのせいで日照は限られ農産物の生産が出来る場所は物体Oのリング壁からある程度離れた場所のみとなる。建設資材や食料は臨時政府に徴発され、配給となった。本書の冒頭には「女の気まぐれによって世界が破滅したとしたら――なんと美しいことだろうか」とある。ミニ日本沈没とも言える本書の内容ではあるが、その原因の意外なことが、物体Oの種々の描写と共に最後に明かされるが、物理的な説明とはなっていない。これは純粋なSFと言うよりは、著者の発想力を楽しむものなのだろう。
本書は、世相を皮肉った小説が多い。小松左京と言うとSF小説を書く人だと思ったがそうでもなさそうだ。最初の作品「フラフラ国始末記」は夏休みの暇を持て余した僕と高島が、アメリカの金持ちの息子フラーの持つ船に乗り、そこに学生を集めて独立を宣言する話。若者たちの世界への反乱である。星新一に「マイ国家」と言う作品があるが、国家制度と言うものおちょくったものに読める。「ダブル三角」は女性がすっかり強くなり、男を働かせて有閑マダムばかりが溢れた時代、自由に性転換ができるとどうなるかと言う話。ここでも男性優位に拘る男への視線に著者の皮肉が籠る。そうまでして社会で優位を保とうとした結果、男たちはどうなったことか。「先取りの時代」は、まさに高度経済成長の遺物かと思う作品。11月にクリスマスやお正月の準備をすることから始まり、お正月には雛祭りの支度、と先取りをする世相を皮肉っている。語り手は11月の飲み屋で七五三の仮装をしている女性を見かけ感動したが彼女は実は・・。「イッヒッヒ作戦」は、アフリカの新興独立国同士の話。欧米の支援を受けた新興独立国アリアリア連邦にボロボル族だけは加わらなかった。彼らは自分らの伝統を守りたいからだ。アリアリア連邦は欧米の兵器を使ってボロボル族をねじ伏せようとするが、ボロボル族の国に肩入れする日本人の「僕」が意外な作戦を考え付いて・・。と言う話。この当時から「国連は無力」と言う文章を読むが、今の方が真に迫る。執筆時にはアフリカの独立ブームだったのかもしれない。「あれ」は「あれ」を見かけ憂鬱になる人たちの話。「あれ」の正体はさておき、末尾の一文が心に響く。
残り4編のうち「骨」は幻想譚である。ある男が井戸を掘り始めたが骨が出土した。ところが掘れば掘るほど新しい出土品が出て来る。縄文、弥生、鎌倉、近代と掘り進むにつれて・・。「墓標かえりぬ」は半身だけ異次元に行ってしまった男の話、「仁科氏の装置」はある装置の製作に一生をかけた男の話でこれらの2編はSF色があるといえばあるが・・。
「返還」は、短いがスケールの大きな話と言えなくもない。人工知能によって世界が平和になった頃、日本の総理がある本を読み今の日本人はアイヌを追い出して土地を占領したことを知る。それを知った総理は北海道、続いて東北地方をアイヌに返還した。これが世界に感動を呼び白人は欧州に引き上げ、アフリカからも白人やアラブ人が出て行った。そしてついに世界は・・・。
確かに古めかしい部分もあるかも知れないが、小松左京は今読んでも面白い。特に社会を皮肉った視線は今でも十分に通用する。SF作家だけではない小松左京を知る上でも良い短編集である。
「物体O」は、本書最長の小説で50頁程度の中編。1960年代のある日(きっと執筆時からすると未来なのだろう)の4月、日本列島にリング状の物体が落ちて来た。それを物体Oと呼び、関東地方がその物体のリングの壁の底、物体Oの内部に中部以西から九州まで取り込まれた。外側には北海道と東北が取り残された。物体Oのリングの高さは200キロ、厚みは100キロ。中央政府を失った自治体は右往左往したが、京大理学部地球物理学科教授の大隈孝雄博士を中心に物体Oの解明と生き残り策の検討が進む。物体Oのせいで日照は限られ農産物の生産が出来る場所は物体Oのリング壁からある程度離れた場所のみとなる。建設資材や食料は臨時政府に徴発され、配給となった。本書の冒頭には「女の気まぐれによって世界が破滅したとしたら――なんと美しいことだろうか」とある。ミニ日本沈没とも言える本書の内容ではあるが、その原因の意外なことが、物体Oの種々の描写と共に最後に明かされるが、物理的な説明とはなっていない。これは純粋なSFと言うよりは、著者の発想力を楽しむものなのだろう。
本書は、世相を皮肉った小説が多い。小松左京と言うとSF小説を書く人だと思ったがそうでもなさそうだ。最初の作品「フラフラ国始末記」は夏休みの暇を持て余した僕と高島が、アメリカの金持ちの息子フラーの持つ船に乗り、そこに学生を集めて独立を宣言する話。若者たちの世界への反乱である。星新一に「マイ国家」と言う作品があるが、国家制度と言うものおちょくったものに読める。「ダブル三角」は女性がすっかり強くなり、男を働かせて有閑マダムばかりが溢れた時代、自由に性転換ができるとどうなるかと言う話。ここでも男性優位に拘る男への視線に著者の皮肉が籠る。そうまでして社会で優位を保とうとした結果、男たちはどうなったことか。「先取りの時代」は、まさに高度経済成長の遺物かと思う作品。11月にクリスマスやお正月の準備をすることから始まり、お正月には雛祭りの支度、と先取りをする世相を皮肉っている。語り手は11月の飲み屋で七五三の仮装をしている女性を見かけ感動したが彼女は実は・・。「イッヒッヒ作戦」は、アフリカの新興独立国同士の話。欧米の支援を受けた新興独立国アリアリア連邦にボロボル族だけは加わらなかった。彼らは自分らの伝統を守りたいからだ。アリアリア連邦は欧米の兵器を使ってボロボル族をねじ伏せようとするが、ボロボル族の国に肩入れする日本人の「僕」が意外な作戦を考え付いて・・。と言う話。この当時から「国連は無力」と言う文章を読むが、今の方が真に迫る。執筆時にはアフリカの独立ブームだったのかもしれない。「あれ」は「あれ」を見かけ憂鬱になる人たちの話。「あれ」の正体はさておき、末尾の一文が心に響く。
「人生は抜き差しならず、あれの中にどっぷり浸かっている。「何か」をする機会があればほんのわずかでも何かするだろうが、一生回ってこなければ自分の方から進んでやろうとはせず、あれを見た晩には黙って酒を飲むのだろう。そう思いながら黙って酒を飲み続けた」(287~288頁)。過去の積み重ねなど重すぎる。この短編では人口爆発とか公害が取り上げられている。それは日本に於いては過去の話かもしれないが、今なら地球温暖化だろう。普通に生きて人類の過去に対峙するのはあまりにも難しい。そんなことをわからせてくれる作品である。同時にこの年齢になってこの短編の末尾の一文を読むとその深刻さが身に染みる。
残り4編のうち「骨」は幻想譚である。ある男が井戸を掘り始めたが骨が出土した。ところが掘れば掘るほど新しい出土品が出て来る。縄文、弥生、鎌倉、近代と掘り進むにつれて・・。「墓標かえりぬ」は半身だけ異次元に行ってしまった男の話、「仁科氏の装置」はある装置の製作に一生をかけた男の話でこれらの2編はSF色があるといえばあるが・・。
「返還」は、短いがスケールの大きな話と言えなくもない。人工知能によって世界が平和になった頃、日本の総理がある本を読み今の日本人はアイヌを追い出して土地を占領したことを知る。それを知った総理は北海道、続いて東北地方をアイヌに返還した。これが世界に感動を呼び白人は欧州に引き上げ、アフリカからも白人やアラブ人が出て行った。そしてついに世界は・・・。
確かに古めかしい部分もあるかも知れないが、小松左京は今読んでも面白い。特に社会を皮肉った視線は今でも十分に通用する。SF作家だけではない小松左京を知る上でも良い短編集である。
お気に入り度:







掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
神奈川県に住むサラリーマン(技術者)でしたが24年2月に会社を退職して今は無職です。
読書歴は大学の頃に遡ります。粗筋や感想をメモするようになりましたのはここ10年程ですので、若い頃に読んだ作品を再読した投稿が多いです。元々海外純文学と推理小説、そして海外の歴史小説が自分の好きな分野でした。しかし、最近は、文明論、科学ノンフィクション、音楽などにも興味が広がってきました。投稿するからには評価出来ない作品もきっちりと読もうと心掛けています。どうかよろしくお願い致します。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:新潮社
- ページ数:0
- ISBN:9784101097077
- 発売日:1977年07月01日
- 価格:23円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。