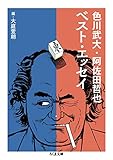ぽんきちさん
レビュアー:
▼
ヒトとは何か。自分とは何か。
「科学道100冊2021」の1冊。
原題は"How to Grow a Human---Adventures in Who We Are and How We Are Made"。「ヒトの育て方---私たちが何者であり、どのように作られるのか」といったところだろうか。
超最先端のバイオテクノロジーは、将来的に人間のありかたを変えるのか?
ゲノム編集、クローニング、脳、生殖医療といったトピックから、技術の発展と社会との関わりを追う。
発端は、著者自身の腕の細胞から作製された脳オルガノイドである。「ミニ脳」とも呼ばれているが、ニューロンの塊で、ネットワークを作り、互いに信号を送り合ってもいる。信号を送り合っているとするならば、何らかの「意識」があると考えてもよいのか。「意識」があるとすれば、それは「誰」なのか?
著者から作製されたが、もちろん、著者自身ではない。ではそれは一体「何者」なのだろう?
最先端の生命科学には、実はそうした倫理的な問題が潜在的に数多く存在する。
やろうとすればできるが、しかしそれは倫理的にやってもよいことなのか。
その議論が十分でないままに、グレーゾーンを抱えながら、技術が発展しつつある。
そんな状況を紹介する本である。
いささかSFめいており、ホラーのようでもあるが、現実である。
元をたどれば、身体の一部である細胞を培養することが可能になったときにそれは始まっていたのかもしれない。
体外に取り出された細胞の培養に成功すれば、ときにそれは持ち主が亡くなった後も増え続ける。そしてiPS細胞のように、さまざまなものに分化する幹細胞にすることができれば、そこから身体の各部や、個体そのものを作ることもできる。それは一体「誰」なのか。
生殖にも技術は入り込む。体外受精は始まった当初は懐疑的に見る向きも少なくなかった(「試験管ベビー」)が、今ではそれほど珍しくはない。
技術を使うとき、そこには何らかの介入がある。受精能力が高い「質」のよい卵子や精子を選ぶことは、目的からして当然のことだろうが、けれども「質」とは何だろうか?疾患のない胚を選択することが許されるなら、疾患になる可能性がある胚を除くことは許されるのか? 疾患になるかもしれないが、ならないかもしれない。線引きは誰がどうするのか、そして疾患になるからといって「抹殺」することは本当に「正しい」のか。
さらには、好ましい形質を選ぶ(=デザイナーベビー)ことが可能ならば、やはりそれを選ぼうと思う者は出てくるだろう。
社会は本当に、それに向き合う準備ができているのだろうか。
原題は"How to Grow a Human---Adventures in Who We Are and How We Are Made"。「ヒトの育て方---私たちが何者であり、どのように作られるのか」といったところだろうか。
超最先端のバイオテクノロジーは、将来的に人間のありかたを変えるのか?
ゲノム編集、クローニング、脳、生殖医療といったトピックから、技術の発展と社会との関わりを追う。
発端は、著者自身の腕の細胞から作製された脳オルガノイドである。「ミニ脳」とも呼ばれているが、ニューロンの塊で、ネットワークを作り、互いに信号を送り合ってもいる。信号を送り合っているとするならば、何らかの「意識」があると考えてもよいのか。「意識」があるとすれば、それは「誰」なのか?
著者から作製されたが、もちろん、著者自身ではない。ではそれは一体「何者」なのだろう?
最先端の生命科学には、実はそうした倫理的な問題が潜在的に数多く存在する。
やろうとすればできるが、しかしそれは倫理的にやってもよいことなのか。
その議論が十分でないままに、グレーゾーンを抱えながら、技術が発展しつつある。
そんな状況を紹介する本である。
いささかSFめいており、ホラーのようでもあるが、現実である。
元をたどれば、身体の一部である細胞を培養することが可能になったときにそれは始まっていたのかもしれない。
体外に取り出された細胞の培養に成功すれば、ときにそれは持ち主が亡くなった後も増え続ける。そしてiPS細胞のように、さまざまなものに分化する幹細胞にすることができれば、そこから身体の各部や、個体そのものを作ることもできる。それは一体「誰」なのか。
生殖にも技術は入り込む。体外受精は始まった当初は懐疑的に見る向きも少なくなかった(「試験管ベビー」)が、今ではそれほど珍しくはない。
技術を使うとき、そこには何らかの介入がある。受精能力が高い「質」のよい卵子や精子を選ぶことは、目的からして当然のことだろうが、けれども「質」とは何だろうか?疾患のない胚を選択することが許されるなら、疾患になる可能性がある胚を除くことは許されるのか? 疾患になるかもしれないが、ならないかもしれない。線引きは誰がどうするのか、そして疾患になるからといって「抹殺」することは本当に「正しい」のか。
さらには、好ましい形質を選ぶ(=デザイナーベビー)ことが可能ならば、やはりそれを選ぼうと思う者は出てくるだろう。
社会は本当に、それに向き合う準備ができているのだろうか。
掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
分子生物学・生化学周辺の実務翻訳をしています。
本の大海を漂流中。
日々是好日。どんな本との出会いも素敵だ。
あちらこちらとつまみ食いの読書ですが、点が線に、線が面になっていくといいなと思っています。
「実感」を求めて読書しているように思います。
赤柴♀(もも)は3代目。
この夏、有精卵からヒヨコ4羽を孵化させました。そろそろ大雛かな。♂x2、♀x2。ニワトリは割と人に懐くものらしいですが、今のところ、懐く気配はありませんw
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:原書房
- ページ数:0
- ISBN:9784562057320
- 発売日:2020年03月19日
- 価格:2750円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。