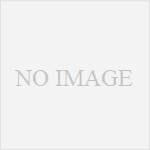hackerさん
レビュアー:
▼
40年間ロシア文学を追い続けてきたヌマヌマご夫婦(沼野充義+沼野恭子)による、現代ロシア文学アンソロジーですが、ウクライナ侵攻後の現在読むと、ロシア文学のこれからが心配になります。
「『全人民を幸福にしてやる』などと厚かましく息巻く老人の顔に唾を吐いてやった」「自分の治める国民に向かって幸福がどうのこうのとしゃあしゃあと嘘をつくなんて馬鹿げてる」(本書収録『空のかなたの坊や』より)
40年間ロシア文学を追い続けてきたヌマヌマ(沼野充義+沼野恭子)にとっても、今回のロシアによるウクライナ侵攻はショックだったことでしょう。戦争の結果がどうなろうと、今後数十年間ロシアは経済的にも文化的にも世界から切り離され、特に欧米ではロシア人というだけで白い目で見られるような事態が続くと思われるからです。ここで引用したような文章が、ロシア国内で今後も平気で書けることが続くのか分かりませんし、既にロシアから出国した若者の数も少なくないそうですが、経済的な魅力も文化的な魅力も薄れた国になってしまえば、ロシア語を学ぼうとする若者の数は、日本でも確実に減るでしょう。
2021年10月、つまり今回の侵攻以前に出版された本書の序文にあたる『はじめに―未来後の世界からの報告』で、ヌマヌマは1985年のペレストロイカのことを「現代ロシア文学にとって決定的な転機となった」と述べていますが、今回の戦争は時計の針をペレストロイカ以前に、下手をするとスターリン時代に戻す可能性があります。というわけで、複雑な思いを抱きながら、本書を読みました。通常、こういう短篇集は、気に入った作品の紹介から始めるのが私の常なのですが、本書に関しては、ロア文学の多様性という観点から、収録された作家の出生等をまず簡単に紹介します。おそらく、大半の作家は知らないという人の方が、圧倒的に多いのではないかと思います。
◆ニーナ・サドゥール 1950年シベリア最大の都市ノヴォシビルスク生まれ
◆ミハイル・シーシキン 1961年モスクワ生まれ、父親はロシア人、母親はウクライナ人で、現在はスイス在住
◆マリーナ・ヴィシネヴェツカヤ 1955年、ウクライナのハルコフ生まれ
◆ヴィクトル・ペレーヴィン 1962年モスクワ生まれ、写真もインタビューも拒否するマスコミ嫌い
◆オリガ・スラヴニコワ 1957年ロシア中央部のウラル山脈東側のエカテリンブルグ生まれ
◆エドワルド・リモーノフ(1943ー2020)は謎に満ちた経歴の持ち主のようで、アメリカに亡命していたこともありますが、ロシアに戻った後は政治家としても知られ、没時は「『共産主義によるロシア人を中核としたユーラシア統一国家の樹立』を主張する」(Wikipediaより)国家ボルシェヴィキ党党首で、テロをも厭わない反プーチン派でしたが、「しばしば研究者などからはネオ・ファシズムの運動家と紹介される」(Wikipediaより)とのことです。
◆タチヤーナ・トルスタヤ 1951年サンクト・ペテルブルグ生まれ
◆ヴィクトル・エロフェーエフ 1947年モスクワ生まれ、「ロシアで初めてのポルノ」と称された『モスクワの美しいひと』の著者
◆エヴゲーニイ・グリシコヴェツ 1967年シベリアの工業都市ケメロヴィ生まれ、自作自演の一人芝居『犬を食った話』で有名になる。
◆アサール・エッペリ 1935-2012 モスクワ生まれ
◆アンドレイ・ピートフ 1937-2018 サンクト・ペテルブルグ生まれ、「ソ連時代には三度日本に招待されながら、一度も当局に出国を許可されなかったという」(解説より)
これらの作家のうち、存命中の方は、おそらく皆ウクライナ侵攻に反対だと思われます。しかし、ウクライナ侵攻を、おそらく支持していると思われる作家も本書には収録されています。1975年生まれのザハール・プリレービンは、解説でも「特別警察の隊員としてチェチェン戦争に参加し」「スターリン再評価を大胆に打ち出した」エッセーを発表したと書かれていますが、ググって見つけた以下のインタビューなどを読むと、そのように推測できます。あまり愉快な内容ではありませんが、興味のある方はご覧ください。
https://jp.rbth.com/arts/2014/12/24/51571
こういう風に並べてみると、収録されている作家たちの人生も多種多様であったことが想像できるでしょう。実際、本書を読んでみると、作家たち同様、作品も多種多様です。それを意識してのアンソロジーです。ですから、どんな方が読んでも、収録作によって好き嫌いはかなり割れるのではないかと思います。
私の好きな作品はというと、人類初の宇宙飛行士ガガーリンの母という設定の「空へ天へと思索をめぐらせていた語り手が、マグマの燃えたぎる『地球の心臓部』にむかって沈み、ついには地球に呑みこまれる」(解説より)という仰天の展開を見せるサドゥールの『空のかなたの坊や』、母を記憶している過去と現在が溶けあう抒情あるシーシキンの『バックベルトの付いたコート』、孫と過ごした別荘での一夏を描くヴィシネヴェッツカヤの心あたたまる『庭』、レーニンの名前ウラジミールの愛称ヴォーヴァを名前に持つ白痴を養子にした家族の血みどろの顛末を描くエロフェーエフの『馬鹿と暮らして』、小さな錨の刺青を手にいれることになった経緯が話される、何とも魅力的な語り口のグリシコヴェッツの『刺青』、汚物と排泄物にまみれたバラック長屋に住んでいる主人公の人妻とよろしくやるまでの、ちょっとセリーヌを連想させる内容のエッペリの『赤いキャビアのサンドイッチ』を挙げておきます。なお『馬鹿と暮らして』に関してですが、書かれたのは1980年で、プーチンの名前もウラジミールですが、そちらは少なくとも書いた時には意識していなかったようです。
というわけで、非常に意欲的なアンソロジーだとは思いますが、収録された作家たちの今後の国内外での活動や評価がどうなるのか、気になってしまうところでした。
40年間ロシア文学を追い続けてきたヌマヌマ(沼野充義+沼野恭子)にとっても、今回のロシアによるウクライナ侵攻はショックだったことでしょう。戦争の結果がどうなろうと、今後数十年間ロシアは経済的にも文化的にも世界から切り離され、特に欧米ではロシア人というだけで白い目で見られるような事態が続くと思われるからです。ここで引用したような文章が、ロシア国内で今後も平気で書けることが続くのか分かりませんし、既にロシアから出国した若者の数も少なくないそうですが、経済的な魅力も文化的な魅力も薄れた国になってしまえば、ロシア語を学ぼうとする若者の数は、日本でも確実に減るでしょう。
2021年10月、つまり今回の侵攻以前に出版された本書の序文にあたる『はじめに―未来後の世界からの報告』で、ヌマヌマは1985年のペレストロイカのことを「現代ロシア文学にとって決定的な転機となった」と述べていますが、今回の戦争は時計の針をペレストロイカ以前に、下手をするとスターリン時代に戻す可能性があります。というわけで、複雑な思いを抱きながら、本書を読みました。通常、こういう短篇集は、気に入った作品の紹介から始めるのが私の常なのですが、本書に関しては、ロア文学の多様性という観点から、収録された作家の出生等をまず簡単に紹介します。おそらく、大半の作家は知らないという人の方が、圧倒的に多いのではないかと思います。
◆ニーナ・サドゥール 1950年シベリア最大の都市ノヴォシビルスク生まれ
◆ミハイル・シーシキン 1961年モスクワ生まれ、父親はロシア人、母親はウクライナ人で、現在はスイス在住
◆マリーナ・ヴィシネヴェツカヤ 1955年、ウクライナのハルコフ生まれ
◆ヴィクトル・ペレーヴィン 1962年モスクワ生まれ、写真もインタビューも拒否するマスコミ嫌い
◆オリガ・スラヴニコワ 1957年ロシア中央部のウラル山脈東側のエカテリンブルグ生まれ
◆エドワルド・リモーノフ(1943ー2020)は謎に満ちた経歴の持ち主のようで、アメリカに亡命していたこともありますが、ロシアに戻った後は政治家としても知られ、没時は「『共産主義によるロシア人を中核としたユーラシア統一国家の樹立』を主張する」(Wikipediaより)国家ボルシェヴィキ党党首で、テロをも厭わない反プーチン派でしたが、「しばしば研究者などからはネオ・ファシズムの運動家と紹介される」(Wikipediaより)とのことです。
◆タチヤーナ・トルスタヤ 1951年サンクト・ペテルブルグ生まれ
◆ヴィクトル・エロフェーエフ 1947年モスクワ生まれ、「ロシアで初めてのポルノ」と称された『モスクワの美しいひと』の著者
◆エヴゲーニイ・グリシコヴェツ 1967年シベリアの工業都市ケメロヴィ生まれ、自作自演の一人芝居『犬を食った話』で有名になる。
◆アサール・エッペリ 1935-2012 モスクワ生まれ
◆アンドレイ・ピートフ 1937-2018 サンクト・ペテルブルグ生まれ、「ソ連時代には三度日本に招待されながら、一度も当局に出国を許可されなかったという」(解説より)
これらの作家のうち、存命中の方は、おそらく皆ウクライナ侵攻に反対だと思われます。しかし、ウクライナ侵攻を、おそらく支持していると思われる作家も本書には収録されています。1975年生まれのザハール・プリレービンは、解説でも「特別警察の隊員としてチェチェン戦争に参加し」「スターリン再評価を大胆に打ち出した」エッセーを発表したと書かれていますが、ググって見つけた以下のインタビューなどを読むと、そのように推測できます。あまり愉快な内容ではありませんが、興味のある方はご覧ください。
https://jp.rbth.com/arts/2014/12/24/51571
こういう風に並べてみると、収録されている作家たちの人生も多種多様であったことが想像できるでしょう。実際、本書を読んでみると、作家たち同様、作品も多種多様です。それを意識してのアンソロジーです。ですから、どんな方が読んでも、収録作によって好き嫌いはかなり割れるのではないかと思います。
私の好きな作品はというと、人類初の宇宙飛行士ガガーリンの母という設定の「空へ天へと思索をめぐらせていた語り手が、マグマの燃えたぎる『地球の心臓部』にむかって沈み、ついには地球に呑みこまれる」(解説より)という仰天の展開を見せるサドゥールの『空のかなたの坊や』、母を記憶している過去と現在が溶けあう抒情あるシーシキンの『バックベルトの付いたコート』、孫と過ごした別荘での一夏を描くヴィシネヴェッツカヤの心あたたまる『庭』、レーニンの名前ウラジミールの愛称ヴォーヴァを名前に持つ白痴を養子にした家族の血みどろの顛末を描くエロフェーエフの『馬鹿と暮らして』、小さな錨の刺青を手にいれることになった経緯が話される、何とも魅力的な語り口のグリシコヴェッツの『刺青』、汚物と排泄物にまみれたバラック長屋に住んでいる主人公の人妻とよろしくやるまでの、ちょっとセリーヌを連想させる内容のエッペリの『赤いキャビアのサンドイッチ』を挙げておきます。なお『馬鹿と暮らして』に関してですが、書かれたのは1980年で、プーチンの名前もウラジミールですが、そちらは少なくとも書いた時には意識していなかったようです。
というわけで、非常に意欲的なアンソロジーだとは思いますが、収録された作家たちの今後の国内外での活動や評価がどうなるのか、気になってしまうところでした。
お気に入り度:







掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
「本職」は、本というより映画です。
本を読んでいても、映画好きの視点から、内容を見ていることが多いようです。
この書評へのコメント
- だまし売りNo2022-06-05 16:59
インタビューに見られるザハール・プリレービンのウクライナもロシア帝国の歴史に包含されるという歴史観は、完全な間違えではないために逆に厄介です。以下で書きましたが、ウクライナ問題は、ロシアではなく、ロシア連邦の否定と考えます。
https://alis.to/hayariki/articles/aRrO98vXlmlqクリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 
コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:河出書房新社
- ページ数:0
- ISBN:9784309208404
- 発売日:2021年10月27日
- 価格:3520円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。