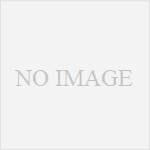hackerさん
レビュアー:
▼
「エルサレムよ/もしも、わたしがあなたを忘れるなら/わたしの右手はなえるがいい」(本書に引用されている旧約聖書の一節)
本書は、自分の「エルサレム」を持たない人々の物語です。
本書は、時代と場所は特定されていない物語です。ただ、語られる時間はバラバラとはいえ、ヒロインのミリアの18歳から48歳の人生が語られていること、(おそらく)ユダヤ人のジェノサイドの写真が登場すること、パソコンは登場しないこと、ハードコアのポルノ雑誌が登場すること、ゲルマン系の名前の登場人物ばかりであることなどから、1950年代から80年代前半にかけての、ドイツを舞台にした30年間の物語と推測はできます。
物語を簡単に紹介します。
ミリアは18歳にして統合失調症を自覚し、両親が診察に連れて行った医師テオドール・ブスベッグは彼女の「他人の胸をざわつかせる、暴力的とも言えるほどの美貌」に魅せられ、結婚します。しかし、周囲が心配した通り、二人の生活はやがて破綻し、ミリアはゴンベルツ博士が院長をしている有名なゲオルグ・ローゼンベルグ精神病院に入院させられます。そこで、ミリアは入院患者のエルンスト・スペングラーと関係を結び、妊娠します。テオドールは激怒して、ミリアと離婚し、病院からは監督不行き届きを理由に多額の賠償金を得ます。ただし、生まれた息子カースは、自分の元に引き取ります。そしてミリアはゴンベルツによって無断で不妊手術をさせられしまい、その後遺症もあって、40過ぎてから、不治の病(おそらく癌)に侵され、余命いくばくもないことを宣告されたのでした。
時系列に書くと、こういう風になるのですが、本書は、まず、腹部の苦痛に耐えきれず深夜の街にさまよい出たミリアが教会を探して、うろつき回り、今まさに自殺しようとしていた、長年会っていないエルンストに電話をするところから始まり、過去と現在の時間を行き来しつつ物語が進んでいくうちに、登場人物を巡る状況が明らかになってくるという構成を採っています。
登場人物で特徴的なのは、精神と身体のいずれか若しくは両方に、問題を抱えていることです。
ミリアは前述した通りですし、同じ精神病院にいたエルンストも不自由な右脚をかかえています。彼らの息子カースは、ひ弱な脚の他、発声に難があります。その他に、重要な役割で登場する、殺人願望を抑えられない元兵士ヒンネルクも不自由な片足をかかえています。
テオドールは、肉体的問題はないものの、人間の恐怖(これが登場人物たちを突き動かしているわけですが)を題材にした、正に狂気じみた研究に憑りつかれ、一巻800ページで全5巻の論文を発表するのですが、著名生物学者によって完璧なまでに叩きのめされるという経験をし、今では学会では相手にされません。「狂人とは不道徳な行いをする者のことであるが、それだけではない。道徳的な行いをしても、不道徳な考えを持つ者は、やはり狂人である」というゴンベルツ博士の信念も、狂気以外の何物でもありません。
興味深いのは、ミリア、エルンスト、カース、ヒンネルクは社会的弱者、テオドール、ゴンベルツ博士、テオドールの父は社会的強者に分類できることで、社会の中でどんな地位にあろうと、意識していても意識していなくても、病んだ人間たちで溢れかえっている現代が象徴的に描かれた作品と言って良いでしょう。カースを除くと、世代的には、全員第二次大戦経験者だということも重要です。
そして、登場人物たちは、結局のところ、意味のない二つの殺人を契機に、お互いのことをほとんど理解しないままバラバラとなるラストが用意されているのは、読後の印象として、不快感と共に強く残ります。作中で引用されている旧約聖書の言葉のように、誰も、失ってはならない「エルサレム」を持っていない、あるいは、それに気づかないままという終わり方ということもあります。実は、1970年生まれで、アンゴラ出身の作者ゴンサロ・М・タヴァレスは、リスボン大学で認識学の教授をしているそうで、それを考えると、本書で多々描かれる「すれ違い」も興味深いところです。
しかし、読後に全体を振り返ってみると、作者が語りたかったのは何なのだろう、という思いが湧いてくるのは避けられません。それは、本書の世界が、あまりにも作りすぎの印象を与えるからのような気がします。ミリアとエルンストの息子のカースの障碍の設定などは、私にはやり過ぎのように思えますし、テオドール、ゴンベルツ博士、テオドールの父のキャラクタ設定なども、いささか類型的に感じられます。また、ミリアはいつも十字架をつけていて、キリスト教に思いがあるようなのですが、それが物語や彼女の行動の動機にどういうインパクトがあるのかは、よく分かりません、というか、あまり語られていないような気がします。キリスト教への思いというのは、本書題名のつけ方からも、作者自身に起因するものなのでしょうが、こちらの宗教全般への無知と興味のなさはあるとはいえ、本書の物語から何らかの宗教観を感じるのは無理だと思います。要するに、こういう小説では、登場人物たちの内面にどれだけ食い込めるかが大事だと思うのですが、個人的には、その点は満足できませんでした。結局のところ、登場人物たちに、私がシンパシーを感じられないというだけの理由かもしれないものの、再読する気にならない小説というのは、私の中では評価が低くなります。
なお、本書はとてもパワフルな作品です。ただし、拙文を読んでいただければお分かりのように、毒もあります。人によっては、不快感を覚えるかもしれないと思うグロテスクな描写もあります。この点はご注意ください。念のため。
物語を簡単に紹介します。
ミリアは18歳にして統合失調症を自覚し、両親が診察に連れて行った医師テオドール・ブスベッグは彼女の「他人の胸をざわつかせる、暴力的とも言えるほどの美貌」に魅せられ、結婚します。しかし、周囲が心配した通り、二人の生活はやがて破綻し、ミリアはゴンベルツ博士が院長をしている有名なゲオルグ・ローゼンベルグ精神病院に入院させられます。そこで、ミリアは入院患者のエルンスト・スペングラーと関係を結び、妊娠します。テオドールは激怒して、ミリアと離婚し、病院からは監督不行き届きを理由に多額の賠償金を得ます。ただし、生まれた息子カースは、自分の元に引き取ります。そしてミリアはゴンベルツによって無断で不妊手術をさせられしまい、その後遺症もあって、40過ぎてから、不治の病(おそらく癌)に侵され、余命いくばくもないことを宣告されたのでした。
時系列に書くと、こういう風になるのですが、本書は、まず、腹部の苦痛に耐えきれず深夜の街にさまよい出たミリアが教会を探して、うろつき回り、今まさに自殺しようとしていた、長年会っていないエルンストに電話をするところから始まり、過去と現在の時間を行き来しつつ物語が進んでいくうちに、登場人物を巡る状況が明らかになってくるという構成を採っています。
登場人物で特徴的なのは、精神と身体のいずれか若しくは両方に、問題を抱えていることです。
ミリアは前述した通りですし、同じ精神病院にいたエルンストも不自由な右脚をかかえています。彼らの息子カースは、ひ弱な脚の他、発声に難があります。その他に、重要な役割で登場する、殺人願望を抑えられない元兵士ヒンネルクも不自由な片足をかかえています。
テオドールは、肉体的問題はないものの、人間の恐怖(これが登場人物たちを突き動かしているわけですが)を題材にした、正に狂気じみた研究に憑りつかれ、一巻800ページで全5巻の論文を発表するのですが、著名生物学者によって完璧なまでに叩きのめされるという経験をし、今では学会では相手にされません。「狂人とは不道徳な行いをする者のことであるが、それだけではない。道徳的な行いをしても、不道徳な考えを持つ者は、やはり狂人である」というゴンベルツ博士の信念も、狂気以外の何物でもありません。
興味深いのは、ミリア、エルンスト、カース、ヒンネルクは社会的弱者、テオドール、ゴンベルツ博士、テオドールの父は社会的強者に分類できることで、社会の中でどんな地位にあろうと、意識していても意識していなくても、病んだ人間たちで溢れかえっている現代が象徴的に描かれた作品と言って良いでしょう。カースを除くと、世代的には、全員第二次大戦経験者だということも重要です。
そして、登場人物たちは、結局のところ、意味のない二つの殺人を契機に、お互いのことをほとんど理解しないままバラバラとなるラストが用意されているのは、読後の印象として、不快感と共に強く残ります。作中で引用されている旧約聖書の言葉のように、誰も、失ってはならない「エルサレム」を持っていない、あるいは、それに気づかないままという終わり方ということもあります。実は、1970年生まれで、アンゴラ出身の作者ゴンサロ・М・タヴァレスは、リスボン大学で認識学の教授をしているそうで、それを考えると、本書で多々描かれる「すれ違い」も興味深いところです。
しかし、読後に全体を振り返ってみると、作者が語りたかったのは何なのだろう、という思いが湧いてくるのは避けられません。それは、本書の世界が、あまりにも作りすぎの印象を与えるからのような気がします。ミリアとエルンストの息子のカースの障碍の設定などは、私にはやり過ぎのように思えますし、テオドール、ゴンベルツ博士、テオドールの父のキャラクタ設定なども、いささか類型的に感じられます。また、ミリアはいつも十字架をつけていて、キリスト教に思いがあるようなのですが、それが物語や彼女の行動の動機にどういうインパクトがあるのかは、よく分かりません、というか、あまり語られていないような気がします。キリスト教への思いというのは、本書題名のつけ方からも、作者自身に起因するものなのでしょうが、こちらの宗教全般への無知と興味のなさはあるとはいえ、本書の物語から何らかの宗教観を感じるのは無理だと思います。要するに、こういう小説では、登場人物たちの内面にどれだけ食い込めるかが大事だと思うのですが、個人的には、その点は満足できませんでした。結局のところ、登場人物たちに、私がシンパシーを感じられないというだけの理由かもしれないものの、再読する気にならない小説というのは、私の中では評価が低くなります。
なお、本書はとてもパワフルな作品です。ただし、拙文を読んでいただければお分かりのように、毒もあります。人によっては、不快感を覚えるかもしれないと思うグロテスクな描写もあります。この点はご注意ください。念のため。
お気に入り度:





掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
「本職」は、本というより映画です。
本を読んでいても、映画好きの視点から、内容を見ていることが多いようです。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:河出書房新社
- ページ数:0
- ISBN:9784309208282
- 発売日:2021年05月24日
- 価格:3245円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。