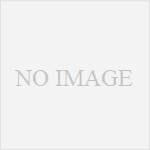hackerさん
レビュアー:
▼
「ほとんどすべてのことは経験した。恋もしたし、そのあとに絶望もした。いまはただ、存在した過去の自分と、存在しなかった過去の自分とを、手に入れることを望んでいるだけだ」(本書より)
「死ぬとき人はスターになって輝く」(本書より)
本書は、ウクライナ生まれのユダヤ系女性ブラジル文学者クラリッサ・リスペクトル(1920-1977)の死の年に発表された遺作です。そして、これが遺作になるということを意識して書かれた本です。また、本書のタイトルは、この引用文から分かるように「死の時」を意味する『星の時』となっていますが、実際には13のタイトルがあります。フル・タイトルは以下のようになりす。
『ぼくのせい』
または
『星の時』
または
『なんとかする彼女』
または
『叫ぶ権利』
または
『未来については』
または
『あるブルーの嘆き』
または
『彼女は叫べない』
または
『ある喪失感』
または
『暗い風のなかの口笛』
または
『ぼくは何もできない』
または
『前に起こった事実の記録』
または
『三文小説の涙物語』
または
『裏口からこっそり抜け出す』
これらは、本書の内容を、そのまま表したタイトルなのですが、では、何が語られているのかというと、これが難物なのです。
本書は、作家である「ぼく」が、ブラジル北西部からリオデジャネイロに出てきてタイピストをしているマカベーアという貧しく無知な若い女性のことを語る、という構成になっています。ところが、作者の分身と思える「ぼく」が自分のことをいろいろと語るのが前半の大半を占めていて、マカベーアの話が本格的に語られだすのは後半からです。そして、作者リスペクトルとその家族がユダヤ人の迫害を逃れて、ブラジルで落ち着いたのは北西部の港町だということもあって、マカベーアにも作者の分身を見ることができるので、一つの小説の中に、語り手である作者の分身と、語られる側の作者の分身が存在するという、あまり例のない構成を採っています。
ところで、ブラジルの北西部というと、作中でも「荒野」という表現が使われていますが、この国でも貧しい地域だそうです。映画好きなら、グラウベル・ローシャ監督の『黒い神と白い悪魔』(1964年)と『アントニオ・ダス・モルテス』(1969年)の舞台はこの地方なので、そこで描かれている、アマゾンのイメージとかけ離れている乾いた大地を思いだせば良いでしょう。Wikipedia によると、作者の生まれ故郷もウクライナでは貧しい地域だったそうで、貧困は作者の幼少期にはなじみのあったものなのだと思います。
ただ、そう考えてくると、結局、本書は作者自身が自分の死の前に、自分自身を主観と客観の双方の視点から語ろうとしたもののようです。つまり「存在した過去の自分」は「ぼく」で、「存在しなかった過去の自分」がマカベーアのように思えます。おそらく、マカベーアは、作者がなったかもしれない北西部の貧しい少女の姿ではないでしょうか。そして、「ぼく」に投影された作者がもうじき世を去る運命であるがゆえに、マカベーアも本書のラストでは死を迎えます。
本書は、そういう意味では、死の匂いに満ちています。題名の一つである『裏口からこっそり抜け出す』は、こっそりと、この世から去りたいという自分の死への願望であることであるのは明らかでしょう。こんな文章もあります。
「ぼくは書くことに疲れ切っている―沈黙だけがぼくの仲間だ。ぼくが書き続けるのは、死を待つあいだ、この世界で他にすることもないから」
ただ、本書は決して読みやすい小説ではありません。特に前半は、難渋します。訳者あとがきで、福嶋伸洋も、言語構造のまったく違う日本語への翻訳には苦労したという主旨のことを書いていますが、原文は独特のリズム感があるように思えるので、詩が特にそうですが、原音の美しさは、日本語では表現できませんからその苦労も分かります。しかし、この独特の構成といい、死の匂いに満ちた雰囲気といい、ちょっと忘れ難い印象を残す作品です。
また、本書では、いくつか気に入った文章がありますが、最後に一つだけ紹介します。今の私には、この感覚はすごくよく分かります。
「こう問いかけたことのない人がいるだろうかー自分は怪物なのか、それともこれが人間というものなのか、と」
本書は、ウクライナ生まれのユダヤ系女性ブラジル文学者クラリッサ・リスペクトル(1920-1977)の死の年に発表された遺作です。そして、これが遺作になるということを意識して書かれた本です。また、本書のタイトルは、この引用文から分かるように「死の時」を意味する『星の時』となっていますが、実際には13のタイトルがあります。フル・タイトルは以下のようになりす。
『ぼくのせい』
または
『星の時』
または
『なんとかする彼女』
または
『叫ぶ権利』
または
『未来については』
または
『あるブルーの嘆き』
または
『彼女は叫べない』
または
『ある喪失感』
または
『暗い風のなかの口笛』
または
『ぼくは何もできない』
または
『前に起こった事実の記録』
または
『三文小説の涙物語』
または
『裏口からこっそり抜け出す』
これらは、本書の内容を、そのまま表したタイトルなのですが、では、何が語られているのかというと、これが難物なのです。
本書は、作家である「ぼく」が、ブラジル北西部からリオデジャネイロに出てきてタイピストをしているマカベーアという貧しく無知な若い女性のことを語る、という構成になっています。ところが、作者の分身と思える「ぼく」が自分のことをいろいろと語るのが前半の大半を占めていて、マカベーアの話が本格的に語られだすのは後半からです。そして、作者リスペクトルとその家族がユダヤ人の迫害を逃れて、ブラジルで落ち着いたのは北西部の港町だということもあって、マカベーアにも作者の分身を見ることができるので、一つの小説の中に、語り手である作者の分身と、語られる側の作者の分身が存在するという、あまり例のない構成を採っています。
ところで、ブラジルの北西部というと、作中でも「荒野」という表現が使われていますが、この国でも貧しい地域だそうです。映画好きなら、グラウベル・ローシャ監督の『黒い神と白い悪魔』(1964年)と『アントニオ・ダス・モルテス』(1969年)の舞台はこの地方なので、そこで描かれている、アマゾンのイメージとかけ離れている乾いた大地を思いだせば良いでしょう。Wikipedia によると、作者の生まれ故郷もウクライナでは貧しい地域だったそうで、貧困は作者の幼少期にはなじみのあったものなのだと思います。
ただ、そう考えてくると、結局、本書は作者自身が自分の死の前に、自分自身を主観と客観の双方の視点から語ろうとしたもののようです。つまり「存在した過去の自分」は「ぼく」で、「存在しなかった過去の自分」がマカベーアのように思えます。おそらく、マカベーアは、作者がなったかもしれない北西部の貧しい少女の姿ではないでしょうか。そして、「ぼく」に投影された作者がもうじき世を去る運命であるがゆえに、マカベーアも本書のラストでは死を迎えます。
本書は、そういう意味では、死の匂いに満ちています。題名の一つである『裏口からこっそり抜け出す』は、こっそりと、この世から去りたいという自分の死への願望であることであるのは明らかでしょう。こんな文章もあります。
「ぼくは書くことに疲れ切っている―沈黙だけがぼくの仲間だ。ぼくが書き続けるのは、死を待つあいだ、この世界で他にすることもないから」
ただ、本書は決して読みやすい小説ではありません。特に前半は、難渋します。訳者あとがきで、福嶋伸洋も、言語構造のまったく違う日本語への翻訳には苦労したという主旨のことを書いていますが、原文は独特のリズム感があるように思えるので、詩が特にそうですが、原音の美しさは、日本語では表現できませんからその苦労も分かります。しかし、この独特の構成といい、死の匂いに満ちた雰囲気といい、ちょっと忘れ難い印象を残す作品です。
また、本書では、いくつか気に入った文章がありますが、最後に一つだけ紹介します。今の私には、この感覚はすごくよく分かります。
「こう問いかけたことのない人がいるだろうかー自分は怪物なのか、それともこれが人間というものなのか、と」
お気に入り度:







掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
「本職」は、本というより映画です。
本を読んでいても、映画好きの視点から、内容を見ていることが多いようです。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:河出書房新社
- ページ数:0
- ISBN:9784309208190
- 発売日:2021年03月26日
- 価格:2695円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。