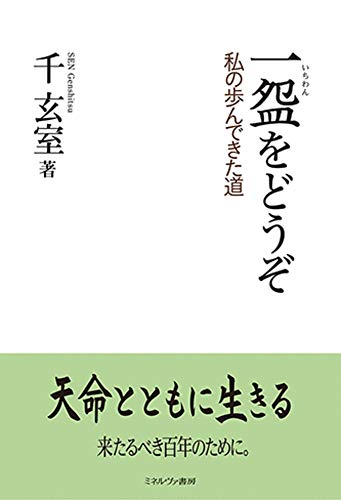▼
裏千家の15代目宗室である著者の一代記。彼の生きざまを知ること以上に感じ入るものがある1冊だった。
誰もが長い血脈を経て現世に生きている。
しかし、誰もが首肯する伝統文化を背負う家柄というものがあり、それを受け継いだ者もおり、余人には計り知れない労苦を引き受けている。
本書の著者は裏千家の15代宗室であり、大正、昭和、平成、そして令和を生きている。
本書はその人生を振り返った1冊である。
千家は千利休を祖とし、「裏千家」と「表千家」、「武者小路千家」がある。
戦国時代から続く千家の長男に生まれ、茶の道を歩むことが宿命づけられていた著者。
“良い家柄”という短絡的な評価が恥ずかしくなるくらい、きちんと考えられた教育を受けてきたことが記されていた。
5歳で初めて袴をつける「着袴の儀」6歳の6月6日に稽古をはじめるとのこと。
今の習い事のような友達がやってるから始めるといったような甘い考えではなく、明確な習俗としての稽古の始め方ひとつとっても重みの差を感じる。
著者は人生で4回名前を変えたそうだ。
しかも、跡目を継いで宗室となったときには、戸籍まで変更するという。
襲名とはこれほどのものと初めて知った。
歌舞伎なんかもそうなのか?
ちなみに、成人してからも「千」を名乗ることが許されるのは跡継ぎの長男だけで、次男、三男は婿養子になったりして名字が変わるものらしい。
このような家の事情は、私のような一般人には関係のないことと思っているし、事実、家を継ぐということの苦労なんかもなく過ごしていた。
「人生百年」と言うようになったが、それは個人の人生だけの話で終始しているし、自分自身もそう思っていた。
しかし、著者は個人の「人生百年」という考え方はよくないことを指摘する。
「各人が自分の百年ではなく、百年後の人たちのため、どういう生き方をするべきなのかを考えておかないといけない。そのことに多くの人が気づいていないようです」(263頁)と。
確かに100年後の人のことを考えて「人生百年」を捉えてこなかった。
著者が指摘する考え方ではなければ、地球温暖化の問題のように長期に及ぶ解決策を講じなければいけない問題を、先々の人たちのこととして軽んじられてしまうことに繋がる。
そして、著者は茶の湯のように長い伝統を引き継いだ立場の者だけではなく、他の職業にも次に伝えるべきことはあると説く。
個人的には、仕事は日々の生活のためのものと思っていた。
自己実現という考えもなかったし、ましてや次に伝えるべきことなんか想像だにしなかった。
少し考え方を変えてみようと思う。
伝統文化を引き継ぐ立場ではなし、自分の仕事に次世代へ伝えるべきことが何なのか考えてこなかったため今のところ何のビジョンもないが、何かしら自分の仕事の金銭以外の意味合いを考えていきたい。
本書に出会った意味は、この考え方の転換にこそあると思う。
しかし、誰もが首肯する伝統文化を背負う家柄というものがあり、それを受け継いだ者もおり、余人には計り知れない労苦を引き受けている。
本書の著者は裏千家の15代宗室であり、大正、昭和、平成、そして令和を生きている。
本書はその人生を振り返った1冊である。
千家は千利休を祖とし、「裏千家」と「表千家」、「武者小路千家」がある。
戦国時代から続く千家の長男に生まれ、茶の道を歩むことが宿命づけられていた著者。
“良い家柄”という短絡的な評価が恥ずかしくなるくらい、きちんと考えられた教育を受けてきたことが記されていた。
5歳で初めて袴をつける「着袴の儀」6歳の6月6日に稽古をはじめるとのこと。
今の習い事のような友達がやってるから始めるといったような甘い考えではなく、明確な習俗としての稽古の始め方ひとつとっても重みの差を感じる。
著者は人生で4回名前を変えたそうだ。
しかも、跡目を継いで宗室となったときには、戸籍まで変更するという。
襲名とはこれほどのものと初めて知った。
歌舞伎なんかもそうなのか?
ちなみに、成人してからも「千」を名乗ることが許されるのは跡継ぎの長男だけで、次男、三男は婿養子になったりして名字が変わるものらしい。
このような家の事情は、私のような一般人には関係のないことと思っているし、事実、家を継ぐということの苦労なんかもなく過ごしていた。
「人生百年」と言うようになったが、それは個人の人生だけの話で終始しているし、自分自身もそう思っていた。
しかし、著者は個人の「人生百年」という考え方はよくないことを指摘する。
「各人が自分の百年ではなく、百年後の人たちのため、どういう生き方をするべきなのかを考えておかないといけない。そのことに多くの人が気づいていないようです」(263頁)と。
確かに100年後の人のことを考えて「人生百年」を捉えてこなかった。
著者が指摘する考え方ではなければ、地球温暖化の問題のように長期に及ぶ解決策を講じなければいけない問題を、先々の人たちのこととして軽んじられてしまうことに繋がる。
そして、著者は茶の湯のように長い伝統を引き継いだ立場の者だけではなく、他の職業にも次に伝えるべきことはあると説く。
個人的には、仕事は日々の生活のためのものと思っていた。
自己実現という考えもなかったし、ましてや次に伝えるべきことなんか想像だにしなかった。
少し考え方を変えてみようと思う。
伝統文化を引き継ぐ立場ではなし、自分の仕事に次世代へ伝えるべきことが何なのか考えてこなかったため今のところ何のビジョンもないが、何かしら自分の仕事の金銭以外の意味合いを考えていきたい。
本書に出会った意味は、この考え方の転換にこそあると思う。
お気に入り度:









掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
ここに参加するようになって、読書の幅が広がったように思います。
それでも、まだ偏り気味。
いろんな人の書評を参考に、もっと幅広い読書を楽しみたい!
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:ミネルヴァ書房
- ページ数:304
- ISBN:9784623088522
- 発売日:2020年11月22日
- 価格:2200円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。