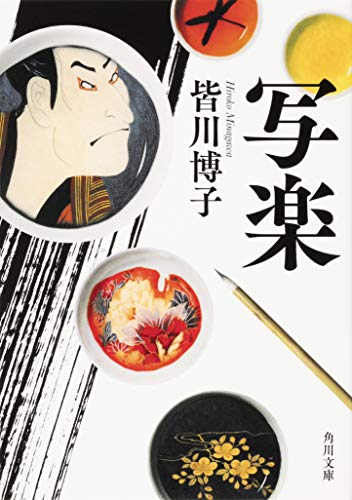efさん
レビュアー:
▼
東洲斎写楽とは一体何者だったのか?
東洲斎写楽は、1794年5月に登場し、その10か月後に突然姿を消した謎の浮世絵師です。
その大胆な絵柄は現在でも高く評価されていることはご存知のとおり。
写楽の正体についても諸説あります。
さて、本作は、そんな写楽について皆川さんなりに書いた作品です。
そもそもは、1995年に公開された、篠田正浩監督、フランキー堺が蔦屋重三郎を演じた映画から始まります。
皆川さんの『みだら栄泉』を読んだ篠田監督が、『写楽』のシナリオを皆川さんに依頼したんです。
シナリオはシナリオとして制作され、映画も公開されましたが、せっかくだからノベライズではなく、小説としても書いて欲しいという角川書店の担当編集者の依頼により、本作が書かれたということです。
ノベライズではないので、しっかりとした作品に仕上がっています。
皆川さんは、写楽の正体については諸説あるけれど、所詮謎は謎、写楽は写楽なのだとある意味割り切ったのでしょうね。
『稲荷町』と呼ばれた歌舞伎の最下級の役者こそが写楽だったという設定にしています。
彼は筋斗(とんぼ)を切るのが上手かったことから、市川團十郎に指名され、團十郎と一対一で絡む役を与えられたのです。
彼はそこで見事に筋斗を切ってみせたのですが、続く場面で團十郎が上る梯子を押さえていた時、彼の足に梯子の足が置かれたのです。
主役を喰うやり過ぎを團十郎に咎められたのか、嫉妬した稲荷町の嫌がらせか……。
激痛が彼を襲いましたが、團十郎を落としてはならないと堪え、結局、足を潰されてしまいます。
彼は、役者を続けられなくなったため、以後、『とんぼ』と名乗り、女門付けに買われ、落ちぶれた生活を始めます。
実は、とんぼの母は砂絵を描いていたことがあり、とんぼにも絵の心得があったことと、ある時期、絵師に買われ(当時、役者は男色も含め色を売るのが普通でした)、絵の手ほどきを受けたことがあったのです。
とんぼは、時々、手慰みに絵を描いていたのですが、それが稀代のプロデューサーである蔦屋重三郎の目に留まりました。
蔦屋はとんぼを自宅に置き、これまでにない斬新な役者絵を描かせ、それを売り出したのです。
しかし、その後……。
しっとりとした情感も交えた手堅い作品だと思います。
また、本作で写楽が実はとんぼであると分かるのは物語のかなり後半になってからなんです。
ですから、読者は「写楽はどうした?」とちょっと気をやきもきさせることになります。
本作は、『写楽』というタイトルであり、確かにとんぼ時代も含めた彼の半生記ではあるのですが、あるいは蔦屋重三郎の方に比重がある作品にすら読めてきます。
皆川さんは役者もの、芝居の原作者(鶴屋南北)などの世界を結構書いており、この辺りはお手の物かもしれません。
非常に手慣れた書き振りで、また、リズムもある文体です。
読了時間メーター
□□□ 普通(1~2日あれば読める)
その大胆な絵柄は現在でも高く評価されていることはご存知のとおり。
写楽の正体についても諸説あります。
さて、本作は、そんな写楽について皆川さんなりに書いた作品です。
そもそもは、1995年に公開された、篠田正浩監督、フランキー堺が蔦屋重三郎を演じた映画から始まります。
皆川さんの『みだら栄泉』を読んだ篠田監督が、『写楽』のシナリオを皆川さんに依頼したんです。
シナリオはシナリオとして制作され、映画も公開されましたが、せっかくだからノベライズではなく、小説としても書いて欲しいという角川書店の担当編集者の依頼により、本作が書かれたということです。
ノベライズではないので、しっかりとした作品に仕上がっています。
皆川さんは、写楽の正体については諸説あるけれど、所詮謎は謎、写楽は写楽なのだとある意味割り切ったのでしょうね。
『稲荷町』と呼ばれた歌舞伎の最下級の役者こそが写楽だったという設定にしています。
彼は筋斗(とんぼ)を切るのが上手かったことから、市川團十郎に指名され、團十郎と一対一で絡む役を与えられたのです。
彼はそこで見事に筋斗を切ってみせたのですが、続く場面で團十郎が上る梯子を押さえていた時、彼の足に梯子の足が置かれたのです。
主役を喰うやり過ぎを團十郎に咎められたのか、嫉妬した稲荷町の嫌がらせか……。
激痛が彼を襲いましたが、團十郎を落としてはならないと堪え、結局、足を潰されてしまいます。
彼は、役者を続けられなくなったため、以後、『とんぼ』と名乗り、女門付けに買われ、落ちぶれた生活を始めます。
実は、とんぼの母は砂絵を描いていたことがあり、とんぼにも絵の心得があったことと、ある時期、絵師に買われ(当時、役者は男色も含め色を売るのが普通でした)、絵の手ほどきを受けたことがあったのです。
とんぼは、時々、手慰みに絵を描いていたのですが、それが稀代のプロデューサーである蔦屋重三郎の目に留まりました。
蔦屋はとんぼを自宅に置き、これまでにない斬新な役者絵を描かせ、それを売り出したのです。
しかし、その後……。
しっとりとした情感も交えた手堅い作品だと思います。
また、本作で写楽が実はとんぼであると分かるのは物語のかなり後半になってからなんです。
ですから、読者は「写楽はどうした?」とちょっと気をやきもきさせることになります。
本作は、『写楽』というタイトルであり、確かにとんぼ時代も含めた彼の半生記ではあるのですが、あるいは蔦屋重三郎の方に比重がある作品にすら読めてきます。
皆川さんは役者もの、芝居の原作者(鶴屋南北)などの世界を結構書いており、この辺りはお手の物かもしれません。
非常に手慣れた書き振りで、また、リズムもある文体です。
読了時間メーター
□□□ 普通(1~2日あれば読める)
お気に入り度:





掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
幻想文学、SF、ミステリ、アート系などの怪しいモノ大好きです。ご紹介レビューが基本ですが、私のレビューで読んでみようかなと思って頂けたらうれしいです。世界中にはまだ読んでいない沢山の良い本がある!
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:KADOKAWA
- ページ数:0
- ISBN:9784041096963
- 発売日:2020年07月16日
- 価格:924円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。