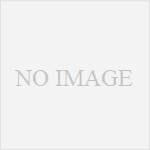ぽんきちさん
レビュアー:
▼
ザリガニが鳴くところとはどこか
32週に渡ってニューヨークタイムズ・フィクションベストセラーの1位を飾り、2019年、アメリカで最も多く売れたという作品である。
著者の経歴が少々変わっていて、元々は動物学者であり、ノンフィクションの共著が3作ある。一方で、小説家になる夢もあったのだそうで、70歳を過ぎて初めて書いたフィクションが本作である。
作品自体も一風変わっていて、ミステリのようでもあり、自然の美しさを描くようでもあり、何よりも主人公「カイア」の人生を描いているようでもある。
時折はさまれる詩も印象的である。幼少期の著者の文学少女ぶりを彷彿とさせる。
作品の舞台はノース・カロライナ州。湿地にある小さな村である。カイアはホワイトトラッシュ(貧乏白人)と呼ばれる、いわゆる「下層」と見なされる階級に属している。父親は戦争で負傷し、その障害手当だけが一家の収入だった。父は家で暴力をふるった。母親は出ていき、兄弟たちも次々に去っていった。やがて父も姿を消し、カイアは湿地の中、一人きりで生きていかなければならなくなる。
物語は、カイアが一人で暮らし始める1952年以降と、1人の青年が死ぬ「事件」が起きた1969年を交互に描く。
富裕階級に属し、アメフトの高校生スター選手としても活躍したチェイス・アンドルーズが死んだのだ。時代を行き来する物語の中で、その事件とカイアとの間の関わりが徐々に明らかになっていく。
1人ぼっちになった幼いカイアは、規則だからと学校に通うことになったが、到底なじめず、1日しか行けなかった。お金もなく、貝や魚を売って暮らしを立てた。親切な黒人の燃料店店主が何くれとなく面倒を見てくれた。
カイアはあるとき、兄の友達であったという青年、テイトと出会う。テイトは先生役を務めてくれ、文字や知識を教えてくれた。生来聡明であった彼女は、多くのことを学び取った。
2人の間には通い合うものがあったが、同時に越えられない壁もあった。
カイアは苦い別れを経験する。
その隙に割り込んできたのがチェイスだった。
表題の「ザリガニの鳴くところ(where the crawdads sing)」には、作品中で何度か触れられる。要は「生き物たちが自然の姿でいられるところ」を指す。
虹のかなた(somewhere over the rainbow)のような楽園にも思えるけれども、実はこれは単純な理想郷でもないようだ。自然は時に残酷だ。カマキリの雌は交尾中の雄を食い殺すし、食べ物が不足した母キツネは小ギツネを見捨てる。本能にしたがい、生き延びるために手段を選ばない。
身一つで生きるすがすがしさの裏には、明日の運命も知れない危うさがある。
「事件」は、ある意味、自然の中で生き抜こうとするものと文明社会で暮らすもの、あるいは下層階級に属するものと富裕層の特権を享受するものとの間の齟齬が生む、必然の結果であったのかもしれない。
長い長い物語の最後に、読者は1つの真実を知る。
だが、事件自体の真相よりも、読者をひきつけるのは、カイアという主人公の生き方それ自体だろう。
「湿地の少女」は鮮烈な印象を残して、「ザリガニの鳴くところ」へと駆け抜けていく。裸足の足跡をかすかに残して。
*crawdadというのはあまり見慣れない単語なのですが、主に米中西部で使われるもののようですね。ザリガニを指す単語としてはcrawfish(主に南部)、crayfish(主に北部)の方がよく使われるように思います。使用の地域的な境界線は割にゆるやかなもののようです。
*実際、ザリガニが鳴くかというと、発音器官にあたるものはなさそうなのですが、ジジジジと鳴くという噂(?)もあり、ザリガニ道を極める(?)か、文字通り「ザリガニの鳴くような」奥地での暮らしに身を投じてみれば、聞こえるものなのかもしれません。また、この言い回しが著者のオリジナルなのか、実際に何らかの伝承があるのかはよくわかりませんでした。
著者の経歴が少々変わっていて、元々は動物学者であり、ノンフィクションの共著が3作ある。一方で、小説家になる夢もあったのだそうで、70歳を過ぎて初めて書いたフィクションが本作である。
作品自体も一風変わっていて、ミステリのようでもあり、自然の美しさを描くようでもあり、何よりも主人公「カイア」の人生を描いているようでもある。
時折はさまれる詩も印象的である。幼少期の著者の文学少女ぶりを彷彿とさせる。
作品の舞台はノース・カロライナ州。湿地にある小さな村である。カイアはホワイトトラッシュ(貧乏白人)と呼ばれる、いわゆる「下層」と見なされる階級に属している。父親は戦争で負傷し、その障害手当だけが一家の収入だった。父は家で暴力をふるった。母親は出ていき、兄弟たちも次々に去っていった。やがて父も姿を消し、カイアは湿地の中、一人きりで生きていかなければならなくなる。
物語は、カイアが一人で暮らし始める1952年以降と、1人の青年が死ぬ「事件」が起きた1969年を交互に描く。
富裕階級に属し、アメフトの高校生スター選手としても活躍したチェイス・アンドルーズが死んだのだ。時代を行き来する物語の中で、その事件とカイアとの間の関わりが徐々に明らかになっていく。
1人ぼっちになった幼いカイアは、規則だからと学校に通うことになったが、到底なじめず、1日しか行けなかった。お金もなく、貝や魚を売って暮らしを立てた。親切な黒人の燃料店店主が何くれとなく面倒を見てくれた。
カイアはあるとき、兄の友達であったという青年、テイトと出会う。テイトは先生役を務めてくれ、文字や知識を教えてくれた。生来聡明であった彼女は、多くのことを学び取った。
2人の間には通い合うものがあったが、同時に越えられない壁もあった。
カイアは苦い別れを経験する。
その隙に割り込んできたのがチェイスだった。
表題の「ザリガニの鳴くところ(where the crawdads sing)」には、作品中で何度か触れられる。要は「生き物たちが自然の姿でいられるところ」を指す。
虹のかなた(somewhere over the rainbow)のような楽園にも思えるけれども、実はこれは単純な理想郷でもないようだ。自然は時に残酷だ。カマキリの雌は交尾中の雄を食い殺すし、食べ物が不足した母キツネは小ギツネを見捨てる。本能にしたがい、生き延びるために手段を選ばない。
身一つで生きるすがすがしさの裏には、明日の運命も知れない危うさがある。
「事件」は、ある意味、自然の中で生き抜こうとするものと文明社会で暮らすもの、あるいは下層階級に属するものと富裕層の特権を享受するものとの間の齟齬が生む、必然の結果であったのかもしれない。
長い長い物語の最後に、読者は1つの真実を知る。
だが、事件自体の真相よりも、読者をひきつけるのは、カイアという主人公の生き方それ自体だろう。
「湿地の少女」は鮮烈な印象を残して、「ザリガニの鳴くところ」へと駆け抜けていく。裸足の足跡をかすかに残して。
*crawdadというのはあまり見慣れない単語なのですが、主に米中西部で使われるもののようですね。ザリガニを指す単語としてはcrawfish(主に南部)、crayfish(主に北部)の方がよく使われるように思います。使用の地域的な境界線は割にゆるやかなもののようです。
*実際、ザリガニが鳴くかというと、発音器官にあたるものはなさそうなのですが、ジジジジと鳴くという噂(?)もあり、ザリガニ道を極める(?)か、文字通り「ザリガニの鳴くような」奥地での暮らしに身を投じてみれば、聞こえるものなのかもしれません。また、この言い回しが著者のオリジナルなのか、実際に何らかの伝承があるのかはよくわかりませんでした。
お気に入り度:





掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
分子生物学・生化学周辺の実務翻訳をしています。
本の大海を漂流中。
日々是好日。どんな本との出会いも素敵だ。
あちらこちらとつまみ食いの読書ですが、点が線に、線が面になっていくといいなと思っています。
「実感」を求めて読書しているように思います。
赤柴♀(もも)は3代目。
この夏、有精卵からヒヨコ4羽を孵化させました。現在、中雛、多分♂x2、♀x2。ニワトリは割と人に懐くものらしいですが、今のところ、懐く気配はありませんw
- この書評の得票合計:
- 48票
| 読んで楽しい: | 5票 | |
|---|---|---|
| 参考になる: | 37票 | |
| 共感した: | 6票 |
あなたの感想は?
投票するには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:早川書房
- ページ数:512
- ISBN:9784152099198
- 発売日:2020年03月05日
- 価格:2090円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。