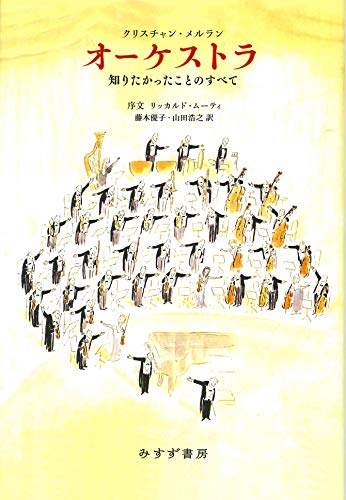ゆうちゃんさん
レビュアー:
▼
オーケストラに関するあれこれの話。一流オーケストラに関して、普段疑問に思うことは全て盛り込まれているのではないか?と思うくらいたっぷりと充実した内容。クラシック音楽ファンにはまさにお勧めの本

朝日新聞の書評で知った本。このサイトの献本にも応募したが見事に落選した。
オーケストラに関するあれこれについて書かれた本である。全体は三部構成で、第一部はオーケストラ奏者に関すること、第二部はオーケストラの構成、第三部は指揮者とオーケストラの関係について論じたものである。本書で取り上げているオーケストラは、世界的なオーケストラ、ベルリン・フィルやウィーン・フィル、日本ならN響や東フィルや大フィルなどであって市民オーケストラとかアマチュア・オーケストラではない。
もう少し詳しく書くと、第一部が楽団員に焦点を当てている。音楽家を志してオーケストラの団員になる(普通、音楽家になるということはソリストを目指すということと解釈される)ことの意味、オーケストラの種類(大編成オーケストラから、室内楽、古楽器などのバロック専門のオーケストラ)、一流オーケストラの団員になる方法、社会階層と楽器の関係、女性の進出(元々は男社会だった)、副業、ミスのあれこれ、などが書かれている。
第二部は、オーケストラ内の序列について、つまり各楽器のパートの首席、次席、その他の団員(本書ではトゥッティストと呼んでいる)の関係、そしてこの部の殆どを占める楽器紹介である。楽器紹介は、ほぼ構成が決まっていて、楽器そのものの紹介、オーケストラの中の役割、過去・近年の有名奏者(オーケストラに所属してソロ活動をしていなくても有名な奏者がいるし、ソリストでもオーケストラのパート出身者が結構いる)の紹介、聴かせどころ(その楽器を使った有名な作品)、主な流派、同属楽器(フルートならピッコロやアルト・フルートなど)、国による楽器の微妙な差異(代表例がドイツのファゴットとフランスのバスン)である。この部の最後で代表的なオーケストラ配置の紹介をしている。
第三部は指揮者とオーケストラの関係、指揮者という職業の歴史、オーケストラから見た理想的な指揮者像、客演指揮者と音楽監督の違い、オーケストラから見た指揮者の実態などが紹介されている。
訳者のあとがきには、
本書は題名の通りオーケストラに焦点を当てたものだが、その半分が社会学的な様相を呈している。これは一言でいえば
そんな、ちょっと捻くれた人の集団に指示をする指揮者とはどんな存在なのか?ハンス・フォン・ビューローに始まり、トスカニーニやフルトヴェングラーを経てカラヤン、バーンスタインに至るまでの指揮者たちはまさに神だったし、当時は指揮者に従うのが当然という雰囲気であった。だが最近では様相が異なるらしい。「指揮者殺し」などという章があるが、パリ管弦楽団などは、合わない指揮者には、いちゃもんをつけて引きずり下ろすので有名らしい(本書で初めて知った)。これは昔観たフェリーニの映画「オーケストラ・リハーサル」の世界である。
面白いと思ったのが、第一部にあるパリ音楽院の学生の家庭環境について書いた下り。弦楽器の学生は金持ちの家庭の出身者が多く、金管楽器は労働者階級の出身者が多いとのこと。木管楽器はその中間だそうだ。理由は読めば納得できるものだが、一番面白かったのが楽器の音域との相関、高音ほど金持ちの家庭の出身者が多いという相関である。これは原因がわからない。
自分はフルートを演奏するので、フルートの描かれ方にも関心がある。
本書の結びは、「錬金術」である。これはCDやDVDによる売り上げではなく、指揮者とオーケストラが対立しながらもひとつの音楽を創り上げていく場面である。540頁もの分厚い人間関係の物語を読んで、最後の文章を目にすると、感動が込み上げてくる。著者は相当コンサートを聞きこんだ音楽ジャーナリスト。クラシック音楽が好きな方に是非お勧めしたい本である。
オーケストラに関するあれこれについて書かれた本である。全体は三部構成で、第一部はオーケストラ奏者に関すること、第二部はオーケストラの構成、第三部は指揮者とオーケストラの関係について論じたものである。本書で取り上げているオーケストラは、世界的なオーケストラ、ベルリン・フィルやウィーン・フィル、日本ならN響や東フィルや大フィルなどであって市民オーケストラとかアマチュア・オーケストラではない。
もう少し詳しく書くと、第一部が楽団員に焦点を当てている。音楽家を志してオーケストラの団員になる(普通、音楽家になるということはソリストを目指すということと解釈される)ことの意味、オーケストラの種類(大編成オーケストラから、室内楽、古楽器などのバロック専門のオーケストラ)、一流オーケストラの団員になる方法、社会階層と楽器の関係、女性の進出(元々は男社会だった)、副業、ミスのあれこれ、などが書かれている。
第二部は、オーケストラ内の序列について、つまり各楽器のパートの首席、次席、その他の団員(本書ではトゥッティストと呼んでいる)の関係、そしてこの部の殆どを占める楽器紹介である。楽器紹介は、ほぼ構成が決まっていて、楽器そのものの紹介、オーケストラの中の役割、過去・近年の有名奏者(オーケストラに所属してソロ活動をしていなくても有名な奏者がいるし、ソリストでもオーケストラのパート出身者が結構いる)の紹介、聴かせどころ(その楽器を使った有名な作品)、主な流派、同属楽器(フルートならピッコロやアルト・フルートなど)、国による楽器の微妙な差異(代表例がドイツのファゴットとフランスのバスン)である。この部の最後で代表的なオーケストラ配置の紹介をしている。
第三部は指揮者とオーケストラの関係、指揮者という職業の歴史、オーケストラから見た理想的な指揮者像、客演指揮者と音楽監督の違い、オーケストラから見た指揮者の実態などが紹介されている。
訳者のあとがきには、
この本は、オーケストラにまつわるいろんな疑問に対し、丁寧に、そして楽しく答えてくれる事典的エッセイであるとあったが、まさにその通りだった。例えば、女性が一流オーケストラに進出したのが20世紀はじめのハープ奏者リリー・ラスキーヌからだったが、女性指揮者について言及がない、と思いつつ読んでいくと最後の方でちゃんと触れていた。全く頭が下がる。
トロンボーン奏者のトーマス・ホルヒが正式採用されなかったのは、ラヴェルのボレロで音をはずしてしまったからだ(彼はその後バイエルン放送交響楽団に行った)(105頁)というエピソードが載っているが、実はこの公演の録音を自分は持っている(1980年頃のカラヤン/ベルリン・フィルの来日公演でFM放送の生中継だった。40年も前だったが、トロンボーンがまさに転んだのには驚いたことをよく記憶している)。こんな書き方は失礼だが、ベルリン・フィルからすればバイエルン放送交響楽団は格落ちである。
本書は題名の通りオーケストラに焦点を当てたものだが、その半分が社会学的な様相を呈している。これは一言でいえば
本来個性的であるべき音楽家が集団に埋没し歯車となって動かなければならないという矛盾する状況から生まれると思う。本書で色々な場面が登場するが、それは結構面白い人間同士のぶつかり合いであり、それらはこの矛盾から生じる。更にその人間の集団であるオーケストラに個性が生じる(代表例はウィーン・フィルの独特の響き、アメリカのフィラデルフィア管弦楽団のフィラデルフィア・サウンドなど)のだから様相はますます複雑になる。オーケストラは時にあたかもひとつの人格のように一体となり、更にお国柄も出る。一流のオーケストラの奏者になるには相当な関門があり、本書を読む限りソリストになるより難しいのではないかと思うくらいである。今年はどうなるか心配だが、日本では年末の第九公演は慣習である。12月になると毎日のように第九を演奏することは、芸術的な活動と言い難い面もある。本書では「幻想交響曲を450回も演奏した奏者であっても、新鮮な気持ちを失わずにいられるものだろうか?」と問いかけている。
そんな、ちょっと捻くれた人の集団に指示をする指揮者とはどんな存在なのか?ハンス・フォン・ビューローに始まり、トスカニーニやフルトヴェングラーを経てカラヤン、バーンスタインに至るまでの指揮者たちはまさに神だったし、当時は指揮者に従うのが当然という雰囲気であった。だが最近では様相が異なるらしい。「指揮者殺し」などという章があるが、パリ管弦楽団などは、合わない指揮者には、いちゃもんをつけて引きずり下ろすので有名らしい(本書で初めて知った)。これは昔観たフェリーニの映画「オーケストラ・リハーサル」の世界である。
面白いと思ったのが、第一部にあるパリ音楽院の学生の家庭環境について書いた下り。弦楽器の学生は金持ちの家庭の出身者が多く、金管楽器は労働者階級の出身者が多いとのこと。木管楽器はその中間だそうだ。理由は読めば納得できるものだが、一番面白かったのが楽器の音域との相関、高音ほど金持ちの家庭の出身者が多いという相関である。これは原因がわからない。
自分はフルートを演奏するので、フルートの描かれ方にも関心がある。
フルートはいつでもディーヴァになれる。弦楽器におけるヴァイオリンのように、こぢんまりしたハーモニーを奏でることも可能だ。音域が高いためにトゥッティから容易に抜け出すことが出来る(オーケストラが全奏してもフルートの音色は容易に聞き分けられるという意味)。木管楽器の中でも国際的なスターを生み出すことのできる唯一の楽器であるこう書かれると演奏していて全く悪い気はしない。
本書の結びは、「錬金術」である。これはCDやDVDによる売り上げではなく、指揮者とオーケストラが対立しながらもひとつの音楽を創り上げていく場面である。540頁もの分厚い人間関係の物語を読んで、最後の文章を目にすると、感動が込み上げてくる。著者は相当コンサートを聞きこんだ音楽ジャーナリスト。クラシック音楽が好きな方に是非お勧めしたい本である。
お気に入り度:









掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
神奈川県に住むサラリーマン(技術者)でしたが24年2月に会社を退職して今は無職です。
読書歴は大学の頃に遡ります。粗筋や感想をメモするようになりましたのはここ10年程ですので、若い頃に読んだ作品を再読した投稿が多いです。元々海外純文学と推理小説、そして海外の歴史小説が自分の好きな分野でした。しかし、最近は、文明論、科学ノンフィクション、音楽などにも興味が広がってきました。投稿するからには評価出来ない作品もきっちりと読もうと心掛けています。どうかよろしくお願い致します。
この書評へのコメント
- keena071511292020-12-21 19:15
>献本にも応募したが見事に落選した
なんか献本の書評って
毎日全ての書評を読んでいる僕でも
知らないレビュアーばかりなんですけど
この人たちは普段何をしているのか…クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 
コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:みすず書房
- ページ数:608
- ISBN:9784622088776
- 発売日:2020年02月19日
- 価格:6600円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。