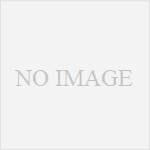hackerさん
レビュアー:
▼
『地下鉄のザジ』でもお分かりのように、パリにストライキはつきものです。本書は、主役の二人がパリに着いたら、大規模ストライキの真最中で苦労する場面から始まるのですが、なんだかなつかしかったです。
私事ですが、駐在するために初めてロンドンに行った時のことお話しします。その時は直行便が取れなくて、パリに行ってからエール・フランスに乗り換える便で行きました。ところが、シャルル・ド・ゴール空港に着いてみると、エール・フランスがストライキをしていたのです。パリのストライキ自体には驚きませんでしたし、乗継便は遅れて出発するということだったので、気長に待っていたのですが、突然運休になってしまったのです。もう夜になっていたので、仕方ないのでパリで一泊しようかと思ったのですが、よく考えてみたら、当時のフランス入国にはビザが必要で、トランジット・エリアから外へは出られません。携帯電話はおろか、クレジットカード利用の公衆電話もない時代でしたし、仏フランの小銭も持っていないので、ロンドンのホテルで待っている同僚に連絡することもできません。さすがに焦りましたが、15年ぶりぐらいに話す、たどたどしいフランス語で、エール・フランス職員に窮状を訴えたことも手助けになったのか、キャンセル待ちで取ったロンドン・シティー空港への便に乗ることができました。ただ、シティー空港は開港直後で、名前を聞いたことがなく、ガイド・ブックにも載っていないので、どこに連れて行かれるのだろうと不安でしたが、結局、真夜中過ぎにロンドンのホテルに着くことができました。
また、前置きが長くなりました。最近これが多くていけませんが、本書の主役の二人が、パリに着いてみると大規模ストライキで、「パリのアパルトマン」にたどり着くのに苦労するという出だしを読みながら、なつかしく、こんなことを思い出してしまった次第です。ストライキ自体は、労働者の権利だと思っているので、なんら腹が立ちませんが、遭遇した時には落ち着いて行動することが肝要のようです。
さて、本書は、クリスマス前の12月20日にパリにやって来た、アメリカ人の著名劇作家ガスパール・クタンスと、元刑事でアメリカで活躍してきたイギリス人女性マデリン・グリーンが、ダブル・ブッキングの結果、宿泊予定の同じアパルトマンで鉢合わせするところから始まります。この時期にパリに単身来るというだけで、二人にはクリスマスを一緒に過ごす家族や恋人がいないことが分かります。ところで、二人がとも気に入ったアパルトマンは、ショーン・ローレンツというニューヨーク生まれの天才画家が住んでいたもので、彼の私物がそのまま残されていました。彼は2年前に、ニューヨークで、創作のインスピレーションであり妻だったペネローペと溺愛していた3歳の息子を誘拐され、妻は重傷を負い、息子は妻の眼前で殺された上、死体もまだ見つかっていないという悲劇に見舞われていました。それから1年後に、画家はニューヨークの路上で心臓発作を起こして、亡くなったのです。描いても、気に入らなかった絵は破棄していた画家は、わずか40点の作品しか遺していませんでしたが、死ぬ前に3枚の絵を描いていたと言われていたものの、その所在は不明のままでした。ショーンを世に送り出した画商であり、アパルトマンの管理人のベルナール・ベネディックは、ショーンの生涯と芸術を、マデリンに説明した後で、こう言います。
「あなたは刑事ですよね。それにもう言ったことだが、わたしは人を見るときの自分の勘を信じてる。何かがわたしに囁くのだが、もし例の絵が存在するのなら、というか、わたしはそう確信しているのですが、それをみつけられる能力のあるのはあなたしかいないということです」
こうして、同じくショーンをめぐる謎に興味を惹かれた、アルコール依存症のガスパールと反目し合いながらも一緒に、マデリンは絵の行方の捜査を始めるのでした。
さて、本書は、前半ではこの絵をめぐる謎を、後半では誘拐事件の真相を追求する構成となっています。全体の印象としては、警察小説のヴァリエーションということろで、それゆえに、ラストはあまりひどいことにならないだろうという予想がつき、その通りに進んでいきます。やや強引ながら、テンポの良い語り口で、全体として一応の水準作になっています。また、個人的に楽しめたのは、パリところどころとでも言うべき、パリの街々の雰囲気描写―必ずしも好意的なものばかりではありませんが―と、これもあちこちで紹介されている著名人の名言です。いくつか紹介します。
「パリに行くならいつだって賛成」(オードリー・ヘプバーン)
「もしあなたがそれを言葉で言い表せるなら、絵に描く必要はまったくない」(エドワード・ホッパー)
「芸術は火のようなもので、燃えるものから生まれる」(ジャン=リュック・ゴダール)
「芸術とは、わたしたちに真実を理解させてくれる嘘である」(パブロ・ピカソ)
というわけで、ミステリー・ファンで「パリを見ずして結構と言うなかれ」と思っている方なら、より一層楽しめる本です。
また、前置きが長くなりました。最近これが多くていけませんが、本書の主役の二人が、パリに着いてみると大規模ストライキで、「パリのアパルトマン」にたどり着くのに苦労するという出だしを読みながら、なつかしく、こんなことを思い出してしまった次第です。ストライキ自体は、労働者の権利だと思っているので、なんら腹が立ちませんが、遭遇した時には落ち着いて行動することが肝要のようです。
さて、本書は、クリスマス前の12月20日にパリにやって来た、アメリカ人の著名劇作家ガスパール・クタンスと、元刑事でアメリカで活躍してきたイギリス人女性マデリン・グリーンが、ダブル・ブッキングの結果、宿泊予定の同じアパルトマンで鉢合わせするところから始まります。この時期にパリに単身来るというだけで、二人にはクリスマスを一緒に過ごす家族や恋人がいないことが分かります。ところで、二人がとも気に入ったアパルトマンは、ショーン・ローレンツというニューヨーク生まれの天才画家が住んでいたもので、彼の私物がそのまま残されていました。彼は2年前に、ニューヨークで、創作のインスピレーションであり妻だったペネローペと溺愛していた3歳の息子を誘拐され、妻は重傷を負い、息子は妻の眼前で殺された上、死体もまだ見つかっていないという悲劇に見舞われていました。それから1年後に、画家はニューヨークの路上で心臓発作を起こして、亡くなったのです。描いても、気に入らなかった絵は破棄していた画家は、わずか40点の作品しか遺していませんでしたが、死ぬ前に3枚の絵を描いていたと言われていたものの、その所在は不明のままでした。ショーンを世に送り出した画商であり、アパルトマンの管理人のベルナール・ベネディックは、ショーンの生涯と芸術を、マデリンに説明した後で、こう言います。
「あなたは刑事ですよね。それにもう言ったことだが、わたしは人を見るときの自分の勘を信じてる。何かがわたしに囁くのだが、もし例の絵が存在するのなら、というか、わたしはそう確信しているのですが、それをみつけられる能力のあるのはあなたしかいないということです」
こうして、同じくショーンをめぐる謎に興味を惹かれた、アルコール依存症のガスパールと反目し合いながらも一緒に、マデリンは絵の行方の捜査を始めるのでした。
さて、本書は、前半ではこの絵をめぐる謎を、後半では誘拐事件の真相を追求する構成となっています。全体の印象としては、警察小説のヴァリエーションということろで、それゆえに、ラストはあまりひどいことにならないだろうという予想がつき、その通りに進んでいきます。やや強引ながら、テンポの良い語り口で、全体として一応の水準作になっています。また、個人的に楽しめたのは、パリところどころとでも言うべき、パリの街々の雰囲気描写―必ずしも好意的なものばかりではありませんが―と、これもあちこちで紹介されている著名人の名言です。いくつか紹介します。
「パリに行くならいつだって賛成」(オードリー・ヘプバーン)
「もしあなたがそれを言葉で言い表せるなら、絵に描く必要はまったくない」(エドワード・ホッパー)
「芸術は火のようなもので、燃えるものから生まれる」(ジャン=リュック・ゴダール)
「芸術とは、わたしたちに真実を理解させてくれる嘘である」(パブロ・ピカソ)
というわけで、ミステリー・ファンで「パリを見ずして結構と言うなかれ」と思っている方なら、より一層楽しめる本です。
お気に入り度:





掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
「本職」は、本というより映画です。
本を読んでいても、映画好きの視点から、内容を見ていることが多いようです。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:集英社
- ページ数:464
- ISBN:9784087607611
- 発売日:2019年11月20日
- 価格:1265円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。