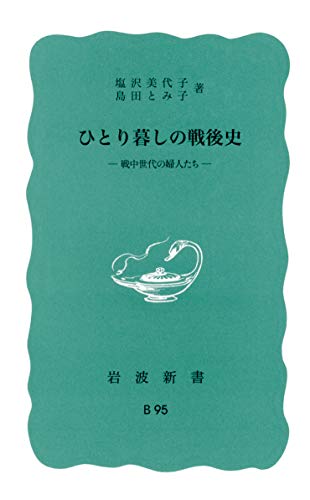ぽんきちさん
レビュアー:
▼
戦争が終わっても人生は続く
初版は1975年、終戦30年後である。
2015年、戦後70周年を機にアンコール復刊された。
女性たち、特に、夫や家族を奪われ、1人で生きることを余儀なくされた女性たちに焦点を当てる。
多くの戦死者を生んだ第二次大戦。徴兵された多くの男たちが死んだ。それはその一方で、男たちの妻、あるいは婚約者が、伴侶を失ったことを意味する。
戦後の厳しい状況下、彼女たちはどのように生き延びたのかを追う。
当時の社会モデルとして、主たる働き手の世帯主男性がいて、その妻は家庭に入るかまたは従属的な職業に就くという形の家庭が一般的とされていた。企業等の給与体制や厚生制度もそれに合わせたものとなっており、ひとり暮らしの女性にとって手厚いものではなかった。
加えて、(本人らのせいではないとしても)ひとり身でいること自体がどこか「不完全」と見られ、本人ら自身にとってもどこか後ろめたく思わせる風潮があった。
本書では、月収や住居形態、職種といったさまざまな統計データと併せて、個々の聞き取り調査も収録されている。
統計部分は、労働局によるものであったり、国勢調査であったり、(当時女性就労者が多かった)繊維業の組合のものであったり、多様なところから採られている。それはつまり、データ同士を単純に比較はできないということでもあるが、異なる目的で実施されたであろう調査の奥にうっすら見えてくるのは、苦境にあったであろう女性たちの影である。
だが、やはり本書の読ませどころは聞き取り調査部分だろう。あるいは姉妹で協力し合い、あるいは組合活動に没頭し、あるいは得意な洋裁を武器に苦闘し、幾人もの女性らが戦後を生き抜いてきた。中には、当初、対象とされていたであろうような戦争未亡人(婚約者を失ったものも含む)の枠からは若干はみ出すような人もいるのだが、いずれにしろ、彼女らが「ひとり暮らし」の戦後を生きてきたことに違いはない。
つまりはこれは、戦後という時代を、(ある種、不平等・不利な条件下で)独身女性が生きるとはどういうことだったのかを切り取ったものなのだ。
但し、著者らも認めているが、取り上げられているのは、どちらかといえば恵まれた人たち、成功した人たちであり、「最下辺」の人にはなかなか手が届かないのは残念なところであろう。これはこうした人たちがそもそもそうした調査に応じられるほど、経済的・精神的な余裕がないことが大きかったと思われる。
これが戦後30年か、と思いつつ、今から45年前のことなのか、とも思う。
取り上げられた女性の多くが、「老後」を心配している。「老人ホームに入れれば」と話している人も多いが、実際、彼女らの老後はどのようなものだったのだろうか。本書が出た当時に50歳前後であったとすれば、現在95歳前後。亡くなった人も多いだろうが、あるいは存命の人もいるものか。彼女らのその後を聞いてみたい気もする。
時代の空気も漂わせる読み応えある1冊。
2015年、戦後70周年を機にアンコール復刊された。
女性たち、特に、夫や家族を奪われ、1人で生きることを余儀なくされた女性たちに焦点を当てる。
多くの戦死者を生んだ第二次大戦。徴兵された多くの男たちが死んだ。それはその一方で、男たちの妻、あるいは婚約者が、伴侶を失ったことを意味する。
戦後の厳しい状況下、彼女たちはどのように生き延びたのかを追う。
当時の社会モデルとして、主たる働き手の世帯主男性がいて、その妻は家庭に入るかまたは従属的な職業に就くという形の家庭が一般的とされていた。企業等の給与体制や厚生制度もそれに合わせたものとなっており、ひとり暮らしの女性にとって手厚いものではなかった。
加えて、(本人らのせいではないとしても)ひとり身でいること自体がどこか「不完全」と見られ、本人ら自身にとってもどこか後ろめたく思わせる風潮があった。
本書では、月収や住居形態、職種といったさまざまな統計データと併せて、個々の聞き取り調査も収録されている。
統計部分は、労働局によるものであったり、国勢調査であったり、(当時女性就労者が多かった)繊維業の組合のものであったり、多様なところから採られている。それはつまり、データ同士を単純に比較はできないということでもあるが、異なる目的で実施されたであろう調査の奥にうっすら見えてくるのは、苦境にあったであろう女性たちの影である。
だが、やはり本書の読ませどころは聞き取り調査部分だろう。あるいは姉妹で協力し合い、あるいは組合活動に没頭し、あるいは得意な洋裁を武器に苦闘し、幾人もの女性らが戦後を生き抜いてきた。中には、当初、対象とされていたであろうような戦争未亡人(婚約者を失ったものも含む)の枠からは若干はみ出すような人もいるのだが、いずれにしろ、彼女らが「ひとり暮らし」の戦後を生きてきたことに違いはない。
つまりはこれは、戦後という時代を、(ある種、不平等・不利な条件下で)独身女性が生きるとはどういうことだったのかを切り取ったものなのだ。
但し、著者らも認めているが、取り上げられているのは、どちらかといえば恵まれた人たち、成功した人たちであり、「最下辺」の人にはなかなか手が届かないのは残念なところであろう。これはこうした人たちがそもそもそうした調査に応じられるほど、経済的・精神的な余裕がないことが大きかったと思われる。
これが戦後30年か、と思いつつ、今から45年前のことなのか、とも思う。
取り上げられた女性の多くが、「老後」を心配している。「老人ホームに入れれば」と話している人も多いが、実際、彼女らの老後はどのようなものだったのだろうか。本書が出た当時に50歳前後であったとすれば、現在95歳前後。亡くなった人も多いだろうが、あるいは存命の人もいるものか。彼女らのその後を聞いてみたい気もする。
時代の空気も漂わせる読み応えある1冊。
お気に入り度:







掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
分子生物学・生化学周辺の実務翻訳をしています。
本の大海を漂流中。
日々是好日。どんな本との出会いも素敵だ。
あちらこちらとつまみ食いの読書ですが、点が線に、線が面になっていくといいなと思っています。
「実感」を求めて読書しているように思います。
赤柴♀(もも)は3代目。
この夏、有精卵からヒヨコ4羽を孵化させました。そろそろ大雛かな。♂x2、♀x2。ニワトリは割と人に懐くものらしいですが、今のところ、懐く気配はありませんw
- この書評の得票合計:
- 35票
| 素晴らしい洞察: | 3票 | |
|---|---|---|
| 参考になる: | 30票 | |
| 共感した: | 2票 |
あなたの感想は?
投票するには、ログインしてください。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:岩波書店
- ページ数:219
- ISBN:9784004110958
- 発売日:1975年01月01日
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。
『ひとり暮しの戦後史―戦中世代の婦人たち』のカテゴリ
- ・歴史 > 日本史
- ・政治・経済・社会・ビジネス > 社会