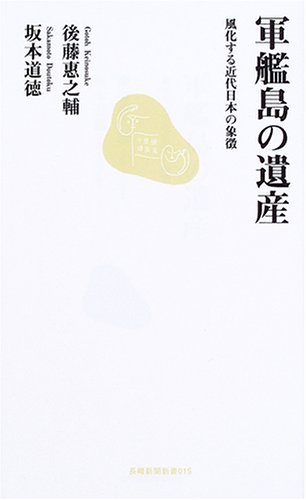ぽんきちさん
レビュアー:
▼
かつて栄えた炭鉱の記憶
軍艦島は正式名称を端島(はしま:「羽島」表記の場合もある)という。
長崎港の南西の海上に位置する無人島だが、かつては5000人を超える人々で賑わっていた。
この島で石炭が産出されたからである。
元々は小さな瀬だったが、何度かに分けて埋め立てられ、面積は約6.3ヘクタールとなった。最盛期の人口密度は当時の東京の9倍であり、世界一であった。
「軍艦島」の名は、洋上に浮かぶその姿がまるで軍艦のようであったことによる。
平たい島に、当時としては最先端の鉄筋コンクリートのビルが林立し、遠くから見れば、なるほど軍艦に見えたことだろう。
端島は、今期、民放のドラマの舞台となっているが、これまでにも何度か映像作品や文芸作品に取り上げられている。
エネルギー政策の転換を受け、石炭の需要が減ったことから、1974年に炭鉱は閉山となった。孤島が無人となり、廃墟化した。
上陸は長らく禁止されていたが、世界文化遺産への登録を目指す動きが出てくる中、2009年からは観光客などが上陸することも可能となった。但し、個人での上陸はできず、クルーズ(現在5社が就航)に参加する必要がある。また、見学できる範囲は限られている。
本書は端島に関する入門書といってよい。
日本の石炭鉱業の歴史、端島炭鉱の遠隔と島民の生活、端島の学術的価値などに触れる。
著者はどちらも父親が元炭鉱マンであり、端島で生活した経験を持つ。後藤は工学系の研究者で、「軍艦島学」を提唱している。坂本はNPO法人「軍艦島を世界遺産にする会」の理事長で、軍艦島上陸ツアーのガイドなどもされていたようである。
本書が刊行されたのが2005年、世界文化遺産として登録されたのが2015年である。
本書中には登録を望む旨の記述もあるが、その思いは遂げられたというところだろう。
石炭がエネルギーの主力とされていた時代、端島は炭鉱労働者とその家族であふれた。
限られた土地に多くの人が住むには、建物を高層化するしかない。端島は日本初の鉄筋コンクリート高層アパートが作られた地である。東京でもレンガ造りの建物が最先端ともてはやされていた時代だ。
電化も進んでおり、近くの高島の発電所から海底ケーブルを通じて電気が送られてきていた。テレビや冷蔵庫など、本土の一般の家庭にはまださほど普及していないものを持つ家もあり、生活水準は比較的高かったという。
ただ、人口が密集しているため、家は狭い。5人~8人の家族が六畳と四畳半と台所程度の家に住む。大抵の家にはベランダがついているため、これも含めて、小部屋を仕切って子供部屋とするなど、各家庭でやりくりしながら暮らしていたそうだ。
水の確保も大変である。当初は海水や蒸留水を使用していたが、後に船で清水を運搬するようになる。だがこれも海が荒れると途絶えてしまう。そこで昭和30年代になって海底水道管の工事が行われ、事業用水と生活用水がようやく安定して確保できるようになった。この工事もまた、最先端であった。それだけ石炭産業が重要であったことの現れでもあろう。
とはいえ、水が貴重なことには変わりはなく、炭鉱夫の風呂もまず海水の風呂で汚れを落とし、上がり湯のみ清水であったし、プールも海水を使用していた。
炭鉱の歴史という意味では他にも参考になる本は多々あるのだろうが、本書で特筆されるのは、実際に住んでいた人の視点があることだろう。それも炭鉱で働いていたのではない、子供の視点であり、これはなかなか貴重なように思われる。
端島は廃墟ブームで注目を浴びた地でもあるが、住んでいた者たちにとっては、そこは紛れもなく住んでいた記憶のある土地である。
一時は繁栄を謳歌した島は、時代が移るにつれ、衰退の途を辿ることになる。エネルギー源が石炭から石油へと移り変わり、また石炭採掘量が減少してきたためだ。他の産業を持たない小さな島では、炭鉱閉山後、暮らしは成り立たなかった。炭鉱夫やその家族は散り散りに去って行った。手入れされない建物は朽ちていき、護岸は台風などで浸食・損傷を受けた。まさに廃墟と化していくわけだが、その陰には、近代化を支えた一大産業があったのだ。
近年は世界遺産認定もあってか、端島を訪れるツアーはなかなかの人気のようである。島はまた別のフェーズに入ったというところだろうか。
海に浮かぶ船のような島。興味をそそる光景ではある。
長崎港の南西の海上に位置する無人島だが、かつては5000人を超える人々で賑わっていた。
この島で石炭が産出されたからである。
元々は小さな瀬だったが、何度かに分けて埋め立てられ、面積は約6.3ヘクタールとなった。最盛期の人口密度は当時の東京の9倍であり、世界一であった。
「軍艦島」の名は、洋上に浮かぶその姿がまるで軍艦のようであったことによる。
平たい島に、当時としては最先端の鉄筋コンクリートのビルが林立し、遠くから見れば、なるほど軍艦に見えたことだろう。
端島は、今期、民放のドラマの舞台となっているが、これまでにも何度か映像作品や文芸作品に取り上げられている。
エネルギー政策の転換を受け、石炭の需要が減ったことから、1974年に炭鉱は閉山となった。孤島が無人となり、廃墟化した。
上陸は長らく禁止されていたが、世界文化遺産への登録を目指す動きが出てくる中、2009年からは観光客などが上陸することも可能となった。但し、個人での上陸はできず、クルーズ(現在5社が就航)に参加する必要がある。また、見学できる範囲は限られている。
本書は端島に関する入門書といってよい。
日本の石炭鉱業の歴史、端島炭鉱の遠隔と島民の生活、端島の学術的価値などに触れる。
著者はどちらも父親が元炭鉱マンであり、端島で生活した経験を持つ。後藤は工学系の研究者で、「軍艦島学」を提唱している。坂本はNPO法人「軍艦島を世界遺産にする会」の理事長で、軍艦島上陸ツアーのガイドなどもされていたようである。
本書が刊行されたのが2005年、世界文化遺産として登録されたのが2015年である。
本書中には登録を望む旨の記述もあるが、その思いは遂げられたというところだろう。
石炭がエネルギーの主力とされていた時代、端島は炭鉱労働者とその家族であふれた。
限られた土地に多くの人が住むには、建物を高層化するしかない。端島は日本初の鉄筋コンクリート高層アパートが作られた地である。東京でもレンガ造りの建物が最先端ともてはやされていた時代だ。
電化も進んでおり、近くの高島の発電所から海底ケーブルを通じて電気が送られてきていた。テレビや冷蔵庫など、本土の一般の家庭にはまださほど普及していないものを持つ家もあり、生活水準は比較的高かったという。
ただ、人口が密集しているため、家は狭い。5人~8人の家族が六畳と四畳半と台所程度の家に住む。大抵の家にはベランダがついているため、これも含めて、小部屋を仕切って子供部屋とするなど、各家庭でやりくりしながら暮らしていたそうだ。
水の確保も大変である。当初は海水や蒸留水を使用していたが、後に船で清水を運搬するようになる。だがこれも海が荒れると途絶えてしまう。そこで昭和30年代になって海底水道管の工事が行われ、事業用水と生活用水がようやく安定して確保できるようになった。この工事もまた、最先端であった。それだけ石炭産業が重要であったことの現れでもあろう。
とはいえ、水が貴重なことには変わりはなく、炭鉱夫の風呂もまず海水の風呂で汚れを落とし、上がり湯のみ清水であったし、プールも海水を使用していた。
炭鉱の歴史という意味では他にも参考になる本は多々あるのだろうが、本書で特筆されるのは、実際に住んでいた人の視点があることだろう。それも炭鉱で働いていたのではない、子供の視点であり、これはなかなか貴重なように思われる。
端島は廃墟ブームで注目を浴びた地でもあるが、住んでいた者たちにとっては、そこは紛れもなく住んでいた記憶のある土地である。
一時は繁栄を謳歌した島は、時代が移るにつれ、衰退の途を辿ることになる。エネルギー源が石炭から石油へと移り変わり、また石炭採掘量が減少してきたためだ。他の産業を持たない小さな島では、炭鉱閉山後、暮らしは成り立たなかった。炭鉱夫やその家族は散り散りに去って行った。手入れされない建物は朽ちていき、護岸は台風などで浸食・損傷を受けた。まさに廃墟と化していくわけだが、その陰には、近代化を支えた一大産業があったのだ。
近年は世界遺産認定もあってか、端島を訪れるツアーはなかなかの人気のようである。島はまた別のフェーズに入ったというところだろうか。
海に浮かぶ船のような島。興味をそそる光景ではある。
お気に入り度:







掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
分子生物学・生化学周辺の実務翻訳をしています。
本の大海を漂流中。
日々是好日。どんな本との出会いも素敵だ。
あちらこちらとつまみ食いの読書ですが、点が線に、線が面になっていくといいなと思っています。
「実感」を求めて読書しているように思います。
赤柴♀(もも)は3代目。
この夏、有精卵からヒヨコ4羽を孵化させました。そろそろ大雛かな。♂x2、♀x2。ニワトリは割と人に懐くものらしいですが、今のところ、懐く気配はありませんw
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:長崎新聞社
- ページ数:222
- ISBN:9784931493537
- 発売日:2005年04月01日
- 価格:1000円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。