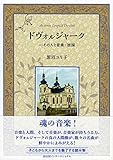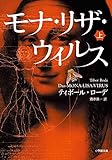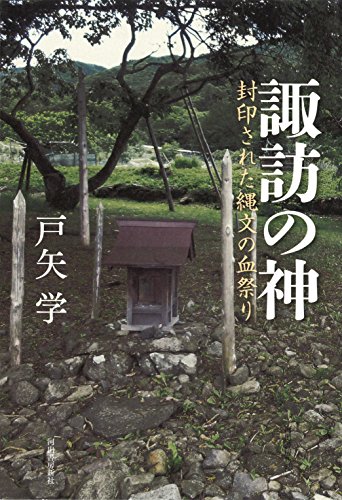oldmanさん
レビュアー:
▼
諏訪大社に隠された天津神と国津神の争い。古代史だけでなく民俗学・宗教学も含んだ面白い説だ。
諏訪大社と言えば、御柱祭 先年も盛況で終わったが、著者同様 以前から僕もこの祭りに違和感が有った。
御柱は、7年毎に立て替えられる。つまり十二支の寅と申の年回りに祭りが行われるのだ。
山から切り出した16本の樅の巨木を、地を引き摺り、急坂を落とし、川を渡って諏訪の上社二宮下社二宮の四隅に立てるのだ。
著者も本書内で言及しているが、普通これを諏訪大社の主張通り神木とするならば、里曳きの時に人が上に乗りコロも無しに引き摺ったり、木落しと称してこれまた人が跨がったままの木を急坂から滑らせたりするのはおかしいのではないかと思っていた。これでは神木というよりも生け贄じゃないかと……
著者は、先ず諏訪大社の祭神である建御名方神(タケミナカタノカミ)に注目する。
建御名方命と言えば、「古事記」に記されている「出雲の国譲り」では、天津神である建御雷神(タケミカヅチノカミ)に挑戦したあげく、手も無く捻られ出雲より諏訪に逃亡、この地より出ぬ事を条件に、命乞いをしたという神話が有名だが、実はこのエピソード、「古事記」のみに記されており、「日本書紀」にも「出雲風土記」にも載っていない。
しかも後世の多くの武家は、このヘナチョコ野郎の建御名方神を守護神として信仰しているのだ。
著者は、これを「古事記」への後世の追加記載ではないかと推測し、建御名方神を当地(諏訪)に封じ様とする力が働いたのではないか?と主張する。
更に、本来の諏訪大社の信仰は原始的な自然信仰であり、これを後の中央政権が天津神信仰へとねじ曲げていく意向が有ったのではないかと推測する。
そして、諏訪大社の本来の拝殿の向きには、守屋山が本来の信仰対象で、守屋山は神奈備(カンナビ)であると主張する。
そこから、弥生の軍神であるモレヤ神信仰 更には縄文の精霊神ミシャグジ神信仰へと想いを延ばし、
その陰に「丁末の乱」で殺された物部守屋(モノノベノモリヤ)の存在と、怨霊信仰。
そして縄文の神である、ミシャグジをサクチ(裂口)と解釈し……ウーン しかしこれをフォッサマグナに比定するのは、さすがに穿ち過ぎではないかと思われる。
確かに縄文時代には九州南部の姶良カルデラに見られる破局噴火も起きているので、フォッサ・マグナにおける大噴火も一概に否定できないが、著者はその証拠を提示はしていない。
しかし、著者が主張する原始自然信仰においての要素が、
神奈備・神籬(ヒモロギ)・磐座(イワクラ)・靈(ヒ)
である事には異論は無い。
余談ではあるが、かって伝奇小説で一世を風靡した半村良は産霊山秘録で、主役となる一族を「ヒ」と名付け、その能力の利用する場所を神籬としている。このメチャクチャ面白い小説を思い出してしまった。
本題に戻ろう。 御柱の意味が神木等ではなく、巨大な封じの楔であることには納得できるものがある。
不勉強にも諏訪大社には御柱祭以外にも、御頭祭という生け贄を求めるような祭りが有ることを、今回本書で初めて知った。
確かに、贄を求めるこの考え方は、狩猟文化であった縄文を連想させるものだし、それによって祟り神を鎮める事は納得できるぶぶんではある。
ただ、著者の記す意見には些か我田引水的な部分が散見され、その全てに賛同できるものではない。
しかし、長野地方の氏神信仰は諏訪以外にも天津神対国津神、ひいては弥生文化対縄文文化の土地を巡る争いが多く見られる気がする。
長野には德武(トクタケ)<德の字に注意 この姓では旧字体の德(心の上に横棒が入る)を使うが、この 德武氏は高皇産霊尊(タカギムスビノカミ)直系の子孫を名乗っている。>という姓が存在するが、これひとつとっても、長野を中心とする一帯には、とてつもなく古い神が存在している気がする。
例えば諏訪以外にも長野市の北にある、戸隠神社も掘り起こせば天津神に封じられた古い神々が見つかるのでは無いかと、かねてから思っているので、これに関する本も読んでみたいものだ。
追記
この書評を書いている時点で、「大山(だいせん)古墳(仁徳天皇陵)」を含む百舌鳥(もず)・古市古墳群が7月にも世界文化遺産に登録される見込みとなった。
それ自体は大変結構な事だが、ちょっと気になったのはテレビのニュースなどで、盛んに大山古墳を「仁徳天皇陵」と呼んでいた点だ。
僕が子供の頃は、呼称も表記も「仁徳天皇陵」だったが、その後考古学的に正しくない(仁徳天皇陵はあくまでも宮内庁による比定)ということで、大山古墳と呼称してた筈だ。
今回の、仁徳天皇陵の呼称は日本側がそう登録申請したらしいが、この様なやり方で半ば強引に陵墓の呼称を決定するのは感心できない。
今回の登録で今は宮内庁による拒絶で不可能となっている、陵墓の考古学的調査が行われれば、この国の古代史研究は飛躍的に進むと思う。
今後そうなることを期待したい。
御柱は、7年毎に立て替えられる。つまり十二支の寅と申の年回りに祭りが行われるのだ。
山から切り出した16本の樅の巨木を、地を引き摺り、急坂を落とし、川を渡って諏訪の上社二宮下社二宮の四隅に立てるのだ。
著者も本書内で言及しているが、普通これを諏訪大社の主張通り神木とするならば、里曳きの時に人が上に乗りコロも無しに引き摺ったり、木落しと称してこれまた人が跨がったままの木を急坂から滑らせたりするのはおかしいのではないかと思っていた。これでは神木というよりも生け贄じゃないかと……
著者は、先ず諏訪大社の祭神である建御名方神(タケミナカタノカミ)に注目する。
建御名方命と言えば、「古事記」に記されている「出雲の国譲り」では、天津神である建御雷神(タケミカヅチノカミ)に挑戦したあげく、手も無く捻られ出雲より諏訪に逃亡、この地より出ぬ事を条件に、命乞いをしたという神話が有名だが、実はこのエピソード、「古事記」のみに記されており、「日本書紀」にも「出雲風土記」にも載っていない。
しかも後世の多くの武家は、このヘナチョコ野郎の建御名方神を守護神として信仰しているのだ。
著者は、これを「古事記」への後世の追加記載ではないかと推測し、建御名方神を当地(諏訪)に封じ様とする力が働いたのではないか?と主張する。
更に、本来の諏訪大社の信仰は原始的な自然信仰であり、これを後の中央政権が天津神信仰へとねじ曲げていく意向が有ったのではないかと推測する。
そして、諏訪大社の本来の拝殿の向きには、守屋山が本来の信仰対象で、守屋山は神奈備(カンナビ)であると主張する。
そこから、弥生の軍神であるモレヤ神信仰 更には縄文の精霊神ミシャグジ神信仰へと想いを延ばし、
その陰に「丁末の乱」で殺された物部守屋(モノノベノモリヤ)の存在と、怨霊信仰。
そして縄文の神である、ミシャグジをサクチ(裂口)と解釈し……ウーン しかしこれをフォッサマグナに比定するのは、さすがに穿ち過ぎではないかと思われる。
確かに縄文時代には九州南部の姶良カルデラに見られる破局噴火も起きているので、フォッサ・マグナにおける大噴火も一概に否定できないが、著者はその証拠を提示はしていない。
しかし、著者が主張する原始自然信仰においての要素が、
神奈備・神籬(ヒモロギ)・磐座(イワクラ)・靈(ヒ)
である事には異論は無い。
余談ではあるが、かって伝奇小説で一世を風靡した半村良は産霊山秘録で、主役となる一族を「ヒ」と名付け、その能力の利用する場所を神籬としている。このメチャクチャ面白い小説を思い出してしまった。
本題に戻ろう。 御柱の意味が神木等ではなく、巨大な封じの楔であることには納得できるものがある。
不勉強にも諏訪大社には御柱祭以外にも、御頭祭という生け贄を求めるような祭りが有ることを、今回本書で初めて知った。
確かに、贄を求めるこの考え方は、狩猟文化であった縄文を連想させるものだし、それによって祟り神を鎮める事は納得できるぶぶんではある。
ただ、著者の記す意見には些か我田引水的な部分が散見され、その全てに賛同できるものではない。
しかし、長野地方の氏神信仰は諏訪以外にも天津神対国津神、ひいては弥生文化対縄文文化の土地を巡る争いが多く見られる気がする。
長野には德武(トクタケ)<德の字に注意 この姓では旧字体の德(心の上に横棒が入る)を使うが、この 德武氏は高皇産霊尊(タカギムスビノカミ)直系の子孫を名乗っている。>という姓が存在するが、これひとつとっても、長野を中心とする一帯には、とてつもなく古い神が存在している気がする。
例えば諏訪以外にも長野市の北にある、戸隠神社も掘り起こせば天津神に封じられた古い神々が見つかるのでは無いかと、かねてから思っているので、これに関する本も読んでみたいものだ。
追記
この書評を書いている時点で、「大山(だいせん)古墳(仁徳天皇陵)」を含む百舌鳥(もず)・古市古墳群が7月にも世界文化遺産に登録される見込みとなった。
それ自体は大変結構な事だが、ちょっと気になったのはテレビのニュースなどで、盛んに大山古墳を「仁徳天皇陵」と呼んでいた点だ。
僕が子供の頃は、呼称も表記も「仁徳天皇陵」だったが、その後考古学的に正しくない(仁徳天皇陵はあくまでも宮内庁による比定)ということで、大山古墳と呼称してた筈だ。
今回の、仁徳天皇陵の呼称は日本側がそう登録申請したらしいが、この様なやり方で半ば強引に陵墓の呼称を決定するのは感心できない。
今回の登録で今は宮内庁による拒絶で不可能となっている、陵墓の考古学的調査が行われれば、この国の古代史研究は飛躍的に進むと思う。
今後そうなることを期待したい。
お気に入り度:





掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
最近歳のせいか読書スピードが落ちているにもかかわらず、本好きが昂じて積読本が溜まっております。
そして、歩けるうちにとアチコチヘ顔を出すようになりました。
現在はビブリオバトルを普及することに力をいれております。
その為読書メーターにはコミュニティーも作りました。
( ゚∀゚)つ https://bookmeter.com/communities/337701
いささかひねくれた年寄りですがよろしくお願いいたします。
2016年12月 読書メーターのプロフィル画像とハンドルネームをちょっと変えてみました(*^^*)
読メハンドルネーム oldman獺祭魚翁
この書評へのコメント
- oldman2019-05-21 23:20
あかつきさん
まさにそうだったんですが、今回文化庁は卑怯にも「仁徳(にんとく)天皇陵古墳」(大山(だいせん)古墳、堺市)を含む大阪府南部の「百舌鳥(もず)・古市(ふるいち)古墳群」という形で申請したらしいです。
これを契機に是非陵の本格的調査が進むことを希望しますが、四半世紀ほど前 砂防の専門家だった亡父が、陵の周囲の水による侵食の助言のため訪れたところ、管理の宮内庁職員が入陵時に斎戒沐浴の上白装束に身を包んでいるのを見て、僕に「あれじゃぁ調査は当分無理だな」と言っていたのを思い出します。
墓なんて暴いてナンボなのに(*_*)クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 
コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:河出書房新社
- ページ数:210
- ISBN:9784309226156
- 発売日:2014年12月08日
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。
『諏訪の神: 封印された縄文の血祭り』のカテゴリ
登録されているカテゴリはありません。