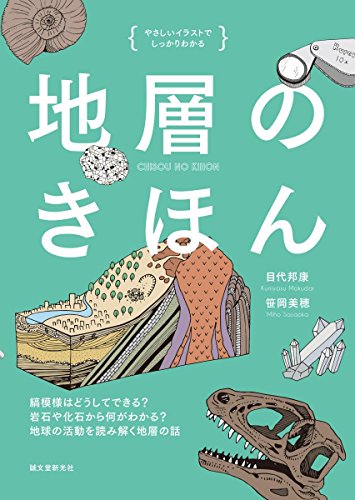休蔵さん
レビュアー:
▼
地球の歴史を知るために、地球そのものを観察することが必要。地層はそのもっとも重要な教材。本書はそんな教材を理解するための入門書。スッキリしたイラストが理解を助けてくれる。
当たり前のように地球に暮らす私たち。
地球は46憶年の歴史があるとされ、それを信じるしかない術がない。
そんな「ボーッと生きている」私にも、自分が暮らす地球の歴史を知る方法はある。
最も手っ取り早い方法は読書だ。
しかし、本によってその難易度はさまざま。
本書はスタートを切るうえで、最適な1冊と感じた。
本書はその名も『地層のきほん』。
地質学の基本とも言える地層のなりたちやその見方などをスッキリとしたイラストとともに教えてくれる。
さらに、地層の調べ方を具体的に教えてくれる。
まず通常の地図と地形図、地質図を用意する。
そして、さまざまなガイドブックをもとに調査地点を絞り込み、ルートマップを作成して、いざ調査へ。
調査に赴くさいにはフィールドワーク用の作業着に身を包み、フィールドノートとルーペを手にする。
土層の色を調べるためには土色帳が必需となる。
調査が本格化すると穴を開けたり、震源車を用いたら打音検査のような方法、場合によっては人工衛星も利用するそうだが、これらの方法は専門家におまかせ。
私たちは身近な場所で、やり良い方法を採用すればそれで大丈夫だ。
もちろん、地層の見方だけに終始するわけではなく、岩石のなりたちや各岩石の特徴、化石についても触れている。
ところで、月はクレーターだらけだ。
しかし、地球にあるクレーターの大部分はどこにあるやら?
この違いの背景には、空気と水の存在があるそうだ。
空気や水は暖められると軽くなり、冷やされると重くなる。
大気中の温度の違いは空気の循環を生む。
空気の循環は泥や砂、石なども一緒に動かす。
その移動が積み重なることで、やがて地形の変化に結びつき、結果的にかつてのクレーターは隠れてしまうというのだ。
日本列島は複雑な地形に位置する。
複数のプレートが沈み込み、その影響で100を超える活火山がある。
地震も多く、そのことがさらなる地形の変化をもたらしている。
毎年、台風が上陸し、さらに梅雨に秋雨と相当量の雨量が洪水や土砂災害を繰り返す。
日本列島は地形的に落ち着きのない場所なのだ。
そこに暮らすならば、地質について学ぶことは必須の仕事と言えよう。
本書は文章も平易で読みやすいうえに、イラストだけでも十分理解できる仕組みとなっている。
自分が暮らすところを知るための第一歩目として最適な1冊だ。
地球は46憶年の歴史があるとされ、それを信じるしかない術がない。
そんな「ボーッと生きている」私にも、自分が暮らす地球の歴史を知る方法はある。
最も手っ取り早い方法は読書だ。
しかし、本によってその難易度はさまざま。
本書はスタートを切るうえで、最適な1冊と感じた。
本書はその名も『地層のきほん』。
地質学の基本とも言える地層のなりたちやその見方などをスッキリとしたイラストとともに教えてくれる。
さらに、地層の調べ方を具体的に教えてくれる。
まず通常の地図と地形図、地質図を用意する。
そして、さまざまなガイドブックをもとに調査地点を絞り込み、ルートマップを作成して、いざ調査へ。
調査に赴くさいにはフィールドワーク用の作業着に身を包み、フィールドノートとルーペを手にする。
土層の色を調べるためには土色帳が必需となる。
調査が本格化すると穴を開けたり、震源車を用いたら打音検査のような方法、場合によっては人工衛星も利用するそうだが、これらの方法は専門家におまかせ。
私たちは身近な場所で、やり良い方法を採用すればそれで大丈夫だ。
もちろん、地層の見方だけに終始するわけではなく、岩石のなりたちや各岩石の特徴、化石についても触れている。
ところで、月はクレーターだらけだ。
しかし、地球にあるクレーターの大部分はどこにあるやら?
この違いの背景には、空気と水の存在があるそうだ。
空気や水は暖められると軽くなり、冷やされると重くなる。
大気中の温度の違いは空気の循環を生む。
空気の循環は泥や砂、石なども一緒に動かす。
その移動が積み重なることで、やがて地形の変化に結びつき、結果的にかつてのクレーターは隠れてしまうというのだ。
日本列島は複雑な地形に位置する。
複数のプレートが沈み込み、その影響で100を超える活火山がある。
地震も多く、そのことがさらなる地形の変化をもたらしている。
毎年、台風が上陸し、さらに梅雨に秋雨と相当量の雨量が洪水や土砂災害を繰り返す。
日本列島は地形的に落ち着きのない場所なのだ。
そこに暮らすならば、地質について学ぶことは必須の仕事と言えよう。
本書は文章も平易で読みやすいうえに、イラストだけでも十分理解できる仕組みとなっている。
自分が暮らすところを知るための第一歩目として最適な1冊だ。
お気に入り度:







掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
ここに参加するようになって、読書の幅が広がったように思います。
それでも、まだ偏り気味。
いろんな人の書評を参考に、もっと幅広い読書を楽しみたい!
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:誠文堂新光社
- ページ数:144
- ISBN:9784416618158
- 発売日:2018年05月02日
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。