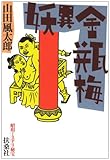三太郎さん
レビュアー:
▼
団塊世代のフェミニスト、上野千鶴子が団塊世代の女性のために書いたベストセラー。
この本は2007年に出版され2011年に文庫化されてベストセラーになったとか。出版当時の著者はまだ東京大学の教授だった。現役の東大教授の書いたベストセラーだったわけだ。この後の上野氏は「おひとりさま」の老後についての発言でマスコミでもよく目にするようになった気がする。
ところで、2007年当時の僕はまだ50歳だったが、もう直ぐ中古マンションのローンも払い終え、60歳で退職するにはこれから老後資金をいくら貯金したらよいのか計算していた。厚生年金がフルに貰えるのは65歳からなのは分かっていた。でも当時はまだ年金定期便もなく、正確にはいくら年金が貰えそうなのか分からなかった。
(その後年金定期便が届くようになったのは、かつての民主党が”消えた年金”問題を追及してくれたおかげです。遅まきながら、民主党ありがとう!)
さて、この本は独身女性の老後についてがテーマなので(上野氏は彼女の仮想敵である男性については心配してくれていない)、もし僕が先にいなくなり奥さんが一人になった場合を想定して読んでみよう。
ところでこの本の想定していた読者層は、結婚後仕事を止めて子育てをして、子供が独立し、伴侶と死別したか離婚した妻ということらしい。この状態をシングルアゲインと呼んでいる(別に英語にしなくてもと思うけれど)。経済的には夫の遺族年金などで経済的にはあまり困らない層だ。年代的には団塊世代の女性を想定しているが、下の年代にも参考になる点があるだろう。
シングルアゲインの鉄則は自分”だけ”の家をもつことだ。子供一家との同居などはいらない。年をとったら施設に送られてしまう。つまり自分だけで暮らす覚悟が必要らしい。
(我が家の場合は子供がいないから、悩まなくても上記の条件を満たす。)
一人で暮らすなら〇LDKのマンションよりワンルームがよいと著者は言うけれど、うちの奥さんには無理かな。若い頃から本とマンガが大好きで読んだものは全て取ってある。読んだらブックオフに売りに行く僕とは大違いだ。
介護サービスは都会の方が選択肢が多いと言うが、彼女はずっと都会暮らしだから自然にそうなるだろう。
パソコンは高齢者の強い味方だというが、彼女はネットを見るのが趣味のようだし、キーボードの入力は会社員時代に覚えた親指シフトで、ローマ字入力しかできない僕より巧みだ。今後は音声入力も普通になるだろうしPCは老人の味方だ(画面の小さいスマホは若者向けだ。目が霞んできたら読めなくなるだろう)。ただし彼女はハードウエアやPCの仕組みに弱いから、これからもう少し覚えてもらおう。
年をとったら気の合う友達が大事というのは、彼女の場合は心配なさそうだ。高校時代の同級生や会社員時代の友人もまだ続いているし、ネットで知り合ってまだ一度もあったことのない友人がいて、年に何度か長電話をしている。
この本は途中から調子が変わってくる。PPK(ピンピンコロリ)運動をファシズムだ!と批判し、また尊厳死も批判している。確かにこれらは死んでいく本人より周りの人間の利益を考慮した疑いがある。百歳まで生きてある日ぱったり死んでしまう人も確かにいるでしょうが、それが人間の生き方の理想だというのは怪しい。元気なうちは延命処置を拒否していても死ぬ間際にも同じかどうかは分からない。
まあ誰でも、まだ死んだことはないわけで、死については本当は何も言えないのではないでしょうか(例えば、僕は実は”脳死”という概念を信じることができません)。
多くの人は倒れてから亡くなるまで要介護の状態になるのだから、自分が介護を受けることを考えておくことが必要なようだ。上野氏の年代の女性は自分が介護されることに心理的な抵抗が強いというが、生きるためには介護される際のノウハウを知っておく必要があるのかな。
介護を受ける十か条というのが載せられている。第三条は「不必要ながまんや遠慮はしない」というのだが、うちの奥さんには(誰にでも?)ハードルが高そうだ。でもがまんの結果病気が悪化したらなんにもならない。
最後は死んだ後の遺産を誰に残すか、墓をどうするかなどだが(子供がいないから墓は不必要という点では僕ら夫婦の意見は一致しているが・・・)それはおいおい考えてもらいましょう。
ところで、2007年当時の僕はまだ50歳だったが、もう直ぐ中古マンションのローンも払い終え、60歳で退職するにはこれから老後資金をいくら貯金したらよいのか計算していた。厚生年金がフルに貰えるのは65歳からなのは分かっていた。でも当時はまだ年金定期便もなく、正確にはいくら年金が貰えそうなのか分からなかった。
(その後年金定期便が届くようになったのは、かつての民主党が”消えた年金”問題を追及してくれたおかげです。遅まきながら、民主党ありがとう!)
さて、この本は独身女性の老後についてがテーマなので(上野氏は彼女の仮想敵である男性については心配してくれていない)、もし僕が先にいなくなり奥さんが一人になった場合を想定して読んでみよう。
ところでこの本の想定していた読者層は、結婚後仕事を止めて子育てをして、子供が独立し、伴侶と死別したか離婚した妻ということらしい。この状態をシングルアゲインと呼んでいる(別に英語にしなくてもと思うけれど)。経済的には夫の遺族年金などで経済的にはあまり困らない層だ。年代的には団塊世代の女性を想定しているが、下の年代にも参考になる点があるだろう。
シングルアゲインの鉄則は自分”だけ”の家をもつことだ。子供一家との同居などはいらない。年をとったら施設に送られてしまう。つまり自分だけで暮らす覚悟が必要らしい。
(我が家の場合は子供がいないから、悩まなくても上記の条件を満たす。)
一人で暮らすなら〇LDKのマンションよりワンルームがよいと著者は言うけれど、うちの奥さんには無理かな。若い頃から本とマンガが大好きで読んだものは全て取ってある。読んだらブックオフに売りに行く僕とは大違いだ。
介護サービスは都会の方が選択肢が多いと言うが、彼女はずっと都会暮らしだから自然にそうなるだろう。
パソコンは高齢者の強い味方だというが、彼女はネットを見るのが趣味のようだし、キーボードの入力は会社員時代に覚えた親指シフトで、ローマ字入力しかできない僕より巧みだ。今後は音声入力も普通になるだろうしPCは老人の味方だ(画面の小さいスマホは若者向けだ。目が霞んできたら読めなくなるだろう)。ただし彼女はハードウエアやPCの仕組みに弱いから、これからもう少し覚えてもらおう。
年をとったら気の合う友達が大事というのは、彼女の場合は心配なさそうだ。高校時代の同級生や会社員時代の友人もまだ続いているし、ネットで知り合ってまだ一度もあったことのない友人がいて、年に何度か長電話をしている。
この本は途中から調子が変わってくる。PPK(ピンピンコロリ)運動をファシズムだ!と批判し、また尊厳死も批判している。確かにこれらは死んでいく本人より周りの人間の利益を考慮した疑いがある。百歳まで生きてある日ぱったり死んでしまう人も確かにいるでしょうが、それが人間の生き方の理想だというのは怪しい。元気なうちは延命処置を拒否していても死ぬ間際にも同じかどうかは分からない。
まあ誰でも、まだ死んだことはないわけで、死については本当は何も言えないのではないでしょうか(例えば、僕は実は”脳死”という概念を信じることができません)。
多くの人は倒れてから亡くなるまで要介護の状態になるのだから、自分が介護を受けることを考えておくことが必要なようだ。上野氏の年代の女性は自分が介護されることに心理的な抵抗が強いというが、生きるためには介護される際のノウハウを知っておく必要があるのかな。
介護を受ける十か条というのが載せられている。第三条は「不必要ながまんや遠慮はしない」というのだが、うちの奥さんには(誰にでも?)ハードルが高そうだ。でもがまんの結果病気が悪化したらなんにもならない。
最後は死んだ後の遺産を誰に残すか、墓をどうするかなどだが(子供がいないから墓は不必要という点では僕ら夫婦の意見は一致しているが・・・)それはおいおい考えてもらいましょう。
お気に入り度:





掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
1957年、仙台に生まれ、結婚後10年間世田谷に住み、その後20余年横浜に住み、現在は仙台在住。本を読んで、思ったことあれこれを書いていきます。
長年、化学メーカーの研究者でした。2019年から滋賀県で大学の教員になりましたが、2023年3月に退職し、10月からは故郷の仙台に戻りました。プロフィールの写真は還暦前に米国ピッツバーグの岡の上で撮ったものです。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:文藝春秋
- ページ数:285
- ISBN:9784167801625
- 発売日:2011年12月06日
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。
『おひとりさまの老後』のカテゴリ
- ・政治・経済・社会・ビジネス > 社会問題
- ・趣味・実用 > 生活の知恵