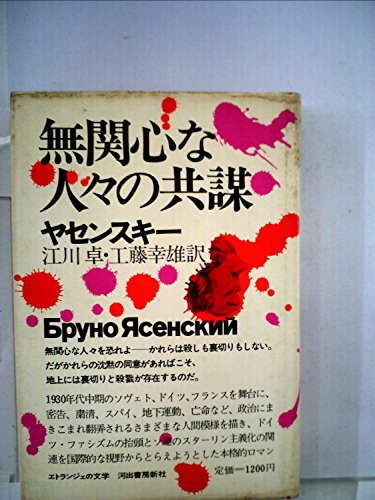hackerさん
レビュアー:
▼
「無関心な人々を恐れよ-かれらは殺しも裏切りもしない。
だがかれらの沈黙の同意があればこそ、
地上には裏切りと殺戮が存在するのだ」
(ロベルト・エバルハルト作『ピテカントロープ最後の皇帝』より)
「1937年夏、夫ヤセンスキーは『無関心な人々の共謀』第一部の終章の仕上げにかかっていた。連日、何時間も机に向かうか、さもなくば書斎の中を歩き回っていた」(アンナ・ベルジンによる本書序文より)
しかし、その直後、作者ヤセンスキーは逮捕され、投獄されます。当時吹き荒れていたスターリンによる粛清の一環で、結局ヤセンスキーは流刑地となったシベリアで1939年初めにチフスにて病死しましたが、没日すらはっきりしていません。遺作にあたる本作は、逮捕された時、第一部がほぼ完成した状態で、アンナ・ベルジン夫人が官憲の目を逃れ保存していた原稿を発表できたのは1956年5月、つまり同年2月のフルシチョフによるスターリン批判の後でした。
さて、本書の内容の前に、1901年ポーランド生まれのヴィクトル・ブルーノ・ヤセンスキーについてですが、彼は詩人としてデビューし、若いうちから左翼運動に係わっていました。そしてポーランド共産党への弾圧により20代でパリに亡命し、その地で傑作『パリを焼く』(1927年)を発表します。この作品は、カミュの『ペスト』に先立つこと20年、ペスト蔓延により外界より隔離され、小「国家」が乱立し争い合うパリを描いたもので、小「国家」とは、中国共産党の秘密工作員をリーダーとする黄色人種国家、アフリカ系住民を中心とする黒人国家、ユダヤ人国家、英米富豪を中心とする「現代資本主義」体制国家、ソ連からの亡命者による白衛軍国家、ソ連共産党関係者による赤衛軍国家等で、最後の大団円に至るまで、一気に読ませてくれる作品です。ただこれにより、当局から暴動扇動者と見なされ、ロマン・ロラン等の文学者の抗議にもかかわらず、国外退去を命じられ、ソ連に亡命します。そして、その地で粛清の対象となって、生涯を閉じることとなったわけです。
1934年の大晦日に始まる、本書の現在時間は1935年で、舞台はソ連、ドイツ、フランスとなります。そして、現在時間の進行は現在形で語られています。まず、1935年とはどんな年だったのでしょうか。
ソ連ですが、建国の父とも言うべきレーニンの死去以降に勃発した権力争いは、1927年にトロツキー、ジノヴィエフ、カーメネフを共産党から除名することにより、スターリン独裁体制が確立します。翌年より、いわゆる5ヶ年計画が始まり、急速に工業化は進みますが、一方で農業軽視のあまり、1932年から33年にかけて「親が子を食った」と言われるウクライナ飢饉を巻き起こします。本書でも、パンの配給不足の実情が率直に語られています。一方で、国際連盟に1934年9月に加盟し、常任理事国入りすることにより、国際社会での存在は認知されるようになりました。
ドイツでは、1933年1月に首相となったヒトラーが自分の権力を拡大させ、ヒンデンブルグ大統領の死去の後、1934年8月に総統の地位に就いて完全に独裁者となり、1935年3月に再軍備を宣言します。
そしてフランスでは、1935年6月に、社会党・共産党・急進社会党の三党による人民戦線が結成され、翌年の選挙で勝って、政権を把握することになります。
本書を読む際には、こういう当時の歴史を、一応頭に入れておいた方が良いでしょう。本書は、まさにリアルタイムの世界の物語だからです。
本書はまず、ソ連の地方工場を舞台に、大晦日に、そこで皆に親しまれていた男が党籍剝奪されるというニュースから、その男の家に新年の祝いで集まっていた人間たちが、三々五々いなくなるという場面から始まります。ただ、興味深いのは、彼がそんな人間であるはずがないと主張する人間も少なくなく、党員同士できっちり議論する場面が描かれていることで、これはおそらく自分の身の危うさを感じていた作者の気持ちの反映だと思います。少なくとも、党の上層部の言うがままという人間ばかり登場するわけではありませんが、当時の現実がどうだったのかというのは、別の話でしょう。
ただ、当時は、まだ共産主義の幻影が生きていたのだなというのは、地方工場に掲げられている、以下のスローガンからも分かります。
「ソヴィエト労働者は皆に羨ましがられて働く。十時間ではなく、七時間。忘れまい、むだに費やす一時間、いや一分が盗みにひとしい罪なのだと!」
また、次のスローガンは、ある意味で今風なので、これも紹介しておきます。
「どの会議も30分以上つづけてはならないし、つづけることはできない」
さて、物語は、ここから工場幹部の一人がパリに出張することになり、その旅先で偶然助けることになる、エルンストというドイツ共産党員へと移ります。生粋の共産主義者である彼が、この第一部では実質的な主人公であり、彼の少年時代から、ヒトラーの台頭と共産党の非合法化というドイツの歴史が語られ、現在は地下に潜って活動を続ける姿が描かれています。そして、彼の幼いころからの親友で、人類学者であり、唯物論者というだけで、マルケス主義者と見なされ、悲劇的な最期をとげるロベルトと、その婚約者で父親はヒトラーの側近であるマルグレートとの三人の関係は、本書で最も面白い部分でもあります。人民戦線の大会に参加するために、パリにやってきたエルンストは、その地に逃れているマルグレートと会って、ロベルトの父親から聞かされた彼の死の様子を語るのですが、エルンストの助けをしたいというマルグレートに、彼女の父親と仲直りをしたふりをして、スパイ活動を働くことを提案するのです。そして、アンナ・ベルジンによる本書序文では、第二部では、彼女も悲劇的な最期をとげる展開を、ヤセンスキーは考えていたことが簡単に述べられています。
さて、本書を読んでいて痛ましいのは、自分の不安定な立場にもかかわらず、ヤセンスキー自身が共産主義の未来というものを信じていることが読み取れることです。特に、本書を書いてから二年後の1939年8月に独ソ不可侵条約が締結されるなど、まったく念頭になかったのは間違いありません。それを知っていたら、反ファシズム色が濃厚な、こういう雰囲気の本にはなっていなかったでしょう。映画『ニュールンベルグ裁判』で、B級戦犯の弁護人(マキシミリアン・シェル、熱演)が「ここにいる被告たちが有罪なら、独ソ不可侵条約によって、ヒトラーがヨーロッパを蹂躙することを可能にさせたスターリンに罪はないのか」と啖呵を切る場面を、私は忘れることができません。
というわけで、その後の作者の人生と、その後の歴史を知る者にとっては、読んでいて複雑な思いを抱くことが避けられません。ただし、『パリを焼く』同様、ストーリー・テラーとしての筆の冴えは見事なもので、その豊かな才能を感じさせてくれる本です。しかし、この題名の意味するところは、書かれなかった第二部で鮮明に打ち出されたはずで、この点は本当に残念です。また、最終章で描かれる、郷愁に満ちたパリの街の美しい描写は、個人的にはとても印象的でした。
なお、訳者あとがきによると、ヤセンスキーは社会主義リアリズムの代表的作家で、自殺したファジェーエフ(1901-1956)とは友人だったそうで、こちらの作家も、近いうちに再読してみたいと思っています。
しかし、その直後、作者ヤセンスキーは逮捕され、投獄されます。当時吹き荒れていたスターリンによる粛清の一環で、結局ヤセンスキーは流刑地となったシベリアで1939年初めにチフスにて病死しましたが、没日すらはっきりしていません。遺作にあたる本作は、逮捕された時、第一部がほぼ完成した状態で、アンナ・ベルジン夫人が官憲の目を逃れ保存していた原稿を発表できたのは1956年5月、つまり同年2月のフルシチョフによるスターリン批判の後でした。
さて、本書の内容の前に、1901年ポーランド生まれのヴィクトル・ブルーノ・ヤセンスキーについてですが、彼は詩人としてデビューし、若いうちから左翼運動に係わっていました。そしてポーランド共産党への弾圧により20代でパリに亡命し、その地で傑作『パリを焼く』(1927年)を発表します。この作品は、カミュの『ペスト』に先立つこと20年、ペスト蔓延により外界より隔離され、小「国家」が乱立し争い合うパリを描いたもので、小「国家」とは、中国共産党の秘密工作員をリーダーとする黄色人種国家、アフリカ系住民を中心とする黒人国家、ユダヤ人国家、英米富豪を中心とする「現代資本主義」体制国家、ソ連からの亡命者による白衛軍国家、ソ連共産党関係者による赤衛軍国家等で、最後の大団円に至るまで、一気に読ませてくれる作品です。ただこれにより、当局から暴動扇動者と見なされ、ロマン・ロラン等の文学者の抗議にもかかわらず、国外退去を命じられ、ソ連に亡命します。そして、その地で粛清の対象となって、生涯を閉じることとなったわけです。
1934年の大晦日に始まる、本書の現在時間は1935年で、舞台はソ連、ドイツ、フランスとなります。そして、現在時間の進行は現在形で語られています。まず、1935年とはどんな年だったのでしょうか。
ソ連ですが、建国の父とも言うべきレーニンの死去以降に勃発した権力争いは、1927年にトロツキー、ジノヴィエフ、カーメネフを共産党から除名することにより、スターリン独裁体制が確立します。翌年より、いわゆる5ヶ年計画が始まり、急速に工業化は進みますが、一方で農業軽視のあまり、1932年から33年にかけて「親が子を食った」と言われるウクライナ飢饉を巻き起こします。本書でも、パンの配給不足の実情が率直に語られています。一方で、国際連盟に1934年9月に加盟し、常任理事国入りすることにより、国際社会での存在は認知されるようになりました。
ドイツでは、1933年1月に首相となったヒトラーが自分の権力を拡大させ、ヒンデンブルグ大統領の死去の後、1934年8月に総統の地位に就いて完全に独裁者となり、1935年3月に再軍備を宣言します。
そしてフランスでは、1935年6月に、社会党・共産党・急進社会党の三党による人民戦線が結成され、翌年の選挙で勝って、政権を把握することになります。
本書を読む際には、こういう当時の歴史を、一応頭に入れておいた方が良いでしょう。本書は、まさにリアルタイムの世界の物語だからです。
本書はまず、ソ連の地方工場を舞台に、大晦日に、そこで皆に親しまれていた男が党籍剝奪されるというニュースから、その男の家に新年の祝いで集まっていた人間たちが、三々五々いなくなるという場面から始まります。ただ、興味深いのは、彼がそんな人間であるはずがないと主張する人間も少なくなく、党員同士できっちり議論する場面が描かれていることで、これはおそらく自分の身の危うさを感じていた作者の気持ちの反映だと思います。少なくとも、党の上層部の言うがままという人間ばかり登場するわけではありませんが、当時の現実がどうだったのかというのは、別の話でしょう。
ただ、当時は、まだ共産主義の幻影が生きていたのだなというのは、地方工場に掲げられている、以下のスローガンからも分かります。
「ソヴィエト労働者は皆に羨ましがられて働く。十時間ではなく、七時間。忘れまい、むだに費やす一時間、いや一分が盗みにひとしい罪なのだと!」
また、次のスローガンは、ある意味で今風なので、これも紹介しておきます。
「どの会議も30分以上つづけてはならないし、つづけることはできない」
さて、物語は、ここから工場幹部の一人がパリに出張することになり、その旅先で偶然助けることになる、エルンストというドイツ共産党員へと移ります。生粋の共産主義者である彼が、この第一部では実質的な主人公であり、彼の少年時代から、ヒトラーの台頭と共産党の非合法化というドイツの歴史が語られ、現在は地下に潜って活動を続ける姿が描かれています。そして、彼の幼いころからの親友で、人類学者であり、唯物論者というだけで、マルケス主義者と見なされ、悲劇的な最期をとげるロベルトと、その婚約者で父親はヒトラーの側近であるマルグレートとの三人の関係は、本書で最も面白い部分でもあります。人民戦線の大会に参加するために、パリにやってきたエルンストは、その地に逃れているマルグレートと会って、ロベルトの父親から聞かされた彼の死の様子を語るのですが、エルンストの助けをしたいというマルグレートに、彼女の父親と仲直りをしたふりをして、スパイ活動を働くことを提案するのです。そして、アンナ・ベルジンによる本書序文では、第二部では、彼女も悲劇的な最期をとげる展開を、ヤセンスキーは考えていたことが簡単に述べられています。
さて、本書を読んでいて痛ましいのは、自分の不安定な立場にもかかわらず、ヤセンスキー自身が共産主義の未来というものを信じていることが読み取れることです。特に、本書を書いてから二年後の1939年8月に独ソ不可侵条約が締結されるなど、まったく念頭になかったのは間違いありません。それを知っていたら、反ファシズム色が濃厚な、こういう雰囲気の本にはなっていなかったでしょう。映画『ニュールンベルグ裁判』で、B級戦犯の弁護人(マキシミリアン・シェル、熱演)が「ここにいる被告たちが有罪なら、独ソ不可侵条約によって、ヒトラーがヨーロッパを蹂躙することを可能にさせたスターリンに罪はないのか」と啖呵を切る場面を、私は忘れることができません。
というわけで、その後の作者の人生と、その後の歴史を知る者にとっては、読んでいて複雑な思いを抱くことが避けられません。ただし、『パリを焼く』同様、ストーリー・テラーとしての筆の冴えは見事なもので、その豊かな才能を感じさせてくれる本です。しかし、この題名の意味するところは、書かれなかった第二部で鮮明に打ち出されたはずで、この点は本当に残念です。また、最終章で描かれる、郷愁に満ちたパリの街の美しい描写は、個人的にはとても印象的でした。
なお、訳者あとがきによると、ヤセンスキーは社会主義リアリズムの代表的作家で、自殺したファジェーエフ(1901-1956)とは友人だったそうで、こちらの作家も、近いうちに再読してみたいと思っています。
お気に入り度:









掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
「本職」は、本というより映画です。
本を読んでいても、映画好きの視点から、内容を見ていることが多いようです。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:河出書房新社
- ページ数:275
- ISBN:B000J95692
- 発売日:1970年01月01日
- 価格:1296円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。
『無関心な人々の共謀 (1974年) (エトランジェの文学)』のカテゴリ
- ・文学・小説 > 文学
- ・歴史 > 世界史
- ・政治・経済・社会・ビジネス > 社会
- ・政治・経済・社会・ビジネス > 政治