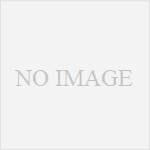darklyさん
レビュアー:
▼
最後になるまでつかみどころがない物語だが、最後まで読めば人間に関する洞察の鋭さに驚嘆する。
まだ北極点に誰も到達したことがない時代、初めて到達した人には莫大な賞金が与えられるという。主人公アダムはその調査団メンバーの補欠であった。なんとかアダムを調査団に入れようと婚約者のクローダはやきもきしていた。そのような時、偶然にも調査団の一人が薬物により中毒死する。そしてアダムは調査団に加わることになった。
北極点への苦難な道のり、仲間割れ、そして青酸化合物と思われる紫の雲による仲間たちの死、一人生き残ったアダムはヨーロッパに戻ろうとするが、その道中人々はすべて死に絶えていることを発見する。紫の雲により全滅したのだ。一人きりとなったアダムは孤独に苛まれると思いきや、街を焼いたり、破壊したり、やりたい放題、各地を転々とする。
そしてコンスタンティノープルで若い女性を発見する。彼女は言葉も話せず、世の中のことを何も知らないようだ。彼女はスルタンの娘らしい。地下の牢獄で紫の雲の影響を受けなかった母親からその後生まれたようだ。やがて彼女との出逢いがアダムに大きく影響することになる。
たまたま本屋で見つけて読んだ本ですが、読み進めるにつれてこれほど印象が次々と変わり、途中まで一体何を言いたい話なのか分からない小説でした。オカルトっぽい雰囲気で始まり、アダムの婚約者が毒殺者なのか、そしてサイコホラーのような展開なのかと思いきや、あっさりその可能性はなくなり、一人で何十年も各地を旅するロードムービーのようなものになったと思ったら運命の出逢いがあったり。
もし突然世界で人間が自分一人になったらどうなると思いますか?当初は他の人を探したり、孤独に苛まれることは想像できます。しかし人間の心というのはある意味とても柔軟なものです。その環境に慣れてくると社会性を失いやがて自我が肥大し、この街、いやこの国、いやいやこの地球すべてが自分の物だと思うようになる。アダムはある街で人を見かける(そのような気がしただけ)と殺意を抱きます。「この地球は私のものだ。誰にも渡さないと」
そしてレダ(後に名付ける)を見つけた時も当初はそのように思います。しかし無垢な彼女と一緒にいるうち少しづつアダムは以前の人間性を取り戻し、やがて自分にとって大事なのは単なるこの世界ではなくレダがいるこの世界であることに気付きます。つまるところ人間というのは社会性という箍が外れるとどこまでも酷い動物に成り下がるものであり、その獣性を鎮めるのは人間のつながりという社会であり、また愛でもあるのでしょう。
もちろんアダムとレダはこの世界におけるアダムとイヴであり、ここから新しい世界を創っていくという希望に満ちた終わり方ということで、最初からほとんど最後まで暗い話であったのを読み通したことが少し報われます。
権力を握った独裁者は見方によっては社会性を失っており、つまり人を人と思わなくなっており、この小説が書かれたのが1901年、20世紀の初頭ですが、その後ホロコーストが起こることを考えると単なるSF作品を超えた示唆があるような気がします。
北極点への苦難な道のり、仲間割れ、そして青酸化合物と思われる紫の雲による仲間たちの死、一人生き残ったアダムはヨーロッパに戻ろうとするが、その道中人々はすべて死に絶えていることを発見する。紫の雲により全滅したのだ。一人きりとなったアダムは孤独に苛まれると思いきや、街を焼いたり、破壊したり、やりたい放題、各地を転々とする。
そしてコンスタンティノープルで若い女性を発見する。彼女は言葉も話せず、世の中のことを何も知らないようだ。彼女はスルタンの娘らしい。地下の牢獄で紫の雲の影響を受けなかった母親からその後生まれたようだ。やがて彼女との出逢いがアダムに大きく影響することになる。
たまたま本屋で見つけて読んだ本ですが、読み進めるにつれてこれほど印象が次々と変わり、途中まで一体何を言いたい話なのか分からない小説でした。オカルトっぽい雰囲気で始まり、アダムの婚約者が毒殺者なのか、そしてサイコホラーのような展開なのかと思いきや、あっさりその可能性はなくなり、一人で何十年も各地を旅するロードムービーのようなものになったと思ったら運命の出逢いがあったり。
もし突然世界で人間が自分一人になったらどうなると思いますか?当初は他の人を探したり、孤独に苛まれることは想像できます。しかし人間の心というのはある意味とても柔軟なものです。その環境に慣れてくると社会性を失いやがて自我が肥大し、この街、いやこの国、いやいやこの地球すべてが自分の物だと思うようになる。アダムはある街で人を見かける(そのような気がしただけ)と殺意を抱きます。「この地球は私のものだ。誰にも渡さないと」
そしてレダ(後に名付ける)を見つけた時も当初はそのように思います。しかし無垢な彼女と一緒にいるうち少しづつアダムは以前の人間性を取り戻し、やがて自分にとって大事なのは単なるこの世界ではなくレダがいるこの世界であることに気付きます。つまるところ人間というのは社会性という箍が外れるとどこまでも酷い動物に成り下がるものであり、その獣性を鎮めるのは人間のつながりという社会であり、また愛でもあるのでしょう。
もちろんアダムとレダはこの世界におけるアダムとイヴであり、ここから新しい世界を創っていくという希望に満ちた終わり方ということで、最初からほとんど最後まで暗い話であったのを読み通したことが少し報われます。
権力を握った独裁者は見方によっては社会性を失っており、つまり人を人と思わなくなっており、この小説が書かれたのが1901年、20世紀の初頭ですが、その後ホロコーストが起こることを考えると単なるSF作品を超えた示唆があるような気がします。
お気に入り度:







掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
昔からずっと本は読み続けてます。フィクション・ノンフィクション問わず、あまりこだわりなく読んでます。フィクションはSF・ホラー・ファンタジーが比較的多いです。あと科学・数学・思想的な本を好みます。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:書苑新社
- ページ数:320
- ISBN:9784883753369
- 発売日:2018年12月12日
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。
『紫の雲 (ナイトランド叢書3-4)』のカテゴリ
登録されているカテゴリはありません。