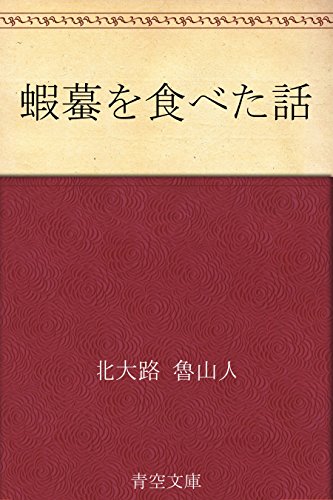ぽんきちさん
レビュアー:
▼
魯山人、ヒキガエルを食べるの巻
北大路魯山人(1883-1959)といえば、陶芸家・書家にして、稀代の美食家である。
その魯山人が蝦蟇(ヒキガエル)を食べるお話。
上海で「大田鶏」と称する肉を食べた魯山人先生。これが実はカエルであると知る。田の鶏とはうまいことを言ったものである。実物を見せてもらうと、日本のヒキガエルを小さくしたようなもので、アカヒキという種類と思われた。
食用ガエル(おそらくウシガエル?)よりもよほどうまいと思った魯山人、機会があったら日本のヒキガエルも食べてやろうと思っていた。
ある時、瀬戸から来た陶工から、地元ではヒキガエルを捕って食うのはよくあることだと聞く。カエルだけでなく、カメなども食べるという。実際に瀬戸に行った際、あちこちと聞いて回るが、誰もそんなことは知らないという。
京都に戻り、常食論者にそういうが、「いや、本当に食う」と言って聞かない。どうも要領を得ないが、ヒキガエルなんて瀬戸まで行かなくてもここにもいるのだから、捕ってきて食べてみればよいという話になる。魯山人が1匹1円で買うというと、その場にいた陶工仲間は皆、やる気になって伏見稲荷の池に捕りに行くことになる(*この時代の1円は、原稿執筆時点の昭和10年の100円にあたるといい、今現在の価値としては20~30万円・・・? いや、さすがに2~3万というところかな・・・? えーと、この換算が正しいのかどうかよくわからないが、ともかくヒキガエル1匹の報酬としては相当なものだったのは間違いない)。
冬のこととて、カエルは冬眠中である。穴倉に手を突っ込んで、それらしきものを掴んで引っ張り出すのだが、これがなかなか気味が悪い。カエルと思ってもヘビかもしれないじゃないか、と、金目当てのものたちも尻込みする。それでも何とか5匹集まり、常食論者に捌いてもらった魯山人、早速晩餐に試してみる。
うまいにはうまいが苦味がある。しかし、「ともかく、苦いものには毒はない」(ほんとか!?)とぱくぱく食べてしまう魯山人先生であった。
魯山人は大丈夫だったようだけれど、ヒキガエルには結構毒が強いものもいて、実際、ヒキガエルを食べて死亡した例もあるらしい。苦味があったということは、実は毒があったんじゃないのかなぁと今さらながら心配になるのだが、まぁ無事だったようなのでよかったというところか。
ところでこの蝦蟇という字。私は「ガマガエル」と読んだのだが、魯山人は「ひきがえる」とルビを振っている。古くは別々のものを指していたようだが、現在では同じものを指すようだ。「がまくんとかえるくん」のがまくんで、英語ではtoadにあたる。
フランス料理で出てくるカエルはトノサマガエルの仲間で、これはfrogのようだ。
その魯山人が蝦蟇(ヒキガエル)を食べるお話。
上海で「大田鶏」と称する肉を食べた魯山人先生。これが実はカエルであると知る。田の鶏とはうまいことを言ったものである。実物を見せてもらうと、日本のヒキガエルを小さくしたようなもので、アカヒキという種類と思われた。
食用ガエル(おそらくウシガエル?)よりもよほどうまいと思った魯山人、機会があったら日本のヒキガエルも食べてやろうと思っていた。
ある時、瀬戸から来た陶工から、地元ではヒキガエルを捕って食うのはよくあることだと聞く。カエルだけでなく、カメなども食べるという。実際に瀬戸に行った際、あちこちと聞いて回るが、誰もそんなことは知らないという。
京都に戻り、常食論者にそういうが、「いや、本当に食う」と言って聞かない。どうも要領を得ないが、ヒキガエルなんて瀬戸まで行かなくてもここにもいるのだから、捕ってきて食べてみればよいという話になる。魯山人が1匹1円で買うというと、その場にいた陶工仲間は皆、やる気になって伏見稲荷の池に捕りに行くことになる(*この時代の1円は、原稿執筆時点の昭和10年の100円にあたるといい、今現在の価値としては20~30万円・・・? いや、さすがに2~3万というところかな・・・? えーと、この換算が正しいのかどうかよくわからないが、ともかくヒキガエル1匹の報酬としては相当なものだったのは間違いない)。
冬のこととて、カエルは冬眠中である。穴倉に手を突っ込んで、それらしきものを掴んで引っ張り出すのだが、これがなかなか気味が悪い。カエルと思ってもヘビかもしれないじゃないか、と、金目当てのものたちも尻込みする。それでも何とか5匹集まり、常食論者に捌いてもらった魯山人、早速晩餐に試してみる。
うまいにはうまいが苦味がある。しかし、「ともかく、苦いものには毒はない」(ほんとか!?)とぱくぱく食べてしまう魯山人先生であった。
魯山人は大丈夫だったようだけれど、ヒキガエルには結構毒が強いものもいて、実際、ヒキガエルを食べて死亡した例もあるらしい。苦味があったということは、実は毒があったんじゃないのかなぁと今さらながら心配になるのだが、まぁ無事だったようなのでよかったというところか。
ところでこの蝦蟇という字。私は「ガマガエル」と読んだのだが、魯山人は「ひきがえる」とルビを振っている。古くは別々のものを指していたようだが、現在では同じものを指すようだ。「がまくんとかえるくん」のがまくんで、英語ではtoadにあたる。
フランス料理で出てくるカエルはトノサマガエルの仲間で、これはfrogのようだ。
掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
分子生物学・生化学周辺の実務翻訳をしています。
本の大海を漂流中。
日々是好日。どんな本との出会いも素敵だ。
あちらこちらとつまみ食いの読書ですが、点が線に、線が面になっていくといいなと思っています。
「実感」を求めて読書しているように思います。
赤柴♀(もも)は3代目。
この夏、有精卵からヒヨコ4羽を孵化させました。そろそろ大雛かな。♂x2、♀x2。ニワトリは割と人に懐くものらしいですが、今のところ、懐く気配はありませんw
この書評へのコメント
- keena071511292019-02-12 07:57
かつて“中島らも”さんが書いてましたが
カエルの体液に麻薬と同じような成分があって
ドラックをやる代わりにカエルを舐める
というのがあるそうです
これは流石に法律では規制されないでしょうし
カエルが生きている限りずっと使えるという…
案外“がまの油”というのはこれのことなのかもしれませんクリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 
コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:
- ページ数:6
- ISBN:B00SB11M8E
- 発売日:2015年01月10日
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。