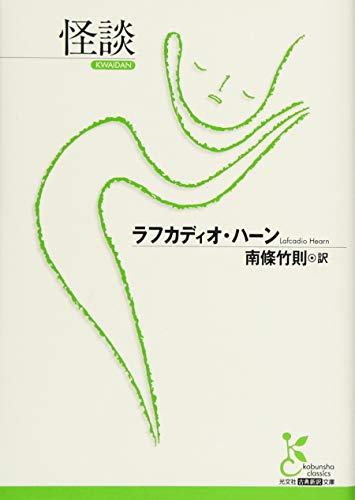星落秋風五丈原さん
レビュアー:
▼
朝ドラばけばけにちなんで読んでみる お盆にちなんで怪談話をどうぞ!
日本の幽霊といえば、決め台詞が「恨めしや~」である。番町皿屋敷のお菊も、吉備津の釜の磯良も、牡丹灯籠のお露も、全て恨みから凄まじい凶行に及んでいる。しかし本編を読むと、あまり恨みが感じられない。というか、恨みが生じても、相手に憎しみが向かわないのだ。
『耳なし芳一の話』
知名度の高い話。琵琶の名手芳一は、和尚も小僧もいないある夜に、武士から「やんごとなき方がお前の琵琶を所望している」と言われて、ついていく。彼らは平家滅亡の壇ノ浦の件になると、いたく涙を流し、七夜通って欲しいと頼む。誰にもこの事を言ってはならないと言われ、芳一はこっそり出かけていたが、ある日ばれてしまう。
再読してわかったのは、芳一の通う期限があったことだ。永遠に琵琶コンサートをやってほしかったわけではない。七日といえば初七日が浮かぶが、呼び出した相手からすれば、とっくにその期限は過ぎている。普通に誰にも知られず七日通えば、無事に過ぎたのでは。それとも七日過ぎて、いよいよこの名手を黄泉へ連れていかんという話になったのか。七日の期限の意味がよくわからない。
また、連れていかれた芳一が、夜な夜なお露と出会ってやつれていった新三郎のように、生気を吸い取られていったわけではない。特に病気になったわけでもないなら、やはり七日行かせてやれば良かったのでは。途中で嫌だといえば八つ裂きにされたかもしれないが、普通についていったら、意外と大丈夫だったという説はないか。墓地で寺男たちに怒ったのも、急に演奏を止められてエキサイトしていただけでは。
面白かったのは、芳一には連れていかれた先もわからず、聞いている武将や女性の気配や声を感じることができるが、和尚や寺男には彼らの姿が見えず、鬼火が見える。怪かしの世界と現実世界が同居している不思議な空間である。
そして和尚は、そんなに心配しているなら、法要をやめて一日くらい傍について様子を見ていればよかったのではないか。もちろん法要も大事だが、一日くらいずらして、自分の取った策が成功するかどうか見届ければよかった。ただそれを行うと、耳なし芳一が完成しない。
本作においても、強い恨みは感じられない。耳と琵琶だけ浮かんでいても、迎えに来た武士は頓着なく、来た証拠に耳をぶっちぎる。
『おしどり』
鴛鴦の契りという言葉のあるくらい、ラブラブ夫婦の鳥である。そんな夫婦の雄鳥が猟師に矢で射られてしまう。その夜猟師の夢に出てきたのは。
これも恨み節はいうものの、リベンジに向かわない。雌鳥の死に方が、かなりアクロバティック。
『お貞の話』
新潟は越後の国に、長尾長生という医師がいた。名前にこめられた意味のごとく、彼は長生きするが、妻お貞が亡くなる。ところが、亡くなる直前にお貞が「私たちはもう一度会える」と予言する。生まれ変わってきた時のサインはないの?と聞くが、ないらしい。さあ、二人はどうやって巡り合えるのか?この手の映画がかなり出回っているので、今となっては珍しい設定ではなくなったのでは。めぐり逢いの地として伊香保が登場。
『雪女』
これも有名どころ。雪山で山小屋で休んでいた木こりの巳之吉と茂作が眠っていた。ふと目を覚ますと、目の前に雪女がおり、巳之吉の目の前で茂作が息を吹きかけられていた。女は美しく、かつ恐ろしかったが、巳之吉に今夜の事を誰にも言い含めないよう命じて立ち去る。やがて巳之吉は美しい娘と結婚し、子供をもうけるが。
めでたしめでたしで終わるはずのない話。姿を現せば思い出し、話すかもしれないととわかっていながら、雪女はなぜ巳之吉の前に現れ、試すような事をしたのか。本作においても、恨みは感じられない。むしろ雪女の悲しみが感じられる。
『むじな』
長らくむじな=たぬきと考えていた。実際、アナグマやタヌキの類のことである。しかし本編ではたぬきは登場しない。実際、たぬきが登場しても怖くない。むしろこの話をむじなというタイトルにしてしまうと、別の妖怪と混同しそうだ。話の幕切れはうまい。
『ろくろ首』
ろくろ首なら、夜ごと油をなめなきゃ!と思うが、そういった絵は出てこない。
元武士だが士官先を失い、やむなく僧侶になった回竜は、物騒な時代に、難行苦行を求めて危険な場所にばかり赴く僧侶版インディ・ジョーンズ。野宿をしようとしていた回竜は声をかけられて、上品な人が住む家に逗留する。ところがそこは、とんでもない者の住処だった。
こちらも恨みというより、とある物を袖にひっつけて歩く回竜無双すぎる。ナントカ英雄伝説になりそうだ。
『食人鬼』
最近法事に詳しくなって、施餓鬼やりません?と言われたが、やった方がよいかも。餓鬼道に堕ちた僧侶が夢窓国師の前で自らの性を嘆きながら告白。こちらも恨み節はなし。
『安芸之介の夢』
唐代の伝奇小説『南柯郡太守伝』からの翻案。
他
乳母の愛が泣かせる『乳母桜』とんでもない者とかけひきする、見方によってはユーモラス?な『かけひき』不思議な能力を持った鐘に群がる金の亡者たちが悲しい『鏡と鐘』亡くなったのに出てくる幽霊が気になったものは?『葬られた秘密』変身もの『青柳の物語』樹木への愛に殉じる老人『十六桜』転生もの『力ばか』なぜか突然舞台が海外に『ひまわり』そこに行けばどんな夢も叶う夢の都について『蓬萊』収録。
虫の研究『蝶』『蚊』『蟻』は、ホラーなし。
『耳なし芳一の話』
知名度の高い話。琵琶の名手芳一は、和尚も小僧もいないある夜に、武士から「やんごとなき方がお前の琵琶を所望している」と言われて、ついていく。彼らは平家滅亡の壇ノ浦の件になると、いたく涙を流し、七夜通って欲しいと頼む。誰にもこの事を言ってはならないと言われ、芳一はこっそり出かけていたが、ある日ばれてしまう。
再読してわかったのは、芳一の通う期限があったことだ。永遠に琵琶コンサートをやってほしかったわけではない。七日といえば初七日が浮かぶが、呼び出した相手からすれば、とっくにその期限は過ぎている。普通に誰にも知られず七日通えば、無事に過ぎたのでは。それとも七日過ぎて、いよいよこの名手を黄泉へ連れていかんという話になったのか。七日の期限の意味がよくわからない。
また、連れていかれた芳一が、夜な夜なお露と出会ってやつれていった新三郎のように、生気を吸い取られていったわけではない。特に病気になったわけでもないなら、やはり七日行かせてやれば良かったのでは。途中で嫌だといえば八つ裂きにされたかもしれないが、普通についていったら、意外と大丈夫だったという説はないか。墓地で寺男たちに怒ったのも、急に演奏を止められてエキサイトしていただけでは。
面白かったのは、芳一には連れていかれた先もわからず、聞いている武将や女性の気配や声を感じることができるが、和尚や寺男には彼らの姿が見えず、鬼火が見える。怪かしの世界と現実世界が同居している不思議な空間である。
そして和尚は、そんなに心配しているなら、法要をやめて一日くらい傍について様子を見ていればよかったのではないか。もちろん法要も大事だが、一日くらいずらして、自分の取った策が成功するかどうか見届ければよかった。ただそれを行うと、耳なし芳一が完成しない。
本作においても、強い恨みは感じられない。耳と琵琶だけ浮かんでいても、迎えに来た武士は頓着なく、来た証拠に耳をぶっちぎる。
『おしどり』
鴛鴦の契りという言葉のあるくらい、ラブラブ夫婦の鳥である。そんな夫婦の雄鳥が猟師に矢で射られてしまう。その夜猟師の夢に出てきたのは。
これも恨み節はいうものの、リベンジに向かわない。雌鳥の死に方が、かなりアクロバティック。
『お貞の話』
新潟は越後の国に、長尾長生という医師がいた。名前にこめられた意味のごとく、彼は長生きするが、妻お貞が亡くなる。ところが、亡くなる直前にお貞が「私たちはもう一度会える」と予言する。生まれ変わってきた時のサインはないの?と聞くが、ないらしい。さあ、二人はどうやって巡り合えるのか?この手の映画がかなり出回っているので、今となっては珍しい設定ではなくなったのでは。めぐり逢いの地として伊香保が登場。
『雪女』
これも有名どころ。雪山で山小屋で休んでいた木こりの巳之吉と茂作が眠っていた。ふと目を覚ますと、目の前に雪女がおり、巳之吉の目の前で茂作が息を吹きかけられていた。女は美しく、かつ恐ろしかったが、巳之吉に今夜の事を誰にも言い含めないよう命じて立ち去る。やがて巳之吉は美しい娘と結婚し、子供をもうけるが。
めでたしめでたしで終わるはずのない話。姿を現せば思い出し、話すかもしれないととわかっていながら、雪女はなぜ巳之吉の前に現れ、試すような事をしたのか。本作においても、恨みは感じられない。むしろ雪女の悲しみが感じられる。
『むじな』
長らくむじな=たぬきと考えていた。実際、アナグマやタヌキの類のことである。しかし本編ではたぬきは登場しない。実際、たぬきが登場しても怖くない。むしろこの話をむじなというタイトルにしてしまうと、別の妖怪と混同しそうだ。話の幕切れはうまい。
『ろくろ首』
ろくろ首なら、夜ごと油をなめなきゃ!と思うが、そういった絵は出てこない。
元武士だが士官先を失い、やむなく僧侶になった回竜は、物騒な時代に、難行苦行を求めて危険な場所にばかり赴く僧侶版インディ・ジョーンズ。野宿をしようとしていた回竜は声をかけられて、上品な人が住む家に逗留する。ところがそこは、とんでもない者の住処だった。
こちらも恨みというより、とある物を袖にひっつけて歩く回竜無双すぎる。ナントカ英雄伝説になりそうだ。
『食人鬼』
最近法事に詳しくなって、施餓鬼やりません?と言われたが、やった方がよいかも。餓鬼道に堕ちた僧侶が夢窓国師の前で自らの性を嘆きながら告白。こちらも恨み節はなし。
『安芸之介の夢』
唐代の伝奇小説『南柯郡太守伝』からの翻案。
他
乳母の愛が泣かせる『乳母桜』とんでもない者とかけひきする、見方によってはユーモラス?な『かけひき』不思議な能力を持った鐘に群がる金の亡者たちが悲しい『鏡と鐘』亡くなったのに出てくる幽霊が気になったものは?『葬られた秘密』変身もの『青柳の物語』樹木への愛に殉じる老人『十六桜』転生もの『力ばか』なぜか突然舞台が海外に『ひまわり』そこに行けばどんな夢も叶う夢の都について『蓬萊』収録。
虫の研究『蝶』『蚊』『蟻』は、ホラーなし。
お気に入り度:







掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
2005年より書評業。外国人向け情報誌の編集&翻訳、論文添削をしています。生きていく上で大切なことを教えてくれた本、懐かしい思い出と共にある本、これからも様々な本と出会えればと思います。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:光文社
- ページ数:307
- ISBN:9784334753801
- 発売日:2018年07月09日
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。