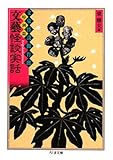休蔵さん
レビュアー:
▼
遊ぶということは、どうやら人間の本質のようです。ならば、それを介して活躍する術があるに違いない。1億総活躍社会を目指す日本において、人間の本質の一端を掘り下げる本書は、必読の1冊なのかもしれません。
久しぶりの中学生棋士、藤井聡太の登場で、将棋界が脚光を集めている。
しかも、ただの中学生棋士ではなく、新記録の樹立や羽生善治や佐藤天彦に勝利するなど話題も尽きない。
そんな将棋も含めた盤の上で駒を扱うものを盤上遊戯というらしい。
本書は、盤上遊戯全般の歴史について取り扱った1冊である。
盤上遊戯の起源は紀元前7000年頃までさかのぼるという。
日本はバリバリの縄文時代だ。
場所はメソポタミア。
もちろん、文字記録で発覚したわけではなく、遊戯盤と目される遺物が出土しているとのこと。
それは、石版に小さなくぼみを2~3列あけた単純なもので、具体的な遊び方は不明という。
遊び方が不明で、なぜ盤上遊戯の起源とされているのか。
じつは後の時代に類似遊戯盤があるとのこと。
種を蒔く行為を真似た「マンカラ」というもので、いまでもアフリカ、中近東からインド、東南アジアで広く遊ばれているゲームだ。
また、小さなくぼみを桝目とし、駒を進めるゲームの可能性もあるらしい。
そもそも盤上遊戯の起源は何なのか。
本書はヒントをくれた。
盤上遊戯は、ものによっては偶然性を楽しむ要素が濃い。
この偶然性という概念は、卜占に通ずる。
たとえば、動物の踵の骨であるアストラガルスやサイコロは、振るって出た目で占うという。
この偶然の行為を遊ぶ余地が、きちんとしたルールの遊戯に昇華したのかもしれない。
類似した遊戯盤が世界各地に存在しているそうだ。
それは偶然の産物というより、シルクロードや海上の道などの交流が大きな役割を果たしたようだ。
例えば、アンコールワットやバイヨン寺院などには、船上で将棋に興じる様子が彫り込まれたレリーフがあるとのこと。
さらに、広東省陽江市沖で沈没した宋代の貿易船では、象棋の駒が見つかったそうだ。
商業としての船旅の慰みに遊戯が導入され、商業都市を介してそれが広域に拡散したというのだ。
盤上遊戯の起源は新石器時代にまで遡るらしいが、このことは遊戯が人間の本質に深く結びつくことを示唆する。
つまり、遊びは人間の本質なのだ。
1億総活躍社会が目指されている。
働いて、金を稼いで税を納め、それで社会を支える。
それはそうなのかもしれない。
しかし、働くということにばかり注目しすぎている気がする。
保育園に子どもを入れられず「活躍できないじゃないか」という憤りの声があった。
それとは裏腹に第二の人生とか言って、年金を元手に老後を満喫する声も聞こえてくる。
総活躍の真意はいったいどこにあるのか。
働くこと?
それとも消費すること?
かつて働きすぎとバッシングされていた日本。
しかし、就職氷河期が到来し、団塊世代が退職し始めると、いつのまにやら働くことを貴ぶ風潮が復活してきた。
活躍=仕事という発想は、その最たるものか。
消費することも立派な活躍なのかもしれない。
そうすることで経済はまわっていく。
できれば消費する側で活躍したいが、元手が乏しくなかなか活躍しきれない。
無論、それは働く面での活躍の乏しさを反映しているわけだが・・・
まあ、可能な範囲で働き、可能な範囲で消費しよう。
将棋ブームに乗っかって盤上遊戯でも購入し、楽しもうか。
そんな活躍の仕方でもいいですか?
しかも、ただの中学生棋士ではなく、新記録の樹立や羽生善治や佐藤天彦に勝利するなど話題も尽きない。
そんな将棋も含めた盤の上で駒を扱うものを盤上遊戯というらしい。
本書は、盤上遊戯全般の歴史について取り扱った1冊である。
盤上遊戯の起源は紀元前7000年頃までさかのぼるという。
日本はバリバリの縄文時代だ。
場所はメソポタミア。
もちろん、文字記録で発覚したわけではなく、遊戯盤と目される遺物が出土しているとのこと。
それは、石版に小さなくぼみを2~3列あけた単純なもので、具体的な遊び方は不明という。
遊び方が不明で、なぜ盤上遊戯の起源とされているのか。
じつは後の時代に類似遊戯盤があるとのこと。
種を蒔く行為を真似た「マンカラ」というもので、いまでもアフリカ、中近東からインド、東南アジアで広く遊ばれているゲームだ。
また、小さなくぼみを桝目とし、駒を進めるゲームの可能性もあるらしい。
そもそも盤上遊戯の起源は何なのか。
本書はヒントをくれた。
盤上遊戯は、ものによっては偶然性を楽しむ要素が濃い。
この偶然性という概念は、卜占に通ずる。
たとえば、動物の踵の骨であるアストラガルスやサイコロは、振るって出た目で占うという。
この偶然の行為を遊ぶ余地が、きちんとしたルールの遊戯に昇華したのかもしれない。
類似した遊戯盤が世界各地に存在しているそうだ。
それは偶然の産物というより、シルクロードや海上の道などの交流が大きな役割を果たしたようだ。
例えば、アンコールワットやバイヨン寺院などには、船上で将棋に興じる様子が彫り込まれたレリーフがあるとのこと。
さらに、広東省陽江市沖で沈没した宋代の貿易船では、象棋の駒が見つかったそうだ。
商業としての船旅の慰みに遊戯が導入され、商業都市を介してそれが広域に拡散したというのだ。
盤上遊戯の起源は新石器時代にまで遡るらしいが、このことは遊戯が人間の本質に深く結びつくことを示唆する。
つまり、遊びは人間の本質なのだ。
1億総活躍社会が目指されている。
働いて、金を稼いで税を納め、それで社会を支える。
それはそうなのかもしれない。
しかし、働くということにばかり注目しすぎている気がする。
保育園に子どもを入れられず「活躍できないじゃないか」という憤りの声があった。
それとは裏腹に第二の人生とか言って、年金を元手に老後を満喫する声も聞こえてくる。
総活躍の真意はいったいどこにあるのか。
働くこと?
それとも消費すること?
かつて働きすぎとバッシングされていた日本。
しかし、就職氷河期が到来し、団塊世代が退職し始めると、いつのまにやら働くことを貴ぶ風潮が復活してきた。
活躍=仕事という発想は、その最たるものか。
消費することも立派な活躍なのかもしれない。
そうすることで経済はまわっていく。
できれば消費する側で活躍したいが、元手が乏しくなかなか活躍しきれない。
無論、それは働く面での活躍の乏しさを反映しているわけだが・・・
まあ、可能な範囲で働き、可能な範囲で消費しよう。
将棋ブームに乗っかって盤上遊戯でも購入し、楽しもうか。
そんな活躍の仕方でもいいですか?
お気に入り度:









掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
ここに参加するようになって、読書の幅が広がったように思います。
それでも、まだ偏り気味。
いろんな人の書評を参考に、もっと幅広い読書を楽しみたい!
- この書評の得票合計:
- 39票
| 読んで楽しい: | 2票 | |
|---|---|---|
| 参考になる: | 35票 | |
| 共感した: | 2票 |
あなたの感想は?
投票するには、ログインしてください。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:平凡社
- ページ数:320
- ISBN:9784582468137
- 発売日:2010年10月26日
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。