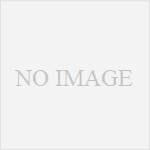ぽんきちさん
レビュアー:
▼
もう手の届かない、あの日々
イサク・ディネセン、本名はカレン・ブリクセン。ペンネームは男性名だが、女性デンマーク人作家である。
28歳でブリクセン男爵と結婚してケニアに移住した。夫は浮気者だった。ディネセンは夫から梅毒を移され、終生その症状に苦しんだという。ケニアでは当初、夫婦でコーヒー農場の経営にあたったが、夫には経営能力がなく、それも理由となって離婚。ディネセンは単身で奮闘することになる。20年近い努力にも関わらず、だが、結局は、農場は軌道に乗らなかった。ついにディネセンは農場をたたみ、デンマークへと帰国する。
これはその間の日々を綴ったエッセイである。
そう書くとまるで失敗者の記録のようにも思えるのだが、本作は実に力強いきらめきを放つ。
上記の著者略歴は、巻末の解説によるもので、夫や自身の病気のことは本文にはまったく登場しない。
ただ、一対の感受性豊かな目が、アフリカの土地や人々をひたと捉えて描いている。直立する一対の足がアフリカの地を闊歩し、かの地の人びとと交わり、かの地に根差そうと挑み、不運にも敗れた。親しいものの死や、もちろん農場を失う悔しさ寂しさもあるのだが、読後感はどこかすがすがしい。
原題は"Out of Africa"(アフリカを離れて)。
つまりはアフリカを去った後の回顧録ということになる。デンマーク生まれのディネセンにしてみれば、ケニアは異国の地であるにも関わらず、本作の端々から覗いているように思うのは「郷愁」である。懸命に生きた日々、親しく交わった人々、二度と帰ることのできない場所。そんな哀惜の念がそこかしこに潜むように思われるのだ。
とはいえ、全体のトーンが湿っぽいわけではない。どちらかと言えば闊達でさばさばとした男爵夫人の姿が思い浮かぶ。
文化人類学者さながらにキクユ族やマサイ族の風習を考察する一方で、実際に彼らを雇ったり、交流したりもする。農場経営者として、1つの「城」を守る矜持もある。20世紀初頭のアフリカで、欧州女性がそうして生きることはどれほどの自立心を必要としたものだろうか。
ところで、本作を原作として、メリル・ストリープ主演、ロバート・レッドフォードが恋人役の映画が撮られている。そう、ディネセンには親しい男友達がいたのだ。デニス・フィンチ=ハットン。恋人といってよいのかどうかは本作からはよくわからないが、大切な存在であったことは確かだろう。映画の方は、かなりロマンス部分に重きを置いた作りであり、原題は原作と同じ"Out of Africa"だが、邦題は『愛と哀しみの果て』といささかメロドラマ的である。
デニスは自由と孤独を愛する人物だった。時折農場を訪れる彼とともに、ディネセンは、時にライオンを狩り、時に飛行機に乗った。本書中でのこのあたりの描写は短いが非常に美しく、読ませどころである。
結局、2人の関係はデニスの事故死という衝撃的な結末で幕を閉じる。ディネセンが彼のことを大切に思っていたのは確かだろうが、レッドフォードほど「色男」であったようには思えない。ブリクセン家で働いていたマサイ族は、デニスのことを「ベダール」(ソマリ語で「はげてゆく人」)と呼んでいたというエピソードもある。興行映画としては幾分かの美化が必要であったのだろうが。
エッセイには点描のようにいくつもの小さな「事件」が描きこまれる。
生きているイグアナは宝石のように美しいが、死んでしまうと途端に灰色のコンクリートのようになってしまう話。
アフリカに来たての頃、スウェーデン人酪農業者がスワヒリ語の数の数え方を教えてくれたが、「9」の発音はスウェーデン語だと卑猥な意味があり、恥ずかしがり屋の彼はディネセンに「スワヒリ語には9はない」と言っていたという話。それでディネセンはしばらく、スワヒリ式の数え方は非常に独創的なものだと想像していたという。
農場をたたむ直前、農園仲間の女性が訪ねてきてくれ、2人で農園内を隅々まで歩いて確認しあった話。
そうした小さな挿話も、背後に物事を見通そうとする作家の「眼」を感じさせる。
失意のうちにデンマークに帰国したディネセンは、作家として歩み始める。
その生涯にわたり、おそらくはこの「アフリカの日々」が脳裏から消えることはなかっただろう。
美しい1冊である。
28歳でブリクセン男爵と結婚してケニアに移住した。夫は浮気者だった。ディネセンは夫から梅毒を移され、終生その症状に苦しんだという。ケニアでは当初、夫婦でコーヒー農場の経営にあたったが、夫には経営能力がなく、それも理由となって離婚。ディネセンは単身で奮闘することになる。20年近い努力にも関わらず、だが、結局は、農場は軌道に乗らなかった。ついにディネセンは農場をたたみ、デンマークへと帰国する。
これはその間の日々を綴ったエッセイである。
そう書くとまるで失敗者の記録のようにも思えるのだが、本作は実に力強いきらめきを放つ。
上記の著者略歴は、巻末の解説によるもので、夫や自身の病気のことは本文にはまったく登場しない。
ただ、一対の感受性豊かな目が、アフリカの土地や人々をひたと捉えて描いている。直立する一対の足がアフリカの地を闊歩し、かの地の人びとと交わり、かの地に根差そうと挑み、不運にも敗れた。親しいものの死や、もちろん農場を失う悔しさ寂しさもあるのだが、読後感はどこかすがすがしい。
原題は"Out of Africa"(アフリカを離れて)。
つまりはアフリカを去った後の回顧録ということになる。デンマーク生まれのディネセンにしてみれば、ケニアは異国の地であるにも関わらず、本作の端々から覗いているように思うのは「郷愁」である。懸命に生きた日々、親しく交わった人々、二度と帰ることのできない場所。そんな哀惜の念がそこかしこに潜むように思われるのだ。
とはいえ、全体のトーンが湿っぽいわけではない。どちらかと言えば闊達でさばさばとした男爵夫人の姿が思い浮かぶ。
文化人類学者さながらにキクユ族やマサイ族の風習を考察する一方で、実際に彼らを雇ったり、交流したりもする。農場経営者として、1つの「城」を守る矜持もある。20世紀初頭のアフリカで、欧州女性がそうして生きることはどれほどの自立心を必要としたものだろうか。
ところで、本作を原作として、メリル・ストリープ主演、ロバート・レッドフォードが恋人役の映画が撮られている。そう、ディネセンには親しい男友達がいたのだ。デニス・フィンチ=ハットン。恋人といってよいのかどうかは本作からはよくわからないが、大切な存在であったことは確かだろう。映画の方は、かなりロマンス部分に重きを置いた作りであり、原題は原作と同じ"Out of Africa"だが、邦題は『愛と哀しみの果て』といささかメロドラマ的である。
デニスは自由と孤独を愛する人物だった。時折農場を訪れる彼とともに、ディネセンは、時にライオンを狩り、時に飛行機に乗った。本書中でのこのあたりの描写は短いが非常に美しく、読ませどころである。
結局、2人の関係はデニスの事故死という衝撃的な結末で幕を閉じる。ディネセンが彼のことを大切に思っていたのは確かだろうが、レッドフォードほど「色男」であったようには思えない。ブリクセン家で働いていたマサイ族は、デニスのことを「ベダール」(ソマリ語で「はげてゆく人」)と呼んでいたというエピソードもある。興行映画としては幾分かの美化が必要であったのだろうが。
エッセイには点描のようにいくつもの小さな「事件」が描きこまれる。
生きているイグアナは宝石のように美しいが、死んでしまうと途端に灰色のコンクリートのようになってしまう話。
アフリカに来たての頃、スウェーデン人酪農業者がスワヒリ語の数の数え方を教えてくれたが、「9」の発音はスウェーデン語だと卑猥な意味があり、恥ずかしがり屋の彼はディネセンに「スワヒリ語には9はない」と言っていたという話。それでディネセンはしばらく、スワヒリ式の数え方は非常に独創的なものだと想像していたという。
農場をたたむ直前、農園仲間の女性が訪ねてきてくれ、2人で農園内を隅々まで歩いて確認しあった話。
そうした小さな挿話も、背後に物事を見通そうとする作家の「眼」を感じさせる。
失意のうちにデンマークに帰国したディネセンは、作家として歩み始める。
その生涯にわたり、おそらくはこの「アフリカの日々」が脳裏から消えることはなかっただろう。
美しい1冊である。
お気に入り度:







掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
分子生物学・生化学周辺の実務翻訳をしています。
本の大海を漂流中。
日々是好日。どんな本との出会いも素敵だ。
あちらこちらとつまみ食いの読書ですが、点が線に、線が面になっていくといいなと思っています。
「実感」を求めて読書しているように思います。
赤柴♀(もも)は3代目。
この夏、有精卵からヒヨコ4羽を孵化させました。そろそろ大雛かな。♂x2、♀x2。ニワトリは割と人に懐くものらしいですが、今のところ、懐く気配はありませんw
この書評へのコメント
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:河出書房新社
- ページ数:528
- ISBN:9784309464770
- 発売日:2018年08月04日
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。