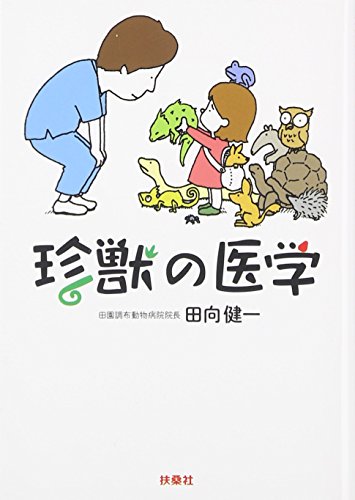ぽんきちさん
レビュアー:
▼
珍獣の治療に必要なのは、向学心と創意工夫、情熱、そして度胸。
ペットの診察にあたる、臨床獣医師のエッセイである。
著者の田向健一先生は、基本、どんなペットも診る。犬や猫などペットとしてお馴染の動物だけでなく、いわゆる「珍獣」も診る獣医さんだ。
日本でペットとして飼われる犬猫の数は現在、それぞれ900万頭前後とされる。ウサギやハムスターなどの小動物、イグアナやカメなどの爬虫類を買う人も多い。ペット天国ともいえる現代である。
だが、日本の獣医学部で教えるのは実のところ、馬や牛、豚などの産業動物についてのものが中心で、ペットとしては犬や猫程度なのだという。歴史上、家畜に関する学問が必要で設立された経緯があるのだろう。
必然的に、街の動物病院の多くは、犬猫専門のような形になる。
時に飼われるアリクイやサルなどの本当の珍獣も含め、ウサギやモモンガ、ハリネズミ、ヘビ、カエルなど(要は犬猫以外のもの)はひっくるめて珍獣=エキゾチックペットと呼ばれる。こうした珍獣に関しては、海外ではともかく日本の診察事例の積み重ねは十分とは言えず、学問として体系的に教えるような状態ではないのだ。
だが、こうした動物たちももちろん、ときに病気になる。
ハムスターが癌になったとき、カメの卵が詰まったとき、ヘビが巨大な異物を呑み込んだとき、さぁどうする?
「動物」病院だからと近所の獣医さんに駆け込んでも、その先生は実はその動物のことをよく知らないというのは珍しいことではない。
田向先生は、飼い主さんがつれてきたペットはどんな種類のものにも基本、手を尽くす。もちろん、対応不能な場合も、不幸にして死んでしまうこともあるが、とりあえずはできることがないか考える。
その際に必要となるのは、知らないことでも学ぼうとする意欲、手に入るものをその動物のために合わせて使う工夫、動物を治そうとする情熱、それから最終的にはえいやっと行動に踏み切る気合だ。
珍獣の症例では、日本語の文献はなくても、海外の論文はあることもある。麻酔の難しいカエルには、犬の呼吸マスクをすっぽりかぶせて全身麻酔する。カメのお腹に出来た巨大な結石をノミと金槌で小さくして取り出す。
そこに困っている動物と飼い主さんがいる限り、何とかしようという思いが滾る。
さまざまなエピソードに加え、写真も豊富で、動物の病気の幅広さと驚きの治療に目を見張る。
ヘビのお腹から水をたっぷり吸ったペットシーツが出てきたり、カエルの白血病を発見したり。入院中に亡くなったカメを飼い主さんが喪服で迎えにきたり。
ときには診察代を踏み倒されたり、ときには身勝手に安楽死を求める飼い主にやるせない怒りを覚えたり。
赤裸々な田向先生の筆致に、読む側も一緒に笑ったり驚いたり泣いたり怒ったりする。
そうして何だか考えてしまうのだ。
私たちはどうして動物を飼うんだろうか。飼った以上、責任を全うするとはどういうことだろうか。そして飼育動物だけでなく、自然界の動物たちと人間とは、どうやってかかわっていくべきなのだろうか。
人間と動物との関わりは所詮、どこかに「業」をはらむものなのかもしれない。けれどもそれだけではない、何か「通じ合う」ものがあると思うのは、ヒトの独りよがりなのだろうか。
帯の「命を飼うとはどういうことなのか」の一文が胸に残る。
著者の田向健一先生は、基本、どんなペットも診る。犬や猫などペットとしてお馴染の動物だけでなく、いわゆる「珍獣」も診る獣医さんだ。
日本でペットとして飼われる犬猫の数は現在、それぞれ900万頭前後とされる。ウサギやハムスターなどの小動物、イグアナやカメなどの爬虫類を買う人も多い。ペット天国ともいえる現代である。
だが、日本の獣医学部で教えるのは実のところ、馬や牛、豚などの産業動物についてのものが中心で、ペットとしては犬や猫程度なのだという。歴史上、家畜に関する学問が必要で設立された経緯があるのだろう。
必然的に、街の動物病院の多くは、犬猫専門のような形になる。
時に飼われるアリクイやサルなどの本当の珍獣も含め、ウサギやモモンガ、ハリネズミ、ヘビ、カエルなど(要は犬猫以外のもの)はひっくるめて珍獣=エキゾチックペットと呼ばれる。こうした珍獣に関しては、海外ではともかく日本の診察事例の積み重ねは十分とは言えず、学問として体系的に教えるような状態ではないのだ。
だが、こうした動物たちももちろん、ときに病気になる。
ハムスターが癌になったとき、カメの卵が詰まったとき、ヘビが巨大な異物を呑み込んだとき、さぁどうする?
「動物」病院だからと近所の獣医さんに駆け込んでも、その先生は実はその動物のことをよく知らないというのは珍しいことではない。
田向先生は、飼い主さんがつれてきたペットはどんな種類のものにも基本、手を尽くす。もちろん、対応不能な場合も、不幸にして死んでしまうこともあるが、とりあえずはできることがないか考える。
その際に必要となるのは、知らないことでも学ぼうとする意欲、手に入るものをその動物のために合わせて使う工夫、動物を治そうとする情熱、それから最終的にはえいやっと行動に踏み切る気合だ。
珍獣の症例では、日本語の文献はなくても、海外の論文はあることもある。麻酔の難しいカエルには、犬の呼吸マスクをすっぽりかぶせて全身麻酔する。カメのお腹に出来た巨大な結石をノミと金槌で小さくして取り出す。
そこに困っている動物と飼い主さんがいる限り、何とかしようという思いが滾る。
さまざまなエピソードに加え、写真も豊富で、動物の病気の幅広さと驚きの治療に目を見張る。
ヘビのお腹から水をたっぷり吸ったペットシーツが出てきたり、カエルの白血病を発見したり。入院中に亡くなったカメを飼い主さんが喪服で迎えにきたり。
ときには診察代を踏み倒されたり、ときには身勝手に安楽死を求める飼い主にやるせない怒りを覚えたり。
赤裸々な田向先生の筆致に、読む側も一緒に笑ったり驚いたり泣いたり怒ったりする。
そうして何だか考えてしまうのだ。
私たちはどうして動物を飼うんだろうか。飼った以上、責任を全うするとはどういうことだろうか。そして飼育動物だけでなく、自然界の動物たちと人間とは、どうやってかかわっていくべきなのだろうか。
人間と動物との関わりは所詮、どこかに「業」をはらむものなのかもしれない。けれどもそれだけではない、何か「通じ合う」ものがあると思うのは、ヒトの独りよがりなのだろうか。
帯の「命を飼うとはどういうことなのか」の一文が胸に残る。
お気に入り度:







掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
分子生物学・生化学周辺の実務翻訳をしています。
本の大海を漂流中。
日々是好日。どんな本との出会いも素敵だ。
あちらこちらとつまみ食いの読書ですが、点が線に、線が面になっていくといいなと思っています。
「実感」を求めて読書しているように思います。
赤柴♀(もも)は3代目。
この夏、有精卵からヒヨコ4羽を孵化させました。そろそろ大雛かな。♂x2、♀x2。ニワトリは割と人に懐くものらしいですが、今のところ、懐く気配はありませんw
この書評へのコメント
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:扶桑社
- ページ数:326
- ISBN:9784594074210
- 発売日:2016年01月31日
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。